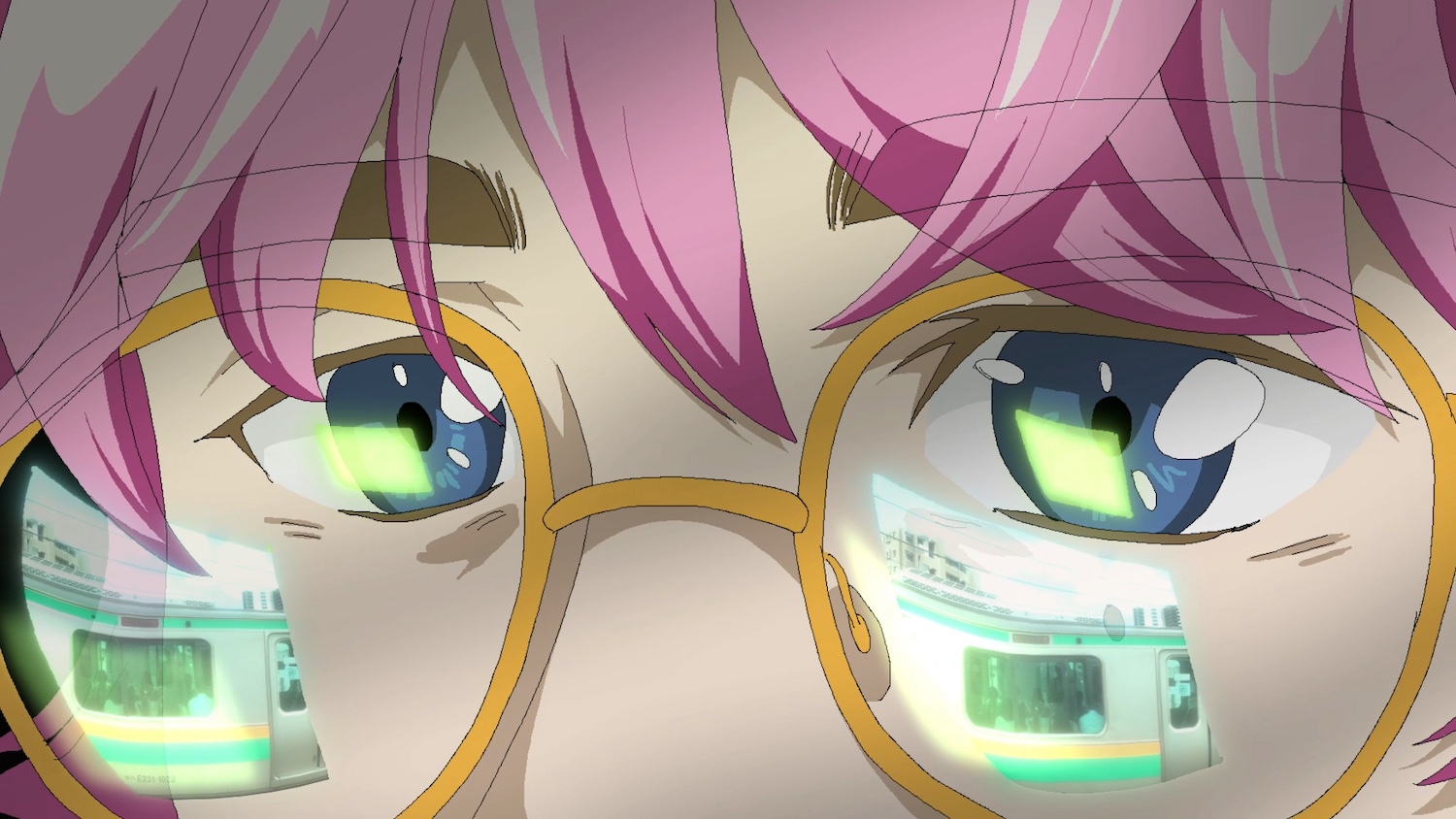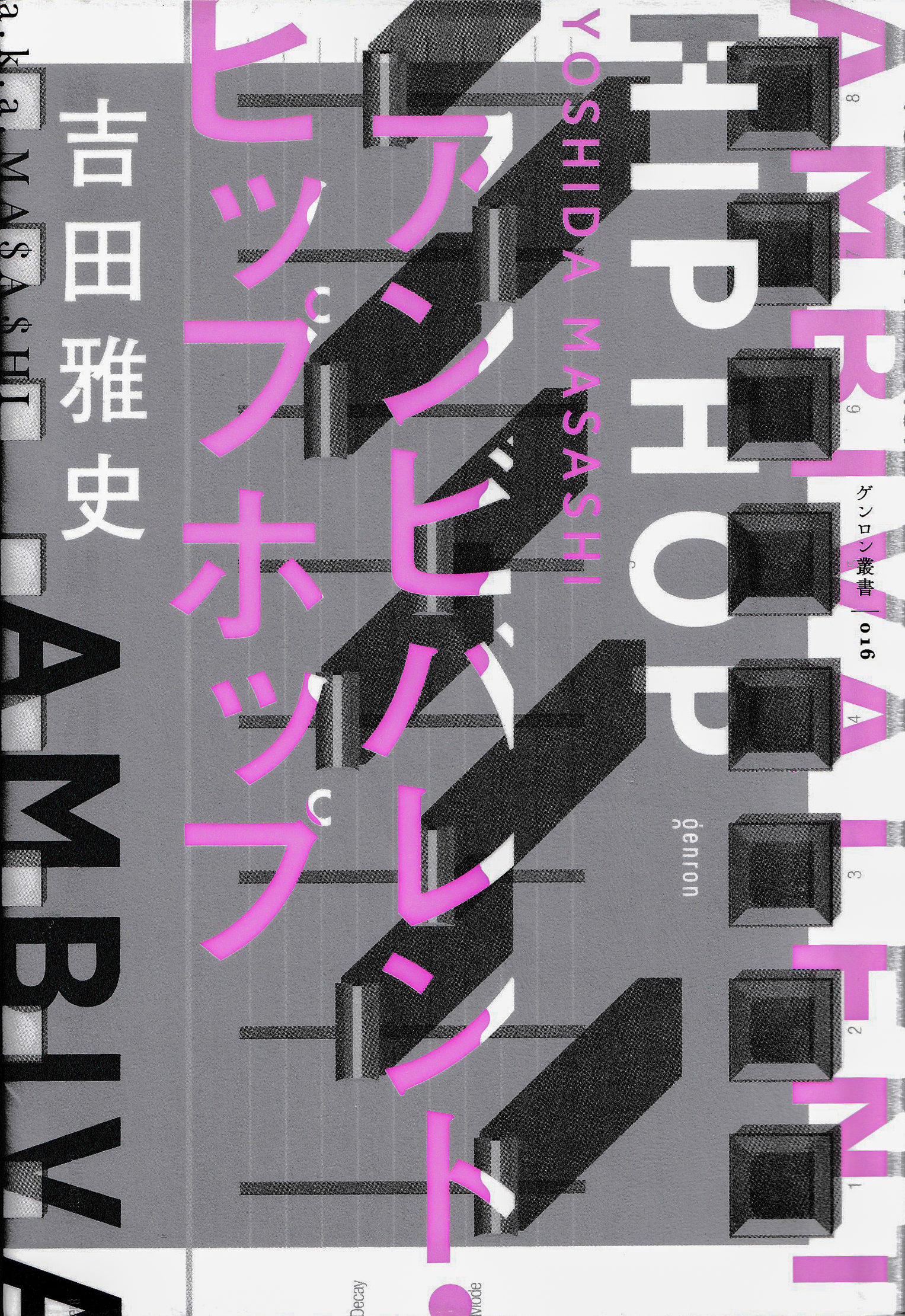
発行所:ゲンロン
発行日:2025/03/07
公式サイト:https://webgenron.com/articles/ambivalent-hiphop
今年(2025年)は、日本語ラップの歴史において画期をなす、重要な書物が登場した年として記憶されるだろう。その筆頭格にあたるのが、本書『アンビバレント・ヒップホップ』である。ビートメイカー・MCである吉田雅史(1975-)は、ゲンロンが主催する「佐々木敦 批評再生塾」の第一期総代としてデビューし、2016年から19年にかけて『ゲンロンβ』に「アンビバレント・ヒップホップ」を連載していた。当時から著者のヒップホップ論を追いかけていた読者として、同連載が大幅な加筆修正を経て一冊の書物に結実したことを、まずは心から喜びたい。
本書を導く最大のキーワードは、タイトルにもなっている「アンビバレント」(=両義的、両価的)である。過去にも繰り返し指摘されてきたことだが、〈日本におけるヒップホップ〉ないし〈日本語ラップ〉は、いずれもその起源である〈アメリカにおけるヒップホップ〉および〈英語によるラップ〉に対する──しばしば歪んだ──関係なしにはありえなかった。日本における、日本語によるラップが本当の意味で「真正(authentic)」であるためには、そこにつきまとう「アメリカの影」(13頁)を徹底的に自覚しつつ、最終的にそれを超克しなければならない。本書が掲げる「アンビバレント・ヒップホップ」は、第一にそうしたアメリカ/英語に対する両義的な関係を意味している。
その一方で、本書では前述したような含意にかぎらず、日米のヒップホップのなかにさまざまな「アンビバレンス」を見出していく。つねに「リアル」であることを要請されるヒップホップという音楽(あるいは文化)において、同時に「フェイク」が召喚されるという両義性(第1章)。あるいは日本語ラップというジャンルが、前述したようなUSラップとの複雑な関係のために抱え込んだ葛藤(第2章)。さらに個々のMCのフロウ、トラックメイカーのビートのなかに畳み込まれた両価的な性格にいたるまで、本書にはヒップホップをめぐるさまざまなアンビバレンスが顔をのぞかせる。
本書の読みどころを紹介していけばきりがないので、さしあたり二つだけ挙げよう。まず、本書はヒップホップについてほとんど知識がない読者でも問題なく読みこなせるよう、ヒップホップのごく基本的な事柄についても必要十分な紙幅を割いている。たとえば序盤では、日本語ラップの前提となる本家アメリカのヒップホップの歴史やスタイルの変遷(e.g. ブーンバップからトラップへ)について、簡にして要を得た説明がなされる。広義の音楽批評に属する類書のなかでも、これは本書の大きな美点である。
そして本書においてもっとも特筆すべきは、第3章「フロウ」や第5章「ビート」における、個々のラッパーやトラックメイカーの分析作業である。たとえば著者が「フロウチャート」と名づける図表に沿って遂行される、Zeebra、SEEDA、KOHHらのフロウの分析(第3章)。あるいはヒップホップの古典のビートを、ハイハット/スネア/キック等に分けてBPMとともに記述したスコアと、そこから導き出される考察(第5章)。本書全体を貫く理論的・歴史的な整理も見事だが、ビートメイカー・MCでもある著者の力量がもっとも発揮されているのは、こうした具体的な分析においてであるだろう。
最終章である第6章「日本語ラップ」が総論ではなく、ひとつの──そしておそらくもっとも野心的な──ケーススタディで締めくくられていることも印象深い。そこでは、今日のグローバル化し、商業化したスタイルのなかに見いだされる「異形のヒップホップ」(360頁)の可能性が探られる。具体的にこの章では、2010年代のUSラップを特徴づけるマンブルラップ、オートチューン、エモラップという三つのキーワードを出発点に、数組のMC/ビートメイカー(DJ KRUSH feat. Jinmenusagi、Tohji, Loota & Brodinski、舐達麻)のトラックが分析される。
おそらく本書を読み終えるころ、読者のYouTubeやSpotifyのプレイリストには、日米のヒップホップのアルバムがいくつも追加されているのではないだろうか。ヒップホップのさまざまな「アンビバレンス」を浮き彫りにした本書は、たんなる総説的な批評ではなく、聴衆の嗜好そのものをアップデートする喚起力に満ちている。
執筆日:2025/12/08(月)