Dialogue Tour 2010
第1回:梅香堂のはなしを聞く@Midori Art Center(MAC)[プレゼンテーション]
後々田寿徳/服部浩之2010年08月15日号
本ツアー初回のゲストは、昨年、大阪に梅香堂をオープンさせた後々田寿徳氏。同じくオープン1年足らずの青森のアートスペースMidori Art Center(MAC)にて、梅香堂の設立経緯と現在の活動、これからのことを語ってもらった。ホストはMACの服部浩之氏。梅雨明けの青森での公開収録は、MAC史上最大(!)の30人ほどが集う会となった。
美術原理主義/市場原理主義
後々田──後々田寿徳と申します。梅香堂というスペースを大阪で運営しております。今日は、そのスペースのことについてはもちろんお話いたしますが、2009年の11月に正式オープンでまだ1年も経っていません。ですから梅香堂の活動だけでなく、自分史というと大袈裟ですけど、そういうスペースをつくることになった経緯みたいなことを先に少しお話したほうが、このスペースのことをご理解いただきやすいかなと思いますので、つまらないお話ですけどおつきあいください。
私は1962年生まれですから、今回この企画で取り上げる予定の8カ所のスペースを運営してらっしゃる方のなかではたぶん飛び抜けて年齢が高い。たぶん一回り以上違う。私だけが年齢とか世代的にも違うんですね。だからそのへんの時代の違いからちょっと最初に説明しておきたいと思います。

後々田氏
私は東京の多摩美術大学の芸術学科というところを卒業しました。最近亡くなられた東野芳明さんという非常に高名な現代美術の評論家の方が学科長、それから評論家の峯村敏明さんや、作家の李禹煥さん、宇佐美圭司さんなど、錚々たるその当時の現代美術の中心的な存在が先生でした。私はそこの第2期生になります。多摩美の芸術学科は、日本ではじめて一般的に“現代美術”と呼ばれている分野に特化した学科としてスタートしたわけですが、それ以前の現代美術は、日本では自立したジャンルではなくて、洋画やデザイン、建築を経て移行していくような時代でした。それからいまは、こういうMAC(Midori Art Center)のような場所とか、青森県立美術館や十和田市現代美術館へ行くと現代美術に日常的に触れることができますよね。私が高校生のころは、美術というものに関心を持っていたものの、福井県の田舎だったこともあって、現代美術がそんなに日常的にある環境ではありませんでした。ですから現代美術というものを知ったのは、『美術手帖』などのメディアをとおしてがほとんどで、現代美術作品の実物を頻繁に見ていたわけではありません。そんななか、浪人して多摩美に入り、4年間“現代美術”といわれるものを学びました。
学部を卒業した後、幸運にもその当時はまだ珍しかった学芸員に採用されて、福井の小浜というところにある福井県立若狭歴史民俗資料館の学芸員に配属されました。最初にやったのは、仏像の展覧会です(若狭の秘仏展[1987])。その時代はいわゆる美術といっても仏像から現代美術まで、なにもかも一緒くたで、「美大を出たんだからなんでもできるだろう」みたいな理由で、古美術をやらされたわけです。ただ、そのときの経験というのはいまでもプラスになっているところはあると思っていますが。とはいえ、現代美術の世界にはなかなか入れず、資料館に勤務していた3年間は現代美術というものから離れていたわけです。しかも東京からいきなり東小浜という無人駅の本当の田舎に移って、美術の情報もまったくない。当時は若かったですから、悔しいというか情報から遅れてしまうみたいな、そういう焦りみたいなものが個人的にはありました。
その後、福井市の福井県立美術館の学芸員になりまして、そこで7年間働きました。もともと私は自分は現代美術が専門だと自負していましたし、まだ若かったこともあって、若狭から福井のほうに変わってすぐに、いわゆる“現代美術”の展覧会をやりたいと美術館の上司らと交渉しました。いまでは皆さんはちょっと理解できないと思いますが、その当時、国公立の美術館で現代美術の展覧会をやるというのは、かなりハードルが高い仕事だったわけです。現代美術というものはまだ評価が定まっていないものだから、公立美術館でそんなものを扱ってはならないというのが一般的な考えかたでした。それが1980年代の半ばくらい。そんな時代です。
福井県立美術館では現代美術の展覧会をいくつか企画しました。自分なりの個性を出してやりたかったことは、一般的に美術やファインアートといわれるものに限らないもの、それまでは美術と認められなかったようなもの、そういったものを紹介することです。たとえば、公立美術館では一番最初にテレビゲームの展覧会をやりました。それから、パチンコや自動車の展覧会をやったり、非常に領域が広いものを扱いました(日本のポップ──1960年代展[1992]、機械・人間展[1994])。そのなかのひとつが、いまでいうメディアアートですね。当時はビデオアートとかテクノロジーアートなんて呼ばれていましたが、1996年春まで福井県立美術館にいて、そういう展覧会をやってまいりました。
それから、東京の初台にあるNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]に移りました。1980年代の末から1990年代の前半くらいというのは、美術館で働いている学芸員が大きく移動した時代でした。すばらしい展覧会で評価されるとどこかに引き抜かれるとか、ヘッドハンティングされるとか。だから、地方の美術館の若い学芸員も一生懸命頑張ると中央とか東京へ行くとか、そのヒエラルキーのなかでさらに上のほうに行くとか、そういう競争的な状況があった。さらに、経済的に日本全体がすごく景気のいい時代でありましたから、あちこちに新しい美術館ができたりして、そういう意味でも人材の交流が積極的な時代だったわけです。そんななかで私も、1996年、ICCができる1年前の準備期間中に福井から移りました。オープニング展の磯崎新さんの展覧会「海市」などを担当して、7年間仕事をしました。
ICCは非常に特殊で、メディアアートを専門に扱う美術館です。現在ではもう規模は非常に小さくなってしまっていますが、当時はものすごい予算がついていました。いまではちょっと想像がつかないほどです。でも人がいないんですよ。基本的にはテレビの番組制作のようなプロダクションのノリで、プロデューサーが立ってディレクターに投げてあとは下請けが全部やる、「1億で1本やろう」みたいなそういうノリに近かった。でも、展覧会とか美術展というのはそういうふうにシステマチックにできるものではないし、あるいはそういうプロダクション会社がいっぱいあるわけでもないし、そう簡単にはできないわけですよね。だからいくらお金があっても大変だった。もちろんいろんなことをやれて楽しかったし、私は非常に感謝しているけど、やっぱり負荷が大きかった。仕事が忙しすぎるし、プレッシャーも大きすぎるし、こんなことをやっていたらただ消耗してしまう。人はいないけどお金はあって、どんどんどんどん展覧会やイヴェントをやらなきゃいけない、そういう話になってくると、自分が本当にやりたいことや、紹介したいアーティストの展示とか、そういうことができないわけです。やれるものをとにかく回して、それでつないでいくしかないわけですから。そうすると、それが非常にストレスになる。
そういう肉体的というか精神的な負担もあって、「もうこれはやばいな」ということを自分でも思いまして、大学の公募に応募したわけですよね。いまでもある程度のルートはありますけど、昔から、学芸員の業界では、大学に行くことがいわゆる「アガリ」と言われまして、それがわれわれの時代くらいにはまだはっきり残っていました。だから「大学にいってよかったね」みたいなことを言われていましたね。
それで美術系の大学に移って、そこに6年間いました。普通はそこでめでたしめでたし、アガリですからもうそれでいいわけですけれども、それまで新宿のど真ん中で働いていたわけで、それがかなり田舎の大学に変わってちょっと経つと「やっぱりなんか違うな」みたいな話になってくるわけですね。元々福井生まれで福井でも働いていましたから、それほどギャップはないだろうと思ってはいたんですけれど。これはあくまで私の個人的な見解で、独断と偏見に満ちていることを前提にお話しますけど、ようするに学校の方針と合わんわけです。どういうことかというと、私は隠居したわけですよね。もう肉体的にも精神的にも学芸員の仕事なんか続けられないから、大学というところに逃げたわけです。私にとっては隠居先ですから、たとえばそこで展覧会やってくれとか、なんかイヴェントやれとか言われても、やりたくないわけです。「そんな展覧会やるんだったら東京で1億使ってやってますよ」みたいな話になっちゃう。そこでやっぱり大学側と僕の気持ちの間にズレがあったと思うんですね。大学側は東京でバリバリやってきたキュレーターだから、田舎にきてもガンガンやってくれて、大学の宣伝をしてくれる、簡単にいえば、それを期待して採用しているわけですよね。やっぱり学校側とのそのへんのズレというのは埋めようがなかった。それによって、6年で契約打ち切りで大学を離れました。

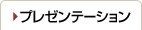

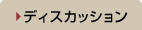
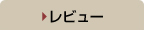
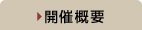

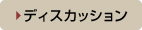
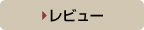
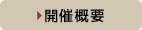





![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)