Dialogue Tour 2010
この「Dialogue Tour 2010」と冠されてリレーされる、全国8カ所のアートスペースのあり様は、私が聴いた服部浩之氏のプレゼンテーションでもそのような発言があったが、「遊び」という点に共有可能な点を持っているのかもしれない。その「遊び」への指向は、このツアーの宣言文にもある、ユルいことの積極的肯定へとも繋がっている。そのようなユルさが、宣言文が語っているように「美術館やギャラリーへの対抗意識」が「希薄」であることによるものであるとして、ではそれは一体どういうことなのか。
コミュニケーションの前景化
それらのアートスペースおよびそこで生産される美術作品が指向しているのは、そこに集う人々がなんらかの「遊び」を共有することをうながす演劇的空間であるということであり、ならば自律的な作品のあり方とは極めて程遠いものになる。そのようなあり様は、紛れもなくポストモダンの時代である今日においては、極めて正当であるといっても良いのかもしれない。そこでは、作品は観客を圧倒するような礼拝的価値を持ち過ぎていてはいけないし、作品それ自体として完成し過ぎていてはいけないし、ひょっとすると作品は「作品」であってすらいけない(=作品未満)のかもしれない。また、スペースの運営は、美術館のように規律的ではいけないし、限られたアートピープルのみに閉ざされてはいけない。場合によってはわざわざ会場に足を運ばなくてもよく(足を運ぶには金銭的、時間的コストがかかって効率悪いから)、USTREAMなりTwitterなりのコミュニケーションツールを使用して、アートを肴にダベっているだけでいい。
そのようなユルいネットワークで形成される作品とそれを取り巻く環境が求めるものは、一言で言えば「コミュニケーション」ということになるだろうが、そのコミュニケーション空間を指して、アートが形成する公共圏と呼ぶことができるだろう。そこで中心を担うものは、アートそのものではなく、アートをきっかけとして発生する公共圏のほうである。歴史を過去に辿るならば、遠く50年ほど前にも同じような議論がある。かつて宮川淳は、1960年代の反芸術やポップアートについて、コミュニケーションそれ自体の自立が、そこで生起していると指摘した。勿論、1960年代と今日とでは、コミュニケーションの質的な差異があるはずだが、かつてといまを腑分けするキーワードは、「ユルさ」にほかならないだろう。ユルさとは、ようするにコミュニケーションのさらなる前景化のことである。極論すれば、そこに作品が有ろうが無かろうが問題ではないし、それは事後的な問題に過ぎない。なぜならそこでは「コミュニケーション」が主題なのであるからだ。コミュニケーションと美術とが関係を持つと主張しようとするならば、スペースの前に「アート」という名前が、きちんと付いてさえいればいい。
Midori Art Centerにせよ、前島アートセンターにせよ、このような空間は、一般にオルタナティヴ・スペースと呼ばれる。しかし、ポストモダンの時代において、原理的に言って「オルタナティヴ」は存在しない。1980年代、ハル・フォスターは、ポストモダニズムの文化について、それを「抵抗のポストモダニズム」と「反動のポストモダニズム」とに弁別しようとした。フォスターが擁護しようとしたのは、言うまでもなく前者のポストモダニズムであるが、そこにはまだ近代的「アヴァンギャルド」の余韻があった。1980年代のポストモダニズムが少なくとも理論上において「抵抗」しようとしたのは、例えばグローバリゼーションや、後期資本主義といったものに対してであり、そこにはマルクス主義的イデオロギーが明確に刻印されていた。だが、今日のユルいポストモダンには、「抵抗」といった概念が発生させる友敵関係は存在せず、ひたすらユルいコミュニケーションによって形成されるネットワークの「空気」しかない。「抵抗」ですらないオルタナティヴ・スペースは、つまりは「空気系」であると言えるだろう。
空気系の典型例としてしばしば挙げられる『けいおん!』に即して言うならば、部室であるアートスペースで繰り広げられる行為は、バンド演奏になぞらえることができるだろう。そこでの演奏行為は、けっして演奏技術の向上や、音楽の質的洗練、ましてやバンド活動による立身出世を目指してはならないし、そもそもそのような上昇志向を持ち合わせていない。あくまで放課後のティータイムでのダベりが主眼なのであり、その口実としてのバンド活動以上でも以下でもあってはならない。学校制度に完全に囲われてはおらず、かといってライヴハウスでの興業のような経済的リスクがあるわけでもない、中間領域的な場所こそが部室なのであり、その部室的アートスペースこそが、アートの新しい領域を開く「現代美術2.0」的空間である、と。しかし本当にそうか。

収録会場となった沖縄のMaejima Art Center
ローカリティの呪縛
「抵抗」ではないオルタナティヴ・スペースについて語るときに発生している事態は、アーキテクチャのコンテンツ化、という転倒だろう。いくら空気系的なユルいコミュニケーションを肯定したところで、結局のところそこで主題化されているのは「制度」の問題であり、仮に意識的な「抵抗」ではないとしても、そこには制度批判をプロモートするという戦略が、無意識的にではあれ内在している。本来コンテンツであるべき「作品」は、アーキテクチャであるべきアートスペースをコンテンツ化させるための「ネタ」として奉仕することを求められる。ネタは、いい感じに調整されたコミュニケーションという空気を発生させるための装置以上でも以下でもなく、「むしろごはんがおかず」なのである。
しかし、「作品」を神聖化しないことがポストモダンの時代の条件であるのだから、それはそれで致し方ないことなのかもしれない。けれども、Midori Art Centerにせよ、前島アートセンターにせよ事情は大して変わらないと思われるが、現代美術が大都市の文化に経済的にも環境的にも根差している以上、いわゆる地方に所在しているアートスペースは、じつは「Web2.0」以降の環境においては旗色が悪い。ハードコアなアートピープルから、アートに少しは関心があるような潜在的な層まで含め、大都市に比べて美術にかかわる人口が相対的に少ない(この相対的であることは決定的な差異である)事実に立脚している、地方のアートスペースは、地方の特定の場所に所在している以上、好むと好まざるとにかかわらず、マイノリティに属すことになる。そこでは、地域格差という名の疎外論的「抵抗」の闘争を暗黙のうえに承認することになるだろうし、そのような地方のローカル性に積極的に居直る場合、「サイトスペシフィック」という40年も前の用語が(しかもその概念をきちんと検討もしないままに)しばしば都合よく使用されることになったりする。そこで肯定されるのは、「サイトスペシフィック」な小さい地域社会との心温まるコミュニケーションであり、「サイトスペシフィック」を共通項に持つ連帯によるマイノリティの小さな抵抗であり、それが自らの(悪しき)ローカル性を承認してくれる格好の口実になる。当事者が楽しければそれはそれでいいのかもしれないが、先細りになるのは目に見えている。そして、もし以上のことが妥当であるとすれば、「現代美術2.0」は幻想に過ぎないということになるだろう。そのような有様は、結局のところ旧来ながらのマイノリティの連帯とか、場合によっては地域共同体でのコミュニケーションとなんら変わらないことになる。
フィクションとしての「聖地」化へ
では積極的な提言として、いかにして「現代美術2.0」的空間が成立しうるか。ひとつの方策としては、アートスペースを「聖地」化することだろう。そのような聖地化の手続きは、瀬戸内海のように莫大な資本を後ろ盾にすることだけに関わるものではない。いわゆる今日のオタク文化やネット文化で言うところの「聖地巡礼」は、礼拝的な行為でも何でもない。巡礼される「聖地」は、そこが確かに現実の場所であるとは言え、コンテンツによって与えられたフィクションとしての「聖地」であり、その巡礼自体が「ネタ」である。ネット環境の発達によって、リアル空間の組織の再編が強いられているということが「2.0」的状況であるとして、そのような状況が美術とは無関係ではないと判断するならば、旧来の地域共同体的なコミュニケーションをいくらネットで配信したところで効果はない。
ようするに私たちは、そのような現状について、本気で考えなければならない。「聖地」化によって、エキゾチックな地方的なるものに対する通俗的ツーリズム的関心の惹起や、またそれとは逆に、諸地域の文化的差異の均質化を招くとしても、すでに私たちの生活圏がネット環境によって均質なるものへと浸されているとするならば、それを単に嘆いても、それこそ疎外論的抵抗という反動にしかならない。必要なのは、そこが「聖地」になるような、良質のコンテンツ(作品)を生産できるようなアーキテクチャ(アートスペース)を編成することである。さらに言えば「2.0」的アートスペースを結び付けるようなハブ的サイトが、それは必ずしも現実の空間ではなく、ネット空間で良いし、「まとめサイト」的なものでも構わないが、メタアーキテクチャとして機能することが必要だろう。そのような過程のなかから、虚構の「聖地」ではあれ、ネタとしての巡礼を媒介とした、アートの来るべきコミュニティが構想しうるのではなかろうか?
すでに議論は、前島アートセンターで行なわれた服部氏のレクチャーに対するレビューという範疇を大幅(というかほとんど完全に)に逸脱してしまったが、この「Dialogue Tour」で提言されている「現代美術2.0」についてきちんと考えるならば、ひとまず以上のようなことが言えるのではないかと思われる。ともあれ現状は、「2.0」どころか「1.0」にも届いていないと判断せざるを得ないし、それは私自身にとっても他人事とは言えない問題であるのだが……。

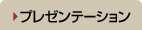

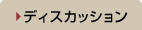
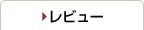
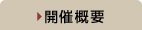
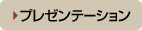
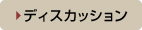

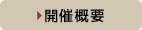




![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)