フォーカス
【シンガポール】さよなら、サブステーション 1.0
堀川理沙(ナショナル・ギャラリー・シンガポール ディレクター[キュレトリアル&コレクションズ])
2021年12月15日号
2021年7月、30年にわたってシンガポールの現代芸術、ポップカルチャーを牽引してきたオルタナティブスペースサブステーションがいったんその幕を閉じた。組織は新しいメンバーと運営で再出発するというが、そのかたちはまだ見えない。ナショナル・ギャラリー・シンガポールの堀川理沙氏にその経緯をレポートしていただく。(artscape編集部)

イベント「The Tree Celebration」が開かれた時のサブステーション(1991年6月)
[Photo by Koh Nguang How, Image courtesy of Singapore Art Archive Project]
「サブステーションはまた電力を流し始めます。かつてここから電力が供給されていったように、その電力源としての役割を、今度はアーツ・コミュニティのために果たしていくのです。元々変電所だったこの建物は、今後はサブステーション─「芸術之家」として生まれ変わるのです」
──1990年、サブステーション、オープニング時の設立者・郭宝崑(Kuo Pao Kun)の言葉
「この建物はシンガポールで唯一、失敗が歓迎される可能性として残された場所だ」
──ヒーマン・チョン(Heman Chong)『NUMEROUS, THINGS (FOR KPK)』より★1
1990年代、サブステーションで育まれたアーツ・コミュニティ
2021年7月18日、シンガポールの独立系アートスペースであるサブステーションが、惜しまれつつ、アルメニアン・ストリート45番地での31年の歴史に幕を閉じた。
サブステーションは、1990年に、劇作家・社会活動家の故・郭宝崑★2によって設立された。郭は、1926年に建設され70年代以降放置されていた街中の古びた変電所を「芸術之家」にすることを考え、多くの協力者を巻き込みながら奇跡的に実現させた。当時のシンガポールは、アーティストが発表できる場がかなり限られていた。今日のような政府主導の大型美術館やギャラリー地区ができる前のことである(シンガポール美術館の設立は1996年)。
設立された90年前後、シンガポールのアーティストたちは、アート・インフラの不在を自ら乗り越えていくかのように、サブステーションはじめ、田舎の養鶏場でアーティストのタン・ダウ(Tang Da Wu)が始めたアーティスト・ビレッジ(1988年設立、90年代に立ち退きにあい各地を転々とした後、スペースをもたずに今日まで継続)や、複数のアーティストがショッピングセンターを拠点に始動させたフィフス・パッセージ(1991年設立、1994年の歴史的なジョゼフ・ン[Josef Ng]のパフォーマンスを契機に解散★3)など、オルタナティブな活動が同時多発的に生まれていた。そのなかでも、サブステーションのあり方は独特だった。
まず第一に、その活動の多様性という点だ。ギャラリー、ミニシアター、稽古場を備え、特定のアーティストや人種・言語グループに偏ることなく、現代アート、音楽(実験音楽からパンクまで)、ダンス、演劇、文学、映画など、ジャンル横断的なプログラムを展開した。第二は、その運営形態。専属のアーティスティック・ディレクターやマネージャーが置かれ、それを上部で管轄するボードメンバーも存在し、それは、アーティストランスペースから想像する規模よりは大きく整備されているが、美術館よりは身軽で、その意味では、オルタナティブスペースというよりは、公式のウェブサイトで使われている「Contemporary Arts Centre」という表現がその形態に近かっただろう。
サブステーションは、国土がきわめて限られた都市国家のシンガポールで、芸術支援の策として1985年に国が導入したArts Housing Scheme(AHS)の最も初期のケースのひとつでもあった。AHSは、古い倉庫やショップハウスなどを改装して芸術団体や個人に安価で貸し出すというもので、賃料の多くを国が負担し、建物の管理費や光熱費は借用者が負担するという仕組みからなる。現在は60を超える芸術団体やアーティストがこの制度を利用しているが、公の助成金を享受しながらもその活動自体は政府からの影響をかわし独立性を保っているという点で、サブステーションの運営手法は画期的だった。
いつ、どの時代のサブステーションに触れたかによって、人々の記憶のなかのサブステーションはさまざまだ。設立当初のサブステーションを覚えている人は、しばしばその頃の様子を牧歌的で、なかばユートピアのように語ることが多い。当時その周りには国立図書館や老舗の書店があり、文化的な雰囲気が漂っていた。ふらりとサブステーションに立ち寄れば、大きな菩提樹が茂るその裏庭で、自然と集まってきた仲間たちと夜更けまで芸術談義に花を咲かせたという。90年代を通じて、新しい文化に飢えていたシンガポールの若者たちは、この裏庭やシアター、ギャラリーで、見たこともないような過激で前衛的なパフォーマンスや作品を目の当たりにし、刺激を受けた。企画は国内のアーティストに留まらず、例えばミャンマーの前衛芸術家を集めたグループ展「New Paintings from Myanmar」が1996年にサブステーションで開催されたように、他国の最新の表現とつながることのできる貴重な場所だった。
時代の変化のなかで揺れる存在意義
しかし時代の流れとともに、サブステーションを残して、アルメニアン・ストリート一帯の風景はどんどん変わっていった。90年代に浮上した都市計画によって、2004年に中央図書館が多くの市民の反対を押し切って移転。その跡地には、オーチャード地域へとつながるトンネルが通され、シンガポール・マネージメント大学の巨大なキャンパスも近隣に設置され、サブステーションの隣に立つ、伝統ある道南学校跡地の建物はプラナカン・ミュージアムとして改装された。身近な市民生活の一部だったこの地域が、次第にピカピカで、よそよそしい町並みに変わっていった。サブステーション自身も、2005年からは資金繰りの苦肉の策として、人々から愛されていた裏庭をライブミュージックの聞けるレストラン・バーのTimbreへと貸し出す決断をした。この時点を境に、それまでのサブステーションとは決定的に何かが変わってしまったと、今日でもこの決断を悔いる声はよく聞かれる。設立以来、サブステーションを、そしてシンガポールのアートをめぐる環境が大きく変化を遂げていくなかで、サブステーションが継続して果たしていく役割はあるのか、実際、過去にその存続意義の再考をうながす声もきかれた★4。
しかしそれでも、サブステーションがこの約30年間にシンガポールのアートシーンに果たしてきた貢献は、日本でも比較的知られている作家たちの展覧会歴を見ていくだけですぐにわかる。ザイ・クーニン(Zai Kuning、1992)、リー・ウェン(Lee Wen、1993)、ヒーマン・チョン(1997)、ホ―・ツーニェン(Ho Tzu Nyen、2003)、ロバート・ジャオ・レンフェイ(Robert Zhao Renhui、2009)、彼らの初の個展はすべてサブステーションの小さなギャラリーだった(括弧内は個展開催年)。また、長く継続されてきたからこそ、サブステーションは、設立当時を知る世代とそれに連なる若いアーティストたちが、世代を越えて出会い交わることのできる希少な場所でもあった。近年、ほかにさまざまなアートスペース、美術館、ギャラリーが増え、かつての勢いはなくなってしまったとしても、サブステーションだけは常にそこに在り、いつでも還れる大切な場所、そんな感覚を多くが共有していたように思う。

環境問題をテーマにした展覧会で、タン・ダウがサブステーション裏庭で発表したパフォーマンス「World’s Number One Pet Shop II」(1991年)
[Photo by Koh Nguang How, Image courtesy of Singapore Art Archive Project]
閉鎖か、存続の可能性はあるのか
閉鎖の知らせはアーツ・コミュニティに大きなショックを与え、各世代、各ジャンルのアーティストたちの思いが一気に表に溢れ出した。元々この閉鎖は、数年前から浮上した老朽化した建物の改装に端を発する。2021年になり、運営予算の半分以上を助成するナショナル・アーツ・カウンシル(NAC)が、2年間の改装工事中はサブステーションを一時的に閉鎖し、改装完了後は、現在の建物全体を占める運営形態ではなく、複数の団体と建物を共有して借りるように求めたことが原因だった。NACとサブステーションボードメンバーは何度も話し合いを重ねたものの、ボードは完全なかたちで戻ることができない以上、設立以来のサブステーションのアイデンティティを保つことは不可能であり、活動や運営の独自の方向性を守ることも、また運営の重要な資金源となっていたスペース・レンタル料の収入という道も閉ざされるため、継続は難しいという判断を下した。コロナによる資金集めの困難もこれに拍車をかけた。この発表に、アーツ・コミュニティの反応は早かった。2月9日にはThe Substation Venue(future)グループがFacebook上に設置され、3月6日には、サブステーション(アーティスティック・ディレクターとボードメンバー数名)、NACの代表者、アーツ・コミュニティとのあいだでZoom会議が開かれ、300名近くの人々が参加した。終始重い空気が流れるなか、そこでは、閉鎖の決断に至った経緯からほかの選択肢の有無など、設定された時間枠を大幅に越えて熱い論議が交わされた。以下、それをかいつまんで記録しておきたい。
チェアマン:NACとは2019年以来、5回に及ぶ話し合いの場が持たれ、回を重ねるごとに建物全体がサブステーションの手から離れることが明るみになっていった。10人のボードメンバーで、現在の建物の全体的管理を失っても(=収入の五割減)同じ規模や方向性での活動を継続できるのか何度も話し合ったが、結論としては不可能と判断した。
NAC:環境が多様化しているなかで、より広いアーツ・コミュニティにこの空間を開放する方向性がベストと考えた。改装中の期間並びにそれ以降のさまざまな資金的な援助もサブステーション側に提案したが、受け入れられなかった。そもそも活動予算の大半を助成金で賄っている手法には持続性がなく、無理がある。
参加者1:コミュニティへの相談なくして今回の決断がボードによって下されたことは、果たして正しいのか。この30年来、運営形態が設立当初のままだったことにそもそも問題があり、運営権をボードからコミュニティへと受け渡すべきではないか(会員制の寄付などによって)。サブステーション本来の存在意義に立ち戻って、コミュニティが集うことで可能となるその力によって再生の道を探るようなあり方が検討されるべきではなかったか。
参加者2:そもそもNACから提案された複数の団体と共存するあり方や、あるいはまったく別の選択肢をボードは十分に検討したのか。
参加者3:このまま、発表されたスペースの閉鎖とサブステーションの解散という道に突き進む前に、ボードメンバーの完全な入れ替わりを求む。
アーティステイック・ディレクター二人(アーティストのウーン・ティエン・ウェイ[Woon Tien Wei]とダンサーのレカ・マイトラ[Rekha Maitra])は、会議中、コミュニティからの発言を最大限に尊重したいかのように、終始沈黙をつらぬいた。チェアマンはサブステーションの閉鎖を仕方のないことだと繰り返したが、例えば2000年以来、21年間も同じ人物がチェアマンを務め続けてていることに象徴されるように、運営のやり方にも根本的な変革が求められていることが認識として共有された。
この会議でのコミュニティからの強い反応を受けて、ボードはそれまでの姿勢を見直し、今後の方向性についてコミュニティからの新たなプロポーザルを募ることを発表した。Zoom会議に出席した有志数名によって一連のサブステーション閉鎖をめぐる経緯を考えるための資料を集めたウェブサイト(The Substation Venue Futures)やプロポーザルをつくるためのワークショップなども矢継ぎ早に開かれ、結果はどうなっても、最後の日までサブステーションを諦めたくないという思いがボードを動かしたのである。
「Substation visits Tang Mun Kit and T.K. Sabapathy at Telok Kurau Studios」
アルメニアン・ストリートでのサブステーション最後の展覧会となったタン・ムンキッ(Tang Mun Kit)の個展「Mandala for Substation」に合わせて収録された著名な美術史家T. K. サバパティ(T. K. Sabapathy)とタンの対談。タンは本展をサブステーションへ捧げるために企画した。
託された「Meant to be(あるべきかたち)」
最終的に建物の閉鎖自体はどうにも避けようのない事実だったが、7月23日、公式な閉鎖から5日後に、サブステーション2.0の起動が発表され、ボードの現メンバーは二人を残して入れ替えられること、提出されたプロポーザルはどちらも長期的な視野という視点からは採用されなかったものの、発案者のアドバイスを続けて聞いていくということなどが知らされた★5。8月以降、この新しいメンバーによってオンライン上でのワークショップやイベントが開催され、11月12日には、新アーティスティック・ディレクターにアーティストのイザム・ラーマン(Ezzam Rahman)が就任することが発表されたが、今後の詳細はまだ不透明である。
毎年、サブステーションの設立記念日(9月16日)に合わせて開催されながら、この6年間は休止していたフェスティバル「SeptFest」が(昨年9月に開かれるはずがコロナで延期)、3月、サブステーション閉鎖の知らせで人々の議論がピークに達していた最中に決行された。そこで、設立当初からのサブステーションをみてきたアーティストのタン・ダウが、そのオープニングとしてパフォーマンス《Tea Leaves Glowing in the Wind》を行なった。サブステーション前の広場に置かれた巨大な二本の大木の幹。78歳の身体を振り絞り、大木を切り、運び、それを静かに見つめ、時に上乗りになり、抱え込み、休み、そしてまた地面に置き、ずらしていくという行為を繰り返し、最後に木片で地面に現われた言葉は「MTB」だった。近くでパフォーマンスを見ていた私たちには、かすかに彼がささやいた「Meant to be」の言葉が聞こえた。サブステーションの「Meant to be」とはどんな状態だろう。場所としてのサブステーションが死んだいま、それを託されたコミュニティ側の手にかかっている。奇しくも、サブステーションと同時代を歩いてきたアーティスト・ビレッジも、解散をほのめかす「エピローグ」展を来年1月開催することを先日発表したばかりだ。

タン・ダウ《Tea Leaves Glowing in the Wind》(SeptFest 2021、2021年3月4日)[筆者撮影]
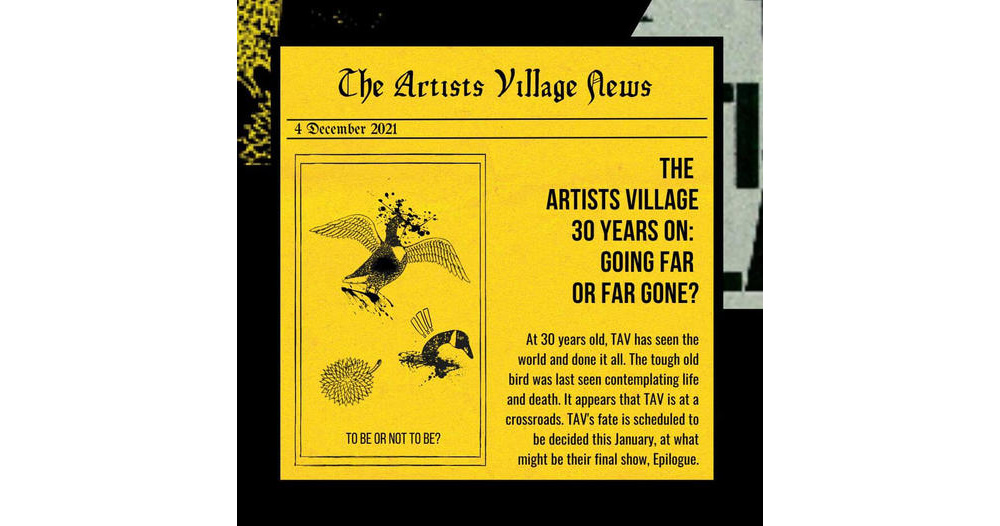
2022年1月に予定されているアーティスト・ビレッジの展覧会案内(出典:The Artists VillageのFacebookより)
本文ではふれることはできなかったが、サブステーション閉鎖発表後のめまぐるしい半年間、コミュニティによるさまざまな動きと並行して、その31年の年月を記録する膨大なアーカイヴ資料が筆者の勤める美術館に寄贈された。私個人はこれを永久的な寄贈というよりは、預かりものとして捉えている。サブステーション2.0のチームと、今後それをコミュニティのアーカイヴとして共同で公開する方法を探る話し合いが始まりつつある。「芸術之家」の灯火は、まだ消えてはいない。
★1──The Substation『25 Years of the Substation: Reflections on Singapore’s First Independent Art Centre』(The Substation & Ethos Book、2015)
★2──郭は、シンガポールの急速な都市化の背景で犠牲を強いられた人々に光をあてた社会派の華語劇で頭角を示し、妻で舞踏家のGoh Lay Kuanと共に演劇や音楽教育の制度形成にも尽力した。しかし、76年に当局から左翼派の危険分子とみなされ、治安維持法のもとに拘束、市民権も剥奪され、4年半にも及ぶ獄中生活を過ごした。勾留から解放された後は、シンガポールの歴史や多文化性をテーマにした多言語の劇作品を発表し、当時は未だ強かった華語圏と英語圏の分裂を乗り越える作品で評価を受け、89年には文化勲章にあたるCultural Medallionを授与され、92年には市民権も復権した。サブステーションに対するコミュニティの強い思いは、設立者の郭が象徴する不屈の精神によるところも大きい。
★3──アーティスト・ビレッジとフィフス・パッセージの共同企画による「Artist's General Assembly」の一環として、大晦日から元旦にかけた12時間のアート・イベントで発表されたジョゼフ・ンによるパフォーマンス「Brother Cane」。ゲイ・コミュニティが不当に逮捕され、個人情報まで公に晒された事件に応答した作品で、最中に自らの陰毛を使ったことが猥褻行為とみなされ、その後、NACによるパフォーマンス・アートへの助成が禁止された(それは10年間に及んだ)。ン本人はそれ以降の公でのパフォーマンスの一切の禁止と罰金が課され、フィフス・パッセージはショッピングセンター内の空間を失い、その関係者までもが提訴された。今日までシンガポール現代アート史のトラウマとして記憶されている。
★4──Lee Weng-Choy "The Substation: Artistic Practice and Cultural Policy", The State & The Arts in Singapore, ed. Terence Chong, Singaopre, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019, p.213
キュレーターで美術評論家のリー・ウェン・チョイは2000年から2009年までサブステーションのアーティスティック・コ・ディレクターだった。
★5── 一連の経緯の詳細については、こちらを参照のこと。Ke Weiliang "The future of The Substation: A timeline of events (Updated)", https://artsequator.com/the-substation-timeline-armenian-street/(ArtsEquator、2021年11月12日)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)