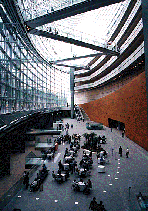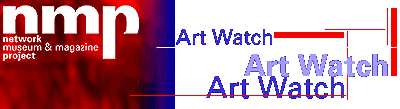
|
Aug. 6, 1996
|
Art Watch Index - Jul. 18, 1996
▼
|
目黒区美術館 http://www.dnp.co.jp/ museum/meguro/ meguro.html |
歴史の本格的な「紹介」こそ ●椹木野衣
雑多さゆえの可能性
本展は、日本の戦後美術を語る時にとかく死角となりがちだった1950年代の動向にスポットを当てるものである。 なぜ「1953年」なのか? 実際、本展の対象は非常に多岐にわたる。そして、それぞれが単独でひとつの本格的な 展覧会を構成するに十分な「テーマ」なのである。だとしたら、いかに本展の目的が、 いまでは自明のものとなってしまっている現代美術の「テーマ」が形成される以前の、 その起源における多様性を問おうとしているにせよ、ひとつひとつの部門を見るうちに 、どうしようもなく欲求不満になってしまうことも、正直な印象としては感じざるをえ ない。百歩譲って、それではこれらの「見足りなさ」が、1953年というより大きい テーマにかかわる可能性を浮き彫りにするために犠牲にされた結果としての必要悪であ るのかといえば、そうでもない。展覧を見終わっても、1953年がいかなる年であっ たのかという焦点は、いっこうに定まることがない。当時の雑多さゆえの可能性が、「批評」的なパースペクティヴを与えられないまま、何か投げ出されているような印象を 受けるのである。 社会的次元の不在
ひとつの問題は、いかに留保がつけられるにせよ、1953年を語る上でけっして欠かすことができない次元が、ここでは正面から避けられているということだろう 。カタログにもあるとおり、それはほかでもない1953年に開催された「第一回ニッポン」展に代表される、美術と社会的次元との接合の問題なのだが、もし企画者が「紹介より批評を重んじる作業であれば、バランスを欠く局面は避けられません」というのであれば、「1953年」の可能性を探る上でひとつのメルクマールになるはずのこの展覧会 をなぜ「除外」したのかについての、それこそ「批評的動機」が明示されていなければ ならない。 [さわらぎ のい/美術批評]
|
|
|
|
|
[ロンドン] ●毛利嘉孝
ロンドンのレスタースクエアにあるフォトグラファーズ・ギャラリーで「都市」をテーマにした展覧会、《ネヴァー・ウォーク・アローン》が開催されている。この展覧会は、ハンス・アースマン、メリー・アルペーン、アジェ、スーキー・ベスト、ドン・ブラウン、ルイ・ルシエールなどさまざまな形で都市を捉えた17人の作家の作品を集めたものだが、面白いのはこの展覧会がこのギャラリーの中に留まらず、タイトルが示唆しているようにロンドンという都市を観客がまた徘徊できるようにガイドブックがつくられ、日によっては簡単なウォーキング・ツアーが組まれて、観客が実際の「都市」を体験きるように趣向を凝らしていることである。 「都市」が近代(モダニズム)の成立と結びついてきたことは、既に多くの識者によ って指摘されてきた。家の外に出て、見知らぬ群衆の中に紛れ込みアーケードを歩き ウィンドウ・ショッピングをしたりカフェでお茶を飲んだりしながら、自分自身を群 衆の中の一人として身を隠し、都市のいろいろな出来事を観察すること、これは近代 以降の都市生活者の特権的な楽しみであり、ベンヤミンはこれを自覚的に行っている 者をフラヌール(遊歩者)と呼んだ。ベンヤミンがそのアイデアの多くを負ったボードレールによれば、こうした活動を自覚的に行う人が「詩人」に他ならないのだが、今では誰もがそういう意味では「詩人」になってしまっている。 とはいえ、本展覧会で提出されているのは、ポストモダン的な状況におけるこうした 「都市」のさらなる変容である。ディレクターのポール・ウォンベルによれば、街中 に設置されたビデオカメラが何よりも都市の性格を変えてしまっている。19世紀の都 市が、写真技術の発展と関わっていたとすれば、現代都市を特徴づけるのはビデオで ある。そこでもたらされているのは、覗き見趣味であり24時間の相互監視システム。 現代人はボードレールのように身を隠して都市を歩くことがますます難しくなってい るのである。本展覧会でも、結局一番インパクトがあるのは「ダーティ・ウィンドウ」と題されたメリー・アラペーンの他人の情事や売春の様子を窓の外から盗み取りしたシリーズ。なぜ、こんな写真が魅力的に見えるのか? 人は覗き見の誘惑と相互監視から逃れることができるのか? もはや人はフラヌールになりえないのか? 展覧会を出てグレート・ニューポート・ストリートを歩くと、そこもまたギャラリーで設置した ビデオによって常に撮影されており、ギャラリーのスクリーン・モニターに自分の姿 が映し出されるアイロニカルな仕掛けがされている。
[もうり よしたか/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aug. 6, 1996
|
[home]/[Art Information]/[Column]
Copyright (c) Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1996
Network Museum & Magazine Project / nmp@nt.cio.dnp.co.jp