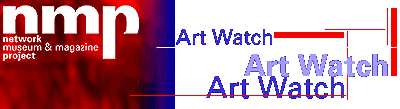
|
|
Oct. 22, 1996
|
Art Watch Index - Oct. 15, 1996
|
………………●名古屋 覚
|
▼
|
ダニエル・ビュレンヌ展 《透きとおった光》

光のための5つの色
拡散―凝縮:白い光 破裂した小屋 または 少年の朝の夢
映り込み―きらきらとした光:噴水のための破裂した小屋
分離―無限の増殖:透かしの入った壁
投影―送風:回廊 いずれも水戸芸術館でのインスタレーション、1996年
水戸芸術館 http://www.soum.co.jp/mito/
|
ダニエル・ビュレンヌ展 ●名古屋 覚
水戸芸術館現代美術センターで11月10日まで開催中のダニエル・ビュレンヌ展《透きとおった光》は、視覚を通した体験によって世界のありようを問い直してみせるという美術本来の役割を明示すると同時に、現在の日本と海外のさほど透き通ってはいない美術の状況にも光を当ててくれる、教訓の多い企画である。 ストライプをモチーフにした「その場における仕事」
ともあれ、展示された作品自体は見事である。30年近くにわたってビュレンヌのモチーフであり続けたストライプは、彼の言うところによると「建設的、構築的でさまざまな示唆に富む視覚の道具」で「どんな空間でも計測できるニュートラルな記号」だという。そのストライプと、「目が見られない物を映し出す“第3の目”」という鏡を組み合わせた〈分離―無限の増殖:透かしの入った壁〉は、なかでもビュレンヌ美術の粋を集めた作品といえよう。 [なごや さとる/美術ジャーナリスト]
|
|
|
|
《ジェンダー―記憶の淵から》

ハンナ・ウィルケ
ローリー・トビー・エディソン
キャリー・メイ・ウィームス 写真:東京都写真美術館『ジェンダー―記憶の淵から』カタログより
Hannah Wilke http://www.arts.ucsb.edu/ terminals/coils/wilke.html
Hannah Wilke - Reference Page
Women En Large Home Page
嶋田美子−現代日本の“女性”に焦点
http://www2.nikkeibp.co.jp/
Contemporary Arts Museum, Houston: Carrie Mae Weems
|
トランスジェンダーとしての写真 ●八角聡仁
写真による表現、そして写真をめぐる言説は、いま女性の表象をめぐって大きな変化に晒されようとしている。もちろんそれは、これまでマイノリティとして抑圧されていた女性による表現が目立つようになったというような単純なことではない。写真における視覚のシステム、見るものと見られるものとの関係そのものが、マイノリティを抑圧する権力構造として機能しているのではないかという問題が露出してきたのである。すなわち写真家はどんな枠組みに拠って立って写真を撮っているのか。それを批評する者はどんな立場から考察しようとしているのか。そこで「男」であること、「女」であることはどのような意味を持っているのか。そしてセクシュアリティやジェンダーをめぐる政治的議論によって写真が試されるとき、そこでは従来の写真による表象にまとわりついていた「芸術」や「作品」といった枠組みそのものが解体しようとしているのではないか。 . 「母」のイメージの政治性 70年代以来のフェミニズムが明らかにしたとおり、男から見た「こうであってほしい」女のイメージが、今日さまざまなメディアを通して無意識のうちに強制され、女性自身においても内面化されている(それは実は「男」にとってもそうなのだが)。たとえば雑誌の広告やポスター、テレビドラマやコマーシャル、そして写真作品の中にも至るところに溢れている「母と子」のイメージは、女性は結婚して子供を生むのが一番幸せなのだと暗に語っているかのようだ。しかもたとえば多くの女性が政界に進出して女性の権利が拡張されるような場合でさえ、そこではしばしば「政治に主婦の台所感覚を」とか「子どもを戦争に行かせるな」といった、社会が容認するステロタイプな「母」のイメージが強化されることになる。そして写真は、どんな個別な問題を抱えた母子であろうと、そうした社会的イメージに従属させてしまうことが可能な力を持っている。つまり写真の視線そのものが、善意のうちに男性中心主義的イデオロギーを体現してしまうのである。もっとも、そのイメージと闘って女性の自立を目指すよりもそれに従うほうが快いのだからなぜ悪いのだ、という考え方もありえよう。しかしそうした「母」のイメージこそが日本の侵略戦争に加担して「従軍慰安婦」問題を引き起こしたことを、本展の嶋田美子の作品は明らかにしているのである。いまやそうした政治的、歴史的、社会的な文脈の中で作品が問いなおされることによって、芸術の自立性、作品の中立性といった神話が解体しようとしている。写真を含む芸術作品はもはや美学的な観点でのみ語られることはできず、現実との関係の中に投げ込まれることになったのである。 写真の持つ両義的な力
しかし一方で、もともと写真とはそうした(広い意味での)ポリティカルなメディアではなかったろうか。写真家がどんなに自分の抱く美的なイメージをそこに投影しようとしても、写真は現実の対象と切り離せない以上、撮影者の意図を裏切ってそこから逸脱したイメージを孕まざるをえない。たとえば19世紀にダゲレオタイプによるヌード写真が出現したとき、人々がそこに見出したのは、従来の絵画のヌード(それはむしろ現実の裸体よりも「美」のイデアの表象である)にはない、猥雑でなまなましい直接的なリアリティだった。つまり、そもそも写真はマジョリティとしての「美」の規範を突き破るようなアクチュアリティを持った、真の意味での「マイナー」なメディアとして現れたのである。 [やすみ あきひと/批評家]
|
|
|
|
東京国際映画祭

The Film Festivals Server - Tokyo http://www.filmfestivals.com/ tokyo/index.htm
Independence Day-The Mothership Site
カップルズ(Mahjong)
|
『インデペンデンス・デイ』と ●森田祐三
何処でどういう作用が働いたのか、今年の東京国際映画祭のオープニングとして 『インデペンデンス・デイ』が上映されることになってしまった。本国では独立記念日にあわせて公開され、たちまち興行記録を幾つか更新したというのだから、この映画が何らかの「価値」を帯びているには違いないのだろうけれど、既にあらわれはじめたその解釈のことはここではおいて、反動と呼ぼうにもあまりに弛緩しているこのさみしい映画について語る道を探ろうと思う。 エドワード・ヤンの上品な過激さ では、生まれて100年以上たつ映画が果たしてこのような無自覚に埋没していてよいのだろうか、という問いをまえに、人はどのように振る舞えばよいのだろうか。どういう巡り合わせからか、おなじく東京国際映画祭で上映されることになった、今秋公開が予定されているエドワード・ヤン監督の 『カップルズ』が、その過激なまでの上品さゆえに比較を許さぬ孤高の煌めきを放つのは、たとえば、こうした逡巡にとらわれた瞬間である。「10年後には、ここが世界の中心だ」、と、ある人物にある文脈でつぶやかせてしまったエドワード・ヤンが、「民主主義的」な合衆国大統領に比べて傲慢だ、などという意見は間違いであることは断言できる。一見万遍なく目配りをするようなものが、いかに、現に今ここで作動している差異化の形式に無邪気にもたれかかって都合よく目前の存在を忘れてゆくかということはすでに述べた通りである。映画はあらゆる物を忠実に表象する媒体では絶対にないのだし、その痛みを引き受けるものだけが、「平等」や「特権」といった、いずれは相対的な、それゆえにそれなりのエネルギーを消費させる差異化の運動に安住することなく、比較を絶した、唯一にしてあらゆるものでもありうる「中心」に巡り合うことができる。しかし、それを教えてくれるのが、あまりの美しさゆえに見るものを恥じ入らせる『カップルズ』のラスト・シーンであることはやはり感動的だ。というのも、ほとんど台詞のないこの場面が、希釈されたイメージによる伝達ではなく、目にみえるものの強度による伝達ならざる伝達を実現してしまっているからである。映画がメディアであるという意識が蔓延しているとするならば、エドワード・ヤンの新作はもはや映画ですらない。そんな絶対的な新しさが、ジョン・フォードのようなロング・ショットからのつなぎのなかで、成瀬巳喜男のように人が振り返るだけで出現してしまうのだから、その恐るべきあっけなさに呆然とするためにも、特殊撮影を「駆使」した、『インデペンデンス・デイ』の「リアル」な映像をやはり目にしておかねばならないだろう。 [もりた ゆうぞう/映画批評]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oct. 22, 1996
|
[home]/[Art Information]/[Column]
Copyright (c) Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1996
Network Museum & Magazine Project / nmp@nt.cio.dnp.co.jp






