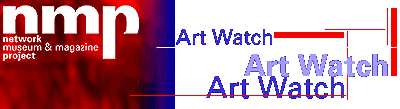
|
|
Oct. 29, 1996
|
Art Watch Index - Oct. 22, 1996
|
at P3 art and environment】 ………………● 四方幸子
|
▼
|
インゴ・ギュンター展 《難民共和国》
難民共和国 / Refugee Republic http://refugee.net/
P3 art and environment
|
インゴ・ギュンター展《難民共和国》 ●四方幸子
このプロジェクトは93年以来ギュンターが取り組んでいるもので、ロールスロイスのロゴをもじったロゴ「RR(Refugee Republic)」とともにTシャツやインターネットなど、多様なメディアを通して展開されてきたが、インスタレーションとしては初めての試みである。 脱国家的〈国家〉をめざす《難民共和国》
このプロジェクトでは、「難民」「資本」「国家」などを未来へ向けた新たな意味において、個々人が再検討することが意図されている。難民とは、政治、経済、文化、戦争などによって強制的に自国やその文化から排除/離散された人々といえるが、私はここに、フィジカルのみならずメンタルな、また潜在的な難民性をも加えたい。つまり積極的に難民になること。フーコーの言い回しを借りるならば「人はみな難民にならなけらばならない」のであり、それは現状の世界における経済、政治などさまざまな規範・制度を客体化し、その機能をずらし逸脱し、ヴォイドとなるその可能性を自覚することである。生まれた瞬間からオートマティックに領属化されている、受動的なアイデンティフィケーションを自覚し、脱領属化、脱国家・ノマド化へ。難民をポジティヴな契機とすること。 脱民族性の自覚から開かれうる未来
このプロジェクトには、たとえば 「難民共和国」に賛同する者は、誰でもインターネットによって参加することができる。しかし実際難民という立場を余儀なくされている人々の多くがインターネット・アクセスのできない状況にあることなどを考えると、両者のスタンスはかなり乖離しているのが事実である。 [しかた ゆきこ/美術批評]
|
|
|
|
《リヴィング・ブリッジ》

ヘンリーIII世に仕えた建築家
コンペティションに出品された
コンペティションに出品された
「ガーデン・ブリッジ」の断面図
Richard Rogers : biography http://www.latech.edu/ tech/arch/projects/ pamn/pamnbio.html
|
[ロンドン] ●毛利嘉孝
再び盛りあがりつつあるテムズ川再開発プロジェクト
ロンドンでは、テムズ川の周辺の再開発の議論が再び騒々しい。しかし、ごく最近まで、80年代に脚光を浴びたドックランドを中心としたリバーサイド再開発は、90年を境に急速に冷え込んだイギリス経済環境のあおりを受け、計画の途中で頓挫してしまったかのように見えていた。実際、現在でもサリー、カナリーワーフを中心とするドックランド・エリアはかつて期待されていたような活況を呈しているとは言いがたいし、何よりも景気が回復しつつあるというわけではない。にもかかわらず、テムズ川にまつわる議論は一部で盛り上がっているのである。 実在する歴史的な居住橋とユートピア的な過去のプランで構成される展覧会 最初のパートは居住橋の歴史である。1176〜1209年にかけられたロンドン・ブリッジは、18世紀までにテムズ川にかかったロンドン市内の唯一の橋だったが、その当初から両脇に住・商空間を持った居住橋だった。中世から18世紀にかけて居住橋は少なくなかったのだが、交通テクノロジーの発達につれて、車両の通行をその一義的な目的とする橋がこうした居住橋にとってかわり、現存する居住橋はヨーロッパでもごくわずかになってしまった。また、この時代、数多くのユートピア的な居住橋のプロジェクトが多くの建築家によって夢想された。ここではそうした実現しなかった企画も見ることができる。なかでも、ジャック1世アンドルー・デュ・セルソーのポン・ヌフのためのプロジェクトは壮観。
今日、居住橋をテムズ川にかける意義はあるのか?
もうひとつのパートは、賛否両論の(いや、実際メディアを見る限り否の方が多いように思われる)テムズ川の新しくかけるという橋のコンペティション。与えられた課題は、テムズ川北岸のテンプル駅と南岸のロンドン・テレビジョン・センターに多目的型の住・商空間を含んだ複合型居住橋をつくるというもの。参加建築家は、ザハ・ハディド、アントワーヌ・グランバック、ブランソン・コーツ、フューチャー・システムズ、クリア/コール、ダニエル・リベスキンド、イアン・リッチーの8組。展覧会に先立った委員会審査では、ザハ・ハディド、アントワーヌ・グランバックの2名が優秀作となっているが、最終的には展覧会会期中に行なわれている一般投票によって決定される。
[もうり よしたか/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oct. 29, 1996
|
[home]/[Art Information]/[Column]
Copyright (c) Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1996
Network Museum & Magazine Project / nmp@nt.cio.dnp.co.jp



