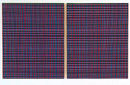| この記事は、中村ケンゴがnmp-international1/25号のartist file掲載のためにインタヴューしたものである。
――佐藤さんは、イギリス、ロンドンのゴールドスミス・カレッジ・オブ・アートを卒業されているということですが、日本の美術大学に行こうとは考えなかったのですか。
佐藤:僕は日本で3浪までしていたんです。
大学に入ったら現代美術をやりたいと考えていたんですけど、日本の美術大学は入学のさいにカテゴリーがあって、そこにある油絵とか彫刻とかアカデミックなことはやりたくなかった。そういったことに縛られずに自由に制作するためにはデザインを専攻すればいいと考えていたのですが、3浪しているあいだに何人かの友人が先に大学に入ったんですけど、彼等から話を聞くと、どうもそこに僕が行きたい場所はないということに気がついたんです。
そこから海外に行くしかないと考えて、いろいろと調べてみたらゴールドスミス・カレッジが日本人を受け入れる、大学に入る前の予備課程の段階のファンデーションがあることがわかって、アプライをして受かったんです。
――ゴールドスミスでは何を専攻したんですか。
佐藤:ゴールドスミスはちょっと変わったところで枠が全くないんですよ。ファイン・アートというくくりだけで、もうそれだけなんです。
一応クラスわけはあるんですけど、それはタテマエだけで、すべて個人で動くんです。教えてもらいたい先生には自分で手紙を書いて、時間を作ってもらって会う、といった感じですね。非常に個人主義が進んでいるんです。
僕は絵画をベースにやっていたんですけど、やっぱり日本の大学と違うのは手法のくくりではなくて思考のくくりなんですね。絵画に対する見方をどんどん拡大していこうという。非常に学ぶべきところは多かったです。
――評価はどういった方法で行なわれるんですか。
佐藤:学年ごとの進級と卒業試験だけです。大学に来る、来ないも自由です。
ただ、試験のときにいい作品がつくれなければ落とされる、ということです。試験はほとんどインタヴューなんですよ。作品をハンギングして、講師達5、6人の前でインタヴューを受けるといった感じです。そのなかで総合的に判断されると。
――それは作品について語ることをあまり学ばない日本の美大生には厳しい試験でしょうね。それに日本の美大は技法によって専攻が分かれているので、自分が入学した専攻によってその後の制作の技法がある程度規定されてしまうことが多いんです。
佐藤さんは、ある意味では全く規定されないところにいたわけですが、そんななかで絵画を選んだというのはどうしてですか。
佐藤:日本と西洋の絵画を見比べてもわかりますが、日本人のものの見方ってすごく、二次元的だと思うんですよ。西洋の絵画の空間処理は立体的な表現ですが、日本の場合は空間を舞台美術の書き割りのように平面的に表現しますよね。僕もそのようにものごとを立体的に見るというより平面的に見る意識のほうが強かったんじゃないかと思うんです。そういう意識が僕にとっては武器なんだと思ったし、それが自分が最も伸ばせる能力だと思ったんです。
――それは西洋文化のなかで学ぶことを通して自分の日本的な感性を相対化できたということでしょうか。
佐藤:そうです。
――ということは、日本の大学に行っていたら絵画をやらなかったかもしれませんね。
佐藤:そうですね。
――大学を卒業してからもロンドンに残ろうとは考えなかったんですか。
佐藤:大学を出て1年間はロンドンのスタジオで制作していました。でも94年のヨーロッパ統合くらいから、ヨーロッパ以外の外国人の締め出しみたいなものが始まって、ロンドンにとどまるのが非常に厳しい状態になったんです。
――日本に積極的にもどってきたというわけではなくて、もどらざる得なかったという状況があったということですね。ある意味で、やむを得ずもどって来たときの東京のアートシーンというのは、どういう印象がありましたか。もちろん、東京にロンドンのようなアートシーンがあるのか、という問題もありますが……。
佐藤:まず、非常にフォーカスしづらい、というのがありました。情報がどこから来てどこに行くのかとてもつかみづらかったですね。アートシーンが確立していないというか、成熟していないというか……。
僕は95年に日本に帰ってきましたから、今でだいたい3年くらいになるんですけど、情報を揃えて、自分のポジションを確立するまで1年くらいかかりました。
今度初の個展(1月に東京のレントゲンクンストラウムにて開催された)をするのですが、これまで一度もプレゼンしてないんです。今回の個展もギャラリーのほうからオファーがあったので。
僕にとってはいい作品をつくるということが一番大事で、作品を作り続けていれば、僕の意志とは関係なく時期が来れば、いつかは声がかかると思っていました。
――でもちゃんとしたアートシーンがあるロンドンからある意味で何もない東京に来て3年間、あせりみたいなものを感じたりしませんでしたか。
佐藤:ない、と行ったら嘘になりますけども(笑)。そんなに深刻にはなりませんでしたよ。
――東京の状況を考えると3年間プレゼンしないというのはけっこう勇気のいることだと思いますが。
佐藤:逆に巻き込まれたくないというのがあったんですよ。非常にサイクルが速いですし、展覧会やって、オープニングパーティやって……さて次は誰ですか、みたいな。メディアからの反応もないですし。
――やっぱり東京というのは「消費」というイメージが強い。
佐藤:強いですね。多分、文化に骨格がないというのが問題なんだと思うんです。僕は日本にアンダーグラウンドとかサブカルチャーってないと思ってるんですね。もともとの大本になる文化がないから、アンダーグラウンドになりえない。サブカルチャー的なものが出てきても、それがいきなりグラウンドの部分に出てきてしまって……。
――消費されてしまうということですね。文化に骨格がない、という話をされましたが、それはすなわち、近代的な歴史の積み重ねというものが行なわれていない、ということなんでしょうか。そして、そういう状況は良くないんではないか、ということでしょうか。
佐藤:やはり何かが進んでいくためには何かがあって、それに対してリアクションが必要だと思うんです。僕はオリジナルというものは信じてはいませんが、強い杭が打たれないと次には進めないと思うんです。
――戦後の日本の現代美術は歴史的に見てもそれぞれのスクールが連続していないんですよね。例えば、もの派があって、次にそれを受け継いでいくようなスタイルが登場するかと言うとそんなことはなくて、いきなりニューペインティングが入ってきて、今度はネオジオというか、そういった海外からのモードを輸入することばかりが目立っています。
佐藤:そういうことが日本的なのであっていいじゃないか、という意見もよく聞きます。だからと言って何がいいのか僕にも整理はついていませんが、コミュニケーションができていないのかな、ということは非常に感じています。それに対して象徴的なことなのですが、前回のヴェネツィア・ビエンナーレでイギリスからはデミアン・ハーストが若手で出て、そしてリチャード・ハミルトンが一緒に出ましたよね。それが非常に美しい光景だなと思ったんですよ。彼らはやってることも世代も違うけども、どこか深いところでグッと繋っているのかなと、そういうことがとても美しい事だなって思いましたね。
――そういった考え方はやはりロンドンで培われたたのでしょうか。
佐藤:そうですね。何というか、僕はロンドンでもう一度生まれ変わったような感じがすごくするんです。
――昨年のドクメンタ10を見てもいかに日本は彼らの歴史からは関係ないかということがわかります。日本にとって現代美術というものは、いかに土台のないものかということが……。
佐藤:そうですね。でも僕は、ドクメンタ10は非常に好感を持って見ました。やはり西洋の力というものを感じましたが、日本には、あの力は感じないですね。日本で大きく美術が成長していくためには国内で充実していかないと無理だと思います。僕はイギリスのことしか知りませんからそればかりになってしまいますが、国内で非常に充実しているんですね。なので東京に帰って来るまで結構不安もあったんですが、帰って来たら、同世代の人達が意外にも元気があって、決して状況は悪くないと思ってます。非常に刺激的だし、東京には、これから何かできる、できつつあるという予感がしています。
――作品をつくるさいに過去の美術史を参照していますか。
佐藤:参照はしますけど、反映はしませんね(笑)。僕は美術史に対してあまりスタンスは持っていないんです。美術史からリアクションをとって作品をつくるということに対してあまり心は動かないですね。
かつて美術は美術史を持っていたと思うのですが、今美術史を語れるのは絵画だけだと思うんです。
――絵画という形式が?
佐藤:そうです。ちゃんと継承されている唯一の形式だと思います。僕は絵画に対して非常に皮肉なポジションをとっていますけど。
もちろん絵画でない作品をつくることもあるかもしれません。あまりスタンスを限定したくありませんし、そのつどより鮮明に実現する手段をとっていきたいと思っていますから。 ただ、今は絵画が唯一出入りできるドアかもしれません。
――昨年のドクメンタやヴェネツィア・ビエンナーレを見てもほとんど絵画はありませんでしたね。僕もペインターのひとりとして興味があるのですが、今さら絵画をやっていて保守的ではないかと思ったりしませんか。
佐藤:保守的なものというのは次に向かう大きな壁になっていいと思うんです(笑)。
アバンギャルドって古い言葉ですけど(笑)、実験的なことをやっている人っていうのは、僕は次への予想はできないからあんまりおもしろくないんです。
保守的なものほどいきなり変態してミュータントになる可能性があると思いますし、僕はそうなりたいと思っています。ぼくの作品は美術史とかと言うよりも体感、体験的要素が強いんですよ。
僕は作品見るときはどれだけトリップできるかっていうのが基準になってるし、トベないのは全然好きじゃないですね(笑)。
(東京、スタジオ食堂にて)
[from nmp_i 1998 Feb.] |