フォーカス
鼎談「アジアで、しなやかなネットワークを築く」
大友良英/相馬千秋/崔敬華
2015年01月15日号
2015年は「アジア」の年になる……。
日本は東京オリンピックに向けて文化都市をアピールし、シンガポールでは東南アジアの美術をコレクションする国立新美術館(ナショナル・アート・ギャラリー・シンガポール)が、韓国の光州では国立アジア文化の殿堂がオープンします。
そんな国家的プロジェクトの一方で、アーティストやプロデューサーが、個人どうしの信頼関係を基に、お互いを理解しあい、問題を共有するためのネットワーク・プロジェクトをたちあげています。
artscape2015年新春号の focusでは、美術、音楽、パフォーミング・アーツの分野で活躍する3人の方に、それぞれが始められたプロジェクトについてお話をうかがいました。
ノイズ、即興音楽から映画やテレビドラマの劇伴、ポップスのプロデュースまで手がけ、昨年、東南アジアと日本の音楽のフロンティアを探り、音を楽しむ人をつなぐ「アンサンブルズ・アジア」をたちあげた大友良英氏。2013年まで「フェスティバル/トーキョー」のディレクターを務め、2012年に東アジアをベースにしたレジデンシー・プログラムの「r:ead」を開始し、今年その運営のためのNPO法人「芸術公社」をたちあげたアートプロデューサーの相馬千秋氏。昨年、アジア太平洋地域のキュレーターや研究者を招聘したシンポジウム「歴史の配合」を企画し、今年はアジアの現代美術をテーマにした展覧会を開催するキュレーターの崔敬華氏。
単独の文化施設のプロジェクトではなく、一人のカリスマプロデューサーが牽引するのでもない。個と個が対等であるためのネットワークづくりのための試みは始まったばかりです。彼らが発する言葉や生まれ出る作品から、私たちは何を受け取れるでしょうか。
ヨーロッパとアジア 自分の立ち位置を探る
──本日は、みなさんがアジアをベースに始められたプロジェクトについてお話をうかがいたいと思います。まず最初は崔さんから、東京都現代美術館(以下、MOT)で開催されたシンポジウムについてお話いただけますか?
崔──昨年の11月に「歴史の配合」★1 というシンポジウムを開催しました 。ここでは、アジア……アジアという言葉、ほんとうは使うのが嫌なんですけど、アジア太平洋地域の30代を中心としたキュレーターやアーティスト、歴史家たちに集まってもらい、欧米をベースにした美術の言説や美術史、あるいは国家という単位を軸にまとめられた歴史をほどいていくような研究や活動について話をしてもらいました。例えばオーストラリアにおけるアボリジニ美術に対する認識が、研究や実践を通じていかに変わってきているのかということなど。
このシンポジウムは、東京都現代美術館の開館20周年を記念するイベントのひとつなのですが、来年の春に開催する展覧会のプレイベントとして行なったというところもあります。展覧会は、あえて一言で言ってしまえば、アジア太平洋地域の若手作家たちのひとつの流れを紹介します。が、その前提として、日本で90年代に「アジア」がどのように表象されてきたかという問題を必ずベースとして考えなくちゃいけない。例えば、国際交流基金がその頃からこつこつとアジア美術の紹介をやってきた。そこからアジア内のアーティストとキュレーターのネットワークの構築をしてきたという歴史があります。その一方で、2000年に入る少し前から福岡アジア美術館がアジアの現代美術というものに特化して研究と紹介をやってきた。その過程でアジアの定義、アジアとの関係性というものは何度も問われてきました。そこにはいろいろな歴史的な問いが含まれますが、他の国々にはない資源をもって「アジア」の表象を構築してきた日本がどういう立ち位置にあるのかという微妙な問題も含まれます。その流れを踏まえて、今「アジアの現代美術」への眼差しをいかに刷新できるのか、むしろそれをある種解体できないかということを考えています。しかし、日本の中での閉じられた考察では限界があると思い、共同企画として、シンガポール美術館とクイーンズランド州立美術館と大阪の国立国際美術館のキュレーターたちと議論をしてきました。最近のアジア主義的な自意識や、「他者としてのアジア」への眼差しをどう乗り越えていけるのかという問題について。

シンポジウム「歴史の配合」
──崔さんが美術館に入られるまでの経歴を紹介していただけますか。
崔──日本で外国語大学を出たあと、現代美術史と美術理論を学びにイギリスの大学院に行きました。ちょうど2000年、カルチュラル・スタディーズがとても盛り上がっていた時期で、どれもものすごくおもしろい、でもこれがほんとうにアジアの状況で通じるのかなという疑問はあったんです。当時イギリスでも、中国などアジアの美術に対しての興味の拡張みたいなのが起こり始めていたときでしたが、まだそんなに資料もないし、研究もなされていない。そんななかで、疑問を持ちながら1年間を過ごし、アジアで何が起こっているのかを実際に見たいと思い、シンガポール美術館で1年ぐらいインターンとして仕事をしました。その後、縁がつながって、オーストラリアに半年行って。
大友──オーストラリアのどこですか?
崔──アデレードです。小さな非営利のギャラリーで、若い地元のアーティストとじっくり話をしながら展覧会をつくっていくというようなことをしていました。その後、国際交流基金から、「アンダー・コンストラクション」★2 という展覧会の次の東アジア版をやるから手伝ってくれないかとお声がけをしていただいて、初めて日本で現代美術の展覧会に携わりました。その後、2004年の韓国の光州ビエンナーレ★3
で仕事をして、完全に燃え尽き症候群みたいになっちゃったんです。すごく大変だった。多くの観客数を動員するための、まるでアミューズメントパークのようなアートの見せ方と、国際的なアートシーンに向けて発信しようとするキュレトリアルな意図が、矛盾や乖離となって現場に現れていて、これはアートのための場ではない、二度とビエンナーレには関わるまいと当時は思っていました。
その矢先に、インドネシアのジャカルタのルアンルパというアーティストグループから声がかかり、ジャカルタに移り住んで「OK Video Festival」★4を共同で企画しました。彼らは2003年に初めてインドネシアでビデオフェスティバルをオーガナイズしていました。私が参加した第2回目でも、まだビデオアートというものは浸透しておらず、一方で携帯電話が爆発的に普及し始めたときで、若い人たちがそれを使って作品をつくっていました。ビデオアートというものが日本と全然違う歴史のなかでわっと浸透しようとしているときに、アーティストで、オーガナイザーでもあるルアンルパのメンバーたちとビデオフェスティバルをやるというのはすごくおもしろかったし、学ぶものも多かったです。
それが、美術についてもう一度きちんと考えたいと思うきかっけとなって、スウェーデンのマルメ・アート・アカデミー★5 のクリティカル・スタディーズというポスト・マスターズコースに入りました。アーティストとか、ライターとか、批評家とか、10人弱の小さなグループで、1年間セミナーやプロジェクト、一緒にいろんなことをやって。そのあと、モラトリアムでオランダに半年ぐらいいました。
大友──アムステルダム?
崔──アムステルダムです。友人のキュレーターやアーティストのプロジェクトを手伝ったりしていましたが、毎日すごい悶々としていました。どうやって自分の仕事を積み重ねていくべきかを考えると、一個人としてどの社会にコミットすべきかというところと切り離しては考えられない。そうだとわかっていても、それまで何年も日本を避けていましたから。でも結局、自分が外国人として生まれ育った日本社会に一度はきちんと向き合って、むしろ自分がそこで何ができるかということを考えなきゃいけないと思って。そんなとき、たまたま日本から国際電話がかかってきて、「ちょっと手伝ってほしいプロジェクトがあるんだけど」と。それが2007年ですね。そこから、片足は日本、もう片方の足はどこか違うところという感じで小さなプロジェクトをやっていました。MOTには、ちょうど大友さんが展示をしていらしたとき★6 に入りました。
他者との対話が問いを深める
──では、次に相馬さんのお話に移りたいと思います。相馬さんが「フェスティバル/トーキョー(以下、「F/T」)」★7 のディレクターをされていたということと「r:ead」★8 を始められたというのはつながっていると思うのですが、まずはどういう経緯で始められたのか、お話いただけますか。
相馬──私は崔さんとは世代感としてはほぼ同じくらいで、私も日本で勉強した後にフランスに行っていました。そこで大友さんに初めてお会いしたんですよね。2000年前後にリヨンという町で勉強していて、リヨン・ビエンナーレでジャン=ユベール・マルタン★9 が、まさに非西洋圏のアートにフォーカスしていて、それが非常に鮮明に記憶に残っています。さっきの話じゃないけど、自分がアジア人、非西洋人として西洋に行って、西洋の制度の中でのアジア、ないし非西洋圏の表現と位置づけられる、リアルタイムに位置づけられているのをまざまざと見て。でも、そのときは多分消化できなかった、まだわからないことだらけだったと思います。
実は、あまり話す機会はなかったんですけど、日本に帰ってきた2002年、今の職場に入って一番最初にやった仕事が、アジアの若手舞台芸術人のネットワークづくりだったんです。だけど、当時いわゆる国際共同というと、異なる国籍のアーティスト達が一緒に作品をつくることだったんです。例えば舞台芸術ジャンルでは、国際交流基金が王景生(オン・ケンセン)★10 に依頼をして、異なる国籍の俳優たちを集めて一緒に『リア王』を創作する、というような。つまり日本のイニシアティブがあって、そこにアジアの人たちが集まって一緒につくるというのが定番だった。そういうところから、もっと対等で双方向な関係性を築いていくにはどうしたらいいのかということを考えていました。
しかし、なかなかうまくいかない。単純に舞台芸術といっても、それぞれの国や地域に固有の伝統や文脈があって、相手もこっちのことを知らなさすぎるし、こっちも相手のことを知らなさすぎて、結局共通言語が西洋の基準にしかない。では西洋を経由せずに直でやろうとしても、なかなか共通のベースが持てなくて、それぞれ個別にあるものをリスペクトはしたいんだけれども、ひとつのプロジェクトをつくり上げるには十分ではない、ディスコミュニケーションだけが生成していくみたいな、そういうジレンマを感じていたんです。
ただ、そうこうしているうちに2000年代も中盤になって、中国や韓国、シンガポールの国家レベルでの文化政策が急速に発達していきました。私も韓国に毎年何かの機会につけ招聘して頂いていて、まさに今年オープンする光州の「文化の殿堂」のプランも、2007年にシンポジウムに参加した際、同じパネルで韓国の官僚が国家プロジェクトとしてプレゼンする様に立ち会いました。そういう国家主導で動いていくアジアのプロジェクトも、さっきの光州ビエンナーレの話ではないけれど、本音と建前があるというか、なかなか難しい面があるんじゃないかと感じたんです。
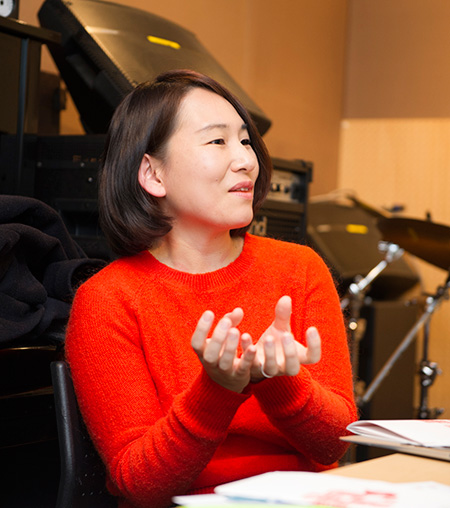
相馬千秋氏
その後、2007年頃から「F/T」の企画を立て始めました。日本には、いくつかの例外をのぞき、海外、特にヨーロッパを中心にした舞台芸術の標準に準拠した国際的なフェスティバルというものはほとんど根付いてはいなかったんです。なので、「F/T」が一番最初にやろうとしたことは、まずは日本と世界を繋ぐインターフェース機能を持つ「国際空港」として、国際フェスティバルの標準OSをしっかり搭載した上で、独自の東京、あるいは日本ならではのものをうち出していこうということでした。例えば国際共同制作という作品制作の仕組、普及の仕方、オーディエンスとのシェアの仕方など、なるべくメジャーな国際フェスティバルと齟齬がない形で日本に根付かせる、ということを最初の3年ぐらいかけていっきにやったんです。その試みは大分成功したというか、一定の定着は得て、かなり世界と日本との風通しというのはよくなったというふうに思うところまできました。ただ、それだけをやっていても、結局ヨーロッパがつくったルールの中におさまってしまい、そのカウンターとはなり得ず、中心=ヨーロッパからみたマージナルな存在としてのアジアという構図は変えられないと思って、アジアにおける独自のプラットフォームをつくっていく必要性を感じ始めたんです。必ずしもヨーロッパのルールに則らずとも、アジアの中で共有できる、例えば言語であるとか、共有できるシステムのようなものをつくっていくことができないかと、かなり切実に思い始めて、「F/T」の「公募プログラム」をアジア全域から応募してもらえるようにしたんです。3年やっていくうちに、200件に近い数のアーティストたちがアプライしてくれて。その多くは東アジアの国だったんですけど、そういったところからアーティストが参加してくれるようになりました。
でも、結局はフェスティバルって、当たり前のことなんですが、基本的にはアウトプットの質と量が問われる場で、いい作品、強い作品、そしてより多くのお客さんということが評価基準で、それだけではアジアという地理的なパースペクティブの中でやっている我々自身の問いもそんなに深まっていかないということに気付くことにもなりました。そのためには、もっとアウトプットを前提にしないインプットの場、対話の場が必要なんじゃないかと思い始めたんです。そういう強い危機感とモチベーションから「r:ead」という企画を考えたんですね。
★1 2014.11.1 アジア太平洋地域のキュレーター、研究者5名を招聘して開催されたシンポジウム。http://www.mot-art-museum.jp/mot20/
★2 2002.12.7-2003.3.2 「アンダー・コンストラクション:アジア美術の新世代」と題して、国際交流基金アジアセンターと東京オペラシティ文化財団の共催として開催。インドネシア、インド、韓国、タ イ、中国、日本、フィリピンの7カ国の新進のキュレーターが「“アジア”って何だろう」という問いかけをもとに、43組のアーティストを紹介。国際交流基金フォーラム (赤坂)とオペラシティの2会場の2カ所で展示が行なわれた。https://www.operacity.jp/ag/exh37.php#info
★3 5.18光州民主化運動の歴史を踏まえ、光州を国際的な文化都市にしようと1995年にスタートした韓国最大の国際芸術祭。http://www.gwangjubiennale.org/
★5 Malmo Art Academy http://www.khm.lu.se/
★6 2012.10.27-2013.2.3 大友氏は、東京都現代美術館で「東京アートミーティング(第3回) アートと音楽-新たな共感覚をもとめて」と題して開催されていた展覧会に、大友良英リミテッド・アンサンブルズの名義で出品。http://www.mot-art-museum.jp/music/
★7 東京池袋を中心として毎年開催されている日本最大の国際舞台芸術フェスティバル。相馬千秋氏は第9〜13回までディレクターを務めた。http://www.festival-tokyo.jp/
★8 「レジデンス・東アジア・ダイアローグは東アジアにおける芸術や社会に対する問題意識を共有し発達させることを目的とした、中国、韓国、台湾と日本に在住し ているアーティスト及び、彼らと組む評論家・ドラマトゥルク・キュレーターのためのコミュニケーション・プラットフォームを目指します。」(公式サイトより)http://r-ead.asia/
★9 Jean-Hubert Martin: 1944- キュレーター。ソルボンヌ大学美術史学卒業。ポンピドゥーセンター国立近代美術館、クンストハレ・ベルン、アフリカ・オセアニア国立美術館、クンスト・パラスト美術館などヨーロッパの主要な美術館の館長を歴任。第5回リヨン・ビエンナーレ(2000)、第3回モスクワ・ビエンナーレ(2009)など国際展のキュレーターも務める。1985年にポンピドゥーセンターで企画、開催した「大地の魔術師展」は、西欧の現代美術とアジア・アフリカの美術、民芸を同列に配し、それまでの美術史、美術批評のあり方を一変させた。2000年のリヨン・ビエンナーレのテーマは「partage d’exotismes /エキゾティズムの共有」。
★10 1963- シンガポールの演出家。1988年、シンガポール国立大学法学部在学中に「シアターワークス」を設立し、演出家として活動をスタート。ニューヨーク大学大学院にてパフォーマンス研究の修士を取得。ジャンルや国を超え、異文化を混在させるような作品を世界中の劇場やフェスティバルで発表している。





![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)