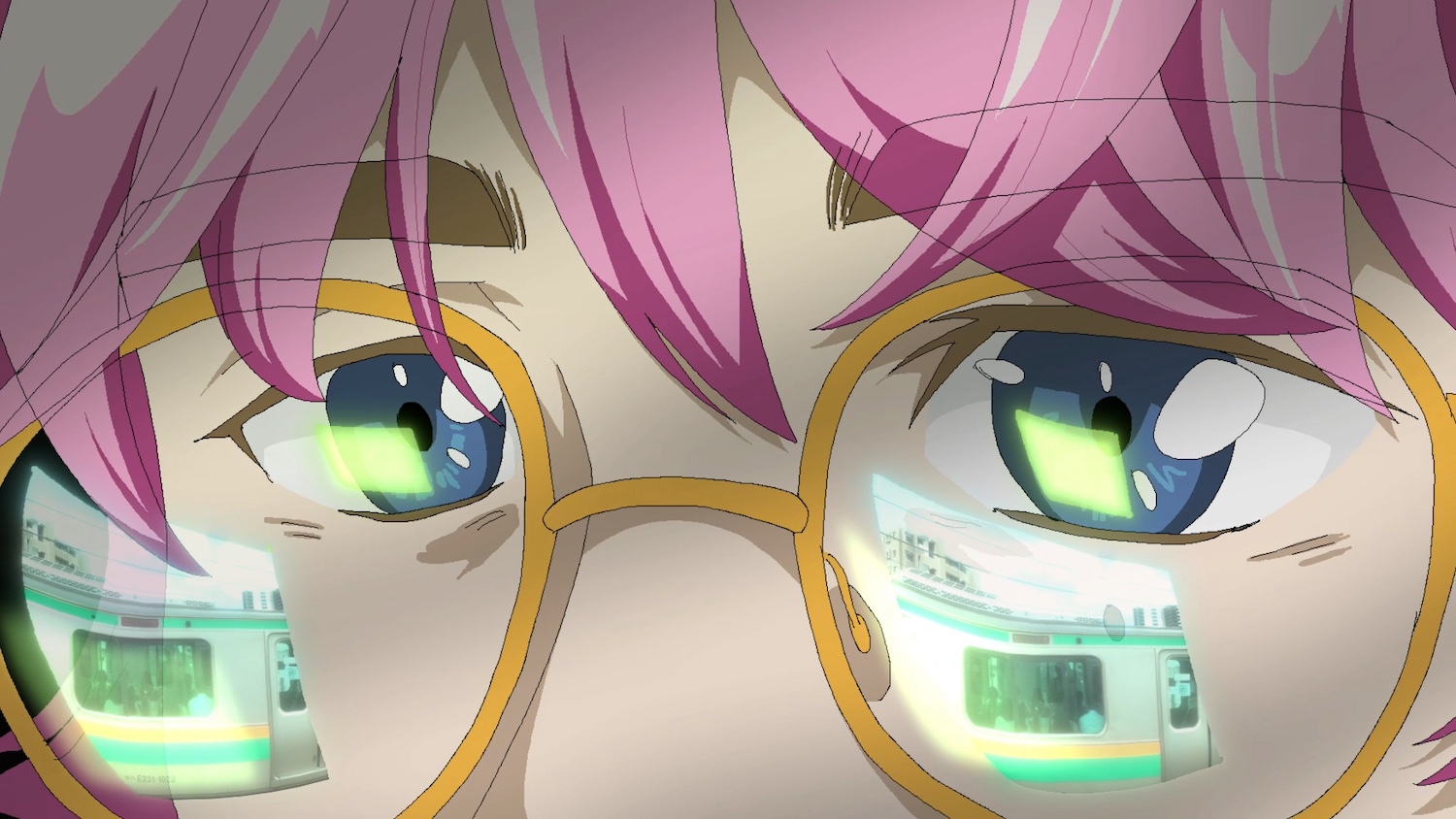会期:2024/03/27~2024/04/14
会場:PURPLE[京都府]
公式サイト:https://purple-purple.com/exhibition/lin2024/
他者と共有できない痛みと孤独を、ポートレートの撮影を通して一人ひとりに「個人」として向き合うことで、穏やかな光に包まれた連帯へと開いていくこと。他者への眼差しの可能性を静かに示す、稀有な写真だ。
1991年生まれで台湾出身の写真家・林詩硯は、東京藝術大学大学院の先端芸術表現専攻修士課程を修了。メンタルヘルスの助け合いサイトで被写体を募集し、自身も当事者である自傷行為を行なう者たちを撮影した。初写真集『針の落ちる音』(赤々舎)の刊行記念展である本展では、ポートレートの合間を縫って、「手」のクローズアップ、生/死のあわいを揺らぐような動植物を捉えたカットで編まれていく。それらすべてを、日常の中の穏やかで静謐な光が包み込む。
 [撮影:Daido Bro]
[撮影:Daido Bro]
募集にあたり、年齢や性別の制限は設けられていないが、ポートレートは、林と同世代の20〜30代の女性でほぼ占められている。顔の一部を手で覆ったり、窓越し、ガラスの水槽越しなど心理的な距離感を感じさせるカットもあるが、等しくこちらをまっすぐに見据える眼差しが鮮烈だ。その眼差しと、見る者は対峙する。
 [撮影:Daido Bro]
[撮影:Daido Bro]
彼女たちのあいだをつなぐのが、死や虚無感と、命への希求が同居する動植物のカットだ。白馬の毛並みにたかる小蝿に見える、小さな枯れ葉の断片。獲物を待つ蜘蛛の巣。抜け殻のように風にはためく白いワンピース。葉っぱにしがみついたままのセミの抜け殻。
そして、傷痕のある腕や手首のクローズアップがたびたび挿入され、これは「痛み」についての物語なのだと語りかける。ただし、ショッキングに撮るのではなく、穏やかな自然光の下、「日常的な手の仕草」が切り取られる。フルーツの入った容器を差し出す手。シャボン玉をそっと掌にのせる手。カーテン越しの光が照らす、花を持つ手。何かに触れる手。水槽のガラス越しに魚に触れようとする手は、他者に、生命に触れたいという欲求と、それを拒む透明な壁や冷たい感触を示し、極めて両義的だ。
 [撮影:Daido Bro]
[撮影:Daido Bro]
「女性の身体に刻まれた傷痕を捉えた写真」としては、石内都の「Scars」「INNOCENCE」のシリーズが想起される。ただし、石内と林の間には、事故や病気による手術痕、火傷、先天的な変形といった外在的な要因か、自ら付けた傷痕なのかといった違い以上に、大きな相違がある。石内の写真には、個人としての「顔」が排除され、徹底した身体の断片化と「皮膚のテクスチャーへの関心」が際立ち、「表面」へと還元されていく。一方、林の写真には、匿名化に対する抗いがある。個別的な痛みを提示しつつ、個人としてのポートレートの連なりは、ある種の連帯性を帯びてくる。「私は確かにここに存在している」と。写真集を閉じたあと、「個であることと、孤独で連帯できないこととは矛盾しない」という声が聴こえてくる。
それは声高ではなく、耳を澄ましても聴き取れないほどの、まさに「針の落ちる音」かもしれない。ほとんど聞こえないが、確かに存在している音/声。それは、自傷行為そのものや、当事者の置かれた状況の謂いでもある。「どのくらいの深さで切れば、大量出血や致命傷に至らないのか」が習慣的に把握され、「悲鳴」は出ない。他人に気づかれない場所で行なうし、気づかれたくない。ポートレートの一枚には、片袖だけ上着を脱ぎ、無数に傷痕の残る左腕を見せる女性がいるが、真夏でも上着で腕を隠したり、自傷行為を誰にも話せない当事者もいる。社会のなかで生きづらさを抱えながらも、声を上げること自体が困難なため、社会的にほぼ不可視化されている。あるいは、声を上げたとしても、痛覚と結びつく「針」という言葉が象徴するように、それは刺すような痛みの記憶を伴った声なのだ。
 [撮影:Daido Bro]
[撮影:Daido Bro]
一方、傷や皺、老人性色素斑(シミ)など「皮膚に刻まれた時間の堆積」を接写した石内作品(上述の「Scars」「INNOCENCE」に加え、石内自身と同年生まれの中年女性の手足を接写した「1・9・4・7」、舞踏家・大野一雄の老いた身体を接写した「1906 to the skin」など)を傍らに置いてみると、林の写真は、ただ「傷を撮った写真」ではないことを語りかけてくる。長年、繰り返し自傷を続けたことで、ケロイドや節くれだった古木のように変形した腕の皮膚は、刻まれた年輪のように「生き延びてきた年月の証」でもある。誰に見せなくとも、林の写真はそれを肯定する。
自傷の傷でなくとも、「“普通”と違う見た目の人」は日常的に奇異や侮蔑の視線を向けられる。スマホで誰でも瞬時の撮影が可能になったいま、それは「同意のない撮影行為」「盗撮」として、カメラという暴力に転じうる。林の写真は、「shot=ショット/狙撃」という言葉の二重性がまさに示すように、撮影行為が潜在的にはらむ暴力性を注意深く取り除き、肯定と共感の眼差しへと変えていく。
写真集の最後の一枚は、暗くなった部屋の電球を消そうと、「紐を引っ張る手」で終わる。だが、絶望感や暗さはない。1日の終わりに、それぞれに等しく休息と安らぎの時間が訪れますように。祈りのような願いが込められたラストだ。
 [撮影:Daido Bro]
[撮影:Daido Bro]
関連レビュー
林詩硯「針の落ちる音」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2024年03月26日)
鑑賞日:2024/03/29(金)