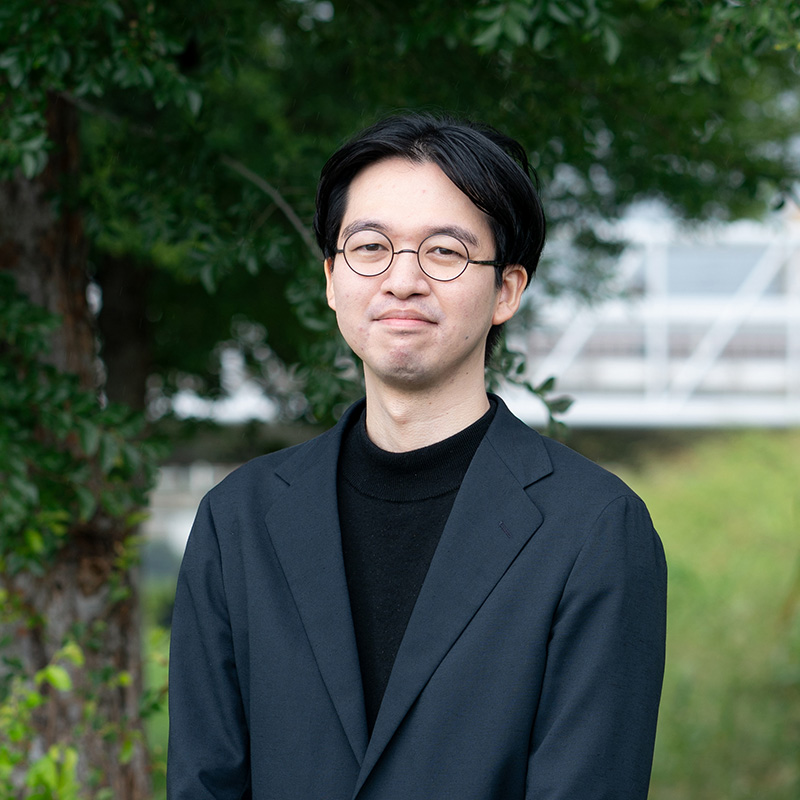釜山ビエンナーレや光州ビエンナーレをはじめ、韓国国内でさまざまなアートイベントが時期を同じくして開催されているいま、釜山からもほど近く朝鮮半島の東南端に位置する都市・昌原(チャンウォン)では「第7回昌原彫刻ビエンナーレ2024」が開催中だ(2024年11月10日まで)。都市のビジョンそのものを「彫刻」と捉えながら、新たな問いと風景を模索するこのビエンナーレに今回「co-thinker of gudeul」として関わり、キュラトリアルチームと協働して準備を行なってきたキュレーター/横浜美術館学芸員の飯岡陸氏に、現地の様子をレポートしていただいた。[artscape編集部]
昌原彫刻ビエンナーレ
2024年8月よりベルギー出身の美術史家のフィリップ・ピロットとニュージーランド出身のキュレーターのヴェラ・メイによる釜山ビエンナーレ2024「Seeing in the Dark」が、9月よりフランス出身のキュレーター、ニコラ・ブリオーによる第15回光州ビエンナーレ「パンソリ 21世紀のサウンドスケープ」が開幕した。
そんななか、釜山からバスで1時間ほどの昌原(チャンウォン)市を舞台に、9月27日に第7回昌原彫刻ビエンナーレ2024「silent apple」が開幕した。地方の芸術祭や美術館が大きなインフラとなっている日本の現代美術シーンと異なり、釜山や大邱などの存在もあるが、韓国の現代美術シーンはいまだ圧倒的にソウル中心であり、芸術祭として注目されてきたのも上記の二つにソウル・メディアシティ・ビエンナーレを加えた三つの大規模国際展だ。こうした状況への新たな挑戦として、第7回となる昌原彫刻ビエンナーレは、評論・出版活動とともにAudio Visual Pavilionのディレクターとして多くの実験的なプログラムを手がけてきたインディペンデント・キュレーターのヒョン・シウォン(Seewon Hyun)氏をアーティスティック・ディレクターに抜擢した。
テーマとして掲げられた「silent apple」は韓国フェミニスト詩人を代表する金恵順(キム・ヘスン、Kim Hyesoon)の詩「よく熟した林檎(A Well-Ripened Apple)」(2001)の⼀節から取られたもの。ステイトメントではSculptureの語源である「Scul(彫る/刻む)」ことが「書く」行為と重ね合わせられ、このビエンナーレが既存のシステムの間を自由に移動しながら、彫刻と言語、労働と産業、地方と地域の関係をめぐる問いを投げかけ、私たちを取り巻く世界を見る新たな方法を提供することが示されている★1。
ビエンナーレには、都市に常設された作品も含めて16カ国から64組86名が参加(キュレーターはイ・ミジ[Miji Lee]とパク・ヒョン[Park Hyun])。そのうち日本から黒田大スケ、恩田晃、進藤冬華、Transfield Studio(山川陸+武田侑子)、インドネシアから来年東京オペラシティ アートギャラリーで個展を予定している今津景が参加した。美術関係者向けのバスツアーも行なわれたオープニングには多くの美術関係者が訪れ、韓国のアートシーンにおける新たな展開として注目されていることを感じさせた。キュラトリアルチームをサポートする「co-thinker of gudeul」として準備に関わり、日本からの作家推薦を行なった立場からこのビエンナーレをレポートしたい。
 クドゥル(gudeul)とはオンドルとも呼称される韓国の伝統的な床暖房の名称で、このビエンナーレにおいてはワークショップが行なわれたり、ビエンナーレのレファレンスが掲載された小冊子や70年代にこの地で起きた地域文化運動「馬山文化」をはじめとする地域史料を参照できる場となっている。なお筆者はビエンナーレのためにクドゥルの機能と昌原の盆地を重ね合わせるダイアグラムを作成した。壁面および回廊に展示されているのはキム・イクヒョン(Ikhyun Gim)《1、2、多(One, two, many)》(2024)
クドゥル(gudeul)とはオンドルとも呼称される韓国の伝統的な床暖房の名称で、このビエンナーレにおいてはワークショップが行なわれたり、ビエンナーレのレファレンスが掲載された小冊子や70年代にこの地で起きた地域文化運動「馬山文化」をはじめとする地域史料を参照できる場となっている。なお筆者はビエンナーレのためにクドゥルの機能と昌原の盆地を重ね合わせるダイアグラムを作成した。壁面および回廊に展示されているのはキム・イクヒョン(Ikhyun Gim)《1、2、多(One, two, many)》(2024)
 手前がホン・スンヘ(Hong Seung-Hye)。左壁面は公民権運動の報道写真を楽譜にしたホン・ヨンイン(Young In Hong)の《空から見下ろして(Looking down from the sky)》(2017)。奥に展示されているのが黒田大スケの映像インスタレーション
手前がホン・スンヘ(Hong Seung-Hye)。左壁面は公民権運動の報道写真を楽譜にしたホン・ヨンイン(Young In Hong)の《空から見下ろして(Looking down from the sky)》(2017)。奥に展示されているのが黒田大スケの映像インスタレーション
水平性(horizontality)という態度
まずこのビエンナーレを特徴づけているのは長らくオルタナティヴ・スペースを運営してきたディレクターらしい共同性と実験性、そして地域性への注目であり、都市や環境と相互作用をもたらし、その見方に介入するような作品群である。メイン会場となるソンサン・アート・ホールは2000年に開館した文化施設で、エントランスのガラス外壁にピクトグラムのパターンを掲出したホン・スンヘ(Hong Seung-Hye)、研修室や池を使い、ミニマルな反復と有機的な要素が交差する空間をつくり上げたチョン・ソヨン(Soyoung Chung)など、各所に既存の空間を利用した作品が見られた。台湾を拠点とするルオ・ジーシン(Luo Jr-Shin)はかつてキッチンだった地下空間の天井パネルの一部を外し、照明演出の下で下水汚泥と火山性粘土を焼成した平板を並べた新作《トマトの種は身体を通過して発芽する(Tomato Seeds Pass Through the Body and Germinate)》(2024)を発表。また去勢された猫を通して漂白された計画都市を批判的に分析するノ・ソンヒ(Songhee Noh)《キャットウォーク(Catwalk)》(2024)や釜山ビエンナーレ2022にも参加していたキム・イクヒョン(Ikhyun Gim)による、紙がレイヤー状に重なる華奢な構造体や吹き抜け空間の壁を使い、昌原の歴史的なアーカイブ写真や現在の歴史的なモニュメントの姿を交差させる試みも印象に強く残った。
また美術館からの借用作品を交えながら、第一世代の女性彫刻家である金貞淑(キム・ジュンソ、Kim Chungsook、1917-91)、韓国抽象美術を代表する金鍾瑛(キム・ジョンヨン、Kim Chong Yung、1915-82)、ポップアートから影響を受け90年代から活動する画家パーク・ミーナ(MeeNa Park)らの作品群が展示されていることも特筆すべきだろう。完成した作品だけでなく、空間と平面が交差するスケッチや、すでに失われてしまった彫刻の記録写真、あるいは女性像と検閲をめぐるエピソードを合わせて紹介することで、これらの作品をフェミニズムや制作の過程という視点から再考している。
第二次世界大戦中の彫刻史が空白であることへの応答として近代彫刻家について調査し、その声を演じてきた黒田大スケは、芦屋市美術博物館でのグループ展「時代の解凍」(2023)のために制作した映像に、金鍾瑛の師でもあった建畠大夢(1880-1942)を加えた映像インスタレーションを発表。顔に動物の姿を塗り行なわれる独白・会話は、近代彫刻がヨーロッパから東アジアへ伝播するさまを伝えながら、ユーモアとともに時代に翻弄された彫刻家たちの息づかいを蘇らせる。進藤冬華は2名のみの参加者と行なったワークショップ《石狩川から水を運ぶ》の記録を展示した。もともとは大きく蛇行し頻繁に洪水を起こしてきた石狩川は、1910年代以降、近代化を支えるインフラとして人の手により絶え間なく姿を変えてきた。タイ農村部の人々に西洋絵画を見せるアラヤー・ラートチャムルーンスックの作品と合わせて展示される北海道の内国植民地化の歴史は、1970年代に韓国最初の計画都市として建設された昌原の歴史と重なり合う。
 絵画作品とそれを制作するためのドローイングが併置されたパーク・ミーナ(MeeNa Park)の展示。奥はユン・ジョンイ(Yun Jeong-ui)の作品
絵画作品とそれを制作するためのドローイングが併置されたパーク・ミーナ(MeeNa Park)の展示。奥はユン・ジョンイ(Yun Jeong-ui)の作品
 手前が進藤冬華《石狩川から水を運ぶ》(2024)。奥がアラヤー・ラートチャムルーンスック「ふたつの惑星(The two planets)」(2008-11)シリーズ
手前が進藤冬華《石狩川から水を運ぶ》(2024)。奥がアラヤー・ラートチャムルーンスック「ふたつの惑星(The two planets)」(2008-11)シリーズ
このようにビエンナーレは彫刻や都市の堅固さや永続性を疑い、その脆弱性や流転性によって基礎づけられている。ここでは出版物『ASPEN』のフルクサス特集号に掲載されたロバート・スミッソンの《地層:ジオフォトグラフィック・フィクション》(1971)によって強調されるように、歴史の堆積による地層と現在が交差する。またマーサ・ロスラーの映像作品《キッチンの記号学》(1975)が示すように、展覧会の各所に現われる詩的なテキストは概念的な考察の対象ではなく、私たちの生を省察するための手立てとなる。そしてA4用紙やコピー機を用いたパフォーマンスを行なってきたマリー・クール/ファビオ・バルドゥッチの作品が示すように、本展に満ちたエフェメラルな要素もまた彫刻として扱われる。
展覧会のチームはこのビエンナーレのために仮設壁をつくることをなるべく控え、その代わり展示台をはじめとする什器や照明の設計に趣向を凝らしたという(会場設計はソウルを拠点とするIn-between Space Lab)。照明設計からは、完成された作品とそれに至るためのスケッチ、あるいは作品の大小や新旧に対して優劣をつけず、この建築自体から壁の染みにまでも等価に光を当てようと思慮深くチューニングされていることがわかる。ハイライトを避けたこうした展示方法はステイトメントに示された「水平性(horizontality)」というキュラトリアルな態度を明確に表明しているように感じられた。日韓を拠点とする批評家の紺野優希が主催するJeilyeogaegによるツアーやカム・ドンファン(Donghwan Kam)による詩のワークショップなど会期中絶えず行なわれるイベントやワークショップもこのビエンナーレの重要な一部だ★2。
 儀礼に用いられることの多い鐘/ベルは世界各地に見られるが、由来がわかっていないものも多い。恩田晃は15年間世界各地で鐘/ベルを集め、失われた音を呼び起こそうとする。初日にはソウルを拠点にするパク・ジハ(Park Jiha)をゲストに迎えたパフォーマンスが行なわれた
儀礼に用いられることの多い鐘/ベルは世界各地に見られるが、由来がわかっていないものも多い。恩田晃は15年間世界各地で鐘/ベルを集め、失われた音を呼び起こそうとする。初日にはソウルを拠点にするパク・ジハ(Park Jiha)をゲストに迎えたパフォーマンスが行なわれた
昌原という都市を巡る
サテライト会場の設定も興味深い。三つの会場は1日で周りきれるボリュームを意識しながら、その場所がもっている文脈によって選ばれたものだ。ひとつ目の会場は、昌原⼯業団地の建設中に1973年11⽉に発⾒されたソンサン貝塚だ。工業地帯に突如現われる小高い丘と紀元前5世紀の貝塚を展示する施設には、野外に彫刻が置かれるほか、Transfield Studio(山川陸+武田侑子)がオーディオガイドによる作品を発表した。観客はガイドを聴きながら周囲の地形を歩き、昌原市の三つのエリア、昌原と馬山(マサン)、鎮海(チネ)のそれぞれ異なる──日本統治とも深く関係する──地理的条件と都市の成り立ち、そこに人々が集い、棲んできたことに意識を巡らせる。
二つ目の会場は1980年に建設された⼯場労働者のためのコミュニティ・教育センターに併設されたトンナム・グラウンドだ。ここは労働者による運動会やセレモニーなどが行なわれてきた場所で、工業都市昌原とそのコミュニティの記憶が眠る。ここではイ・ウソン(Eusung Lee) の退廃的な人体像とともに、6本の黒々とした木製の柱、ヒョン・チョン(Chung Hyun)の《⽊製の電信柱(Wooden Telegraph Pole)》(2006)が目に入る。昌原で制作されたこの作品は、2007年まで韓国国立現代美術館のエントランスに展⽰された後、京畿美術館に収蔵されたものが今回のビエンナーレのために里帰りし、再設置されたものだ。Tangerine Collectiveは、1970年代の⼥性⼯場労働者たちが割り当てられた席を拒否した「席替え」という政治的⾏動を、スピーカーから流れるサウンドを通して蘇らせる。
最後の会場は韓国人の父と日本人の母のもとに生まれた彫刻家文信(ムン・シン、Moon Shin、1922-95)自身が住居のそばに設計した文信美術館である。韓国系アメリカ人アーティスト、クリス・ロー(Chris Ro)の作品やゴン・オサン(Gwon Osang)の作品が昌原という都市や文信にオマージュを捧げ、池にはチョン・ソヨンの作品が置かれ、昌原彫刻ビエンナーレが始まるきっかけとなった彼の建築設計を彼の作品として見ることが求められる。そして何より重要なのは、点在する会場を巡りながら計画都市の端の峠へ登り、最後にこのビエンナーレが繰り返し引用してきた馬山文化や民主化運動を生み出した馬山地区を眺めるという経験であるように感じられた。
 トンナム・グラウンドの展示風景。左奥に立つのがヒョン・チョン(Chung Hyun)《⽊製の電信柱(Wooden Telegraph Pole)》
トンナム・グラウンドの展示風景。左奥に立つのがヒョン・チョン(Chung Hyun)《⽊製の電信柱(Wooden Telegraph Pole)》
 文信美術館から馬山地区を望む展望。手に持っているのは昌原の地形を示したTransfield Studioの印刷物
文信美術館から馬山地区を望む展望。手に持っているのは昌原の地形を示したTransfield Studioの印刷物
ともに考えること
最後に筆者の関わりについて補足しておきたい。筆者は昨年、韓国のキュラトリアル・スタディーズに関する調査★3をするなかで、アーティストの鎌田友介氏の紹介を通してヒョン・シウォン氏と知り合った。筆者と関心が重なる部分が大きく交流を深めるなかで、同氏のアーティスティック・ディレクターの就任が決まり、徐々に芸術祭への関わりを深めることになった。まずは2023の12月に開催されたプレプログラムにおいてビエンナーレのためのアイデアを提供したのだが、改めて当時の資料を見返すと、アーティストの生やそこから生まれた作品、都市やそこに住まう人々、動植物や事物らのネットワークがCollective Speculation(集団的思索)を構成するというアイデアについて話している。また参照先としてアクター・ネットワーク・セオリーやエコロジーに関する視点から、宮澤賢治の著作について論じたグレゴリー・ガリーの研究★4を挙げたが、「書くこと」への着目も含めて、最終的なビエンナーレの成り立ちに寄与できたように思う。
筆者は今年の3月にタイで開催された国際交流基金バンコクオフィス主催の若手キュレーター向けワークショップ「CURATOR CAMP 2024: CLOSER GROUNDS」に参加した。最終日にはメンターとして参加していた国立国際美術館主任研究員の橋本梓氏から共有された「地域アート」に関する資料に応答し、バンコクを拠点とするアーティスト/インディペンデント・キュレーターのポンサコーン・ヤナニソーンとともに地域性に関するプレゼンテーションを行なったが、この資料も昌原のキュラトリアルチームに共有した。冒頭で言及したように、韓国では地方芸術祭的な試みが盛んに行なわれてきたわけではないため、これらの議論も新鮮な参照項となったようだ。
また調査や準備に従事するなかで、過熱するソウルのアートシーンの裏側で、労働環境の厳しさや過度な競争によりアーティストが自身のペースで活動を続けることができない、状況を反省的に振り返ることができないなどの声を少なからず耳にしたことを付記しておきたい。準備に携わってきたひとりとして、地方都市で開催されたこの試みが、ソウルを中心に過密化する韓国のアートシーンの変化を促すものになっていたら嬉しく思う。
★1──公式ウェブサイトより。
https://changwonbiennale.or.kr/2024/teaser/en/
★2──こうした態度と関連するものとして、展覧会をイベントの積み重ねとして扱い、彫刻を地域史やアーティストの労働という問題に結びつけた下記展覧会を挙げておきたい。
「クロニクル、クロニクル!」(CCO クリエイティブセンター大阪、2016-17)
https://www.chronicle-chronicle.jp/
こちらも参照されたい。
能勢陽子「クロニクル、クロニクル!」(『artscape』2016年03月01日号、キュレーターズノート)
https://artscape.jp/report/curator/10120416_1634.html
★3──0-eAの主催で大坂紘一郎(ASAKUSA)、インディペンデント・キュレーターの池田佳穂とともに実施中の「アジア地域におけるキュラトリアル・スタディーズ」の一部として実施。また昨年国立アートリサーチセンターが主催するNCARスタディツアーに参加したことも韓国の現代美術シーンを理解するうえで手助けとなった。
★4──グレゴリー・ガリー『宮澤賢治とディープエコロジー 見えないもののリアリズム』(佐復秀樹訳、平凡社、2014)
https://www.heibonsha.co.jp/smp/book/b183295.html
第7回昌原彫刻ビエンナーレ2024「silent apple」
(The 7th Changwon Sculpture Biennale 2024: silent apple)
会期:2024年9月27日(金)〜11月10日(日)
会場:Seongsan Art Hall、Seongsan Shell Moundほか[韓国、昌原市]
公式サイト:https://changwonbiennale.or.kr/2024/teaser/en/