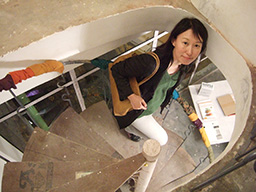前回記事ではムンバイのアートシーンについてお伝えしたが、今回はさらに南下して西インドのゴア州の総合芸術祭「セレンディピティ・アートフェスティバル(SAF)」を中心に、日本では知られていない土地で起きているアートシーンの活況についてお伝えしたい。同地域のアーティスト・スペースについてもレポートする。
(前編「ムンバイのアートシーンの歩き方」はこちら)
ゴア州の文化的背景
ゴア州はムンバイからアラビア海沿いに400キロ強ほど南下した地域にある。世界史に登場するバスコ・ダ・ガマによる、1498年のインド大陸発見を経て、ポルトガルはケーララ州コーチン(コチ)を拠点にしたのち、1510年にゴアを植民地化した。英国からのインド独立後もポルトガル領の支配は残り、インド政府の解放作戦によって同地がインドに併合されたのは、独立から14年後のことだ。そのため、ゴアはインド国内で植民地化が最初に始まり、最後に独立を果たした州とされる。400年以上に渡ってポルトガルの影響下にあったゴアは、ほかの地域とは異なる文化も形成され、ポルトガル姓をもつキリスト教徒のインド人が多数住んでいることでも知られる。このような宗主国の影響は、建築、食文化、音楽、言語、祭事において色濃く残り、インド人にとってゴアは異国情緒に浸れる旅行先である。また、日本に縁のある、キリスト教の布教に従事した聖フランシスコ・ザビエルは、ゴアを足掛かりにアジアへ宣教の旅に向かった。最後は中国の上川島で没したが、遺体はオールド・ゴアに運ばれ、今日に至るまで防腐処理を施されて安置されている。十年に一度、セー大聖堂にてその特別公開が行なわれ、ガラス張りの棺の周りで拝観できる。2024年の公開年には、インド人の信者が列をなして拝観に訪れており、多宗教からなるインドの一面を見る機会にもなった。

セー大聖堂[筆者撮影]
 クリスマス前の市内の様子[筆者撮影]
クリスマス前の市内の様子[筆者撮影]
独立後においては、1960年代以降、ゴアのビーチや自然、温暖な気候に惹かれた欧米からのヒッピーたちの聖地となり、ゴアと母国の二拠点生活の人たちが現われた。彼らの存在は、現地のファッションや現地の音楽シーンに影響を与え、1990年代にはゴアトランスと呼ばれる音楽を生んだ。現代美術に至っては、2010年代半ばから、都会の家賃高騰や大気汚染を避け、落ち着いた制作環境を求めた国内作家、特にムンバイ在住の作家たちから注目され始めた。時をほぼ同じくして、2016年からは、次に紹介する、総合芸術祭が州都パンジムで始まった。

ゴアのボート・パーティーの様子
[Courtesy: Noriko Shakti]
フェスティバルの背景
美術関係者がゴアに定期的に訪れる契機となった、総合芸術祭「セレンディピティ・アートフェスティバル」(以下、SAF)は、2010年以降に始まったインド国内の国際芸術祭のひとつに挙げられる。芸術支援に特化したニューデリーの非営利財団セレンディピティ・アーツ財団が主催しており、SAFは同財団のなかの最大のアウトリーチ・イベントとなる。コチ=ムジリス・ビエンナーレほか、多くの芸術祭が国内で生まれたが、ほとんどは資金と運用面で、継続できないか、延期が生じる事態に直面した★1。そのなかでSAFは、コロナ禍が世界を襲った2020年と2021年を除いて、12月中旬からクリスマス・イヴ直前まで毎年開催されている。
 SAF2024のプログラムのひとつ、カラ・アカデミーでのパフォーマンス《Mudiyettu(Performance)》[筆者撮影]
SAF2024のプログラムのひとつ、カラ・アカデミーでのパフォーマンス《Mudiyettu(Performance)》[筆者撮影]
財団の創設者でパトロンとなるのはヒーロー・グループ会長のスニール・カント・ムンジャル氏。同社は自転車製造からスタートした企業で、80年代には本田技研工業株式会社と合弁で「ヒーロー・ホンダ・モーターズ」を設立。インドのオートバイ市場の首位を独走した、国内で知らない者はいない企業である。日本との合弁はとうに解消されたが、人々のなかでは、いまでも同社とホンダを結びつけて語る人は多い。
そんなビジネス界のリーダーが音頭をとっているフェスティバルは、アート、音楽、演劇、ダンス、ファッション、食を取り上げた総合芸術祭のかたちを取り、現代美術に特化したコチ=ムジリス・ビエンナーレとは趣が異なる催しだ。年々その規模は大きくなっており、2024年は、8日間で国内外の参加作家1800人による、約200のプロジェクトが行なわれた。それらは、SAFが委託した各分野のキュレーターによるコア・プログラムのほか、分野を超えたスペシャル・プロジェクトと呼ばれる企画など、多様な企画形態が見られ、扱う表現も伝統的なものから現代的なものに至るまで幅広い。
 メイン会場の旧ゴア医科大学(The Old GMC COMPLEX)[筆者撮影]
メイン会場の旧ゴア医科大学(The Old GMC COMPLEX)[筆者撮影]
展示や公演はアジアでもっとも古い医科大学のひとつ、旧ゴア医科大学(Old GMC Complex)を拠点に、旧会計局(Old Directorate of Accounts)、税務局(Exercise Department)などのポルトガル統治時代の建物や芸術アカデミーなどの海岸に面したパンジムの市内各所で繰り広げられるほか、海辺や丘、公園などの屋外施設なども使われた。観客はこれらの会場に待機する、フェスティバル専用のタクシーで、朝から夜10時頃まで会場を巡ることができ、一部の公演以外はすべて無料で鑑賞できる。
 SAF会場のひとつ、アート・パークでの音楽イベント[筆者撮影]
SAF会場のひとつ、アート・パークでの音楽イベント[筆者撮影]
地域の伝統・歴史・文化と出会う場
SAFには全体のキュレーション・コンセプトがあるわけではないが、各企画者は予期しない幸運や偶然の出会いを指す「セレンディピティ(Serendipity)」を個々に解釈したキュレーションをしていることがわかる。例えば、キュレーターが異なる地域の職人と美術作家に声をかけて、共同制作が試みられたクリスティン・ミシェル企画の「Past Forward: Remix and Collaborations in Ceramics and Glass」では、ゴアに残るポルトガル伝来のブルータイルの工房作家と西ベンガル州の美術作家がそれぞれの持ち味を生かしてひとつのインスタレーション作品《Sailing in the Blue》を制作した。地域の伝統工芸と先住民族の共同制作を試みるブランド「ブリッジ・バラート(インドの架け橋)」は、「昼と夜の歌」展においてゴンド画で知られる先住民族が描く生命樹の図に、ヒマラヤのチャンバ地方にあるカラフルな絹糸刺繍「チャンバ・ルマール」とペルシャ伝来の白糸刺繍「チカンカリ」を施し、昼夜を表現、異なる地域の伝統工芸をひとつに落とし込み、新たな表現を引き出そうと試みる。
 パールタ・ダスグプタ(協力:シャンカール・トュリとジッルー)とダッタラム・ハルマルカール(キンバール陶芸工房)《Sailing in the Blue》。写真は左から、シャンカール・トュリ、パールタ・ダスグプタ[筆者撮影]
パールタ・ダスグプタ(協力:シャンカール・トュリとジッルー)とダッタラム・ハルマルカール(キンバール陶芸工房)《Sailing in the Blue》。写真は左から、シャンカール・トュリ、パールタ・ダスグプタ[筆者撮影]

ヴェンカット・ラマン・シャーム、ラリタ・ヴァキル《Songs of Day and Night》(2024)[筆者撮影]
Commissioned by Serendipity Arts for the Serendipity Arts Festival 2024.
アートパークでの屋外展示「Goa Familia: Archives of Potential (Goan) Futures」は、地元の歴史や文化に出会えた場であった。解説を添えたパネル展示には、個人やアーティスト、コミュニティから集めた物語やオブジェ、写真、土着の文化、キリスト教の祭事、工芸、特徴的な屋上の貯水タンクなどがテーマごとにまとめられている。写真家から提供を受けた展示のなかには、ゴアの伝統的な家屋とその住人のポートレイトと不動産投資で増えたセカンドハウスによって変わりゆく今日の風景を対比させたり、年配のヒッピーたちがゴアで過ごすクリスマスの様子を、ポルトガル由来のインド料理にたとえて「X’mas Vindaloo」と評した、ユニークなパネルも見られた。キュレーターのリナ・ヴィンセントとアクシャイ・マハジャンは、アーカイブを単なる歴史や文化の保存に留めず、未来において現在のゴアを振りかえり、語り合えるようにしたいという。日没後、公園を訪れた地元民たちは、展示を前にすでにその意図を感じ取っているようだった。
 「Goa Familia: Archives of Potential (Goan) Futures」展示風景[筆者撮影/Courtesy: Serendipity Art Festival 2024]
「Goa Familia: Archives of Potential (Goan) Futures」展示風景[筆者撮影/Courtesy: Serendipity Art Festival 2024]
海外アーティストとの交流の場
海外から招聘されたアーティストやキュレーターとの出会いによる企画も至るところで見られた。例えば、カランザレム・ビーチでは、インドの舞台制作チームとインドネシアのダンサーによるパフォーマンス《Littoral States of Being》が上演され、振付家でもあるアグン・グナワン(Agung Gunawan)は、シヴァ・ムルガンによる浜辺のインスタレーションに対して、ジャワ舞踊とコンテンポラリーダンスを融合させた即興的な舞いで応えた。日本のダンスグループ「アオキ 裕キと新人Hソケリッサ!」は、路上生活経験者によるメンバーとともに、現地の参加者とワークショップを行ない、パンジム市場で新作《Super Stranger》として発表、初の海外公演を果たしている。
 アオキ裕キと新人Hソケリッサ!《Super Stranger》パフォーマンス風景、パンジム市場
アオキ裕キと新人Hソケリッサ!《Super Stranger》パフォーマンス風景、パンジム市場
[Courtesy: Serendipity Art Festival 2024]
スイス人キュレーターダミアン・クリスティンガーによる「Ghosts in Machines」展では、作品を通して、歴史の負の遺産や近代化に伴う問題が幽霊のように立ち現われる。ラヴィ・アガラワルの《The Power Plant》(2023)は、インド独立後に近代化を目指して建設されたものの、運用が途中で頓挫し、廃墟となった石炭火力発電所が舞台だ。発電所を語り部としてその顛末をモノローグで語る映像作品で、エネルギーと環境問題に焦点を当てている。マリアンヌ・ハルターとマリオ・マルキセラの《Opera of Trade and Commerce》では、上海の電子機器市場と出荷される荷物が積み上がる映像が広がるなか、梱包テープのリズミカルなスクラッチ音が響くことで、消費の背後にある労働の存在に目を向ける。高山地帯のラダック出身のアヌジャ・ダスグプタの《Elemental Whispers》(2022-)では、気候変動や温暖化を憂う自然界からのささやきを、太陽光で感光させる「アントタイプ」技法によって露わにした。それらは、手作りした高山植物や果物由来の乳剤を水彩紙に塗布し、太陽の下で、風や川の流れ、絶滅の可能性を含む種も含む鳥、家畜、昆虫の営みが刻まれるなかで、カメラを使わずに淡いイメージを作り出す。同地域に関しては、持続可能性と文化の保存に関する展覧会が別会場で開かれており、ヒマラヤ山脈の限りある資源と、それらを活かした創造性や持続可能な実践への関心が国内で高まっていることを感じさせた。
 ラヴィ・アガラワル《The Power Plant》(2023)
ラヴィ・アガラワル《The Power Plant》(2023)
[Courtesy of the Artist]
 アヌジャ・ダスグプタと《Elemental Whispers》(2022-)[筆者撮影]
アヌジャ・ダスグプタと《Elemental Whispers》(2022-)[筆者撮影]
観客が作品に参加する場
コア・プログラムのキュレーターのうち、現代美術展を担当したのは、バローダ在住のヴェランカーナー・ソランキーと、ニューデリー(グルグラム)在住の作家デュオ、トゥクラール&ターグラ。どちらの展覧会にも参加型の作品が含まれており、体験を通して思いがけない出会いの場を提供する。ソランキーが手がけた「A Haptic Score」展では、触覚、音、記憶の交差を15組の作家が探求した、共感覚的なインスタレーションが紹介された。音楽プロデューサーでありミュージシャンのサナヤ・アルデシル(サンドデューン)とクリシュナ・ジャヴェリは、「触覚は人間の五感のうち、衰えても死の直前まで残る感覚」★2だとし、降霊術に用いられるウィジャボードから着想を得て《The Medium》を制作。文字盤の代わりに点字に訳した墓碑の詩を配し、それらに触れると神秘的な音が流れる仕掛けになっている。暗がりで盤を挟んだ参加者が、神妙な面持ちで点字に触れる様子は霊媒の儀式のようであった。ゴア在住のアラン・レゴによる《Enmeshed; I emerge.》(2024)も、触覚が別の感覚へと結び付く。暗室に招かれ、ふわふわとした床に足を踏み入れると、その動きに応じて音や映像、スポットライトが周囲に現われる。また、ヴィシュワ・シュロフは祖母宅の建築ドローイングと建物周辺の日常の忙しない生活音を組み合わせた《13 Old Post Office Lane》を展示、視覚と聴覚が観客の記憶や想像力を掻き立てる作品となっている。
 サナヤ・アルデシル(サンドデューン)+クリシュナ・ジャヴェリ《The Medium》(2024)[筆者撮影]
サナヤ・アルデシル(サンドデューン)+クリシュナ・ジャヴェリ《The Medium》(2024)[筆者撮影]
トゥクラール&ターグラの「Multiplay」展も、20組の作家による作品への関わり方(Play)を通して、観客が個別の鑑賞体験を得られる試みがされている。二人は、作家活動のほかに、アートと他分野のコラボレーションプロジェクト「Pollinator.io」を立ち上げており、そのうちの二つが会場に展示された。そのひとつ、《Nafrat/Parvah》では、参加者が嫌いなオブジェとその理由を手渡す代わりに、髪のセットをしてくれるユニークな出張美容室が登場する。作品を通して個人が抱える大小のネガティブな感情(Nafrat)を手放し、美容師からケアと思いやり(Parvah)を受けることで、不寛容な社会に生まれる負の感情を解きほぐそうとする。環境保護活動家であり作家のラチナ・トシュニワルは、アラビア海に浮かぶプラスチックや網などのゴミで作ったインスタレーション《There is no such thing called waste》を展示、海洋ゴミを使ったカラフルなオブジェ制作のワークショップを行なった。L.N.タルールの《The 6th Sense》では、目隠しされた参加者は暗室に導かれ、粘土を前に、触覚と与えられた花の香りを手がかりに自己の姿をかたどる。視覚に頼らない彫刻制作は自己と対峙の場でもあったようで、感想会では、個人的な話をする参加者が多かったのが印象的であった。
 トゥクラール&ターグラによるPollinatorプロジェクト《Nafrat/Parvah》(2024)[筆者撮影]
トゥクラール&ターグラによるPollinatorプロジェクト《Nafrat/Parvah》(2024)[筆者撮影]
 タチナ・トシュニワル(右)と《There is no such thing called waste》(2024)のワークショップ風景[筆者撮影]
タチナ・トシュニワル(右)と《There is no such thing called waste》(2024)のワークショップ風景[筆者撮影]
 L.N.タルール《The 6th Sense》(2024)[筆者撮影/Courtesy: Serendipity Arts Festival 2024]
L.N.タルール《The 6th Sense》(2024)[筆者撮影/Courtesy: Serendipity Arts Festival 2024]
芸術祭周辺の展覧会とアートスペース
ここで、芸術祭周辺の展示についても紹介したい。パンジム市内には、コロニアルスタイルのカラフルな邸宅を活用したスナーパランタ・ゴア芸術センターがある。ゴアの伝統的な住宅の特徴を生かした施設には、広い庭園や風通しのよい中庭にカフェがあり、旅行者や地元の人々の憩いの場となっている。訪問時には、「An Alternative Contemporary─現代細密画の祝典」展が開催されており、インド、バングラデシュ、パキスタン、アフガニスタン、欧米からの作家が細密画の様式や技法で今日的な視点を表現していた。西南アジアが共有する伝統的表現が、現代美術のなかで連綿と受け継がれていることを示した展示であった。
 スナーパランタ・ゴア芸術センター外観[筆者撮影]
スナーパランタ・ゴア芸術センター外観[筆者撮影]
 スナーパランタ・ゴア芸術センター中庭[筆者撮影]
スナーパランタ・ゴア芸術センター中庭[筆者撮影]
アーティスト主導のスペースは市内から小一時間のところに点在している。ひとつは、オールド・ゴアの船着き場から対岸へ渡ったディーバ島にある、シュレヤス・カルレとヘマリ・ブータ主宰のCONA財団だ。ブータとCONAは2022年にシンガポール・ビエンナーレに参加したほか、カルレは2016年のあいちトリエンナーレや京都造形大学グローバル・ゼミのゲスト講師を務めた経験がある。二人は2012年にムンバイでCONAを設立、同期の若手作家とともに多様なプログラムを実践していたが、コロナ禍の2021年に娘と共にゴアへ移住した。以降、同地でレジデンスやワークショップ、セッションを行ないながら、音楽や農業、娘のホームスクーリングなど、日常の営みと美術の実践が緩やかに交わる場を築いている。批評家の故アヴィーク・センは、CONAを食事、読書と議論、実践の三つのテーブルがある家★3と評したが、そこには異なるテーブルをつなぐ参加者同士の友愛の精神も根づいている。スタジオ兼自宅には、CONAに関わった作家からの寄贈作品が並んでおり、「Multiplay」展では、カルレとブータの作品に加え、寄贈作品の一部を《DIORAMA of Exhibition》としてガラス越しに公開した。会期後半はCONAに移され、家庭的な空間の中で《Dwelling for a DIORAMA》に再編成され、作品を身近に感じられる体験を促した。「Multiplay」展のサテライト会場として、CONAの寄贈コレクションから選ばれた楽曲を鑑賞するリスニング・セッションも行なわれた。筆者の訪問時には、クラシックとインド音楽が融合した楽曲が選ばれ、異なる音楽体系が交わる独特の響きに身をゆだねる鑑賞体験が提供された。

CONA財団共同設立者のシュレヤス・カルレ。
背後にあるレコードは音楽評論家の遺族から寄贈されたコレクション[筆者撮影]
 机上に並べられたCONAの作品について語る共同設立者のヘマリ・ブータ[筆者撮影]
机上に並べられたCONAの作品について語る共同設立者のヘマリ・ブータ[筆者撮影]

リスニング・セッションの様子
[Courtesy: CONA Foundation]
もうひとつのスペースは、2025年12月から始まる第6回コチ=ムジリス・ビエンナーレのキュレーション陣を務めることが発表された、HH Art Spacesが挙げられる。2014年にムンバイからゴアに移住した、ニキル・チョプラとマドゥヴィ・ゴールがフランス人のロマイン・ルスタウとアルドナ地区に立ち上げた財団で、ライブアートやパフォーマンスアートに焦点を当てた実験的な表現の場で知られる。これまで、国内外の作家や美術機関と協力しながら、南アジアのパフォーマンスアートの基盤づくりをしており、近年はパートナーに写真家のシバニ・グプタとシャーイラ・セケイラ・シェッティ、共同キュレーターにマリオ・デ・ソーザのほか数人が加わり、パフォーマンス以外の表現活動も展開している。チョプラはコチ=ムジリス・ビエンナーレ2014や2022の関連イベントのほか、第53回ヴェネツィア・ビエンナーレやドクメンタ14への参加などの海外での発表も多い。日本では2008年に横浜トリエンナーレや森美術館でも発表したことがある。スペース訪問時は、デ・ソウザ企画の「Feral Ecologies」展が開催されており、歴史や近代化の過程で生じた搾取的な行ないや気候危機が生態系の変化を加速させる現代を取り上げていた。チョプラに来たるビエンナーレについての話を聞くと、予想通りパフォーマンス作品が多くなりそうだという回答が返ってきた。また食についても関心を寄せているようで、どう展示に反映されるか気になるところだ。開催1年前の就任で準備の時間は限られているが、多彩な経歴で構成されたキュレーター陣のコレクティヴの力が生かされるのではないかと期待している。
 HH Art Spaces「Feral Ecologies」展入口
HH Art Spaces「Feral Ecologies」展入口
[Courtesy: HH Art Spaces]
 「Feral Econogies」展示風景
「Feral Econogies」展示風景
[Courtesy: HH Art Spaces]
 コチ=ムジリス・ビエンナーレの調査に訪れた、メイン会場アスピンウォール前でのHH Art Spaces集合写真。写真左から、ニキル・チョプラ、マダヴィ・ゴール、シャーイラ・セケイラ・シェッティ、シヴァニ・グプタ、マードゥリヤ・デイ、ロマイン・ルスタウ、マリオ・デ・ソーザ
コチ=ムジリス・ビエンナーレの調査に訪れた、メイン会場アスピンウォール前でのHH Art Spaces集合写真。写真左から、ニキル・チョプラ、マダヴィ・ゴール、シャーイラ・セケイラ・シェッティ、シヴァニ・グプタ、マードゥリヤ・デイ、ロマイン・ルスタウ、マリオ・デ・ソーザ
[Courtesy: HH Art Spaces]
SAFの海外巡回と文化施設THE BRIJ構想
再びSAFに戻って、SAFの今後について触れたい。回を重ねるごとに強化していると思われるのは、海外の文化機関との関係だ。例えば、英ロイヤル・カレッジ・オブ・アーツ(RCA)とセレンディピティ・アーツ財団は新たに、「シニア・アーティスト・レジーデンシープログラム」を設立した。これは、両機関によって選抜されたインドの中堅作家がRCAに3カ月間滞在制作できるもので、初回はニューデリー在住のスカンヤ・ゴーシュが派遣され、その成果がSAFでの個展「Field Measures」となった。このような、文化機関との協働した財団主導の企画は、フランス国立美術センター(CNAP)との共同企画展やロサンゼルス郡立美術館(LACMA)と共に制作を委託した、生成ゲームにも認められる。財団が一過性の助成先に留まらず、海外機関と能動的に関係を構築することで、インドを含む南アジアのアートを世界に広めようとしているのが読み取れる。そして、さらにSAFの10周年にあたる今年は、プログラムの一部が英国バーミンガムシティー大学(BCU)を含めた10都市に巡回される。現地で会った英国からの調査団らは、市内には南アジアにルーツを持つ住民が多く、ボリウッドのような表現は見慣れているので、違う角度からインド文化を伝えるコンテンツを招聘したいと、熱心に会場視察に励んでいた。芸術祭の参加作家を海外に送り出す動きは、コチ=ムジリス・ビエンナーレにも認められる★4。セレンディピティ・アーツ財団も同様の動きであるといえるが、その規模はほかと一線を画している。確かなことは、自然と文化遺産は豊富にあれども、インフラ整備も途上にある一地方都市から、世界と直接つながるプロジェクトが育っているということだ。
 スカンヤ・ゴーシュ《Field Measures》(2024)。「The Royal College of Art x Serendipity
Arts Senior Artist Residency 2024」展 展示風景[筆者撮影]
スカンヤ・ゴーシュ《Field Measures》(2024)。「The Royal College of Art x Serendipity
Arts Senior Artist Residency 2024」展 展示風景[筆者撮影]
また、創設者のムンジャル氏は、12月のオープニングパーティーにて、2022年に発表された、財団による文化センター「THE BRIJ」建設をニューデリーで進めていることに触れていた。これは、教育と研究、学際的な体験、イノベーション・インキュベーションの三要素を軸にした、美術館、劇場、教育とワークショップ、図書館、劇場、遊び場などを備えた複合施設となる。今後、財団はSAFと都心のBRIJをどう接続するのか未知数だが、2020年代に入ってニタ・ムケッシュ・アンバニ・アートセンターをはじめとする、ビジネスや教育部分野で成功した人々が文化施設を設立する動きが国内で活発化している状況の一端を表わしているといえよう★5。そのなかで、財団は箱ものを造る時点で、SAFで培ったソフトパワーの蓄積をすでにもち合わせている稀有な立ち位置にある。
結びに:地域から
本文では、ゴア州のSAFを取り上げ、芸術祭が多彩な表現の出会いの場となっている様子を紹介した。コチ=ムジリス・ビエンナーレが現代美術に特化する一方、SAFは分野を横断する表現の交流の場として固有のかたちで発展しつつある。本稿では視覚美術を中心に取り上げたが、演劇や食、音楽、ファッションに焦点を当てて巡るとSAFに対してまた違った視点が得られるはずだ。現地では、CONA財団やHH Art Spacesのようなアーティスト主導のスペースが各々独自の流れで活動していることをお伝えしたが、さらに若い作家が運営する場所も生まれているという。異文化を地域に取り込んできたゴアらしく、これらの多くは、州外からの移住者や多拠点居住者によってもたらされている。国の公的支援が現代美術に対してほぼ流れないインドのなかで、セレンディピティ・アーツ財団のような民間が設立した財団の取り組みから、支援していることから、国内の美術事情を垣間見ることもできるだろう。地域のアートシーンが中央や世界に向けて発信する、それぞれの新たな展開を、今後も関心をもって見守っていきたい。
★1──開催の延期と遅延が起きたコチビエンナーレ2022、開催が一度で終了したプネ・ビエンナーレなど。コロナ禍もあり、3年以上開催が遅れた芸術祭もある。
https://artscape.jp/focus/10152669_1635.html
★2──会場作品解説より。
★3──「Diorama of an Exhibition」の冊子内のテキスト「Bringing CONA home」より。
★4──https://artreview.com/hayward-gallery-durjoy-bangladesh-foundation-and-kochi-biennale-foundation-partner-for-new-award/
★5──2020年代に入ってムンバイのNita and Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC)(2023)、バンガロールのMAP Museum of Art & Photography(2023)、カルナータカのHampi Art Labs(2024)、ニューデリーのKiran Nadar Museum(2026年に空港近くに本館開館予定)など、現代美術を扱う私設美術館、文化施設の開館が相次いでいる。