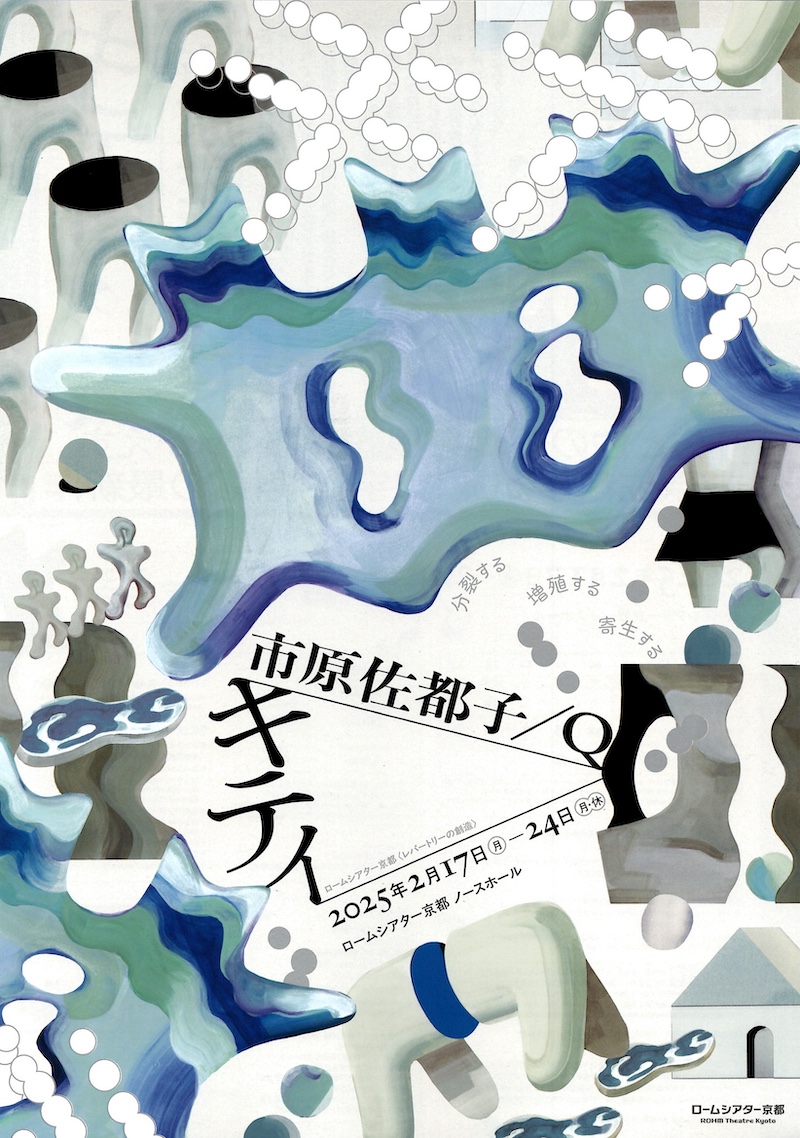
会期:2025/02/17~2025/02/24
会場:ロームシアター京都 ノースホール[京都府]
公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/119939/
スーパーに並ぶ食肉と、性売買の対象となる女の肉。「おいしそうに見せる/淫靡に見せる」ために、ともに「赤い光」で照らされる肉(体)。本作は、肉食/肉欲という「肉」がもつ多義性を起点に、家父長制、女性の家庭内の再生産労働、強制的な性行為というDV、AVというファンタジーで覆われた日常、性被害の日常化、性産業、「生殖に結びつく性」を正しいものとする性規範、家畜/愛玩動物という人間中心的な視点、あらゆるものを商品化する消費資本主義といった問題群をユーモラスかつ挑発的にえぐり出す、市原佐都子の最新作である。こうしたテーマ群は、特に、第64回岸田國士戯曲賞を受賞した『バッコスの信女―ホルスタインの雌』(2019)から引き継ぐものだ。
三部構成の本作では、〈パパ〉と〈ママ〉と暮らす主人公の少女〈ねこ〉の成長の物語が、性と生殖をめぐるさまざまな構造的問題を浮上させたのち、SF的想像力が描き出すユートピアの惑星という壮大な射程を通して、肉食/肉欲をめぐる人間の欲望と禁忌の相関関係をあぶり出す。
一場の舞台は、主人公の〈ねこ〉が暮らす、一夫一婦制の核家族のリビング。帰宅した〈パパ〉が食卓の中央につくと、〈ママ〉が準備した夕食が何も言わずに差し出され、家庭内という私的領域がすでに家父長制の支配の空間であることを暗黙のうちに示す。「ママのつくったアップルパイしか食べたくない」と言う〈ねこ〉に対し、「肉を食べないと、おっぱいやお尻の肉が大きくならないぞ」と圧をかける〈パパ〉。傍らでは、調理道具や食器、食材が置かれた「台所」を示す家型のケージのような舞台装置の中に、エプロン姿の〈ママ〉が立ち続け、専業主婦を再生産労働に閉じ込める家父長制やジェンダー規範という「檻」「独房」を暗示する。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
だが、ある日の夕食で、〈パパ〉は肉だと思って食べていたものが実は大豆ミートだったことに気づいて激怒し、〈ねこ〉の目の前で、「懲罰」として食卓の上で〈ママ〉をレイプする。本作では、主人公以外のキャラクターは、猫のような被り物で頭部を覆い、基本的に台詞の発語はなく、〈ねこ〉のモノローグを介して状況説明がなされる。レイプされる〈ママ〉も、「ニャーニャー」という猫の交尾のような悲鳴を上げ続けるだけだ。猫の被り物と「台詞がないこと」は、個人の顔貌も発語も奪われた動物的な隷属状態に置かれていること、そしてこれが〈パパ〉〈ママ〉という一般名詞で語られる普遍的な物語であることを示す。
その後、〈ママ〉と〈ねこ〉は、〈パパ〉へのお詫びとして、あらゆる種類の肉を買い漁ってつくり上げた料理〈肉ニンゲン〉を差し出す。〈肉ニンゲン〉の造形は、〈パパ〉のカメラロールに入っていた、シリコンで豊胸手術をした若い女性に似せてつくられており、〈パパ〉を魅了しようとバレエの優雅なステップを交えたダンスを披露する。だが、〈パパ〉は「大好きな肉」でできた〈肉ニンゲン〉を拒絶し、もみ合いになった挙句、〈肉ニンゲン〉に刺し殺されてしまう。〈パパ〉の肉は、主人公のペットである猫に食べられ、普段はキャットフードという人工的な加工肉しか与えられていなかった猫に、「菩薩のような満ち足りた表情」という恍惚をもたらす。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
二場では、成長した〈ねこ〉が受付嬢として就職した会社が、実は「AVの撮影現場」だったことが、コミカルかつグロテスクに描かれる。「男性を収入やイケメンかどうかで選別する美人受付嬢が、低収入や非モテの外見のため、女性と一度もセックスしないまま死んだ男の幽霊にレイプされ、射精で成仏する」という荒唐無稽な設定は、AV自体の非現実性と、男性が内面化したミソジニーを痛烈に揶揄するものだ。
ここで特筆すべきは、レイプされる先輩の受付嬢の「顔面=衣裳」の強烈なユーモアである。「両眼」は、真ん中に眼球=乳首のついた「巨乳」に、「唇」は「ヴァギナの割れ目」に置き換えて造形され、口/ヴァギナにペニスが挿入され続ける間、猫のようなあえぎ声が延々と発せられる。フェラチオかつヴァギナへの挿入である「ありえない究極のAV」が、グロテスクな人形劇として演じられる。固有の顔貌と人格を持った個人ではなく、「乳房とヴァギナ」に記号化された欲望の対象として女性を眼差す視線は、女性の顔をヌードのトルソに置き換えてヘテロ男性の性幻想を絵画化したルネ・マグリットの《陵辱》に対する痛烈なアンチでもある。衣裳を担当した南野詩恵(お寿司)の貢献が特に光るシーンだ。
二場の後半では、電車やマッサージ屋、人間ドックなどどこに行っても「知らない間にAVの世界に参加している」こと、すなわちAVのファンタジーで覆われ、性被害が日常化した公共空間に疲弊した〈ねこ〉は、癒しを求めてホストクラブに通い始める。そして、担当ホストをナンバーワンにする資金稼ぎのため、自らも性風俗店で働くようになる。ホストの身体には、高級ブランドを思わせる柄の布でできた巨大なペニスが付いており、自己顕示欲と男性性が誇示されている。だが、担当ホストは動画で炎上して失職し、〈ねこ〉に無理心中を迫った挙句、〈肉ニンゲン〉に刺し殺されてしまう。
 [撮影:中谷利明]
[撮影:中谷利明]
本作の演出上の最大の特徴として、俳優は(終盤をのぞき)生の声で一切発話せず、AIによる人工音声が台詞を語り、かつ日本語・韓国語・広東語の3言語がひとつの台詞の中に「混在」する仕掛けがある。市原は、主人公の〈ねこ〉役を、日本、韓国、香港の3人の俳優に分散して演じさせると同時に、「多言語上演と翻訳字幕」という装置それ自体を「作品内部」に取り込み、演劇を含めて私たちが何を「自然だ」と感じているのかに対して何重にも揺さぶりをかける。
人工音声の使用、特に「エラーのような3言語の混在」は、狂った世界のカオスや歪みを加速させると同時に、登場人物たちが感情や意志のない操り人形であることを強調する。繰り返される「ははははは」という無機的な笑い声は、もはや感情すら摩耗して麻痺した事態を音響的に示唆する。人間/操り人形の区別の撹乱は、前作の『弱法師』(2023)とも共通する演出だ。また、「声」を生身の身体から、そして母語という共同体からも切り離す仕掛けは、国境を超えた構造の普遍性や集合的生命体が登場するSF的展開への「伏線」であるとともに、俳優たちの身体表現の雄弁さに対して逆説的に目を向けさせる。〈ねこ〉は何度も、「しゃっくり」に合わせて、痙攣的に、カクカクと無機質な動作でダンスを踊る。言葉にできない、声に出せない、あるいは沈黙を強いられた苦痛や抑圧が、不随意的な身体反応である「しゃっくり」を伴うダンスとして表出される。AIの声の人工性が際立つほど、身体表現の饒舌さは増していく。

[撮影:中谷利明]
演劇にAIの人工音声を導入することは、一見「不自然」に感じられる。だが、人工音声は、公共交通機関の構内・車内放送などで日常的に流れており、作中で言及される「大豆ミート」「性被害の日常化」などと同じく、すでに私たちの世界の一部を構成している。本物の肉と見分けがつかないまま〈パパ〉が食べていた大豆ミート、豊胸手術で膨らませた胸、AVが描く性幻想を「お手本」とした性行為の蔓延……。「人工物かどうかの見分けがつかない世界」が「日常」「自然」と化していることそれ自体が、まさに「演劇における自然さとは何か」という問いに重ねられているのだ。そしてその射程は、家父長制、ジェンダー規範、「生殖に結びつく性」を正しいものとする性規範といった社会構造の自明性の問い直しをも含んでいる。
このように、本稿の前編では、「現実世界」で物語が進行する前半の一場と二場について考察した。後編では、SF的な想像力で紡がれる三場に移行し、本作のキーとなる〈肉ニンゲン〉とは何かという問いと、主人公が移住する惑星〈アップル星〉を舞台に描かれる「肉」をめぐる欲望と禁忌について考える。また、「宙に浮いたままのリンゴ」という舞台装置により、本作の上演それ自体が「終わりも始まりもないループ構造」に観客もろとも世界を閉じ込めてしまう壮大な仕掛けについても考えたい。
(後編は3月28日に公開予定)
鑑賞日:2025/02/22(土)
関連レビュー
Q『弱法師』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年10月15日号)
Q/市原佐都子 オンライン版『妖精の問題』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年06月15日号)
あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)
市原佐都子/Q『妖精の問題』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月01日号)







