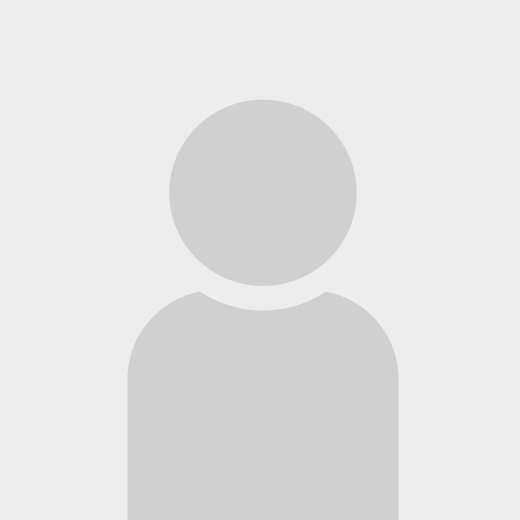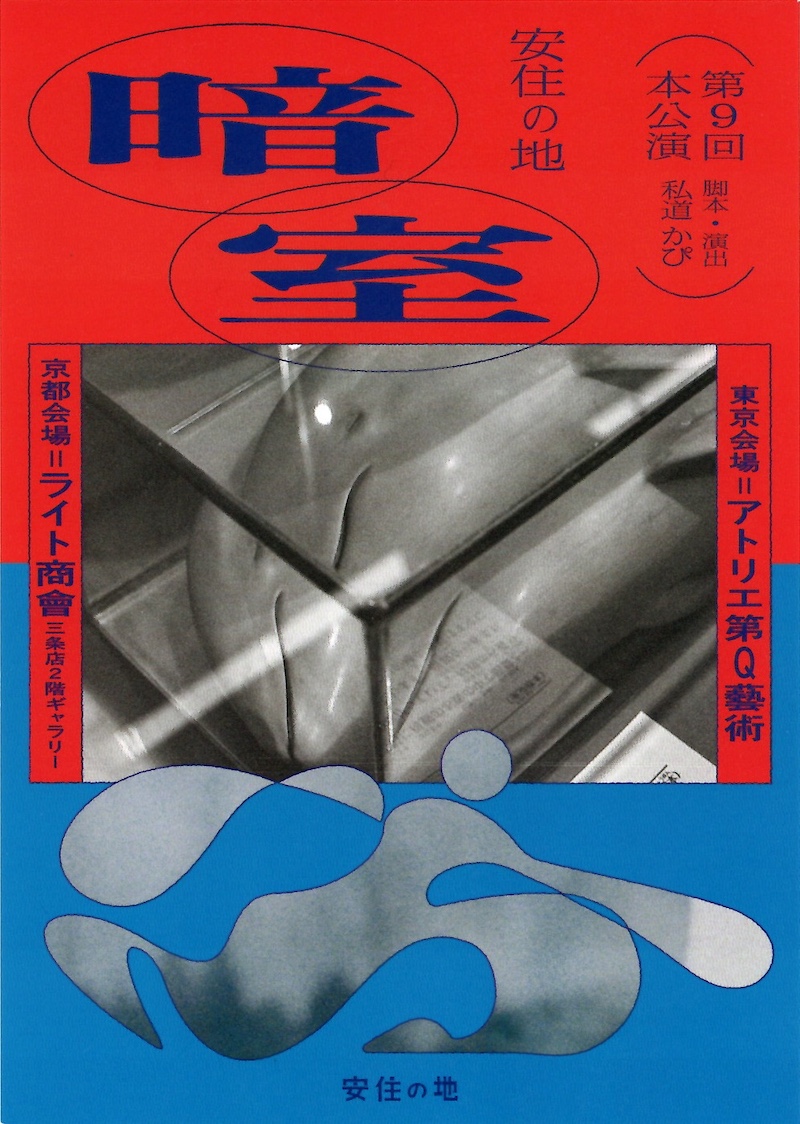
会期:2025/03/18~2025/03/24
会場:ライト商會[京都府]
公式サイト:https://anju-nochi.com/news/work/darkroom/
はじまりは何も見えない暗闇。ポチャンと水の滴る音が響く。天井に小さなオレンジ色の灯がともる。赤い光がゆっくりと空間を満たす。目が慣れてくると、波の揺らぎのように両腕を動かす人影がおぼろげに見えてくる。空中に吊られた何かをそっとつまみ、体の向きを変えて移動し、見えない何かを液体に浸し、重たげな波に腕を沿わせるようにゆっくりと上下させ、指でつまんで引き上げ、目を凝らす。一連のマイムの動作が何度も反復され、次第に速くなり、ダンス的なリズム感の獲得に呼吸の音が重なる。
闇と繊細な光、水音、流れるような美しい所作、息遣い。神経の集中を要するが、深い海中に身を浸しているような安堵も覚える。印象的な導入で始まる本作は、「暗室での現像作業」と「被災した写真の洗浄作業」という、液体をくぐらせて写真を物質としてこの世に残すことに携わる2つのエピソードを交互に描く。戦時中の軍艦内の暗室と、写真洗浄ボランティアの作業場。時代も場所も隔たったエピソードが、美しいマイムの所作で呼応し、「現像液/洗浄液/海水/羊水」と「暗室/子宮/洗浄部屋」という比喩が幾重にも重なり合うことで、死と生命の再生という壮大な射程が描き出されていく。
 [撮影:山下裕英]
[撮影:山下裕英]
交互に語られるエピソードは、暗闇で次第に目が慣れてくるように、あるいは現像液に浸した印画紙に像が浮かび上がるように、次第に明確な輪郭や焦点をもち始める。1つめの舞台は、戦時中の軍艦内に設けられた暗室。上官の 明津 に命じられ、部隊の集合写真や「立派な艦内」の記録を撮影している 波並 という2人の人間関係が、戦況の悪化の示唆とともに描かれる。それまでのように部隊の集合写真ではなく、「隊員を1人ずつ撮影するように」という方針の変更の指示に戸惑う波並。分厚い名簿。波並は着々と任務をこなすが、艦内で撮影した「笑顔の隊員たちの写真」が明津に見つかり、処分するようにと叱責を受けてしまう。
 [撮影:山下裕英]
[撮影:山下裕英]
一方、もう1つのエピソードでは、澄と 海塩 という2人だけで運営する小さな写真洗浄作業場に、 朝来 というボランティアがやって来る。泥水に浸かった写真を乾燥させた後、洗浄液に浸して慎重に洗い、汚れを剥がす作業を教えてもらう朝来。「被災地から離れていても、専門知識がなくても、人の役に立てる社会貢献ができること」に感動してボランティアを志望した朝来は、習得も早く、写真の持ち主から感謝の手紙をもらったことでさらに意志を燃やし、知り合いに声をかけて作業人数と効率を増やそうとする。だが、その「善意の行為」は、この作業場を立ち上げた澄との軋轢を生み、「もう、来ていただかなくて結構です」と告げられてしまう。
 [撮影:山下裕英]
[撮影:山下裕英]
一方、戦況の悪化の示唆とともに、波並には撮影任務終了と下船命令が突然下される。戸惑う波並に対し、明津は「最後の仕事」を頼む。「私が1人で写る写真を撮ってほしい」と。言葉には出されないが、それは遺影である。先に撮影された隊員たちの写真が水中にどれだけ沈んでいるのだろうかと問う明津。「でも大佐、像は、水の中から生まれるんです」と返す波並。彼にとって写真の現像は、唯一、現実に対抗できる手段なのだと。暗い室内で、マイムでカメラをまっすぐ明津に向けて構え、シャッターを切り続ける波並。現像された写真を受け取った明津は、持ち出しが禁じられているカメラを波並に手渡す。「撮り続けろよ」「残し続けろよ」と。
 [撮影:山下裕英]
[撮影:山下裕英]
朝来もまた、海塩を通して、澄の過去と写真洗浄に関わり続けている理由を聞く。海辺の捜索が許可されず、変貌した町で写真を拾い、洗い始めたきっかけ。被災地の大きな体育館で行なっていた写真洗浄作業。実直だった夫の浮気が写った写真が明るみに出てしまい、妻の激しい抗議を受けたこと。澄は施設を行政に託して辞めるが、閉鎖された。その後、澄が個人で立ち上げた洗浄作業場で、海塩も再び一緒に活動を始めた深い縁。海塩がボランティアを始めた頃、洗浄に失敗して顔の表情が流れてしまった写真の被写体が、行方不明になった澄のきょうだいだったのだ。
どうにもならないことがあるとわかっていても、果てしなくても、目の前で消えかかっているものを今だけでも留めたい。澄は祈るような気持ちで写真洗浄を続けていることを朝来に話し、わだかまりが解けた2人は並んで淡々と洗浄作業を行なう。たゆたう波のような腕の動きがシンクロし、海塩が加わる。そこに、波並と明津を演じていた俳優も加わり、現像液に印画紙を浸す動き、洗浄液に浸けて写真をゆすぐ動き、現像液から引き上げたプリントを確かめる動き、汚れの落ち具合を確認する動きが、円陣と反復のなかで次第に混ざり合っていく。見えない何かをそこに見て、晴れやかになる表情。そこには、「海中から戻ってきた写真」を再び手にした死者も混ざっているのか。美しく余韻の残るラストだ。
 [撮影:加藤優里]
[撮影:加藤優里]
現像液の中から現われる像。洗浄液の中から(崩れかけつつも)再び現われる像。海水に浸かり、再び戻ってきた写真。これから海底に沈むかもしれない写真。国家的威厳/個人のプライベートという大きな隔たりはあるが、そのなかには、ともに「表に出せない写真」もあること。写真の命を奪う海水。消えかけた命を繋ぎとめるための水。これから現われる、あるいは消えかかった像をこの世に留めるために紡がれる手の動き。その反復と美しさ。
本作では、時代も場所も隔たった2つのエピソードの交差と、詩情に満ちたモノローグを介することで、「写真」というまさに近代の産物によって日本の近現代史に射程を当てつつ、「生命体としての写真の死と再生」という壮大な視座が浮かび上がる。写真が浸される液体は、死を与える海水であり、(再び)命を与える羊水でもある。そのとき通過する「暗くて狭く、独特の臭気がこもる部屋」が、暗室/子宮/洗浄作業場だ。現像液に含まれる酸の、鼻を刺す臭い。泥水に浸かった写真の放つ臭気。命の終わりを迎えた物質が放つ匂い。
だが、澄は言う。泥水に浸かった写真の像が溶けても、「完全になかったこと」には決してならないと。像が消えて見えるのは、銀塩プリントに使われたゼラチンをバクテリアが食べたためであり、バクテリアの体内に吸収されて、別の形で生き続けるのだ。写真(紙焼き写真)は、私たちと同じ有機生命体である。写真には、「暗室」という命が始まる場所がある。私たちもかつてそこにいた。

[撮影:山下裕英]
本作が描くのは、「遺影の撮影者」「洗浄作業者」という、写真そのものには写らないが、記憶を留め、残そうとする営みを紡ぐ人々の存在と、波のように反復される手作業である。また、作・演出を手がけた私道かぴによる戯曲では、暗室・洗浄作業の描写が、いわゆるト書きではなく、小説のような詩情あふれる文体で描かれていることも特筆すべきだ。同じく私道の作による安住の地『かいころく』も、小説のような文体を駆使して、「養蚕」という視点から、「生命の誕生と死」というスケールと重ね合わせて近現代史を描く点で通底する。続編ともいえる本作もまた、近代性の刻印と物質性を帯びた「写真」に仮託して、生命と記憶が紡ぎ出される営みを、静謐な詩情とともに描く秀逸な作品だった。
鑑賞日:2025/03/23(日)
関連レビュー
安住の地『かいころく』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年10月01日号)