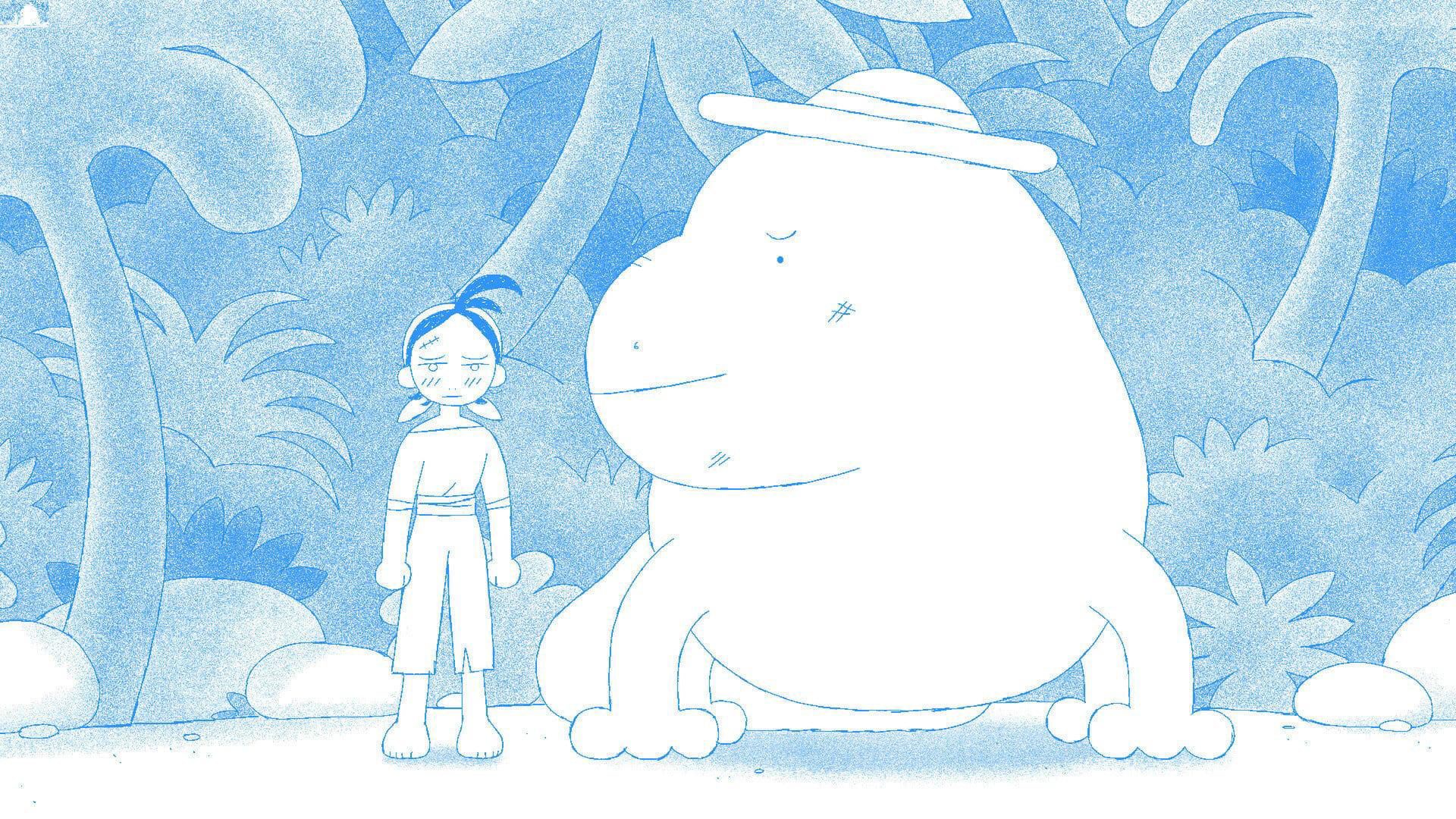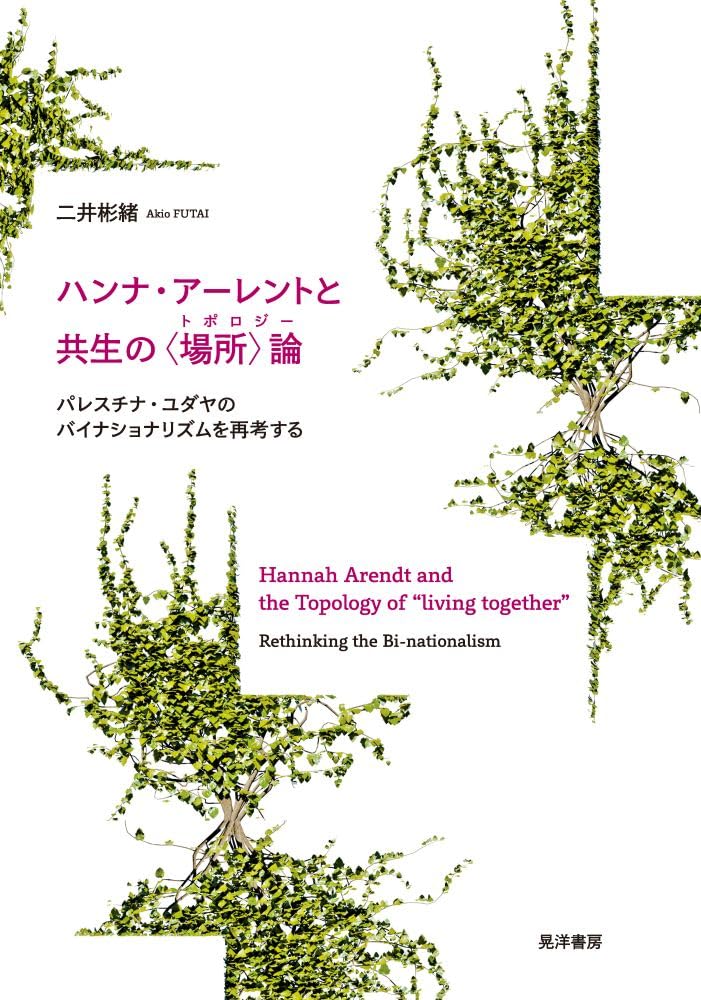
発行所:晃洋書房
発行日:2025/02/20
公式サイト:https://www.koyoshobo.co.jp/book/b657721.html
この文章を書いている2025年4月7日をもって、イスラエルによるガザ侵攻から1年半が経過した。この間、イスラエルによる大規模な空爆等によって、犠牲になったパレスチナ人は5万人以上にのぼる。もちろん、それはここ1、2年に限られた話ではない。今日にいたるまでの75年以上にわたり、彼の地でパレスチナ人たちが被ってきた被害の大きさは筆舌に尽くしがたいものがある。歴史家イラン・パペの言葉を借りれば、1948年以来世界が目撃してきたのは、史上類のない「漸進的ジェノサイド(incremental genocide)」にほかならない。
そのような状況のなかで上梓された本書は、思想家ハンナ・アーレント(1906-75)が1940年代に提唱した「バイナショナリズム(bi-nationalism)」論を詳細に検証した労作である。アーレントの思想は近年ふたたび大きな注目を集めており、日本語にかぎっても、ここ数年重要な研究書が続々と現われている。そのなかでも、パレスチナ人とユダヤ人の共生国家の建設にむけた思想にして運動である初期のバイナショナリズム論には、さほど大きな注意が払われてこなかったか、あったとしても不十分なものにとどまってきた──本書はその事実にこそ注目する。
その背景には、初期アーレントの共生国家論が、ある種の危うさを秘めているという事実があるだろう。1940年代にアーレントが唱えたユダヤ軍創設論やバイナショナリズム論は、その時代状況を考慮せずに表面的な議論だけを追ってしまえば、後年の非−暴力論から切り離された「実力行使」の肯定にも読まれかねない。げんにアーレントの議論は、当時のシオニズム主流派からもしばしば疑念を呈されてきた。こうした状況を打破すべく、本書の第一部「パレスチナという『革命』」で、著者はこの初期アーレントの議論を丹念に検証する。その結果として明らかにされるのは、アーレントのいう「ユダヤ軍」とは、離散したユダヤ人が集結し、世界に現われるための方法であり、あくまで強制収容所の解放を主目的とする──つまり、主権国家には結びつかない──軍事力の構想だったということである(33頁)。
むろん、本書が取り組むのは初期アーレントの議論にはとどまらない。本書の第二部および第三部は、『人間の条件』『革命について』『エルサレムのアイヒマン』といった1960年代までのアーレントの仕事に視野を広げ、そこに一貫して見て取れる「共生」の思想を慎重に追跡していく。そして、著者はそれをひとつの〈場所〉論として練り上げることで、これまで相対的に等閑視されてきた初期アーレントの思想を忘却から救い出そうとするのだ。(なお、本書がおもな対象とするのは、アーレントにおいて〈場所〉論がひとつの区切りを迎える『エルサレムのアイヒマン』までの仕事である。)
冒頭で述べたような惨禍のなかで、パレスチナ人とユダヤ人の「共生」を論じることには大きな逡巡をともなう。本書の「はじめに」がそのような問題意識から始められているのも、著者の偽らざる思いの反映だろう。ガザの惨状が日々報じられる現在の状況下で、アーレントの初期思想をこのように読み、提示するのは勇気の要ることである。そのような葛藤のうえで、本書は初期アーレントの連邦国家論、およびその生涯を賭けた共生の〈場所〉論を、「停戦」や「和平」へとむけた選択肢として読みなおすことを訴える。著者が強調するように、それは生涯の約四分の一(1933年から51年まで)を無国籍者として過ごしたひとりの難民、ないし〈場所喪失〉者としてのアーレントにとって、このうえなく切実な理論=実践であったはずだ。
2025年のガザでは、いまなお「人間の恥」(プリーモ・レヴィ/岡真理)というべき事態が進行している。アーレントの「共生」論が提起されたのは今から半世紀以上前のことだが、イスラエル・パレスチナ問題がいまだ解決にいたる気配はない。そのような状況が続くかぎり、本書で論じられるアーレントの議論が、過去のものになることはありえない。
執筆日:2025/04/08(金)