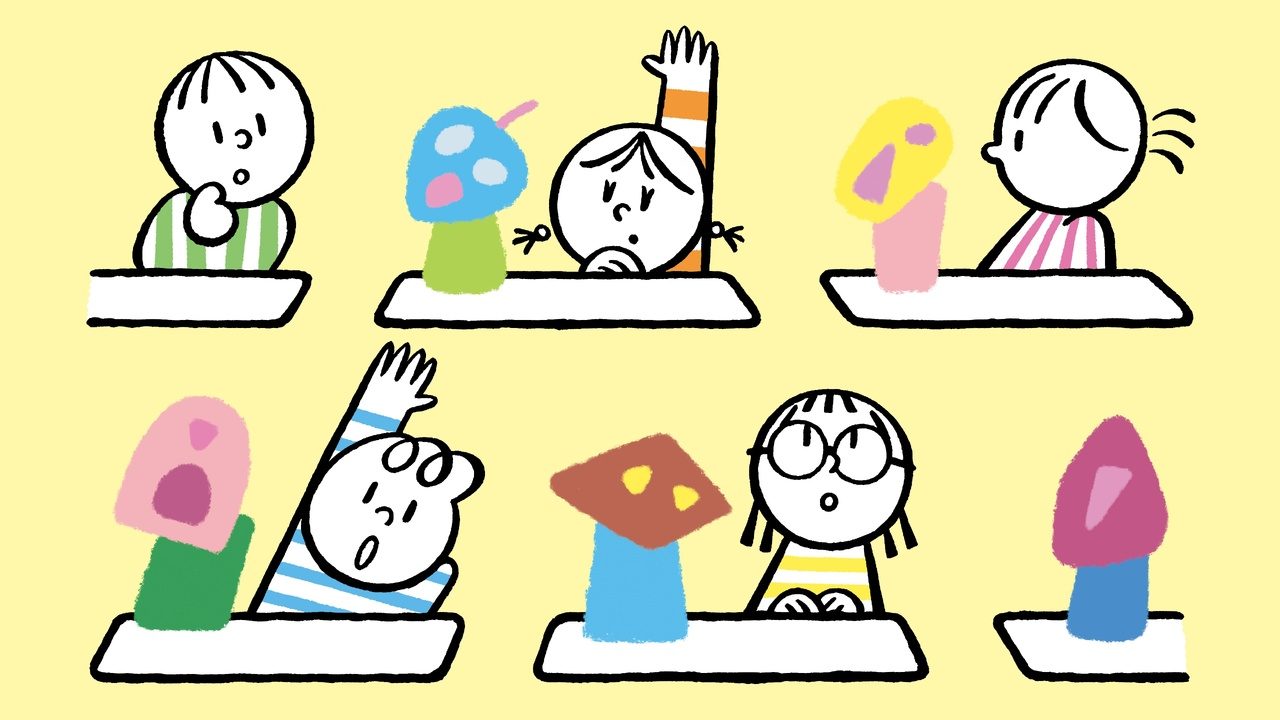会期:2025/03/01~2025/04/06
会場:群馬県立近代美術館[群馬県]
公式サイト:https://mmag.pref.gunma.jp/exhibition/exhibition-4949
ホセ・ダヴィラは、20世紀を代表する前衛芸術家や建築家の作品を引用、考察することで知られる作家である。群馬県立近代美術館で開催された本展「ホセ・ダヴィラ 私は目を閉じて見るほうがいい──ジョゼフ・アルバースとの対話」では、ジョセフ・アルバース(1888-1976)の代表的なシリーズである「正方形讃歌」と、ダヴィラによるアルバースへのオマージュが並置して展示された。
アルバースはアーティストであると同時に、戦後を代表する芸術家たちを育てた美術教育者としての側面でも知られている。バウハウス初期のワイマール校の一期生としてヨハネス・イッテンに学び、後に自身も美術教師としてバウハウスを始め、ブラックマウンテン・カレッジとイェール大学で教鞭をとり、制作と教育活動を往還するなかで、素材、色彩、造形について探求した。彼はバウハウスがナチズムの圧力により縮小を続け完全閉鎖された後、フィリップ・ジョンソンの紹介で渡米、ブラックマウンテン・カレッジに携わるようになる1940年代から実験的な色彩研究を始めた。1963年には色彩論をまとめた書籍『Interaction of Color』を刊行する。同書でアルバースは、色彩が単独で存在するのではなく、周囲の色との相互作用や文脈によって知覚が変化する相対的な媒体であると説き、色彩を理論として学ぶのではなく、体験を通じて見る方法を養う実践的な教育を重視した。
「正方形讃歌」(1950-76)シリーズは、そんなアルバースの色彩に対する読解と知覚の仕組みを可視化した代表作である。入れ子状に配置された四角形にさまざまな色彩を組み合わせ、視覚的な前後関係の揺らぎや、色と色のあいだで生まれる相互作用を探求している。
対してダヴィラは、ステンレスと工業用塗料で作られたフレームを組み合わせたモビールや、手作業で成形したセラミックを積層した作品などを通して、アルバースが平面で展開した色彩の視覚的効果を三次元空間へと拡張する。動的に揺れ動き、時間とともに変化するモビールは視覚的に空間を変容させる。
また、アルバースの「正方形讃歌」をよく観察すると、色彩のコンポジションの外縁に白い余白が設けられていることに気づく。環境とのあいだに生まれるさまざまな相互作用は、作品の内側だけでなく、外側に広がる要素を意識させる。ダヴィラのレリーフもまた、白い金属棚の上に配置されるなど、余白を作品構成の一要素として捉える両者の共通したアプローチが見て取れる。
本展のタイトルに引用されたアルバースの言葉★は、アルバースの観察眼を象徴している。見ることを視覚的な操作として捉えるのではなく、自己の内側にある抽象的な環境に意識を向ける実践によって初めて獲得される知覚に言及しているようである。
鑑賞日:2025/03/25(火)
★──「私は目を閉じて見るほうがいい」というタイトルは、アルバースがインタビューに答え、「私にとって、抽象は現実だ。たぶん自然より現実だ。(中略)抽象は私の心の近くにある。私は目を閉じて見るほうがいい」と語った言葉から取られている。