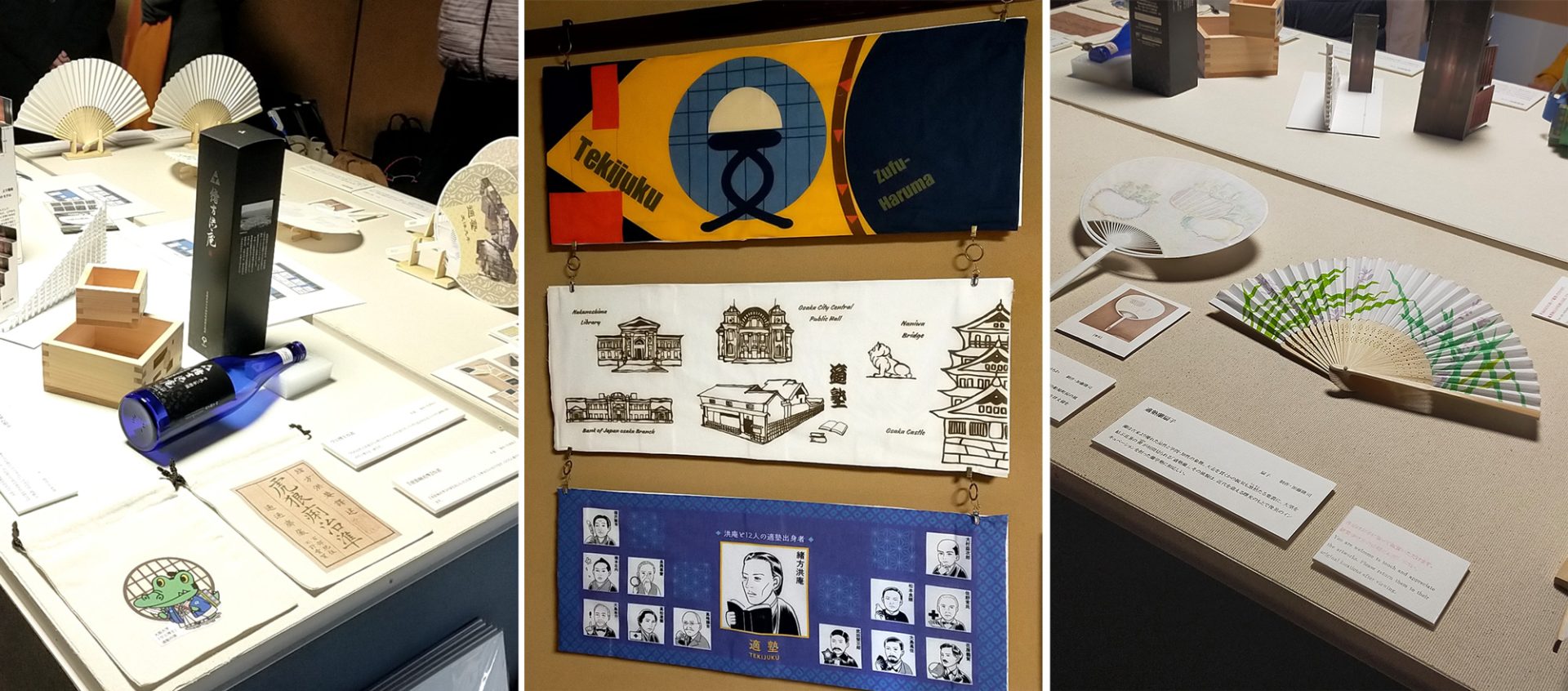日本におけるオペラのその独特な広がりの歴史を追うことは、西洋文化の受容の歴史を追うことでもあるのかもしれない。昨年のベルリンでのオペラの上演事情のレポートに続き、演劇研究を専門とする内野儀氏に、国内ではもっとも人気のあるオペラの演目のひとつ『カルメン』の近年の演出に表出する、グローバル化が進んだ先の西洋文化の現在性について紐解いていただいた。(artscape編集部)
はじめに──〈ガラパゴス進化形〉の日本のオペラ
おおよそ一年前、本サイトに「オペラを追跡する」として、ベルリン長期滞在での経験を生かし、ドイツを中心としたオペラの〈演劇的現在〉について寄稿した。そこでは特に、「演出家のオペラ」と呼ばれる1970年代以降のオペラにおける演出的特色について、「読み替え」「脱植民地化」「多様性」と互いに重なり合う三つのカテゴリーで現状の説明を試みた。
その後日本では、2024年10月上演された東京二期会のリヒャルト・シュトラウス『影のない女』におけるペーター・コンヴィチュニー演出が物議を醸して話題となった。例えば朝日新聞は、11月7日付けで「『改変』オペラがあぶり出したもの 原典に忠実たれ、求める日本」なる記事を掲載し、3人の識者の意見を掲載した。現代的な視点を持ち込んだために、「作品の数少ない最高の聴きどころである部分を確信犯的にカット」(岡田暁生)したコンヴィチュニー演出について、長木誠司は欧州のオペラ演出を参照すると、「過激さ加減で言うと上の下くらいの程度」とし、「作曲者の書いた通りのものを聴きたいのか、それともオペラという『演劇』を通して何か新しい世界をつかみたいと思うのか。日本という国に、前者の方が圧倒的に多いということだ」と語っている。さらに片山杜秀は、「明治以降の教養主義がガラパゴス的に進化した結果、原典に忠実たれという志向を持つ人たちが現代のクラシックファン層の中心になったことが背景にある」と続けている。また、この記事を担当した吉田純子編集委員は、「演劇的発想による斬新な演出に対する過剰なまでのハレーションは、劇場文化の欠如という日本特有の問題をもあぶり出している」とも記している。
ここでいう「改変」オペラが「演出家のオペラ」とほぼ同義であることから、どのように「ガラパゴス的に進化した」「教養主義」的オペラが日本で見られるのか、演劇が専門の筆者は素朴な疑問を抱いた。上記でもわかるように、この問題には演劇が関わっているからである。
だがそこには、吉田も指摘する日本における劇場文化の特異な発展の軌跡という主題が含まれ、「西洋文化の受容」という大きな歴史問題も横たわっている。はたまた近年のグローバル化の影響、つまりは、日本における〈ガラパゴス進化形〉の教養主義がもたなくなった──だからこその『影のない女』「改変」上演と論争──20世紀終盤以降、という時代背景も関わってくる。そのうえ、ここ数年、具体的にはトランプ再登場によって明らかになったグローバル化の〈終焉=強制終了〉という新たな、しかし決定的な時代環境の変化をも視野に入れる必要までもが生じる可能性がある。
グローバル化の〈終焉=強制終了〉は、エマニュエル・トッドのいう「西洋の敗北」の兆候的事例であり、それはつまり、リベラルデモクラシーの失効と呼べる〈規範の喪失=強制終了〉である★1。わたしたちが生きつつあるこの〈世界〉は、〈法〉ではなく〈感情〉が、マスメディアでなくSNSが、
とするなら、スラヴォイ・ジジェク/ムラデン・ドラーのように「オペラは二度死ぬ」というレトリックで、オペラの圧倒的な〈勝利〉をなかば逆説的に言祝ぐというアイロニーの身ぶりも無効になったということだろうか★2。あるいは、「ガラパゴス的」「進化」によって、日本のオペラは、そうした事態を回避することができているのか。はたまた、西洋文化の長い受容史のうえで展開している日本のオペラに、「西洋の敗北」が何らかの兆候を示しているということは、
かなり先走り、また誇大妄想的な問いを並べまくった感があるが、こうした思考にわたしがとらわれたのは、かのニーチェが、一時期熱烈に崇拝していたヴァーグナーを批判するのにあたって依拠した(「ヴァーグナーの場合」、1888)ジョルジュ・ビゼーの『カルメン』(1875年初演)が初演から150年を迎えるにあたり、2025年のほぼ同時期に、二つの上演が東京で行なわれたからである。
『カルメン』の日本受容
日本における『カルメン』受容はかなり特異な経路を辿っている。端的に言うなら、まず、オペラの楽曲がパーツごとに切り出された多様な演奏形態を通じて知られるようになり、その後、大衆文化の領域にも拡張し、それから「原典」の上演が行なわれるという〈下から上〉への道筋だったのである。その結果、『カルメン』は日本でもっとも人気のある演目のひとつとなった。
オペラが未発達であった日本において『カルメン』は、「原典のまま」上演、つまりオペラとして全体が上演されるのに、初演からずいぶんと時間を必要とした(オペラとしての初演は1919[大正8]年のロシア大歌劇団来日公演とされるが、ロシア語上演)。とはいえ、オペラ内の楽曲はかなり早い時期から日本で知られていたことは、井上登喜子の『オーケストラと日本人』(アルテスパブリッシング、2025)が、わざわざ一章をもうけて、「カルメンを愛した日本人──ジャンルを横断するオペラ抜粋レパートリー」(pp.109-129)として、集中的に論じていることからも理解できる。原典のオペラではない管弦楽や吹奏楽(軍楽隊)、あるいはアリア演奏の事例は多数あり、浅草オペラの根岸大歌劇団が1922(大正11)年に日本人の手によるオペラとしての初演を行なった。その後、当時のスター歌手であった藤原義江を中心として結成された藤原歌劇団による上演(1935年以降)が続き、戦後はその藤原歌劇団と二期会という日本のオペラ界を牽引した主要団体が、頻繁に『カルメン』を上演することになった。
『カルメン』の日本受容の特徴は以上のように、オペラそのものが未発達なジャンルだったために、その一部が大衆文化を含む多様な回路でまず先に流通し、そののちに「原典」の上演が行なわれたという経緯を辿ったことである。オペラとしての上演がデフォルトになっても、周知のように、字幕装置が未発達の段階では、オペラの日本語翻訳上演が主流を占めていたことも、日本(だけではないが)のオペラ文化の特徴である。つまり、徐々に、時間を逆流するように、フランス語による真の意味での「原典」上演へと近づいていったのである。そして現在、『カルメン』のオペラとしての上演回数に加えてオペラ内楽曲の別形態での演奏回数は、とうてい数え切れないものになっており、日本における音楽的〈想像の共同体〉の構成要素のひとつに『カルメン』にまつわる〈さまざま〉が混在していると想定できる。これが、オペラというジャンルそのものというより、『カルメン』という特定の作品における日本における「ガラパゴス的進化」の核心である。
二つの『カルメン』──その概要
本稿で取り上げる二つの上演のうち、東京二期会オペラ劇場(以下、二期会)★3の『カルメン』(2025年2月20、22、23、24日)は、フランスのイリーナ・ブルック(1962-)演出だった。もうひとつの新国立劇場のバージョンは2021年初演だが、当時コロナ禍にあって演出に制限すべき部分があったところ、今回はフルに実現するということで演出家を再招聘しての再演となった(2025年2月26日、3月1、4、6、8日)。演出は、スペインのパフォーマンス集団ラフーラ・デルス・バウス所属メンバー、アレックス・オリエ(1960-)が担当した。
上演メンバーとしては、二期会のほうは、従来通りの座組みで、二期会所属会員の歌手を揃え、主役級はダブルキャスト、オーケストラは読売日本交響楽団、指揮が沖澤のどかという陣容。新国立の方も従来通りで、ミカエラをのぞく主役級歌手と指揮者が海外勢で、東京交響楽団が演奏した★4。
両者ともに、大枠では「読み替え」演出に当たる。ブルックは舞台を近未来の廃墟感あふれる「砂漠の無人地帯」(第1幕、公演プログラム、p.6)にした。2幕は同じ舞台装置ながら小道具などで集会場あるいは共同生活の場的変化を示し、3幕は空漠とした荒地、4幕は上手に装置が何もない空間、下手に闘牛場をイメージさせる中が見えない赤の布張り空間である。
 東京二期会『カルメン』より[写真提供:公益財団法人東京二期会/撮影:寺司正彦]
東京二期会『カルメン』より[写真提供:公益財団法人東京二期会/撮影:寺司正彦]

東京二期会『カルメン』より[写真提供:公益財団法人東京二期会/撮影:寺司正彦]
一方のオリエ演出では、現代日本のスペイン祭におけるロック・コンサート会場(第1幕)という設定である。2幕はライブハウスの楽屋、3幕は場末の裏路地、4幕はフェスの会場に戻る。ブルック版では次第に装置類が減ってミニマルな装置になっていくのに対し、オリエ版では全幕を通し、コンサート会場的な巨大な鉄骨組みが舞台の背後や額縁の外枠に見えたままにされた。
 新国立劇場『カルメン』より[提供:新国立劇場/撮影:堀田力丸]
新国立劇場『カルメン』より[提供:新国立劇場/撮影:堀田力丸]
 新国立劇場『カルメン』より[提供:新国立劇場/撮影:堀田力丸]
新国立劇場『カルメン』より[提供:新国立劇場/撮影:堀田力丸]
こうした時代・場所の設定をしたので、両バージョンとも多方面の「読み替え」が必然となった。主だったものでは、ブルック版でのカルメンを含むタバコ工場の女たちや街の子どもたちは〈難民の群れ〉に、ドン・ホセは難民キャンプの監視兵に見える。オリエ版では、カルメンは実在した伝説的な女性ロック歌手(エイミー・ワインハウス、1983-2011)のイメージとなり、群衆は「推し活」のファン(エスカミーリョのファンにもなる)、盗賊団は麻薬の密売人、ドン・ホセは警備のための日本の警察官である。衣装もまたこの設定に従い、時代的・文化的な関係性が可視的なものになっている★5。
 東京二期会『カルメン』より[写真提供:公益財団法人東京二期会/撮影:寺司正彦]
東京二期会『カルメン』より[写真提供:公益財団法人東京二期会/撮影:寺司正彦]
「読み替え」の評価と効果(ハレーション)
当該二公演はともに、このように原典の文脈を離れ、現代日本の観客への近接を試みていると、ひとまずは言っておける。したがって、『カルメン』につきまとう「ファムファタール」や「ロマ」の問題、つまりは〈他者の他者性〉表象の不可能性という問いは横に置かれる。カルメンは、具体的なロマ性(=歴史性)を剥奪され、〈難民〉/芸能人として、「自立した女性」という同時代のクリシェ的形象に限りなく近づくのである。そのため、「ファムファタール」として男性視線に
 東京二期会『カルメン』より[写真提供:公益財団法人東京二期会/撮影:寺司正彦]
東京二期会『カルメン』より[写真提供:公益財団法人東京二期会/撮影:寺司正彦]
このように二つの『カルメン』の「読み替え」は、日本の観客を念頭に置いた現代化/近未来化でありつつも、悲劇(性)という〈普遍〉に加え、「推し活」や難民問題のようなグローバルな時事系の主題まで取り込むことで、そしてまた、大陸ヨーロッパ──フランスとスペイン──を拠点とする二人の演出家を招聘することで、グローバル化したオペラ文化の同時代的文脈に位置づけ可能な上演となる。
先述した『影のない女』演出と比すまでもなく、過激というより穏当と形容すべきと思われる「読み替え」上演の二つの『カルメン』は、それでも演出面での賛否両論を引き起こしはした。つまり、演出家の原典解釈の相違レベルで了解(=批評)可能な上演だったということである。
なかでもブルック版は、そもそもオペラ・コミック様式で書かれた本作について、話し言葉(セリフ)もレシタティーヴォ(朗唱)もすべてカットしたことの意味が問われることになった★6。歌唱だけで物語が進行するのである。この試みは前例があまりないらしいかなり大胆な「改変」だが、あくまでも音楽的な──音楽優先の──「読み替え」だったためか、『影のない女』上演時のような大きな論争にはいまのところなっていない。
ブルックは公演プログラムの「誰にも支配されていない土地で」で書くように、「セリフをカットすることで、非常によいテンポとなり、感情がどんどん繋がっていく感覚があ」り、「通常ではセリフで説明される内容は、動きなどでしっかりと表現することで、物語も繋がるようになってい」くと考えたという(公演プログラム、p.31)。ここに、指揮の沖澤のどかの手腕と読売日本交響楽団の高い技術力が加わり、セリフによる説明──物語を前に進めるための
 新国立劇場『カルメン』より[提供:新国立劇場/撮影:堀田力丸]
新国立劇場『カルメン』より[提供:新国立劇場/撮影:堀田力丸]
 新国立劇場『カルメン』より[提供:新国立劇場/撮影:堀田力丸]
新国立劇場『カルメン』より[提供:新国立劇場/撮影:堀田力丸]
このようにブルック版の上演は、『カルメン』が文脈的に内在させる、〈他者の他者性〉の登記/消却といったリベラルデモクラシー的規範の〈外〉にある、無根拠なのに現実を構成してしまう「感情政治」の同時代的〈闘技場=アリーナ〉を指し示してやまない。オリエ版の『カルメン』がグローバル化したオペラの典型的事例としての
★1──エマニュエル・トッド『西洋の敗北:日本と世界に何が起きるのか』(大野舞訳、文藝春秋、2024)
★2──スラヴォイ・ジジェク+ムラデン・ドラー『オペラは二度死ぬ』(中川徹訳、青土社、2003)
★3──二期会の名称はすでに出ているが、今回の上演は東京二期会によるもの。東京二期会の現在の名称は「公益財団法人東京二期会」である。二期会は1952年、16名の声楽家が結成した団体がその始まりで、多様な音楽活動を展開するなか、オペラ公演の部門が財団法人二期会オペラ振興会(1977)となる。さらに2005年、声楽家団体「二期会」を包含して、公益財団法人東京二期会として再スタート。現在、会員・準会員を合わせ2700名を数える。また、各地の在住者により、1964年「関西二期会(現在「公益社団法人関西二期会」)」、北海道二期会(現在「一般社団法人北海道二期会」)、1970年「名古屋二期会(現在「一般社団法人名古屋二期会」)」、1973年「中国・四国二期会」(現在「中国二期会」「四国二期会」に分離)、2010年「大分二期会」が創設され、それぞれが独自の活動を展開しているという(東京二期会ホームページ「公益財団法人東京二期会について」を参照)。
★4──『カルメン』2作のスタッフ・キャストなどの比較は下記の通り。
| 主催・制作団体 | 東京二期会 | 新国立劇場(NNTT) |
|---|---|---|
| 演出 | イリーナ・ブルック | アレックス・オリエ |
| 美術・装置 | レスリー・トラバース(装置) | アルフォンス・フローレス(美術) |
| 衣装 | イリーナ・ブルック | リュック・カステーイス |
| 指揮 | 沖澤のどか | ガエタノ・デスピノーサ |
| 管弦楽 | 読売日本交響楽団 | 東京交響楽団 |
| 会場 | 東京文化会館 大ホール | 新国立劇場 オペラパレス |
| 公演日程 | 2025年2月20日、22日、23日、24日 | 2025年2月26日、3月1日、4日、6日、8日 |
| 東京二期会 | 新国立劇場(NNTT) | |
|---|---|---|
| カルメン | 加藤のぞみ、和田 朝妃 | サマンサ・ハンキー |
| ドン・ホセ | 城宏憲、古橋郷平 | アタラ・アヤン |
| エスカミーリョ | 今井俊輔、与那城敬 | ルーカス・ゴリンスキー |
| ミカエラ | 宮地江奈、七澤結 | 伊藤晴 |
★5──このあたりの説明については、各公演のプログラムを参考にしている。
★6──『カルメン』はパリのオペラ・コミック座のために作曲されたので、楽曲のあいだに話し言葉のセリフが挟まれるのが特徴である。しかし、初演直後にビゼーが亡くなり、エルネスト・ギローがセリフをカットしたうえで朗唱(レシタティーヴォ)版をウィーンでの上演のために作った。こちらは、グランド・オペラ形式となる。今回のブルック版は、セリフがある原典版(アルコア版)を使ったとしており、そのうえで、セリフを全面的にカットしたことが大きな「読み替え」となった。一方、新国立劇場のオリエ版は、公演プログラムの「作品解説」(岸純信)によると、「『カルメン』にはセリフ入りのオペラ・コミック様式の楽譜と、ギローの朗唱入りスタイルが併存し、『朗唱を基本に、ところどころセリフを入れる』折衷版の舞台が多い。今回の新国立劇場のステージも、この折衷版(基本的にオペラ・コミックの体裁を取り、一部、ギロー作の朗唱を挿入)に拠る上演である」としている(公演プログラム、p.13)。