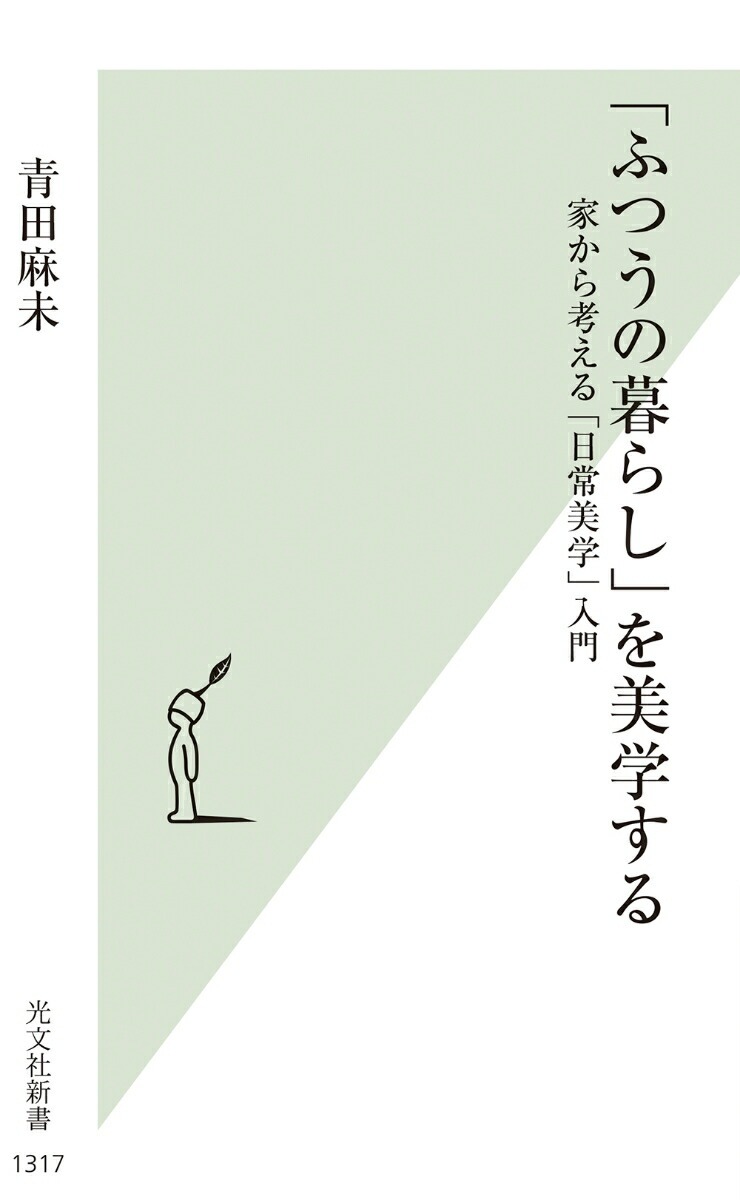
発行所:光文社
発行日:2024/06/30
公式サイト:https://books.kobunsha.com/book/b10125568.html
今世紀に入って本格的に議論されるようになった美学のサブジャンルに「日常美学」というものがある。これは文字通り、芸術作品のような特権的な対象ではなく、わたしたちの日常における感性的経験を対象とする学問分野のことだ。本書は、著者のこれまでの研究と経験の双方にもとづいた、「家」を起点とする日常美学の入門書である。
本書の序章では、なぜ従来の美学に対して、日常美学が「新しい」とされるのかが概説的に語られる。そこで述べられているように、従来の美学は芸術作品をはじめとする特権的な対象にもとづいた「美」の経験(あるいは「崇高」や「ピクチャレスク」の経験)にもっぱら照準を合わせてきた。そこでなおざりにされてきたのは、わたしたちの日常生活をとりまく、より曖昧模糊とした感性的経験である。著者は1970年前後に始まる環境美学の隆盛をその前史に位置づけながら、2000年以後の日常美学の枢要な議論を紹介するところから、本書の議論を始める。
本書のすぐれたところは、各章で大きく取り上げられる具体的事象(対象や現象)と、それを支える理論の組み合わせにある。たとえば、比較的耳馴染みのあるトピックである「機能美」(第一章)については、ここ数年のあいだに開催された「椅子」の展示──「みんなの椅子 ムサビのデザインⅦ」「ジャン・プルーヴェ展」「フィン・ユールとデンマークの椅子」など──が取り上げられ、ウォルトンのカテゴリー論などを参照しながら、「機能美」の精緻な分類が試みられる。他方、掃除や片づけをテーマとする第二章では、シブリーの美的性質論などを手がかりとしつつ、従来の「性質志向」モデルから「行為の過程」を勘案したモデルへの転換の可能性が論じられる。いずれのケースにおいても、読者は椅子や掃除といった具体的事象から、日常美学の主だったアーギュメントをすんなり飲み込むことができるような筋立てになっている。
その後の章でも、中心となる話題は料理(第三章)、地元(第四章)、ルーティーン(第五章)といった、わたしたちの生活と切り離せないものばかりだ。これらの議論においても、著者はしばしばみずからの経験やバックグラウンドを開示しつつ、読者を着実に「日常美学」へといざなっていく。これはおそらく戦略的なものだと思われるが、本書のようなテーマの場合、著者本人の経験をはじめとする自己開示が決定的な意味をもつ。すくなくとも、わたしが同書を最後まで共感をもって読むことができたのは、議論の節々で、仕事と生活の両立に四苦八苦する著者の言葉に共感するところが多かったからだと思う。
そうしたことを考えても、日常美学の魅力と困難は、やはりそれが「わたしたちひとりひとりの」日常と切り離しがたいという事実にこそあるのだろう。世に「わたし」とまったく同じ日常を生きる人は誰ひとりとしていない。著者も言うように、それは日常美学の「ウィークポイント」として捉えられるかもしれない(227頁)。しかしその一方で、さまざまな経験や立場によって日常美学の言説が充実をみせていけば、「わたしたち」の日常をめぐる重なりの大小もまた、より精緻に可視化されることになる。本書が提唱する日常美学の実践は、わたしたちが他者に対して抱く共感と違和のグラデーションを自覚することにも、大いに資するように思われる。
執筆日:2025/06/08(日)







