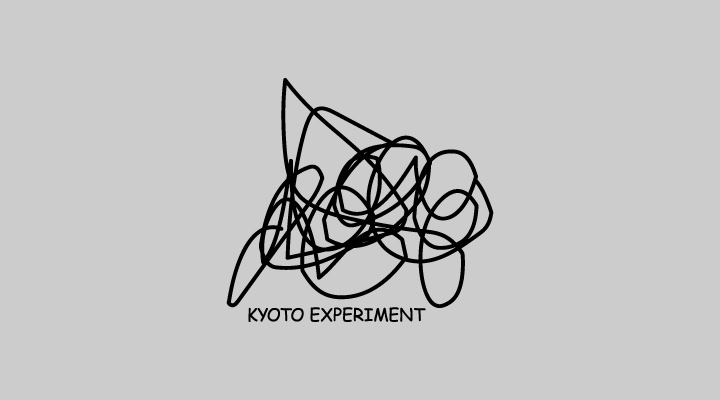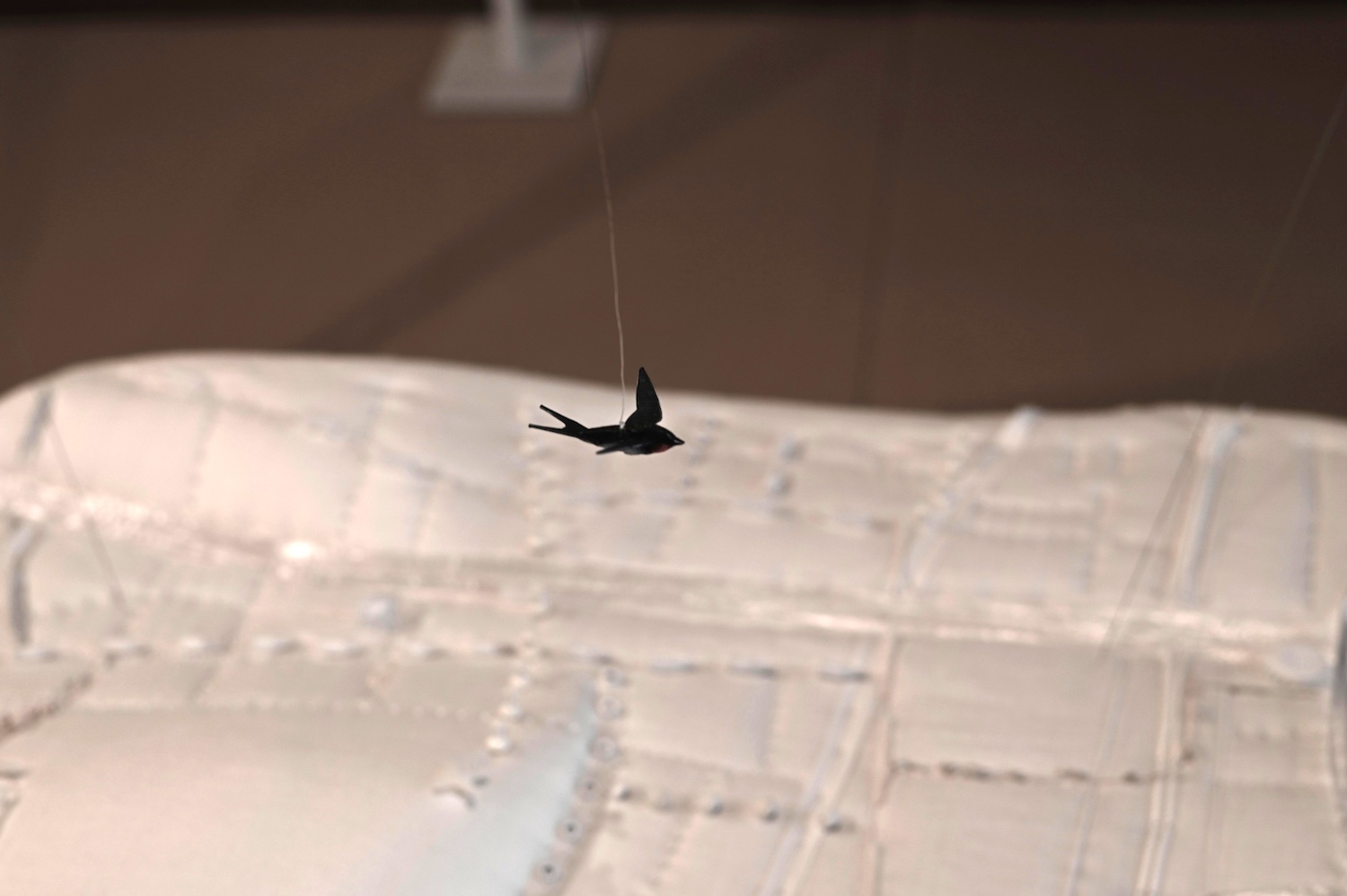会期:2025/10/09~2025/10/13
会場:THEATRE E9 KYOTO[京都府]
公式サイト:https://kyoto-ex.jp/program/jun-tsutsui/
演劇は、アーカイブという物理的装置を介して、歴史の語り方それ自体をどのように批評的に問い直すことができるのか。この問いは、陸軍墓地という日本の近現代史の集積地を多面的に解読する作業から「上演」を立ち上げる本作へと引き継がれる。
『墓地の上演』は、大阪市内中心部にある旧真田山陸軍墓地にまつわるリサーチを元に、演出家・劇作家の筒井潤が創作した計7つの短編で構成される。時代は、西南戦争から日清戦争、日露戦争、日中戦争、アジア太平洋戦争と戦後を経て現代まで、日本の近現代史を貫く。旧真田山陸軍墓地は、1871(明治4)年、陸軍第四師団(当時は大阪鎮台)の拠点であった大阪城の近くに設置された国内最古で最大規模の陸軍墓地である。階級・氏名が刻まれた約5,000基の墓碑、5基の合葬墓碑、そして8,000人以上の遺骨を納める納骨堂がある。
本作の特異性は上演構造にある。実際に上演される5つの短編とその順番は、「観客が一人ずつ引くくじ引き」によって決定される。この「第1の上演」の後、「上演されない短編」の除外も含めて再びくじ引きが行なわれ、上演順序がシャッフルされた「第2の上演」が行なわれる。2024年の初演では、計6つの短編が用意され、各回でそれぞれ5つの短編が異なる順序で上演された(従って、どちらの上演でも必ず1つの短編が脱落するが、「上演されない短編」はない)。一方、今回のKYOTO EXPERIMENT(以下、KEX)の再演では、新たに創作された短編が1つ加わり、「計7編のうち、各回で上演されるのは5編のみ」となったため、「上演されない短編」が必ず1編存在することになる。また、初演と同様、「第2の上演」の一部には、配役の変更やエピソードの追加などの仕掛けが忍ばせてある。従って、くじ引きの結果によっては、「2度目に上演されていたら見られたかもしれない別バージョン」が見られないという欠落も存在する。なお、各上演の後には、ワークシートの質問に答える形で感想をシェアする「対話の時間」が設けられ、観客が再帰的に上演に向き合う時間が組み込まれていた。
 [撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
 [撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
私は初演で大きな感銘を受けたが、KEXでの再演は、また異なる観劇体験と新たな発見をもたらしてくれた。各短編の詳細については、初演の拙評を参照されたい。以下の本稿では、墓地を起点とする定点観測によって見えてくる「時代と価値観の変化」という通奏低音と、「各短編の細部が共鳴する回路」に焦点を当てる。私の観劇した回は、奇しくも、「第1・第2の上演」ともに、最初に上演される短編が「少年」(1945年)だった。そのため、「第2の上演」では、ある順序で一度語られた歴史が、別のバージョンへと分岐していく感覚を強く受けた。また、新たに創作された「未亡人」(1937〜52年)が「第2の上演」のラストを飾るという劇的な上演順序となったため、「もしかしたら新規エピソードが見られないかも……」という期待と諦めを大きくしながら観劇していたぶん、ハイライト感を強く感じた。
「少年」では、大阪大空襲を生き延びたある少年の目を通して、戦時中と戦後をまたぐ「犠牲/加害」の両面と時代の変化が描かれる。玉音放送の後、米兵捕虜の斬首を命じられた兵士が、その後キリスト教に改宗して冥福を祈り続けたこと。戦後、荒れた墓地は子どもの遊び場となり、米兵の相手をするパンパン(街娼)を目撃した少年は、「日本の恥辱」だと感じる。だが、米兵に馬乗りになったパンパンは「日本が勝ってたらアメリカの女の子を抱くやろ。戦時中は特攻に若い男を差し出し、負けたら女を差し出す」と「男性の身勝手な論理」を糾弾する。
 [撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
同様に、女性の性と倫理に向けられる社会的視線の変化を描くのが「未亡人」だ。旧真田山陸軍墓地の納骨堂には、日中戦争開始の1937年以降の死没者の遺骨が納められている。その中には、中国大陸の野戦病院で亡くなった軍医も含まれる。大阪港からの出征を盛大に見送った妻は、同年12月、南京攻略の第一報とともに、夫の遺骨を出迎える式典に参列する。首に下げた箱を(マイムで)手に抱え、「英霊の妻」として涙をこぼすことなく、行列を練り歩いたことが語られる。また、電車内で遺骨の箱をもった人を見かければ、「ご苦労さまでした」と声をかけて席を譲ったという。一方、敗戦後は、戦争未亡人への周囲の態度が一変する。嫁ぎ先で「英霊の妻」として敬意を払われていたが、「子どもはうちと血がつながってるけど、あんたは他人やから」と離縁されたこと。離縁すると、子どもの親権とともに扶助料の支給先も夫の家になるため、裕福でない家では未亡人が厄介払いされた。(英霊の崇拝につながるという理由で)GHQが扶助料を停止したため、役所の窓口に相談するも、「まだ若いんやから、ええ人と再婚して」と済まされてしまう。内職して必死で育てた子どもは、就職面接で「父親のいない欠陥家庭の子」という理由で落とされた。
権威があった存在や崇拝の対象が、時代の変化とともに逆転する構造は、「
 [撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
「未亡人」以外の短編は既に1回以上見ているのだが、初演とは異なる順序で見たこともあり、各短編に埋め込まれた細部どうしのつながりを
「逃げ出した者がいる」という台詞は、前後して上演された「見物」(1894年)において残響のようにこだまする。日清戦争で俘虜となった多数の清国人が、大阪市内を見世物のように歩かされたというエピソードだ。大勢の見物客で込み合うなか、虫かごを首から下げた男は「逃げ出したらこれで捕まえる」と得意そうに連れに語る。「逃げたぞー」という誰かの叫びと群衆のどよめき。人々の好奇の視線に晒された清国人俘虜の行列は、遺骨の箱を抱えて大阪市内を歩いた戦争未亡人の行列とも残像のように重なり合う。
そして、彼女の夫が軍医だったエピソードは、墓地の近くにある高等女学校で墓地の参拝が毎年恒例の行事になっていた「女学生」(1925〜44年)とも接続される。「学級日誌の朗読」では、墓地参拝とともに、映画『病院船』(1940年)を鑑賞したことが語られるのだ。また、「見物」では、収容された清国人俘虜たちが体操を行なう様子にも見物人がいたことが語られるが、手足を伸ばす俳優たちの身体運動は、戦後の墓地がさまざまな市民の集いの場となったことを描く「集い」(1950年~最近)において、ヨガ教室の描写と重なり合う。
こうしたエピソードの細部のリンクは、どの短編をどの順序で上演するかによって、その都度新たな回路として立ち上がるだろう。逆に言えば、上演順によっては、立ち上がることがない回路も存在する。例えば、今回の私の観劇回では上演されなかった「規則」(1904年)では、日露戦争時に持ち帰られなかった遺骨を納めた大連の忠霊塔が、戦後に中国軍とソ連軍に破壊され、現在は公園になっていることが語られる。軍関連施設が「市民が集う公園」に変貌した姿は、「集い」における戦後の墓地の姿とのリンクを潜在させている。
歴史の語りは常に、こうした潜在や欠落を抱えて揺らいでいる。本作は、その揺らぎの構造そのものを「上演」として立ち上げる秀逸な試みである。「単線的かつ完全無欠な唯一のナラティブ」として固定化された国家による大文字の歴史を、「上演」によってどう解体することができるか。そのとき、個人の目線から語られた断片どうしの間に、どう新たな接続の回路が立ち上がるのか。こうした解体と再構築の作業において、観客は傍観者ではなく、責任や権力を負いながら立ち会うこと。その体験は、「異なるバージョンによる別の語り方やアクセスの可能性」が背後に無数に存在することへの想起と同時に、「語られなかった不可視のもの」が必ず存在するという空白や欠落自体を眼差す作業にほかならない。そのとき、墓標が立ち並ぶ「墓地」とは、視線の当て方によって無数の方向を指し示す道標が集積した、巨大で生きたアーカイブとなる。
鑑賞日:2025/10/11(土)