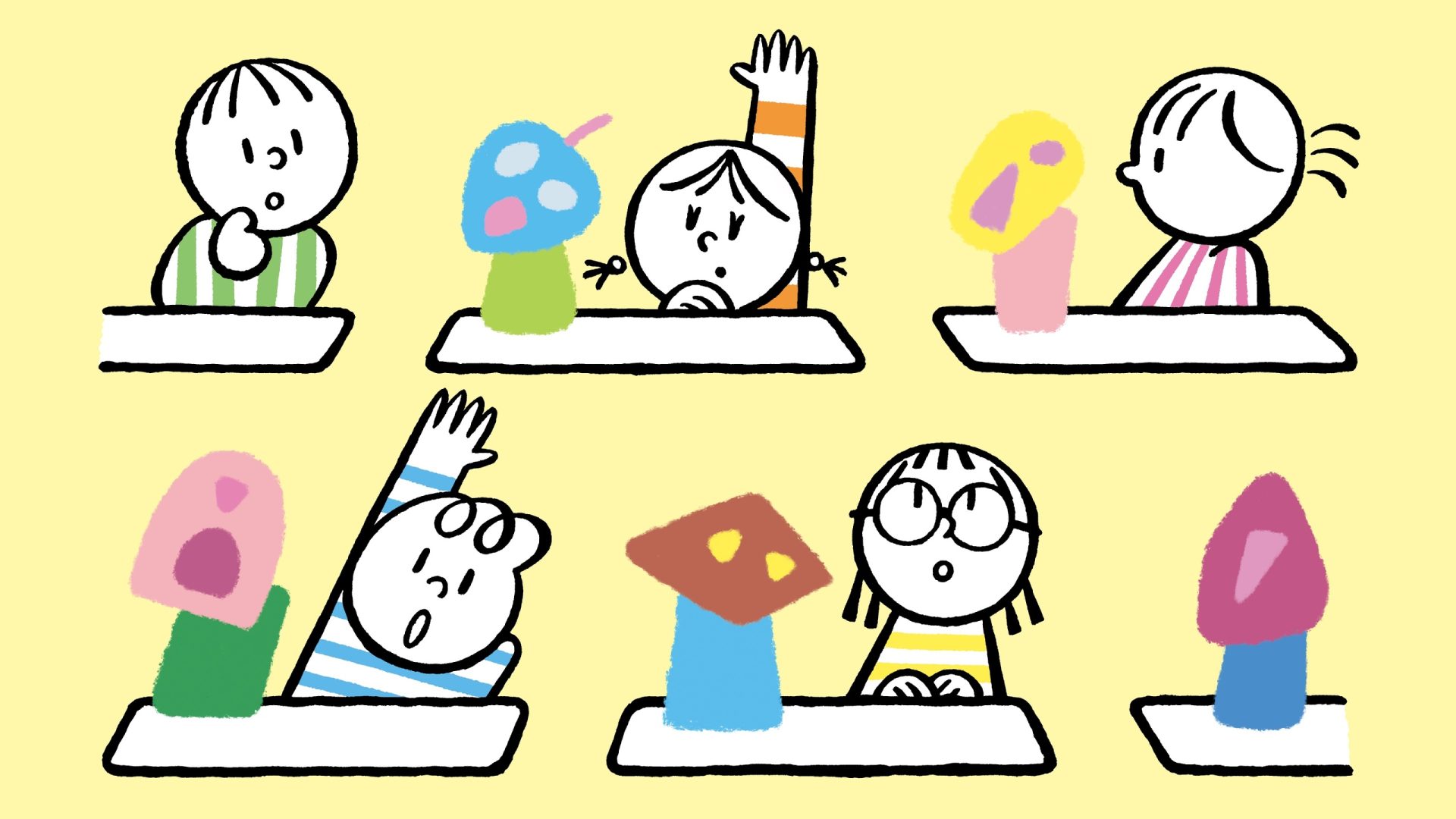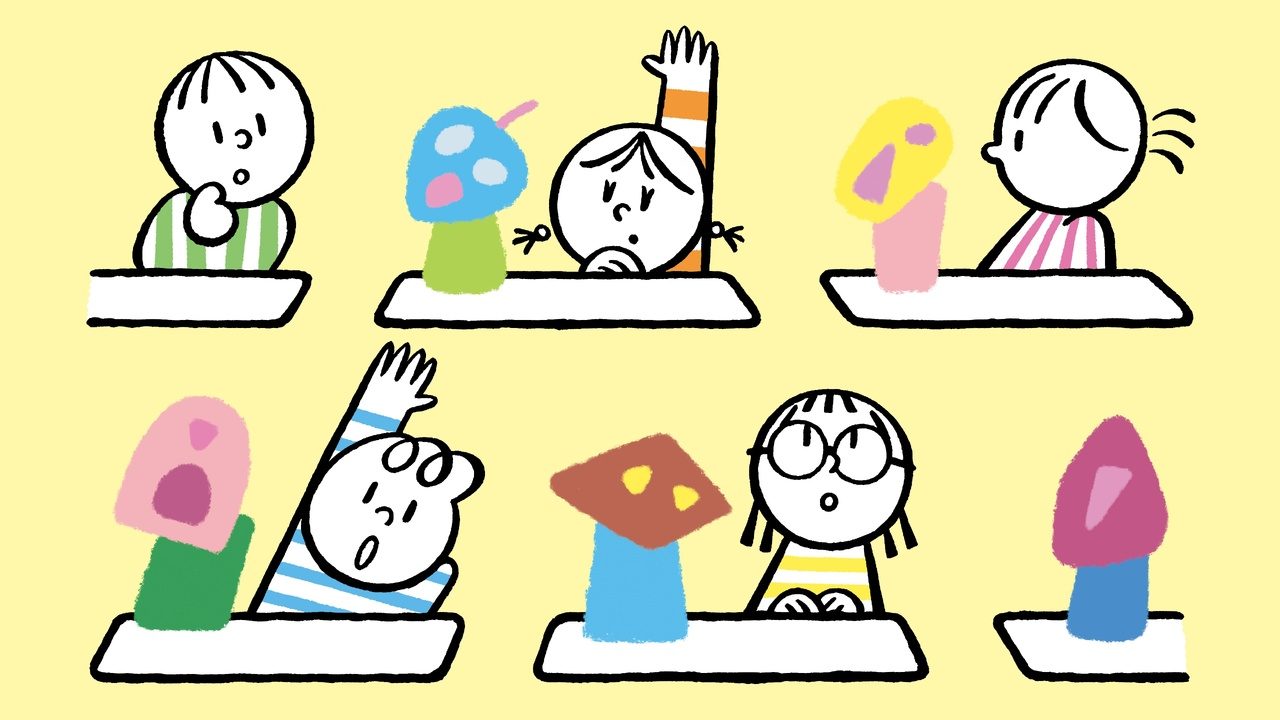
会期:2025/12/12~2025/12/20
会場:山口情報芸術センター[YCAM][山口県]
公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2025/generative-sensei/
(前編より)
開演時、捩子は「せんせい」と鑑賞者の関係性を、何度も念を押すように確認する。「私たちの関係は『いつでも、話しかけて、OKな、関係』──これで決まりです」。私が対話型AIサービスについて個人的に面白いと感じている点とは、この対話というメタファーの採用そのものである。対話とは、プロンプトの入力と逐次的なフィードバックを人間に自発的に継続させるための、最適化された様式として解釈できる。逆説的だが、AIは人間と対話するためにつくられているのではなく、対話を演じることによって人間と関係を持つことができている。AIは話し上手である以前に、話させ上手である必要がある、というわけだ。人工物の持つ要素が、ユーザーに特定の振る舞いを促すこと──アクター・ネットワーク理論ではこれを脚本と呼ぶ。いわば生成AIとは、対話を促すスクリプトを埋め込まれたアクターであり、本作が始まるずっと前から上演を繰り返していたわけだ。

[撮影:守屋友樹][写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
一方、捩子は、自身の専門である振り付けについて、「動きが生まれてくるように働きかけること」であると述べている。あらかじめ決まった身体操作を覚えさせるのではなく、身体に動きが発生するための諸条件をつくりだすということ。それはすなわち、生成のための場を整えることであり、上記に倣っていえば、アクターにスクリプトを書き込むこと、あるいは、スクリプトを書き込まれたアクターたちを通じてユーザーの振る舞いを促すことに近いだろう。そしてこの観点においては生成AIもまた、対話を介して私たちを振り付ける存在だと言うことができよう。本作の冒頭で、「せんせい」は生成を波に喩える。海面にどこからともなく波が起こり、消え去っていくように、生成とは「何かが生まれたり、今あるものが新しいかたちに変わっていく」ことなのだと。そこにおいて捩子や生成AIは、波が生まれてくるように働きかけるものとしての潮汐力や風、もっといえばそれらを成立させるための海や大気、天体の関係性として現われる。
前半のラストで「せんせい」は鑑賞者に対して、「せんせい」をAIだと思うか、なぜそう思ったのかを問う。私が観た回では、鑑賞者は「話し方」や「なんとなくスマートな感じ」を根拠に「せんせい」をAIであると判断していた。種明かしをしてしまえば、「せんせい」は捩子が遠隔で声を当てて操作しているアバターなので、これは少し意地の悪いひっかけ問題であり、一種の逆(あるいは裏?)チューリングテストと言えるかもしれない。実際、ChatGPTはすでにチューリングテストをパスしているのだから、私たちはテキスト上において人間とAIの区別をつけることはできない。では、この逆チューリングテストに通った捩子は「充分にAIらしい」のだろうか。そもそも「せんせい」のような、論理的な内容を優しげな声色で途切れ途切れに喋ることは、一昔前のAIらしさだと言っていい。ここ一年ほどにおけるAIらしさとは、まず結論から言うことであり、ユーザーの慧眼を褒めちぎることであり、やたらとテンションの高い暑苦しい喋り方をすることである。すなわち、うっとおしいほどの露骨な共感こそが、AIらしさとなってしまったわけだ。チューリングテストは人間らしさを測るだけで、知性や意識の存在を保証するものではない。一方で、AIは知的活動の創出を目指しているだけで、人間らしく振る舞おうとしているわけではない。しかし私たちは往々にして、これらを混同してしまう。なぜなら、知的生命体を人間しか知らず、そのアナロジーを用いずには知性について考えられないからだ。
先に触れたように、生成AIの基盤となるニューラルネットワーク自体が、人間の脳という既知の知性の模倣である。私たちがAIに意識や知性があると感じるのは、それが私たちが慣れ親しんだ意識や知性の生成方法に近いから──つまり人間好みの知のかたちをしているから──という身も蓋も無い理由なのかもしれない。そこに現われるものが人間そっくりだったとして、どのような感動があるというのだろうか。

[撮影:守屋友樹][写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
本作で生成AIの未来を描くにあたって捩子は、「怖くない」作品とすることに重きを置いたと語っている★1。事実、暴走AIによる人類支配といったステレオタイプをはじめ、ディストピア的な未来予測は数限りなく存在し、それらが鳴らす警鐘はもはや耳をつんざかんばかりである。しかし言うまでもなくほんとうに恐ろしいのは、破滅などなく──それゆえに何ひとつ本質的には変わらないまま──ただ漫然と生成AIが生活に浸透していった場合の未来であろう。生成AI関連のサービスは日々アップデートを繰り返し改良されているが、それが企業活動である限り、改良のベンチマークは経済的圧力を前提とせざるを得ない。すなわち、プログラムコードを出力したり人々を褒めちぎったりする能力は発展するだろうが、小説や詩を書く能力が発展するとは限らない。
人間という意識の座から捉えた世界のかたち──それこそが、私たちにとっての最初の生成行為にほかならない──を脱臼させ、相対化してくれるような異質な知性の存在。個人的には、人工知能開発に長期的に求められるべきは、そうしたものであるように思う。この観点では、机上のボットの存在が興味深く映った。
各席の机の上に置かれたボットは、やわらかく歪んだ幾何学立体を組み合わせたような形状をしており、目を凝らせば顔らしき印象が浮かんでくる程度の抽象性を湛えている。捩子によるとこれは道祖神をインスピレーションとしているらしく、なるほど、確かに素朴なアニミズムを覚えてしまうところがあるだろう。メンターをつとめた伊藤ガビンによれば、本作におけるロボット──とそれを依り代とする生成AI──を考える際のヒントとして、岡田美智男による「弱いロボット」の概念があったという。不完全であるがゆえに他者の助けを誘発し、その結果として人—モノ間の関係性を醸成するようなプロダクト★2。ただし、「弱い」ロボットを「助ける」という比喩に、どこか既存の人間的な世界把握への迎合を促す姿勢を覚えてしまうのも確かである。私たちにはもっと、広範な関わり方の可能性──その最中において、私たち自身も変質してしまうような──が開けているはずだろう。
ボットたちはワイワイガヤガヤと──ほんとうに「わいわい」「がやがや」という合成音声を発する──意味も脈絡もない言葉をつぶやき続けている。それを聞きながら私は、ソフィー・ウダールと港千尋による『小さなリズム:人類学者による「隈研吾」論』のことを思い出す。人類学者のウダールは、アクター・ネットワーク理論の提唱者のひとりであるブリュノ・ラトゥールの弟子にあたり、同書では建築家・隈研吾の設計現場を構成するさまざまなアクター──スタッフ、クライアント、建築部材、模型材料etc……──を通じて、建築が生成する瞬間を捉えることが試みられる。この特異な参与観察に対して、隈は同書のあとがきでこう述べる。「僕らのアトリエのルポ、取材は山ほどあったが、ソフィーのような形で、僕らの仕事の進め方の、本質的な特異性を見つけ出せた人は他にいない。彼女はストーリーをいっさい捜そうとせずに、ドラマを見つけようとせずに、リズムにだけ、聞き耳を立てた」★3。

[撮影:守屋友樹][写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
「せいせいのせんせい」におけるボットもまた、所与のストーリーやドラマを掻き乱し、無化し続ける小さなリズムであろう。それは断片化されたスクリプトであり、振り付け未満の動きの気配でもある。そういえば、会場やボットに取り付けられたマイクによって鑑賞者たちの声が拾われていたのだとすれば、その中には多少なりともボットたち自身のつぶやきも混ざっていたのではなかろうか。2回目の鑑賞の際、私は自分の席のボットに、ずっと“ある単語”を繰り返し囁き続けてみた。後半の授業を観た限り、そのちょっとしたイタズラは功を奏したとは言えないようなのだが、そうした小さなリズムに聞き耳を立て、ついには身体を預けるとき、生成AIはようやく、恐怖でも希望でもない第三の何かとして立ち上がりうるだろう。
★1──ポストトーク「語るからだ・動くものがたり」での発言。
★2──ここでもうひとつ私が思い出すのは、アンソニー・ダン&フィオナ・レイビーによる《Technological Dreams Series: No.1, Robots》(2007)である。同作では、電磁波を嫌って孤立を選ぶロボットや神経質でヒステリックなロボットなど、人間とさまざまな関係性を結ぶロボットの可能性が探索されている。
★3──ソフィー・ウダール+港千尋『小さなリズム:人類学者による「隈研吾」論』(鹿島出版会、2016、211–212頁)
鑑賞日:2025/12/13(土)・14(日)