バックナンバー
2020年07月15日号のバックナンバー
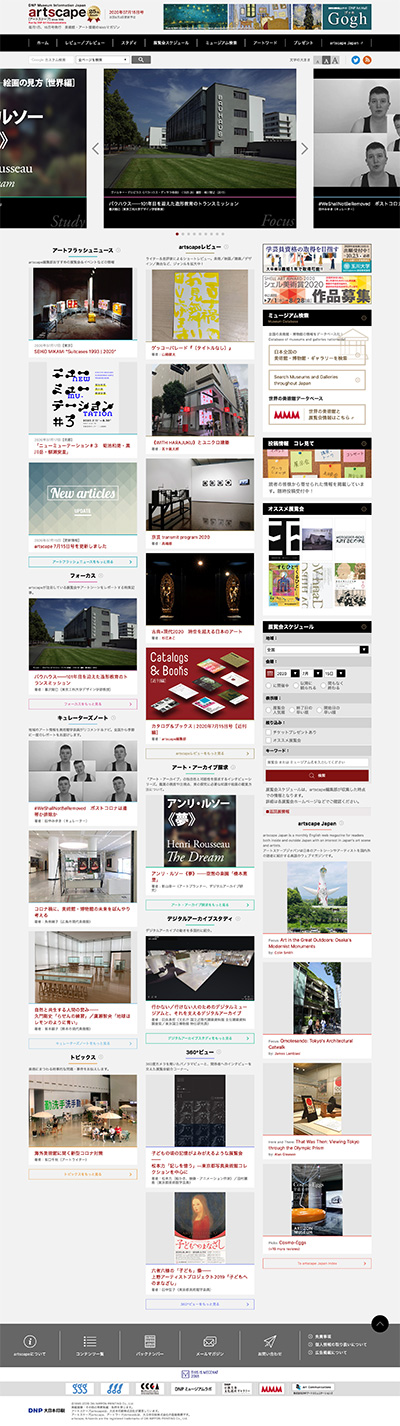
フォーカス
バウハウス──101年目を迎えた造形教育のトランスミッション
[2020年07月15日号(暮沢剛巳)]
1919年、ドイツの古都ヴァイマールでとある学校が産声を上げた。その名もバウハウス。小規模なうえに短命に終わったが、画期的なデザイン教育によって後世に多くの影響を与えた造形学校である。そのバウハウス開校から100年目の節目を迎えた2019年、日本でもそれを記念する多くのイベントが開催された。その一環をなすのが、2019年の秋から全国を巡回し、今月より東京開催(東京ステーションギャラリー)を迎える「開校100年 きたれ、バウハウス ─造形教育の基礎─」展である。
バウハウスは近代デザインに対して重要な問題を提起した教育機関であり、その活動はさまざまな観点から検討されてきた。だがタイトルが明示するように、本展の目的はもっぱらバウハウスにおいて行なわれた教育、とりわけ「造形教育の基礎」を再評価することにある。本稿でもその意図に即して、もっぱら教育へと焦点を合わせていこう。
キュレーターズノート
#WeShallNotBeRemoved ポストコロナは連帯か排除か
[2020年07月15日号(田中みゆき)]
コロナ禍において、障害のある人たちが「命の選別」を危惧している。感染拡大により医療崩壊が起きたとき、障害者の命が軽視されることはないのか。今なお社会に残る優生思想から、当事者たちは危機感を訴えている。実際に、米アラバマ州は人工呼吸器が不足した場合、障害や病気のある人にはつけない可能性があるとする指針を策定し、物議を醸した(後に撤回された)。英国立医療技術評価機構が公表した救命医療の指針に対しては、学習障害や自閉症などを持つ障害者に不利な内容であると親や人権団体が抗議し、後に修正された。
「選別」は、芸術文化の分野にとっても無関係のことではない。新型コロナウイルスにより、それまで少しずつではあるが増えつつあった障害者の表現の機会がリセットされた。社会全体が困窮し、多数派の芸術表現はおろか生活すらままならなくなっている状況で、ポストコロナの芸術文化の復興に障害者は含まれるのだろうか。同様の危機感のもと、感染者数および死亡者数で言えばより深刻な状況にあるイギリスでは、コロナウイルスによって自分たちがこれまでよりもさらに「見えない存在」になることを危惧し、さまざまな抵抗としての芸術活動が行なわれている。
コロナ禍に、美術館・博物館の未来をぼんやり考える
[2020年07月15日号(角奈緒子)]
なんとも難儀な世の中になってしまった。外出したくても、できない。事実、先月中頃までは、不要不急の外出を控えるようにと要請されていた。そして現在、自粛要請は解除され、移動の自由は戻ったものの、死をもたらしうる未知のウイルスに、まったく恐怖を覚えないはずもなく、遠出をするのになんらかの覚悟が求められる時代になってしまったのかと気が遠くなる。ほんの半年前までは、難なく無邪気にできていた、不特定多数の人々と同じ空間で一定時間を過ごすという、なんということもない行為がこれほどまでに難しくなることを誰が想像できただろうか。
とはいえ、経済活動の再開とともに(あるいは少し先んじて)美術館も徐々に開きはじめ、さまざまな段階で停止していた各所での展覧会も、鑑賞可能な状態になってきた。コロナとともにある今回は、広島市内の美術館・博物館を訪問し、そこでの様子と取り組みを紹介しつつ、コロナを経験したあとの館のあり方を考えてみたい。
自然と共生する人間の営み──
久門剛史「らせんの練習」/廣瀬智央「地球はレモンのように青い」
[2020年07月15日号(坂本顕子)]
これまで、1〜2カ月に一度は展示を観に県外に出るのが長年の習慣だったが、展覧会の準備とコロナ禍による自粛のため、この半年はずっと熊本にいた。緊急事態宣言の解除後、初めてとなる越境は、美専車でコレクターや作家アトリエ、他館をまわる作品返却。必要な用務とはいえ、作品を移動させると同時にウイルスも運んでいないかと、躊躇しながらの作業だった。その合間に見ることのできた展示について書いてみたい。







![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)