フォーカス
ひろがる「芸術と医療福祉」のプラクティス
中野詩(「美術待合室」主宰、東京都現代美術館)
2022年08月01日号
世界的なパンデミックを経験して、いま、医療福祉の現場でのアートやデザインの効能についても大きく見直されているのではないだろうか。病院におけるアートやデザインというと、患者が心地よく安心できるためのやわらかなインテリアや病室の絵画を思い浮かべてしてしまうが、それだけではない。治療のための「処方箋」としての芸術、対象も患者だけではなく、医療従事者や患者の家族にも及ぶ。それらが大学の芸術系学部と医学部、また付属する大学病院との連携においてさまざまに実践されているという。芸術と医療福祉のあり方を実践・調査研究されている中野詩氏に、国内のさまざまな事例をもとに、その意義と動向について寄稿していただいた。(artscape編集部)
世界にひろがるアート×ヘルスの動向
2018年、カナダのモントリオール美術館とフランコフォニー医師会が提携して、世界で初めて患者の治療の一環として美術館訪問を「処方」するというニュースが報じられた★1。さらに美術館は、医師や芸術療法士等と編成したリサーチラボでその効果を測定検証し、芸術体験とホリスティックなアプローチを組み合わせた新たな治療法を編み出すという★2。2019年には国立台湾博物館が台北市立連合病院との連携で、認知症の方とその介護者を対象に「博物館処方箋」の発行を始め、その実践や背景をガイドブックにまとめ公開した。東京都美術館は2019年以降にパーキンソン病の方対象のダンスワークショップを実施、2021年からシニア対象企画を始動、2022年に前述の台湾のガイドブックの日本語版を作成・公開している★3。

Room to Breathe, Manchester Art Gallery[Photo: Andrew Brooks Photography]
日々の過剰な喧噪から離れ、休み、呼吸し、回復させるアートとマインドフルネスの部屋。作品(収蔵品)とより深く関わりストレスを軽減できるように、家具、配色、作品の数、展示位置、オリジナルのテキストと音声が慎重に選択されている。2022-2025年の3年間、入場無料で開催する
「芸術と医療福祉」の密接な関わり合いはArts in Health、Arts for Health、Arts and Health等と呼ばれ、いまや「小規模な世界的現象」★4である。それは芸術領域での医療福祉に関係する活動と、医療福祉領域での芸術活動の両方を包括し、主に健康増進を目的にするが、そうでない場合もある。その時々のさまざまな条件によって、「芸術と医療福祉」の活動の目的やあらわれには振り幅が生じる★5。そのメッカであるイギリスのマンチェスターでは、美術館・劇場・ホール等あらゆる芸術領域の施設・団体が一丸となり、十数年前から高齢者にやさしい街づくり事業 “Age-Friendly City”を推進している。2018年、英国政府は世界初の孤独担当大臣を任命し、疾病の要因となる社会的孤立・孤独対策として、医師が患者に地域の文化活動やボランティアを「処方」する、「社会的処方」の普及を推し進めている★6。2019年に世界保健機関(WHO)が、芸術が健康とウェルビーイングに与えるポジティヴな成果を調査発表し★7、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、このフィールドはさらに注目されつつある。
では、日本における「芸術と医療福祉」は、どのようなかたちであらわれ、認識されているだろうか。多くの人が治療のためのアートセラピーを連想し、「病院のアート=癒し」という固定観念をもたれていないだろうか。そこで今回は「癒し」のみにとどまらない、さまざまな目的をもった医療福祉の現場の多様なアート活動を「大学と病院」を切り口に紹介する。また本稿のなかでは、治療を目的とするアートセラピー/芸術療法は扱わず、それ以外の医療福祉の現場におけるアート活動について言及する。
★1──「世界初、治療として患者に美術館訪問を『処方』 カナダ医師会」(AFPBB News、2018年10月26日)https://www.afpbb.com/articles/-/3194788
★2──"MMFA-MFdC Museum Prescriptions: Museum Visits Prescribed by Doctors" (Montreal Museum of Fine Arts, October 11, 2018) https://www.mbam.qc.ca/en/news/museum-prescriptions/
★3──「【翻訳】国立台湾博物館発行「社会的処方」の実践をまとめたガイドブックの日本語版を作成しました。」(東京都美術館ずっとび」https://www.zuttobi.com/research/T4ARw8og
★4──"Arts in Health – What’s In A Name Change?" (Centre for Medical Humanities Blog, Durham University, April 22, 2013) https://medicalhumanities.wordpress.com/2013/04/22/arts-in-health-whats-in-a-name-change/
★5──卑近な例だが、筆者が個人医院で展示やワークショップを行なう「美術待合室」では、作家に癒しを目的とした作品を依頼したことは一度もない。一方、高齢者施設と病院を経営する医療法人惇慧会のArts for Healthcare室に学芸員として勤めた折には、アートを媒体として活用しアートが持つ可能性を用いることで患者や入居者の生活の質を向上させる、という法人の方針のもと、プロからアマチュアの作品や活動の導入に幅広く携わった(Arts for Healthcare室は2005年6月廃止)。水戸芸術館現代美術センターの学芸員として、作家とともにシニア対象のワークショップ・展示・対話型鑑賞を、美術館と館近隣の高齢者施設(認知症の方含む)で実施(2010-2013年)した折には、健康増進を目的としなかった。
★6──西智弘編著『社会的処方 孤立という病を地域のつながりで治す方法』(学芸出版社、2020)
★7──Daisy Fancourt, Saoirse Finn "What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review" (World Health Organization. Health Evidence Network synthesis report; 67, November 5 2019) https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289054553
ヒーリング・アートとエビデンスを得ること
1992年、女子美術大学芸術学部の山野雅之は、病院の白く無機質な環境をアートとデザインで心安らぐ空間に変えるプロジェクトを学生有志とともに始める。ヒーリング・アート/癒しの芸術を「さわやかな気分になって心が落ち着く効果や、元気づけを目的とした芸術」と定義し、アートセラピーとは異なる環境芸術の分野であると考えている。医療空間の快適さや心地よさを高めるアート・デザイン企画の提案、学生の制作指導から医療福祉施設に実際に作品を設置するまでのコーディネート、さらに「アートやデザインは医療環境に対して何ができるのか」を研究テーマに、さまざまな方法を用いた調査と検証を行なう。学生は病院に足を運んで現場を確認し、職員・患者・ご家族と話し合いを重ね、学生・大学・病院三者が求めるイメージを協働で作り上げたうえで作品制作を行なう。例をあげれば、東京都立小児総合医療センターで長い通路を歩く子どもの不安を軽減させるストーリー性のある壁画、茨城県立こども病院では子どもが苦手なCTスキャナ検査室を、海底探検に見立てた緊張感を解きほぐすデザイン、東京都立健康長寿医療センター緩和ケア病棟で病室に籠もりきりの高齢患者が病室から出るきっかけとなった自然の風景の大絵画など、コミュニケーションを誘発するアートが療養の一助となっている★8。2010年、アート・デザイン表現学科ヒーリング表現領域が新たに設置され、このプロジェクトはグラフィック表現や立体表現も含む同領域に引き継がれる。2021年までに約60カ所の医療・福祉施設を手がけ、事後に調査と検証を行なうまでがひと続きのアート活動と捉えている。同領域はエビデンスを積み重ね、日本におけるアート・イン・ホスピタルの実装モデルとし、医療福祉とアート/デザインが融合する新しい領域および新たな職域をも開拓・創成したいと考えている★9。

東京都健康長寿医療センター 緩和ケア病棟、2013年

順天堂大学医学部付属練馬病院小児病棟の施工前のイメージ写真。2022年春、完成
★8──山野雅之「美術大学におけるヒーリング・アートの研究と実践」(なごやヘルスケア・アートマネジメント推進プロジェクト、第7回ヘルスケア・アートマネジメント連続講座, 2019年8月29日開催)https://healthcare-art.net/case/yamano2019.html
★9──女子美術大学芸術学部アート・デザイン表現学科ヒーリング表現領域の教員、保高一仁へのヒアリングより
人にやさしく、利用者が感情移入できる設計デザイン
1997年、名古屋市立大学芸術工学部の鈴木賢一は、小児専門病院の設立準備研究会に多様な専門職と学生と共に参画する。以降、「人の心に寄り添うデザイン」「利用者中心のデザイン」を念頭に、声なき人たちにやさしく、ユーザーが感情移入できる設計を心がけている。プロジェクト毎に学生有志を募り、チーム「はみんぐ」を結成し、そのなかからチームリーダーと研究室を調整役に、学生の既成概念にとらわれない柔軟なアイデアを反映した活動を進める。2003-2007年、名古屋市立大学病院の小児科病棟の新設時には、病棟を宇宙に見立てた空間設計・デザインを行なう。一度も空を見たことのない子どものために天井に光ファイバーで満点の星空を映し、病棟の宇宙に住む架空の動物が療養中の子どもを見守るという設定でキャラクターデザインも手がけた。病棟利用者を対象に実施した「小児病棟における壁面装飾の印象と効果に関する研究」の調査では「デザインの効果あり」が80~94%にのぼり、デザインが患者だけでなく医療者にも寄与することに気づく★10。以後、約40カ所の医療・療養空間の設計を手がけるなかで、医療者が発案した物語を元に空間デザインを行ない、絵筆をとって学生とともに制作に臨むなど、医療者が職場空間のデザインプロセスに直接参加・参画することで、医療者にとって意味のある場所となる様に配慮している。2018年からは医療福祉施設でアートマネジメントを行なう人材の育成を目的に「なごやヘルスケア・アートマネジメント推進プロジェクト」を主催し、シンポジウムの開催・医療福祉施設でのワークショップの実施・オンライン上の事例集のサイト運営などを通して、アート×医療領域のネットワークの構築を目指している★11、★12。

名古屋市立大学病院小児病棟のエレベーターホール天井に光る満点の星

医療者も学生とともに絵筆を握り、病院/職場を自分にとっても「意味のある場所」にする
★10──鈴木賢一、岡庭純子「小児病棟における壁面装飾の印象と効果に関する研究」(日本建築学会計画系論文集、2008年73巻625号、pp. 511-518)
★11──「ヘルスケアアート、そのマネジメントを考える BOOKLET vol.01 子どもにやさしい療養環境-名古屋市立大学 鈴木研究室における取り組みから-」(なごやヘルスケア・アートマネジメント推進プロジェクト事務局、2019)https://healthcare-art.net/archives/002/201904/suzuki_book190430.pdf
★12──鈴木賢一「学生によるヘルスケアアート」(なごやヘルスケア・アートマネジメント推進プロジェクト、第8回ヘルスケア・アートマネジメント連続講座、2018年8月29日開催)https://healthcare-art.net/case/suzuki2018.html
大学と病院をつなぐアートコーディネーター
筑波大学では、芸術系教員だった蓮見孝が2002年から筑波大学附属病院でデザインによる医療支援活動を始め、2005年から開講された「アートデザインプロデュース(adp)」の一環で学生が活動するようになった。以降、ワークショップ・展示活動・家具デザイン・空間改修などを行なう学生チーム「アスパラガス」や「パプリカ」がadpから生まれ、さまざまな分野の教員と学生がアートやデザイン活動を展開している。筑波メディカルセンター病院では、2007年から学生らが院内で展示活動を開始し、2009年頃より病院食の滑り止めマットのデザインなど、医療者と学生が協働で課題に取り組み、環境を豊かにする活動を展開。協働促進のために調整・運営役の病院広報課職員に加え、建築デザインを学び病院で活動していた岩田祐佳梨が2011年からアートコーディネーターに着任した。次いで附属病院も2013年からアートコーディネーターを雇用する。岩田と広報課職員は協働強化のために、作るプロセスをひらき、共有し、職員の声を拾える参加型のカフェやワークショップを実施する。2017年、医療や福祉を応援するアートの普及を目的に大学内にNPO法人チア・アートが設立される。2020年、新型コロナウイルス感染拡大時に実施した写真展「病院のまなざし」では、病院職員の表情や働く姿をとらえた写真の展示を通して、人間性の回復について問い直そうとした。また面会制限下にあった緩和ケア病棟の家族控室の改修に向けて、病棟職員・学生チーム・NPOの協働でクラウドファンディングに挑戦★13。地元の木工所の協力を得て、翌7月に心地よい手触りと香りのヒノキ材を多用した家族控室を完成させた。NPO代表の岩田は自身の役割を、医療者と作り手をつなぎ、本質的な課題を探り、プロセスをデザインすること、としている★14、★15、★16、★17。

筑波メディカルセンター病院 アートカフェ「あふれるカフェ」、2015年

「病院のまなざし」展、筑波メディカルセンター病院内での展示風景、2020年

筑波メディカルセンター病院 改修された緩和ケア病棟家族控室、2022年
★13──筑波メディカルセンター病院緩和ケア病棟×アートプロジェクト「#病院にアートを|患者さんとご家族が笑顔になれる緩和ケア病棟へ」クラウドファンディング(2021年8月31日終了)https://readyfor.jp/projects/tmc
★14──筆頭 齋藤泰嘉ほか「ケア×アート いきいきホスピタル」(筑波大学芸術系、2014年3月31日)https://ocw.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/ikiikiHospital2014.pdf
★15──筆頭 齋藤泰嘉ほか「ケア×アート いきいきホスピタル2」(筑波大学芸術系、2015年3月31日)https://www.cheerart.jp/_files/ugd/94e332_7e2920b121cc44e7a5b09ad624f358e5.pdf
★16──筆頭 齋藤泰嘉ほか「いきいきホスピタル──筑波大学で取り組む病院のアートとデザイン」(筑波大学芸術系、2016年3月31日)https://www.cheerart.jp/_files/ugd/94e332_2e06c9492b3a4f059203dde6b192be9b.pdf
★17──岩田祐佳梨「みんなで描く病院とアートの未来」(なごやヘルスケア・アートマネジメント推進プロジェクト、第3回ヘルスケア・アートマネジメント連続講座、2020年7月22日開催)https://healthcare-art.net/case/iwata2020.html
医学部と文芸学部の合同授業「ホスピタルアートによる患者ケア」
近畿大学では医療環境の快適性の向上を目的に、2009年から文芸学部と医学部が近畿大学病院で協働する「HARTプロジェクト」を始動させる。2016年からは活動初期から携わる文芸学部文化デザイン学科の教員で作家の森口ゆたかと「HART」メンバーが中心となって、美術や舞台芸術の学生による展覧会や舞踊公演、患者のための造形ワークショップ、小児科入院棟の壁画制作、患者と病院職員のコミュニケーションをデザインで可視化させるなど、幅広い表現を用いたアート活動を展開している★18。2022年から文芸学部と医学部合同の授業「ホスピタルアートによる患者ケア」を開講。授業では森口のゼミ生と医学部1年生が、病院から提供された課題をもとに作品のアイデアを出し、グループで企画書を作成し病院でプレゼンテーションを行ない、作品の制作・設置までを行なう。一連の協働を通して、医学部生は多職種から成るチーム医療の理解、その実践に必要なコミュニケーション能力、患者ニーズの聴取について学び、 「社会をデザインする」人材育成を目指す文化デザイン学科ゼミ生は、医療機関という特殊な現場を運営する機会を得ている★19。森口は1998年英国滞在中に、アートでよりよい医療環境を作る概念Arts for Healthに出会い、翌年に英国で開かれた療養環境のアートの第1回国際シンポジウム「CHARTS’99」で、日本の医療福祉・芸術分野の関係者と、世界の医療福祉の現場で芸術活動を行なう人々との橋渡し役を務める。帰国後、NPO法人アーツプロジェクトを設立し、諸芸術の力でよりよい医療環境をつくり出す活動で手応えを感じる一方で、癒しを目的としないそれまでの観念的な作品制作との狭間で作家として揺れるが、徐々に生死や人間関係をも含めた自身の過去・現在・未来を包含する制作アプローチに変化していったという★20。

文芸学部と医学部合同でホスピタルアートについて学び、実際に病院でアート活動を行なう

近畿大学病院小児科入院棟デイルームで壁画制作する入院療養中の子どもたちをサポート

病院の中庭で舞台芸術専攻の学生による現代舞踊公演「もとのみず」をHARTメンバーがプロデュース。雨のなかをエネルギッシュに走り回るダンサーの姿に高齢の患者は若い頃を思い出し、訳がわからないが勝手に涙が出た、という

森口ゆたか《ひかりの刻》(2009)、ビデオインスタレーション、信濃町画廊(大阪)
★18──森口ゆたか「療養環境におけるアートの役割と可能性」(なごやヘルスケア・アートマネジメント推進プロジェクト、2018 ヘルスケア・アートマネジメント シンポジウム、2018年6月23日開催)https://healthcare-art.net/symposium/moriguchi2018.html
★19──2022年度近畿大学医学部シラバスより
★20──森口ゆたかへのヒアリングより
病院から島、私(わたくし)へ──「やさしい美術プロジェクト」
作家の高橋伸行は名古屋造形大学在職中の2002年、医療福祉施設で行なう「やさしい美術プロジェクト」(以下、「やさ美」)をさまざまなジャンルの学生有志とともに始める。「やさ美」メンバーは患者にインタビューを行ない、各々がその場や人に寄り添い、見つけた課題を元に作品制作やワークショップを行なう。新潟県立十日町病院で実施したワークショップ「みぢかな絵画」では、看護師が日々の業務から離れた心の内を手作りの絵はがきに託し患者全員に手渡すことで、各々が「医療者と患者」という固定的な関係性の垣根を低くした。2007年、高橋は瀬戸内国際芸術祭2010の準備中に国立療養所大島青松園に出会い、国の強制的なハンセン病の隔離政策で長年差別や偏見を受けてきた大島を、作家を通して外に繋ぐ構想を立てる。来島者と島民の交流の場となるカフェ、入所者や故人からの預かりものを展示するギャラリー、島のガイドツアー、海中から引揚げたコンクリート製の解剖台の屋外設置、木造の古い釣り船の展示、島民の懐かしの菓子の再現と販売──この一連の{つながりの家}の活動を通して、来島者は入所者一人ひとりの「生」に触れ、大島の歴史を知る★21、★22、★23。現在、ガイドツアーの運営は地域住民へ、カフェの運営は現地のボランティアへ受け継がれ、入所者から寄せられたさまざまなものは、社会交流会館の学芸員が文化財として保管されている。高橋は元入所者で写真家の故「

やさしい美術プロジェクト《みぢかな絵画》(2006)、新潟県立十日町病院でのワークショップ

やさしい美術プロジェクト《{つながりの家}カフェ・シヨル》(2010)、国立療養所大島青松園の旧面会人宿泊所にオープン

やさしい美術プロジェクト《海のこだま》(部分)(2016)、国立療養所大島青松園でのインスタレーション
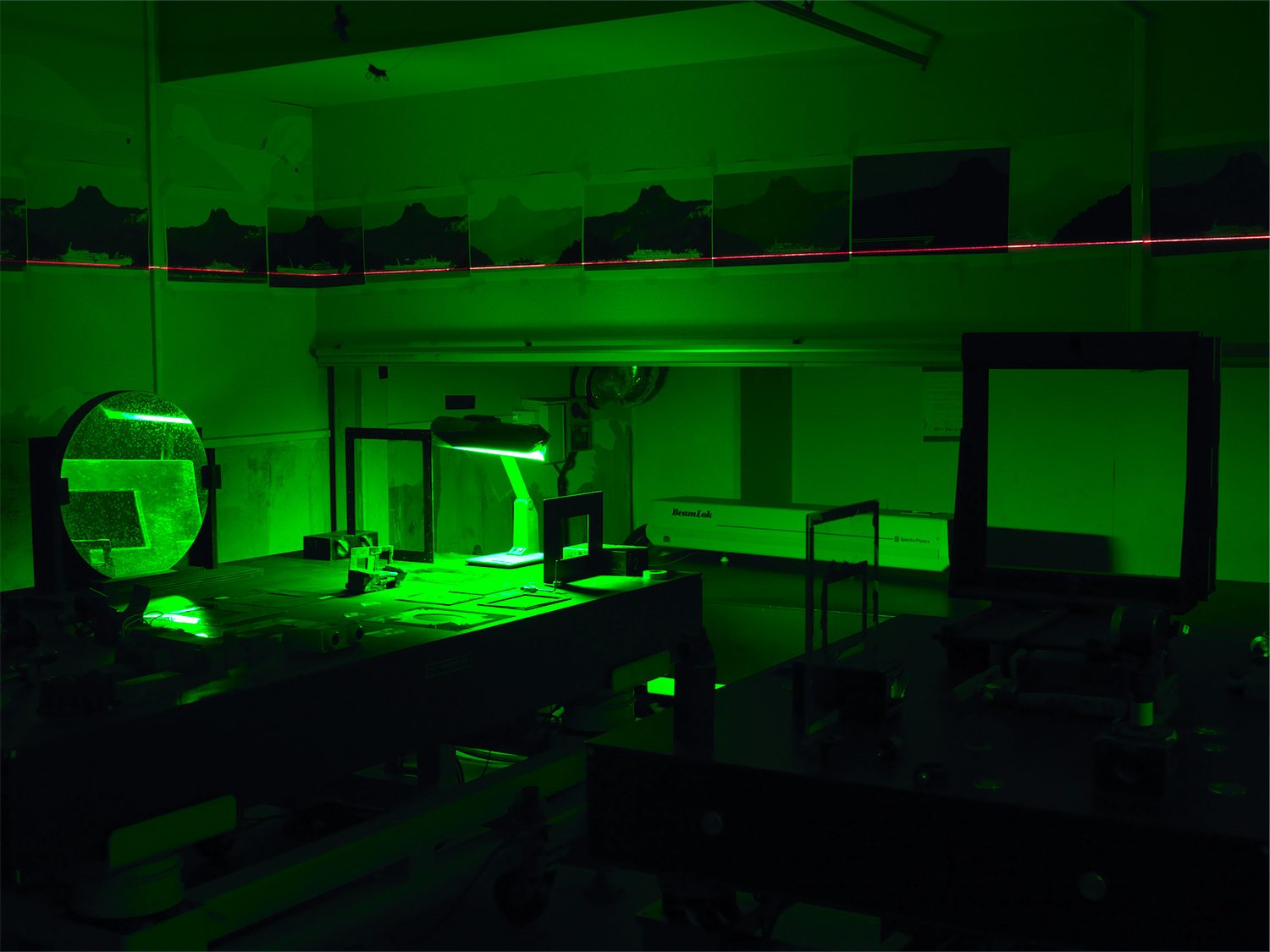
鳥栖喬(髙橋伸行)《ホログラフィー室 対 鳥栖喬》(2018)、名古屋造形大学CB-04倉庫(旧ホログラフィー室)でのインスタレーション、「見えにくい場所」(企画:髙橋伸行)参加作品
★21──「ディレクター高橋伸行のブログ」http://gp.nzu.ac.jp/directorblog/
★22──瀬戸内国際芸術祭2022「やさしい美術プロジェクト」https://setouchi-artfest.jp/artworks-artists/artists/71.html
★23──三浦博史「People / ハンセン病に向き合う人びと 森和男」(ハンセン病制圧活動サイトLeprosy.jp)https://leprosy.jp/people/mori/
★24──高橋伸行×井尻貴子「人や場に寄り添うアートプロジェクト 『やさしい美術プロジェクト』、鳥栖喬との出会いから」(秋田光彦・坂倉杏介責任編集、アートミーツケア学会編『生と死をつなぐケアとアート──分かたれた者たちの共生のために」、アートミーツケア叢書、生活書院、2015、pp.122-143)
★25──椹木野衣「43:再説・「爆心地」の芸術(19)<やさしい美術>と鳥栖喬(中編)」 (ART iT、2014年8月13日) https://www.art-it.asia/u/admin_ed_contri9_j/homhubxs5vyrkw7j9igb
★26──小林祐子「ハンセン病元患者・故鳥栖喬を世に伝える」(朝日新聞、2016年5月25日)http://www.asahi.com/area/aichi/articles/MTW20160525241310003.html
★27──高橋伸行へのヒアリングより
医学教育におけるアートの可能性
病院のアート活動のなかで大学の付属病院の事例が多く見られる理由のひとつは、病院であると同時に医学の研究・教育機関だからではなかろうか。病を診ず人を診る医師の育成は世界共通の課題で、ここ10数年、世界の医学教育の現場では芸術系の授業が積極的に取り入れられている。例えばアメリカの複数の大学医学部では、患者と対話できるコミュニケーション能力や共感力を磨くため、対話型鑑賞をはじめダンスや演劇など芸術系の授業を開講し、総合大学の場合、人文科学や社会科学など他学部の授業も受講できる★28。筆者が前回の記事の執筆時に在籍していた、英国の大学院の医療人類学専攻の約半数が現役医療者とその卵だったことも頷ける。
日本の医学教育者は、臨床の実習時間が少なく知識偏重の傾向にある日本の医学教育が、世界標準から遅れをとることを懸念し、臨床実習を見学型から参加型に変更する大学医学部が増えている★29 。アートの活用の観点では、慶応大学医学部が公衆衛生実習のなかで生命や倫理にまつわる自身の問題意識を掘り下げ、美大の院生やプロの助言を受けながら絵画や写真・楽曲を制作し発表しあう授業を開いている。明確な答えがないアートとのかかわりを通して、多様で複雑な問題に向き合う姿勢を育む狙いである★30、★31。関西医科大学看護学部や独協医科大学医学部では、美術作品をグループで鑑賞し、感じ考えたことを互いに話す、対話型鑑賞の授業を取り入れ、観察力やコミュニケーション能力など診療に必要な能力の向上を促す★32。東邦大学看護学部は『生命と自然と人間の営みについて学ぶ 』ことを目的に、美術を始め7種類の芸術の選択必修授業を開講している★33。これらの授業の共通点は、医療看護以外の幅広い知識と他者の多様な価値観に触れながら、主体的に学べるグループワークの実習を含むことである。このような背景から、病院が大学付属あるいは大学と近しい関係にある場合、大学教員でもある病院職員が、患者や職員にポジティヴな影響を与える病院内でのアート活動に理解を示すのは想像に難くない。
★28──Melissa Bailey "Why medical schools are training doctors in literature and art" (STAT, November 3, 2015) https://www.statnews.com/2015/11/03/why-medical-schools-are-adding-courses-in-literature-and-dance/
★29──庄村敦子「医学部にも黒船襲来『2023年問題』に向け“脱ガラパゴス”」(AERA dot.、2016年9月29日)https://dot.asahi.com/aera/2016092800227.html?page=1
★30──日本医師会「授業探訪 医学部の授業を見てみよう!【前編】 慶應義塾大学『生命・医療とアート』https://www.med.or.jp/doctor-ase/vol34/34page_id22tagaku1.html、「同【後編】 INTERVIEW 授業について先生にインタビュー」https://www.med.or.jp/doctor-ase/vol34/34page_id22tagaku2.html(DOCTORASE)
★31──医学とアートの連携を考える【前編】https://www.med.keio.ac.jp/features/2021/6/8-80126/index.html、同【後編】https://www.med.keio.ac.jp/features/2021/6/8-80160/index.html(慶應義塾大学ウェブサイト、2021年6月1日)
★32──福のり子,伊達隆洋,森永康平「座談会 アートの視点がこれからの医学教育を変える? 対話型鑑賞で鍛える『みる』力」(週刊医学界新聞、2020年7月13日)https://drive.google.com/file/d/1DzJM2KAJA1ZxbACE21a5ljyKa9WqVTvG/view
★33──2022年度東邦大学看護学部シラバスより
アートと個人的な関係を結ぶこと
以上のように、医療福祉領域でのアート活動は、その拠り所やプロセス・最終形態が実に多様で、「癒し」のみに回収できないことがおわかりいただけるだろう。大病院は多様な専門職がチームで患者の治療にあたる、高度に専門分化した医療機関である。その特性から、安全第一で考え抜かれた構造とプロセスに則って、徹底した管理運営が求められている。であるがゆえに医療者は、患者を身体・心理・社会的側面から総合的に「一人の人として」診ることが難しい、というジレンマも同時に抱えている。もしも院内で医療者と患者とのアートやデザイン活動が協働で行なわれた場合、病院の日常にはない非日常がアートによってもたらされ、双方の個人的な感情や思いを託し、伝え、共有する媒介となり得る。それは「患者」や「医療者」といった社会的に与えられた“役割”から一時離れ、「一人の人として」その場に居ることを確かめられる時間でもある。
芸術領域の実践者も同じく、職業人である前に一人の人間である。大学の事例冒頭の山野と、最後に紹介した高橋が病院でアート活動を始めたきっかけは、二人とも大病を患った家族の入院である。前者はアートやデザインで癒しを目指し、心のケアが治療と同じく必要と認識されるために徹底してエビデンスをとる。後者は看護師がアートと言わずとも「日常的に語りかける言葉や接する仕草を創造している」から、「やさ美」の活動は美術やデザインに何ができるのかは語らない★34。この一見、対極にある様にも見える、振れ幅の大きさ・多様さを受け入れる懐の深さが「芸術と医療福祉」の領域の魅力ではなかろうか。
命や安全が最優先の医療福祉施設で芸術を受け入れる仕組みが始めからある訳ではない。多くの動向が、芸術側か医療側の少数のキーパーソンによって始められている。そして筑波大学附属病院と筑波大学が「病院のアートを育てる会議」を毎月1度開くように、両専門領域が互いに歩み寄り、試行錯誤できる協働体制や、芸術領域と医療福祉領域の信頼関係を築くことが、院内でのアート活動を実現し継続可能にさせる。冒頭の英国マンチェスターのまちをあげてのムーブメント “Age-Friendly City”は、1970年代に作家ピーター・シニア(Peter Senior)が病院で始めた活動に端を発している★35。その後、大学を拠点にさまざまな領域の人々と連携して「医療福祉における芸術」の活動と概念を育み、約50年を経た現在、アートは病院や大学の枠を越え、地域社会のなかで人々とともに生きる存在として受容されている。私たちは誰もが地域社会の一員である。一人ひとりが常態から一歩踏み出すことで、この先の「芸術と医療福祉」の姿を描き始めることができるのかもしれない。
★34──高橋伸行「ケアにとってアートとは何かを考える~『やさしい美術』プロジェクトの実践から」(2014年10月29日開催)、前掲『ケア×アート いきいきホスピタル2』(筑波大学芸術系、2015)pp.40-41 https://www.cheerart.jp/_files/ugd/94e332_7e2920b121cc44e7a5b09ad624f358e5.pdf
★35──Peter Coles "Manchester Hospital's Arts Project" (Calouste Gulbenkian Foundation, UK, 1981)https://www.artshealthresources.org.uk/docs/manchester-hospitals-arts-project/
関連記事
【イギリス】「アート」と「医療」 かかわりへの模索──北東英国を中心に|中野詩:フォーカス(2017年12月01日号)
Life Is Beautiful──生の美しさ|能勢陽子:キュレーターズノート(2016年06月01日号)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)