フォーカス
サウンドプログラマー濱哲史に聞く、坂本龍一のインスタレーション作品 制作の流儀
濱哲史(サウンドプログラマー、アーティスト)/畠中実(NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]主任学芸員)
2023年05月15日号
3月28日に逝去された音楽家・坂本龍一氏は、多岐にわたる創作活動で知られているが、さまざまなアーティストやエンジニアたちとともに多くのインスタレーション作品も手がけていた。展示空間をアルバムやコンサートとは異なる音空間として、坂本氏はそこで何を探求し、どのように音を構築していたのだろうか。サウンドプログラマーとして協働していた濱哲史氏を、音楽批評および、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC](以下、ICC)で坂本氏の展覧会のキュレーションも手がけた畠中実氏にインタビューしていただいた。(artscape編集部)

坂本龍一 with 高谷史郎《IS YOUR TIME》(2017)展示風景
[撮影:丸尾隆一 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]]
音は物から鳴る
畠中実(以下、畠中)──坂本龍一さんと仕事をする以前、濱さんにとって坂本さんはどういう存在だったのでしょうか? 坂本さんの音楽は聴いていましたか?
濱哲史(以下、濱)──『ケイゾク』や『トニー滝谷』などテレビや映画のサウンドトラックを聴いて、こんな透き通った綺麗なメロディがあるんだと感動していました。それから高校を卒業してエレクトロニカやノイズにハマり、僕が何も知らない中学生だった90年代後半のころからすでにOval、Pan Sonic、Alva Notoとコラボレーションされていて、すごい方だ……と思いました。YMOは僕が生まれる前に散開されていて、実のところしっかり聴いたのは坂本さんと最初にお仕事をするようになる頃で。そして、『BGM』でとてつもない衝撃を受けました。YMOはエレクトロニックミュージックのビートルズなんだ……と。
畠中──坂本さんとの最初のお仕事はいつだったんですか?
濱──2013年、山口情報芸術センター(以下、YCAM)開館10周年のときの《Forest Symphony》です。そのときはYCAM InterLabのスタッフとしてでした。

濱哲史氏
畠中──そのときの坂本さんの印象はどんな感じでしたか?
濱──とても緊張しました。プログラムについて、事前にアイデアをやり取りするのですけど、坂本さんが現場に入られる前にさらに先回りして作っていくことが多かったです。いろんな可能性をすぐに試せるように。
畠中──濱さんのサウンドプログラマーとしての仕事は、どういったものなのか教えてください。
濱──《Forest Symphony》は日本、アメリカ、オーストラリア、ハンガリーにある樹から取得した電位データから音を鳴らす、いわば樹が演奏するというインスタレーションです。24時間分のデータを45分間で再生する、その間の展開や音色の組み合わせをプログラムしたり、サインウェーブやパッドの音色を鳴らすシンセサイザーもプログラムで作りました。
Forest Symphony from YCAM on Vimeo.
《Forest Symphony》YCAM
僕が関わった坂本さんのインスタレーションではマルチチャンネルスピーカーを使うことが多くて、ステレオというのはあまりありませんでした。《Forest Symphony》の制作初期、14個のスピーカーを地図上に配置して、そこを音源が移動していくというプログラムを僕が自発的に作って、坂本さんに実験してみせたのですが、「そういうことじゃない。音って物から鳴るんだよ」と言われたのが坂本さんと仕事をした最初の衝撃でした。スピーカーからスピーカーへバーチャルに音が移動していくのはステレオの考え方で、それはすでにいくつもやってこられているから、リスニングポジションの制約がないインスタレーションではそれとは違った聴取の可能性を探りたいということだったのかと思います。森で、いろんな方向からいろんな物が立てた音を聞くような、その物に近づけばよく聞こえるような、物由来の音による空間を考えてらっしゃったんだと思います。
畠中──『async』(2017)が出たときに坂本さんにインタビューしたことがあるんですが、同じことをおっしゃっていました。ステレオというものは2つのスピーカーの間に存在しない架空の音像を作り出すわけですが、そうではなく、例えば、右から左に音を動かそうと思ったら本当はスピーカーを動かさなきゃいけないと。それが面白かったです。ずいぶん前からそういう考え方をお持ちだったんですね。音色は濱さんが用意して聴いてもらったりしていたのでしょうか?
濱──サインウェーブやホワイトノイズを使ったシンセサイザーのところはプログラムで生成している音です。パッドやベル、ガムランの音は坂本さんからいただいたサウンドファイルをプログラムで加工して発音していました。《Forest Symphony》のみならず、《LIFE—fluid, invisible, inaudible… 》(2007-)、《Plankton》(2016)や《IS YOUR TIME》(2017)でも、リアルタイム生成の音とサウンドファイル由来の音を組み合わせたプログラムですね。
音律をプログラムで作る
畠中──坂本さんも技術的なことは詳しかったと思うんですけど、それでもYCAM のInterLabと共同制作をするときは何かしら自分の知らないこととか、新しいものを出してくれるんじゃないかっていう期待感があったのではないかと思います。
濱──そうですね。坂本さんは音律をよく気にされていました。平均律なのか、純正律なのか、ピタゴラス音律なのか、またペロッグとかスレンドロなどいろんな民族音楽の音律があって、「それできる?」って言われて。音律を自由に変えられるプログラムを作って、音のピッチを決定していました。《water state 1(水の様態1)》(YCAM、2013)では黄金律やフィボナッチ数列を基にした音律も使いましたし、《IS YOUR TIME》では素数の音律を用いたシーンもあります。音律の実験は結構しました。いま考えると、それはすごく重要だったのだなと思います。
畠中──プログラムでいろいろな調律をデジタルに再現できるということですね。
濱──そうです。MIDIインストゥルメントではないので、1オクターブ分が12鍵のキーボードでピッチベンドで組まなくても実現することができます。素数の音律になってくると2Hzから20,000Hzまでの音高を真面目に表現するには2,200個以上の鍵が必要になってきたりしますが、プログラムでは簡単に実現できます。
素数の音律はよく使われていました。《IS YOUR TIME》のサインウェーブのシーンもそうです。《Forest Symphony》は再展示されるごとにバージョンが変わるのですが、いまのバージョンはシンプルなサインウェーブが基本のプログラムになっていて、そこでも素数の音律を使っています。『LIFE WELL』もそうですね。
いわば、樹木からのデータや、霧の画像解析したデータが、鍵盤を押して発音するようなプログラムなのです。その各鍵に素数の音律をマッピングするときに、素数なんだけれども12平均律に近づけるカーブを使ったプログラムを用意したときに、坂本さんから褒めていただいたことがありました。音の基本中の基本のところを坂本さんはすごく大事にされていたんだと思います。
「設置音楽2 IS YOUR TIME」ICC
畠中──でもそれをやるには音律の勉強とかすごくしなきゃいけないですよね?
濱──はい、ものすごくしました。でも、最初は全然わからなくて。
──もともと大学で音楽を勉強されていたわけではないですよね?
濱──はい、IAMAS(岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー)に行ってそのあと多摩美術大学情報デザイン学科です。音にはものすごく興味があったし、音のことをやりたいと思ってたんです。多摩美に通っていたころ、大友良英さんのライブがICCであって、そのときの打ち上げで大友さんに挨拶して「手伝わせてください」ってお願いしたんです。それで、「今度、新宿ピットインにちょっと来て」と言われたのが始まりです。ギター持ちをしたりして。それからYCAMで開かれた「大友良英 ENSEMBLES」展★1(2008)のときに学生インターンとして参加して、2009年にYCAM InterLabのスタッフになりました。
『async』以降のコンサート──即興とプログラム
畠中──坂本さんとの関係が大きく変わる、頼りにされるようになったのはいつ頃からですか?
濱──大きく変わったのは、ニューヨークのパーク・アヴェニュー・アーモリーでの『async』のコンサート★2(2017)のプログラムを任されたときでしょうか。そのコンサートでは、『async』のサウンドトラックを再生する役割でした。楽譜を渡されて「andata」のここでスタートして、と指示をいただいて。音色ごとに分けられたトラックをいただいて、マルチチャンネルのスピーカーのセットアップでどこからどの音をどれぐらい出して、というような調整をして、坂本さんからの合図に合わせて、ポンと再生して。
畠中──えっ? ポン出しなの?
濱──はい。めちゃくちゃ緊張しました。「andata」のここでヌ〜!(坂本さんの合図)って。(笑)
畠中──(笑)すごいですね。
濱──4公演ほどありましたが、2回目以降ぐらいからは合図がどんどん省かれていきました。
畠中──あうんの呼吸で通じるようになるんですね。
濱──そのニューヨークのコンサートでは、プログラムならでは、といったことはあまりなくて、高谷さんの映像と同期するシンプルな再生ソフトを作ったという感じだったんです。その後のコンサートからプログラムを使ったいろんな仕掛けが出てきます。ガラスの楽器をマレットで擦るのと同時にシンセサイザーEMS SYNTHI-AKSをコントロールして発音するセンサーを組み合わせたプログラムだったり。「disintegration」や「ff」「ff2」では、発音の順番が演奏のたびに組み変わるようにして、音が鳴るその瞬間まで、坂本さんにもどの音がくるかわからないようなプログラムを作りました。その瞬間は即興になるんです。僕が関わったコンサートではそういう即興性というかリアルタイム性が増幅されるような仕掛けが、プログラムだけでなく色々とあって。例えば、外のリアルタイムの音をマイクで拾ってコンサート会場まで入れて、街の雑音がするなかで坂本さんが演奏されたり、全面水が張られた舞台で坂本さんが移動するごとに波が立つとか。
映画『坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async』予告編
畠中──濱さんは《LIFE—fluid, invisible, inaudible...》(2007)は最初からは関わってなくて、Ver.2(2013)からですよね。
濱──もともと矢坂健司★3さんが書かれたプログラムを引き継ぎ、《Forest Symphony》の音を入れたり、新しいシーンを追加したりしました。2013年のYCAMの展示では松本昭彦さん★4にほとんど担当していただいて、それ以降の展示では僕が担当して、というかたちです。
畠中──濱さんからアイデアを出して採用されなかった案はけっこうあったんですか?
濱──いっぱいあります。《water state 1》の初期制作段階に、水滴からできた波紋を水槽の横から撮影して、その形から音を作るということをやったんですけど、それは出音が良くなくてボツになりました。また、水面の波紋を水盤自体を振動子で揺らして作るシーンがあるのですが、いまはすごく低い周波数で揺らして波を作っていますが、もっと高い周波数で揺らすとビキーッと鏡が割れたようなサイケデリックな模様を水面に出すこともできるんです。坂本さんにお見せした時、見た目は面白がっていただいたのですけど、最終的にはその高い音が綺麗でないのでダメだね、ということになって。
畠中──《water state 1》は新作で、ああいう機構★5を作って、試行錯誤しながら時間をかけて、一緒に過ごしながら作れるっていうのは、YCAMならではでしょうね。
water state 1 at YCAM Satellite A from YCAM on Vimeo.
《water state 1(水の様態1)》
孤独な作業と共同制作
畠中──2022年のヴェネチア・ビエンナーレ日本館でのダムタイプの《2022》の展示では、坂本さんはダムタイプのメンバーとして参加されました。坂本さんは、個人での制作とダムタイプのメンバーとしてかかわるときとでは、共同作業における役割は違いますよね。それに対する濱さんの役割も変わると思います。
濱──坂本さん個人の作品制作では、坂本さんが最初にアイデアを話されて、それに対して何をどうできるか提案したり、方法を探したり、坂本さんから具体的な指示も出るし、ジャッジも的確にされます。
ダムタイプは、ほとんど何も決まっていない状態から、最初はメンバーそれぞれの関心事を話し合うことから始まります。いま作品を作るとはどういうことか、一体どんなテーマを立てるべきなのか、何をするべきなのかというレベルのことからずっと話をするんです。それぞれみんな考えてることが深すぎて、最初は理解できないです。理由も説明しないし。何度もミーティングを重ねるうちに、以前に話したり試作したアイデアがふわ〜〜とまるでなかったことかのように忘れられていく。でも実は、そうやって途方もない時間をかけてした話し合いや試行錯誤が、一見消えたようでいて、細部に重層して、締め切りギリギリまで積み重なって作品ができる、というような作り方なのです。なので、作品の細かいことにまで理由やストーリーがあったりします。あと、役割も曖昧で、僕が音のことをやらずに映像をずっと作っていることもあるし、メンバーそれぞれの興味や考えが最優先されるようなやり方ですね。
畠中──アイデア出し千本ノックみたいですね。ダムタイプはそれをできるだけの余裕がある。
濱──僕は人の話を聞いてそれにリアクションするのが好きな人間で、共同作業するアーティストからするとそれはもしかしたら嬉しいことかもしれませんね。勝手に解釈して、勝手に間違えた答えを出してくる(笑)。そうやってふくらんだり、いろんな答えを重ねていくことで作品に厚みが出てくる。
畠中──坂本さんのインスタレーション作品もそういう関係性があるから実現できたような気もします。それこそ『async』みたいなアルバムは完全な個人作業みたいなところがある。そういった個人作業とは逆に、インスタレーションの制作は基本的に共同作業で、人に「こういうことできる?」って聞ける、開かれた感じがあるように思います。
濱──そうですね、開かれた感じはありましたね。坂本さんがみんなのアイデアを吸収するようでいて、みんなも坂本さんからアイデアを受け取っていたのではないでしょうか。僕はそうです。そう考えると、「人生は短し」★6ではないですけど、面白いなと思う人とは会って、何かやっておかないと本当にもったいないですね。坂本さんはリモデルやリミックスで、また東北ユースオーケストラで、いろんな若いアーティストとコラボレーションされている。音楽のみならず、映画も、ラジオも、社会活動も、文筆も本当に多くの方と協働されていたり、新しい才能を見つけて応援されていたり、素晴らしいですよね。
畠中──坂本さんは共同作業の面白さやその意味もよくわかって、一緒に演奏するという行為がすごく好きなんだと思います。一方で『async』のようなソロアルバムをひとりで録音するという、切り分けがあったと思います。コラボレーターを活かすという部分もあったかもしれないですね。坂本さんが自分のいいところをうまく引き出してくれているな、と思ったことはありますか?
濱──坂本さんから任されて、こういうのはどうだろうって思って作っていくことに、とてもやりがいを感じていました。特定の作品のためではないアプリのアイデアを個人的にいただいて、作って返して、というようなやりとりも何度かありました。プログラマーはどういう発想をするのか見ていらっしゃったのかもしれません。いま思えば、こんなチャンスは本当に有り難くて、坂本さんにもっといろんなアイデアを送って使ってもらえばよかった、と反省しています。
ダムタイプ《2022》と「ダムタイプ|2022: remap」
畠中──ヴェネチアでのダムタイプ《2022》とアーティゾン美術館での「ダムタイプ|2022: remap」では、坂本さんが関わられたのはフィールドレコーディングのディスクと、
濱──中央の部屋の中の約1時間のサウンドトラックや、坂本さんからご友人に声をかけていただいて録音された地理の教科書のテキストを読み上げるトラックなどですね。
──あの部屋の部分はヴェネチアのときと同じですか?
濱──サウンドシステムは同じです。アーティゾン美術館の帰国展ではヴェネチアの日本館を90%のサイズで再現しています。90%ですが、大きさの印象はだいぶ違いました。アーティゾンでは壁面を木材で作ってるんで、響き具合も全然違います。ヴェネチアはボワーーンって響きやすい空間で、少しラウドにすると簡単に音が濁ってあまり綺麗に聞こえなかったんです。なので、静かめのボリュームで聴く作品に落とし込みました。でもアーティゾンでは、少し大きくしました。
畠中──ヴェネチアの設置は坂本さん自身は立ち会うことができなかったということですが、そこでも坂本さんによる音響設計はあったということでしょうか。
濱──現地での調整はお任せされていました。ヴェネチアに搬入に行く前に、坂本さんにダムタイプオフィスで回転スピーカーを聴いてもらいました。普通のスピーカもセットして、レーザーや平行光など簡単なインスタレーションのセットアップもして。坂本さんの1時間のトラックと、声のトラックと、フィールドレコーディングのトラックと、モールス信号をあわせて鳴らしてみて。そこで作品の内容がズンズン決まっていったように思います。
畠中──坂本さんはダムタイプのミーティングには入っていらっしゃったんですか?
濱──毎週のミーティングには参加されませんでしたが、高谷さんから連絡をしていただいて、ミーティングに応答していただくような形で共同作業を進めていました。また、ヴェネチア・ビエンナーレへの出展の話があがった初期の段階で、高谷さんと坂本さんの間でテーマについてやりとりされていたことも聞いていました。それとHolland Festivalで初演を行なった坂本さんの『TIME』(2021)というパフォーマンス作品があって、その制作に参加したメンバーも多かったので、そこからのテーマのつながりも大きかったと僕は思います。
「第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示帰国展 ダムタイプ|2022: remap」アーティゾン美術館での展示風景(2023)
音の次元と想像力
畠中──坂本さんは後年、S(サウンド)/N(ノイズ)/M(ミュージック)という言い方をされていましたが、「音」や「音楽」を区別するような言い方を避けていたようなところがあったと思います。その音やノイズの中に音楽を聴くんだ、というような。
音楽をCDなどでリリースする場合、それはまず「音楽」としてリリースされるし、みんな「音楽」として聴いてしまう。坂本さんにとっては、1音しか鳴ってないようなところに「音楽」があることを体験させるものとしてインスタレーションがあったんじゃないかと思うんです。濱さんと出会って、そういうことが実現できるようになったのかもしれないですね。
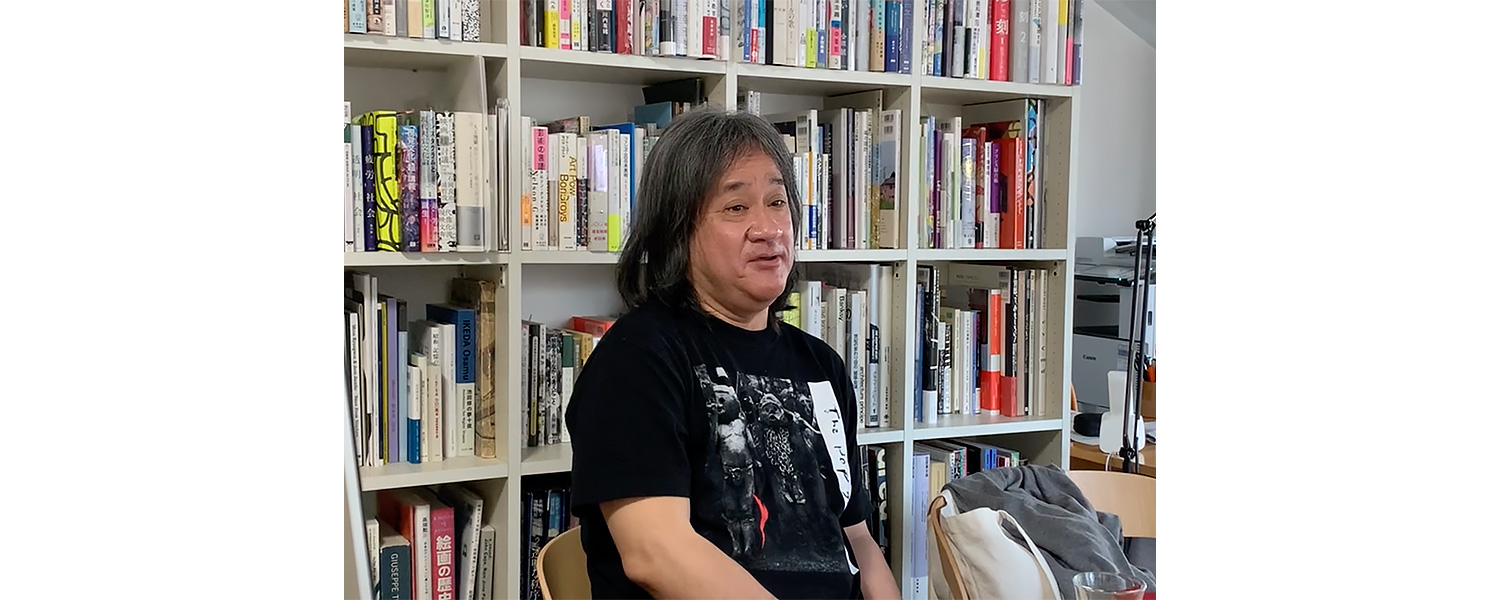
畠中実氏
濱──コンサートの話になるのですが、2019年にシンガポールで上演された「Fragments」は、高谷さんの《ST/LL》という舞台上に水を張った作品をやった後日、その水の舞台をそのまま流用して、その中にピアノやシンセ、ガラスの楽器なども入れたコンサートでした。そこで、会場の外で鳴っている音をマイクを使って取り入れたんです。コンサートの会場だけの音だったら、お客さんは今どの曲が始まったのかを聞く、用意された曲の世界に入ろうとしますよね。でも、外の音が一緒に鳴っていると、本当にちょうどいま、会場の外の世界で無関係に鳴っている予期せぬ音と、音楽の音が出会う場面に遭遇する。いまこの瞬間に起こる響きのほうにグッと注目させられる。そういう仕組みをコンサートに取り入れられたのがとても印象深いです。
それから《Forest Symphony》の最新バージョンでも外の音を利用した仕組みがあります。山口の常栄寺にある雪舟亭というお庭の本堂で、マイクで庭の音を拾って、テープループのような方法でメモリーし続けて、その再生位置を照度センサーで変化させています。太陽の前に雲が入って陰った瞬間に再生位置が過去の方にずれる。庭にはさまざまな音が自然に鳴っていて、本堂からも聞こえるのですが、さらにそのうえに、いまより少し前に鳴っていた音が重ねられる。
畠中──テープはずっと録音され続けているんですか?
濱──そうです。10分のバッファがあって。
畠中──一なるほど。10分経ったら上書きされてしまうんですね。
濱──はい。想定される最も明るい状況になったらほとんど今現在の音が再生され、最も暗くなったら10分前の音が再生されるというような仕組みです。
坂本さんのインスタレーションを思うとき、僕は次元のことをよく考えます。レコードを俯瞰すると、たった一本のひもがぐるぐる回って収まっているように見えます。厳密に言えば三次元の溝ですが、針によって一次元の電気信号に変換される。そうやって、一本のひもから起こされた電気信号を2個のステレオスピーカーで音として聴くと、人の想像力で音像が見える。例えばフィールドレコーディングされた音が流れると、それが鳴っていた過去の空間や状況を想像することができる。もしいくつも違ったフィールドレコーディングの音を同じ空間上で鳴らすと、それが何時のどこそことは同定できない新しい空間ができる。
畠中──時間の奥行きができるみたいな感じですね。
濱──そうですね。ほかにも、詩を読むように一次元の音の配列を解釈したりするのも楽しいですし、聴く身体そのものを知覚したり……音を楽しむ方法はそうやって様々に拡げられるんじゃないかと、考えが膨らみます。
Forest Symphony at Joeiji from YCAM on Vimeo.
《Forest Symphony》常栄寺
《IS YOUR TIME》ではたくさんのスピーカーを使いましたが、「ZURE」というトラックを使ったシーンでは音速を表現しました。会場の端のスピーカーから逆端のスピーカーまでひとつの音が音速で動いたら、というアイデアでした。こっちのスピーカーの近くにいるとブッという短い音しかしないのですが、逆サイドのスピーカーのほうに行くとブワ〜〜ンって、きれいに合成して聴こえるんです。その間を歩くとブとワ〜〜ンが徐々にくっつき始めたり離れたりする。会場ごとに室温やスピーカの距離を測定してちゃんと音速が表現されるように設定しました。バーチャルではなく、その場所の空間の物理を現わしているともいえます。音波の動きを感じるともいえるでしょうか。そうなってくると、ステレオで音楽を聴く想像力とはちょっと違う、別の想像力が喚起されるかと思います。
インスタレーション作品におけるリスナー
──インスタレーション作品で、坂本さんは聴者の位置、聴者の側のことをどういうふうに考えていらっしゃったのでしょうか。
濱──こういう聴き方じゃないといけないっていうのは多分ないような気がしますね。
畠中──坂本さんはまず一番のリスナーとしてそこに居るような気がします。インスタレーションって、その空間で音楽を体験する方法として、コンサートでもないし、ステレオで聴くでもない、特別なジャンルで、だからこそ自在に設計できる。さっきのマルチチャンネルみたいにね。
濱──そういえば、坂本さんはインスタレーションを作るときは、部屋の中心というより、少しずれたところや端に寄ったところにいらっしゃったような記憶があります。いま考えたら、真ん中で聴かれていたことってあんまりなかったかもしれません。どこで聴いてもいいというのが理想だったのかと思います。
もうひとつ印象的だったのが、坂本さんは作品がほぼ組み上がった段階で音量など最終の細かいチェックをするとき、作品をじっと見るのではなくスマートフォンを見られていることがありました。意図的に作品と距離をとって、わざとぼーっとすることで、意識が違うところにあっても何か引っかかるタイミングを探してらっしゃったのではと思います。真意を伺ったことはないのですが、いろんなお客さんがいて、何も知らずに連れてこられた人や、事情があって早く帰りたいと思っている人もいる。そんな人にも何か感じ取れるものがあるかを探ってらっしゃったのかなと。
畠中──作品には始まりも終わりもなくて、いつ帰ってもいいし、聴いても聴かなくてもいい。何か別のことをやってるときにも、飽きずに聴いていられるとか。坂本さんなりの音空間の設計方法があったんでしょうね。楽譜に書かれた音楽だったら全部自分がコントロールできるけど、インスタレーションって、例えばランダムの部分があったり、自分ですべてをコントロール出来ない。そういう要素を導入するのがインスタレーションの良さだったりする。それが坂本さんなりのチェックの仕方だったのかもしれないですね。
TIME──時を越える対話
──濱さんはアーティストとして、坂本さんからどんな影響を受けましたか。
濱──「TIME」というテーマです。長大な時間の視野をもてば、自分が近視眼的に悩んでいることがすごくちっぽけに感じられてくる。「芸術は長く、人生は短し」「TIME」その言葉を何度も反芻しています。
先日、日本語字幕で映画『ラストエンペラー』を見返したときに感動したシーンがありました。若き皇帝の溥儀と家庭教師のジョンストンとの会話で、「お互い問わず語りに相手の心の奥が分かる。孔子と荘子の対話だ」「尊敬に関する内容ですね」というセリフがありました。孔子と荘子は同じ時代に生きた人間ではありませんが、残された言葉によって、また言葉を残すことによって、時を超えて他者と心を通わすことができるという話です。そのために、そこには尊敬が必要なのです。
僕の勝手な妄想ですが、坂本さんも、ドビュッシーやバッハとまさに隣にいて対話するというようなことがあったのかな、と想像します。異なる時代に生きたアーティストとのコラボレーションがあったのではと。そう考えると、作ることって本当に面白くて。芸術をやるっていうのは、みんなでバトンを回していくことなんだなと思います。先も前もなく上も下もなく、そこには尊敬が欠かせない。なぜ人間は芸術をやるのか。すごく大きなテーマをいただいた気がしています。
畠中──自分の人生に収まらない、長い長い芸術をつくらないといけないということだったんでしょうね。
濱──はい。坂本さんとはいろんな作家の話をしました。僕がニューヨークでオフの日に「MoMAに行きます」と坂本さんに言ったら、「何を見るの」と聞かれて、「ブランクーシを見ます」と答えたら、「僕も大好き」って。それから他の画家の話に移って「僕はブラックが好き」とか、話に花が咲きました。ほかにもいろんな人の話をされていたことを覚えています。そんなとき、いつも楽しそうにされていました。時間的にも空間的にも遠く離れた人たちと、隣に、同じ地球に生きていると意識をすることが、僕にも出来るのでは、と今は強く思っています。
LIFE—fluid, invisible, inaudible... from YCAM on Vimeo.
《LIFE—fluid, invisible, inaudible...》(2007)
★1──「大友良英 ENSEMBLES」展(2008年7月5日〜10月13日)https://special.ycam.jp/otomo/
★2──「坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YOURK: async」というタイトルで映画化された。タイトルの「async」は「asynchronization(非同期)」からきている。
★3──90年代中頃からのサウンドエンジニア、プログラマーとして坂本龍一のサウンドインスタレーション作品をはじめ、さまざまなプロジェクトに関わる。https://synthax.jp/user-events/articles/is_your_time.html
★4──作曲家。アルゴリズムを駆使した音楽作品、インスタレーション作品を制作。プログラマーとしてもさまざまなアーティストの作品制作に関わる。http://akihikomatsumoto.com
★5──会場の中央に置かれた水をはった台座には、地球上の気象データをもとに水滴が落下する仕組みになっている。水滴の量やスピード、位置は変化し、照明やサウンドも変わっていく。装置はYCAM InterLabが開発した。https://www.ycam.jp/archive/works/water-state-1/
★6──坂本龍一の座右の銘「Ars longa, vita brevis(芸術は長く、人生は短し)」。元はヒポクラテスの言葉のラテン語訳。
■ 次ページに「資料編」として作品リスト(今後の予定を含む)を掲載




![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)