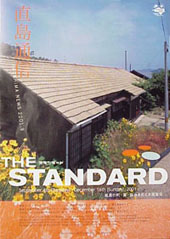 |
瀬戸内の小島を舞台にしながらも、直島コンテンポラリーアートミュージアム、そしてそれを運営するベネッセコーポレーションは、これまでも展覧会や収蔵作品において、またヴェネチアビエンナーレにおけるベネッセ賞の制定など、常に世界の美術界と向き合ってきた。
ここ数年は、島内に対象を広げた家プロジェクトも含めコミッションワークに重きを置いてきたが、今回は開館10周年を記して13名の日本人作家による展覧会を実施。もっともこれも会期設定からして明らかに横浜トリエンナーレ開催を意識しての企画であろう。
作品は、いずれも美術館の展示スペースを離れ、長い年月を経た民家や、路地、それに床屋や診療所として使われていた旧い建物など、直島の各所が会場となっている。
こうした場の選択は、直島という地域の固有性が特殊な形で突出するのではなく、かえって島の日常に浸透し、姿を見せていると捉えてのことだろう。そのうえで、現代の日常的な問題をとらえ、形で示したものとする作品達を選び、そうした島の日常の場=島の規範であり、他地域と比較した場合に直島の固有性を示す場、にあつらえることで、作家達、そして直島という場が示す「スタンダード」=「基準・規範」に対し、観客達自らがスタンダードとする状況を振り返ることをも目指しているとも言える。これもひそやかにカウンターパートとしての横浜トリエンナーレを意識したコンセプトなのだろうか。
さて、出品作家は、これまで展覧会や作品収蔵により直島との関わりの深い大竹伸朗、杉本博司、宮島達男といった国際的にも高い評価を受けている作家。今回のヴェネチアビエンナーレ出品の中村政人、また横浜トリエンナーレ出品の折元立身といった高注目度の作家。それに村瀬恭子 (1963年生) 、金村修(1964年生)、須田悦弘(1969年生)、野口里佳 (1971年生) といった若手をバランス良く配している。
特に地元岡山から1915年生まれの緑川洋一と、1980年生まれでまだ大学4年の鷹取雅一の二人を招いたてくれたのはとても嬉しい。
写真家として全国的な評価を受ける緑川は、近年の光溢れる瀬戸内の風景を見慣れた目には、こんな仕事もあったのだと、その足跡を再確認させる直島の精錬所やそこで働く人々を取り上げたルポルタージュ写真。
またこれまで、この欄でも幾度か取り上げてきた鷹取は、B5程の白い紙に露悪的とも受止められるほどのダイレクトな性的イメージをペン画で描きとめたものを、旧診療所跡の8畳ほどの部屋を使って、天井、壁、床とびっしりと並べている。
あまりの紙の量に、まずはその白い紙により占拠された空間が先にインパクトを与え、のちにそれぞれに書きとめられたイメージが顔を出してくるこのインスタレーションは、これまで表立って人に見せることのなかった彼の一面を、生理臭を巧みに取り除きながら提示しており、保護者のような気持ちの私はほっと一安心。
その他、宮島達雄のホスピスプロジェクトは、いつもながら周到な完成度の高さを見せ、また島に降り立った観客がまず目にするであろう大竹や折元の作品は、その作品を既に知る者にとっても、一瞥では立ち去れない力を発している。
もっともまだ開会当初に訪れたせいだろうが、ところどころに、こなれていない点が目についた。
たとえば、金村修の写真、木下晋の絵画などは、外光が直射する展示場所ゆえ、光の乱反射や映り込みで作品を正視することができなかった。また現在もお住まいの方がいらっしゃる場を使用しての展示では、杉本の作品は極めて限られた時間しか見ることができないことが現場に行って初めてわかり、また須田の作品を見るために、建物のどこまで入ってよいかがわからず難儀した。
また広域に渡る作品の設置場所を把握するための地図も最後まで入手することができず、チラシに表記された設置地域名と、これはこまめに設置された立て看板を頼りに探すこととなったが、それでもある地区ではまるで場所がわからず、ボランティアスタッフに聞いても道に迷うばかりであったのには閉口した。最初にガイドブックを買えばよかった。こうした点については、12月までの長い会期のなかで少しずつ是正され、熟成するだろう。
ともあれも、これだけ広域に島内に展開できたのも、また国際的に高い評価を受ける作家と共に、思い切った若手登用に踏み込めたのも、これまでの地道で、かつ確固たる積み上げがあったからこそ。不思議なもので同じ場所に同じ作品があっても、時が経つとそれがおさまり落ち着いて見えてくるものである。また改めて、今度は一泊くらいかけて、美術館周辺の作品、そしてついにお披露目となる内藤礼の家プロジェクト作品「ぎんざ」を含めて、この10年間の直島コンテンポラリーアートミュージアムの成果を堪能しに行きたい。


