キュレーターズノート
進化するラボ駆動型文化施設、課題解決から実験へ
──メディアセンター WaterShed
菅沼聖(いずれも山口情報芸術センター[YCAM])/竹下暁子
2017年11月01日号
本連載では国内外の文化施設の活動紹介を通じて、社会の中でのミュージアムの可能性を扱ってきた。狭義のミュージアムだけではなく、実験的な活動を展開する文化施設では、どのような取り組みが行なわれているのだろうか。今回はイギリス南西部ブリストルにおいて、都市再生の中核を担うメディアセンターWaterShed(ウォーターシェッド)の取り組みを紹介する。
 Artful Innovation, image by Shamphat Photography
Artful Innovation, image by Shamphat Photography
「変化のための実験」を続けるために
 Watershed, image by Geoff Causton
Watershed, image by Geoff Causton
ブリストルは新しいアイデアを実験し、方法を試すことができる都市です。私たちは急速に英国の創造文化の中心、実験都市になりつつあります★2。
近年、硬直化した状態から脱するために「実験」を謳う場面がとみに増えてきた。都市、企業、教育機関、何かを変える力学が規制や権益といった構造的な要因でうまく働かない中で、良くも悪くも「実験」という言葉は使われることになる。
90年代後半、イギリスは国家でそれを必要としていた。老いた大国というレッテルを剥がし、若々しい文化の表出や新しいコンセプトの提案が国策として求められた。当時の首相トニー・ブレアが打ち出した「クール・ブリタニア」に代表される国家ブランディング、創造産業立国を目指した「クリエイティブインダストリー」政策 がそれだ。もちろんその背景には急速な製造業の衰退に伴う失業者の受け皿の確保や国際的な経済競争力、地域再生など退路のない社会課題があったことは想像に難くない。国家という大船の舵を切り前進するには「実験」が必要だったのだ。
20年後の現在、脱工業化、知識産業への移行を「果たしたイギリス」と「果たせなかったイギリス」に見事に分断した。筆者は実験やイノベーションという言葉を無思考に礼賛し、推進したいわけではない。
「実験」とはつまるところ考えることである。考えることで試し、変えることができる。複雑さをます現代において、都度考えることの重要性はいうまでもないが、筆者の関心はそれを社会全体でどのように「続けられる」のか。否かだ。続けることなしには繰り返し試行することも、失敗から学ぶこともない。実験は継続することでようやくバランスを保つことができる。その意味で、イギリスにおいて30年以上実験を継続している文化施設から学ぶべきことは多いだろう。
都市再生の要としての文化施設

Watershed(ウォーターシェッド)は英国初のメディアセンターとして1982年にブリストルの港湾地区に誕生した。開館当初から映画事業に力を入れており、その多様なプログラム展開から英国の映画館の中での注目度は高い。近年は社会情勢に迅速に呼応し、クリエイティブ産業との関係性を強める実験的、領域横断的な枠組みを実装している。荒廃した港湾地区、仕事の流出、高い失業率など多くの問題を抱えた地域の再生計画の核として生まれた文化施設WaterShed。同地区は現在、創造産業のハブとして活気を再び取り戻した。開館から30年以上たつ今なお「都市とつながる」「人をつなげる」機能を最大化する装置として存在価値を高めている。
ここからは研修として2015〜2016年にWaterShedで勤務した竹下暁子氏(YCAMパフォーミングアーツ・プロデューサー)の協力のもと、現場の視点からWaterShedを読み解いていく。
「実験」を支える土壌
菅沼聖──WaterShedのウェブサイトを見ると館の活動の多様さが伝わります。トップページはシネマ情報が目立ちますが、スタジオやアーカイブをクリックすると魅力的なプロジェクトがたくさんでてきますね。多様さ故にYCAM同様、ある種の「わかりにくさ」があるように思います。地域からはどのように見られているのでしょうか。
竹下暁子──利用者の目的によって見え方は全然違います。地域住民には映画館として定着しているのでそのイメージが強いかもしれません。イギリスでは英国映画協会の活動が盛んで、映画の普及やアーカイブ事業に多くの補助金が出ます。WaterShedも複数のスクリーンでほぼ毎日上映をしていて、100席超の座席数ですが、満員御礼で入れないことも度々あります。
 Watershed cinema audience, image by Benjie Croce
Watershed cinema audience, image by Benjie Croce
菅沼──YCAMの図書館にイメージは近いですね。YCAMは複合文化施設なので図書館に来る日常利用のお客さんがたくさんいます。YCAMの展覧会は基本的に入場無料かつパブリックスペースで展示するので、図書館利用者がアートに偶発的に触れる体験設計になっています。こうしたベースとなる集客機能があるというのは共通点ですね。映画事業はどのように進めていくのですか?
竹下──WaterShedにはフィルムキュレーターが二人いて、テーマに基づいて上映をセレクトしていきます。国産の映画はもちろん、国際映画祭などに頻繁にリサーチに行き、地域性と国際性をバランス良く扱っていました。また、同じ南西部の地域の館同士のコネクションが強く、コストを抑える為に同じフィルムを持ち回りで上映することもあります。WaterShedのフルタイムの従業員はカフェや映画館合わせて約90人程度、その内の半数が文化教育(後述の人材育成やスタジオ事業)のスタッフです。年間の有料観客動員数は約15万人、総来場者数は約40万人にのぼります。
 Watershed Café/Bar, image by Toby Farrow
Watershed Café/Bar, image by Toby Farrow
竹下──それから、施設内にある飲食スペース「カフェバー」も地域住民からの認知度が高いです。 映画の鑑賞後の飲食や大学関係者、ビジネス目的のミーティング使用など使われ方はさまざまです。
菅沼──地域のニーズにしっかりと応えていますね。利用者の日常生活に近い、映画やカフェなどの恒常的な事業は施設の認知度やベースとなる集客モデルを築く効果は非常に高いと思います。これらの事業はどちらかと言うとサービスとしての性質が強いですよね。有料観客動員数の比率から収益モデルが気になります。
竹下──WaterShedの特徴は、映画、カフェバー、カンファレンスのコーディネート(貸館事業)の収益が安定して高いことです(参照:年次レポート)。イベント運営にも力を入れており、DJが入るクラブ的な雰囲気からアカデミックなカンファレンスまで幅広いニーズに対応しています。これらは施設のブランディングの一環としてしっかりと営業努力をしています。WaterShedは日本でいうところのNPOにあたる「チャリティー」団体の運営で、財源の一部となるこれらの収益確保にとても積極的です。
菅沼──強固な収益モデルをつくりだすのは、日本の文化施設が苦手とするところですね。年次レポートの収益構造を拝見しましたが、費目が細かく別れているのが印象的でした、収入源に大きな偏りがないのは、リスク分散の観点から施設運営の強みになりそうです。このモデルを確立するにはある程度の人口や立地が前提条件になると思います。WaterShedを取り巻く周囲の環境を教えてください。
竹下──立地がブリストル中心市街地にあることを活かした事業展開です。ウォータフロント開発により付近には科学館や図書館、ギャラリーなどがあり一帯は文化施設の集合地です。ブリストルは人口約44万人の小さな地方都市ですが、ロンドンへは列車で1時間半の近さなので人やモノの流通が盛んです。
菅沼──ロンドンや日本の主要都市の人口と比べると小さな規模なのがわかります。その分、スモールスケールな都市に対してひとつの文化施設が果たす役割、影響力は大きいと思います。僕は近年のWaterShedの活動しか知らなかったので、施設の根幹を支える映画事業やカフェの運営、収益の話などとても参考になりました。
都市の中に創造の交差点をつくる──Pervasive Media Studio
 Pervasive Media Studio, image by Paul Blakemore
Pervasive Media Studio, image by Paul Blakemore
竹下──映画館として歴史を築いてきたWaterShedの中でも、大きな転機になったのは2007年に始まった「Pervasive Media Studio(以下、PMstudio)」というレジデンス事業でしょう。WaterShedをプラットフォームとしてアーティストやクリエーター、研究者、技術者たちのコラボレーションを促し、あらゆるクリエイティブを支援する「人と人をつなげる」ためのラボ機能です。つながりのキーワードとして「アート」「コマーシャル」「テクノロジー」を用いています。共同制作、開発を主な活動手法とするYCAMと似ている部分があるかもしれません。PMstudioはクリエイティブ産業へのアプローチに積極的で、アウトプットをプロダクトやサービスといったかたちで広く普及していくことも目的の一つです。このスタジオの設立以降WaterShedが都市の中で果たす役割が大きく変化していきます。
菅沼──「Pervasive=普及する、浸透する」という意味ですよね。初めて聞いたときは驚きました。MITメディアラボが使う「Deploy=実装する」と似たものを感じます。社会と接続しようとする意思表明とでもいいますか。このスタジオはどのような人が利用するのでしょうか。
竹下──このレジデンス事業には常時100人程度の登録者がいて、公募で利用者を集めています。利用者の属性は「クリエイティブス」と呼ばれる人たちです。アーティスト、デザイナー、プログラマーなどのクリエーター、ウェアラブルテクノロジー、AI、IoT、ロボティクスなどの研究者や開発者、そのほかにも建築、ゲーム、食の専門家など多種多様な人材が対象です。公募はつねにオープンで国際的にかけますが、ブリストル地域からの参加者も多くいます。利用者は無償でシェアデスクやミーティングスペースなどを使用できます。投資効果の大きいものにはWaterShed側から有償でクリエーターを招聘したり、制作資金を提供する枠組みもあります。
菅沼──スタートアップやインキュベーションと感覚的には近いですね。その中にアートが入っていることが個人的に興味深いです。産業への還元を重視している一方、アーティストが得意とする非予定調和的な創造性への期待を感じます。僕が知っている中だと世界中でプロジェクションマッピング作品を展開している映像チーム「AntiVJ」も2010年までPMstudioに滞在していましたね。スタジオでの活動を通じて、個人から大きなチームとして活動し始めたきっかけになったと聞いています。人と人がつながり、領域横断する仕組みづくりに工夫がありそうです。
竹下──興味深い仕組みとしては、スタジオに専属のプロデューサーが複数人いて、定期的にプロジェクトの進捗をキャッチアップしアドバイスをすることです。その際、マッチングできそうな人や企業、適合性が高そうなプロジェクトの紹介をすることもあります。単身で活動するアーティストやクリエーターに対して、こういったサポートやコネクションの提供は、後の活動を大きく展開させるものになります。ほかにもクリエイティブ・テクノロジストと呼ばれる技術面のサポートをするスタッフも専属でいますが人数は1人です。
菅沼──YCAMのラボには技術スタッフが10名程度。比べてみると、PMstudioはプロデュース機能に特化していると言えますね。人と人が出会い、自律的に創作していくためのプラットフォームの整備に徹している。そもそもPMstudioはどういった経緯で生まれてきたのでしょうか?
竹下──2007年にWaterShedとサウスウェスト地域の複数の大学との連携でPMstudioが誕生しました。発足当初の目的はアカデミックとクリエイティブを横断し、社会と密接に関わる実践的なプロジェクトを生む場をつくることでした。現在でもスタジオ内には大学専属のデスクがあり教授や学生が出入りしています。大学側にとっては学生がPMstudioで実践を学べるという効果もあります。
PMstudioの設立にはデジタルアーカイブサイトDShed(2001)の試みも影響しています。例えばブリストルの都市課題であった高速インターネット回線の敷設をテーマに発足した「オンラインでアニメーションが見られる」システムを構築するプロジェクトでは、イギリス中の作家がオンラインで発表や鑑賞ができるような枠組みを目指していたそうです。インターネット草創期に、今日の動画共有サイトのアイデアがスモールスケールながら実験されていたことに驚きました。WaterShedは、90年代後半から2000年代前半まで、年々めまぐるしく運営体制が変わっています。こういった実験の積み重ねがかたちを変えていったものが現在のPMStudioです。
菅沼──いきなり始まったものではなく、過去の経験の蓄積で現在が形成されていることがよくわかりました。実験の中で生まれた「意味のある失敗と小さな成功の積み重ね」が、長い年月をかけて関わった人や周りの環境を変化させていくのでしょう。小さくはじめて成果を出していくプロセスは実験を中心とした物事の進め方のなかでの正攻法なのかもしれません。
都市とつながる/人と人をつなげる
菅沼──ほかにもPMstudioの「人と人をつなげる」機能を加速させて独自のプロジェクトを展開されていますよね。
竹下──2012年から「遊び」をキーワードに、テクノロジーを用いて都市の未来を考える「Playable City」という取り組みをしています。都市の公共空間に対してのアプローチのアイデアを公募し、それを実装していく一連のプログラムです。この枠組みはブリストルだけでなく世界中で採用され、ブラジル、東京、ナイジェリアなどで実施実績があります。
 Urbanimals by LAX, a Playable City project, image by Paul Blakemore
Urbanimals by LAX, a Playable City project, image by Paul Blakemore
竹下──地域にクリエイティブを実装する手法のひとつだと捉えています。プロジェクトの裏側にはまちづくり政策をベースとした社会実験の要素が並行して走っています。ブリストルで実施した時は、中心地から貧困地域まで社会課題のグラデーションに沿った立地に作品を設置して評価分析の調査をしました。作家とプランニング段階から評価方法との刷り合わせを行ない、制作を進めます。
 Trove by Studio Meineck at The Rooms Festival, image by Max McClure
Trove by Studio Meineck at The Rooms Festival, image by Max McClure
竹下──また、2012〜2016年のあいだに実施された「REACT」は、産学官を結び共同開発を促すプロジェクトです。sandbox(砂場)をキーワードに近隣大学の人文科学系研究室と企業がWaterShedをハブとして、(4年間で)73人の研究者と55の民間団体で計53組のコラボレーションプロジェクトを立ち上げました。歴史遺産研究をテーマにした「Heritage Sandbox」や7〜12才の教育コンテンツ開発を目的とした「Play Sandbox」など、ともすれば埋もれがちなアカデミックの知識体系をクリエイティブ産業の側面から再創造する作用があります。この資金獲得や連携のスキームは2008〜10年に実施した「Theatre Sandbox」や「Media Sandbox」というインキュベーション事業で得た知見を応用したものです。最初は小さな取り組みでも、繰り返し実施することでプロジェクトの精度が上がり、別の機会で開花する。WaterShedはそれを意図的に引き起こしているように思います。
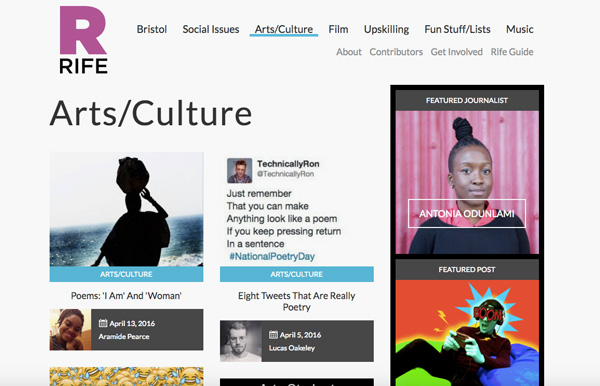 Rife magazineのウェブサイト
Rife magazineのウェブサイト
Rife magazineは主に20代前半向けのプロジェクトで人材育成要素が強いものです。これはイギリスが抱える「若者の失業率」という社会課題と関係があります。2015年当時イギリス全体の失業率は5.7パーセントですが若年層(16才〜24才)に絞ると14.4パーセントと非常に高い数値でした。この課題をどう克服していくのかは国家レベルの命題です。公募制で受け入れを行なうエディター養成プログラムではライティング、デザイン、写真、映像編集、SNS、ブランディングなどの技術を習得します。イギリスではこのような「ヤングタレントデベロップメント」がとても盛んです。この事業はPMstudioの主導ではなくWaterShedに元々あった人材育成部門の事業ですが、PMStudioのマインドに内部的にかなり影響を受けています。
菅沼──発足当初、WaterShed内の一事業にすぎなかったPMStudioが、今やWaterShedの運営全体に影響を与えていますね。映画はベースにありつつも、施設自体が変わろうとしている雰囲気を感じます。組織内に可変領域=ラボを持つことで柔軟なプロジェクト運営が可能になる好例だと思います。
竹下──「まだ名前がついていないことをやる」うえで周囲の理解は大切です。WaterShedではそのような枠組みづくりの巧みさも学びました。その中でもボードメンバーの関わり方が面白かったですね。ボードメンバーはいわゆる理事会です。地域のキーマンが配置されます。中には弁護士もいて、例えばPMstudioで生まれたアイデアに対する知的財産権の扱いなどを相談することもできます。メンバーに20代の若者(Rife magazineの卒業生だったことも)を入れる規定があって、どういう運営がいいかを提言します。これは珍しいことでもなくて、ほかの施設も若者を積極的に理事会に入れる傾向があります。
菅沼──日本では想像しにくい繊細なバランスで組織が構成されいるように思います。欧米の文化施設は地域再生や社会包摂政策(移民や格差、多様性などの諸問題)と蜜月関係を結び運用されていく「課題解決型文化施設」が成立していますね。喫緊の社会課題に対して文化施設が受け皿になり、形態を柔軟に変えながらも「実験」によって適応する。WaterShedの活動から今後の文化施設のひとつのあり方を見ることができました。
「課題解決型文化施設」から「ラボ駆動型文化施設」へ
 写真提供=山口情報芸術センター[YCAM]
写真提供=山口情報芸術センター[YCAM]
筆者の関心は実験の内容そのものより、それを可能にする社会的なフレームワークにある。全3回の連載では、実験性、公共性、継続性を持ったフレームワークとしての文化施設の運用のあり方を現場の視点から考察してきた。
都市におけるミュージアムに期待される役割として「地域活性化の鍵として」「異なる社会集団の融和の拠点として」「都市における情報のノードとして」などが挙げられ、さまざまな利活用の方法が議論、実践されている★2。今回のWaterShedの事例を照らし合わせると顕著だが、今後、押し寄せる社会課題の受け皿として「課題解決型文化施設」が増えていくことは間違いない。特に、日本国内において、人口減少が止まらぬ地方都市の公共文化施設は今後、都市部より早く「先進的な」課題に直面することになり、役割の転換を迫られることになるだろう。
しかし、ここで筆者が留意したいのは「課題解決」という枠組み自体が前提を、ひいては「限界」を無意識に自らの目の前につくってしまうことである。本連載では課題と向き合いながらも、実験と表現によって新たな価値の発見、提案を行なう「課題解決型」の一歩先をゆく、いわば「ラボ駆動型文化施設」の事例として3つの文化施設を紹介してきた。共通するキーワードとして、「ラボ」「アート」「テクノロジー」「オープン」「コラボレーション」といったものが挙げられる。今後、文化施設の創造性を考えるうえでひとつの指標となり得るが、同時にどれも数値的な評価、実証が難しく、社会実装するためには新たなスキームづくりが急務である。
今後、われわれの社会はどのようにアート表現やリスクを伴う実験性を受容していくのか。硬直化する社会の中で創造の源泉たる混沌をマネジメントすることは可能か。 実験を通じて確かな手応えを感じている文化施設も多い。今後、筆者自身が勤務しているYCAMでもこの問いに対し、実験をもって向き合い、社会と有機的に呼応する新たな文化施設像を提案していきたい。
★1──Peter Boyden Consultants “Culture, creativity and regeneration in Bristol: Three Stories” (2013)
★2──光岡寿郎「ミュージアム・ノート:都市を媒介する (artscape、2007)




![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)