キュレーターズノート
ヨコハマ国際映像祭のレビュー記事
住友文彦
2010年01月15日号
対象美術館
ヨコハマ国際映像祭の仕事で、前回の寄稿以降はほとんど展覧会を見に行っていない。そのため展覧会レビューを書くことはできないのだが、むしろ他の人が書いた展覧会レビューは丁寧に見たので、レビューのレビューのようなことを試みることにした。すでに発表されているものと未発表だが原稿が事前に届いているものから、それなりの数の人の目に触れると思われる紙媒体でまとまった分量のものを対象に書いてみる。順番は掲載時期にしたがうものとする。
まず、『Japan Times』11月6日(筆者:Andrew Maerkle)は実施概要を幅広く紹介するもので、後日13日には《PEPPERMINTA》のアジア・プレミアを行なったピピロッティ・リストへ自身が行なったインタビューを掲載した。とくに独自の視点がでているものではないが、記事のなかで取り上げる作品やプログラムに書き手の視点はおのずと現われる。シャンタル・アケルマンとイム・ミノックの作品がカメラが写し取った光景をいまそこあるもののように再現する際に、その日常的な光景をとらえる画像と音声による知覚経験が、審美的な体験の対象になるのを避けるような効果を持つことに言及している点が興味深い。
次は『朝日新聞』11月18日神奈川版(筆者:安部美香子)。鑑賞者に「見せる工夫」が不足している、という指摘が前面に出ている。その理由は解説パネルの文章が難解で、「難解な現代美術」を対象に企画したためだとしている。解説文はたしかに平易なものではない。しかし、それが観客に伝わらないと考えるのはマスメディアにはよくありがちな論旨で、逆に言えば非常に高い関心と知識を持つ観客がたくさんいることを切捨て、マスメディアの側が「観客」を専門性が高くないと見なしていることの弊害のほうが問題ではないだろうか。それともうひとつの指摘については、村田真氏のコメントを引用しながら「商業的な映像」も含めるべきだとしているが、これについてはまったく同意できない。
同じ日の全国版の『朝日新聞』夕刊(筆者:大西若人)は、展示の中身についてはいくつかの作品を紹介して「魅力的な作品もあるが、一般的にはなじみの薄い映像」と述べるにとどまり、むしろ事業予算や入場者数に文字数を割いている。
同じく全国紙では11月19日の『読売新聞』(筆者:市原尚士)がかなり異なる視点を提示していた。「アート」が成立する基盤となる作家と作品という表現のための形式になじまなくても、個人が他人に向けて何かを表現する行為そのものが重要であるならば、「現代美術」「映画」や「メディア・アート」の領域にそぐ わなくても重要視するのが、新港ピアの企画内容だった。この場所と野毛山動物園の展示を「開放性」があるとする内容で、とりわけそうした意図において重要でほとんど他のメディアが注目しなかったGraffiti Research Labの《アイ・ライター》を写真掲載していた。
『美術手帖』に掲載予定の記事(筆者:白坂ゆり)は、かなり網羅的に概要を紹介する。上映プログラムやワークショップなど、実際には見たり、参加したりすることができなかった人も多いプログラムについて文字の記録が残るのはありがたい。さまざまな紹介が続く最後に、映像を撮る動機を問う点は大いに重要と思われる。なぜなら、映像は個人的な制作として絵画や彫刻が留まっていられるのに比較すると、撮影と制作のプロセスにおいて他者と関わる可能性が高いメディアである。何を撮り、編集し、何を除外しているのか、についての自覚が問われるからである。
これも近いうちに批評誌『REAR』に掲載予定の「映像の開放に向けて」(筆者:星野太)は、映像を使う表現が上映からインスタレーションまでかなり多様な形式を持っていることについて、アルフレッド・ヒッチコックの『サイコ』を美術館で、ダグラス・ゴードンの《24時間サイコ》を劇場で上映することも原理的にはありえるとし、「映画」と「映像」の二項対立を受容形態を「恣意的な制度的分断」に過ぎないと指摘する。もちろん、制度的分断が「美術」や「映画」、あるいは「映像」を特定の過去の参照点に引き寄せやすくするうえでは、とりわけ歴史的な参照をするための美術館などで機能することは十分理解できる。しかし、映像を表現として扱う芸術家が非常に多く現われている現状において、受容形態の違いは、星野の言うように二次的なものでしかないように思われる。
この点はむしろ当然同意できるものだが、後半でより強調されている点は私にとって、自分の思考を進めていくうえでもとりわけ重要な指摘だった。それは映像を完結したかたちを持つ作品として使うだけではなく、コミュニケーションの道具としても使うフェスティバルだったことまでを視野に入れたうえで、「映像を美学的な言説の対象から開放する」と述べることである。映像が芸術表現にとって興味深いメディアであるのは、それが日常の生活においても私たちが繰り返し接しているものだからである。それゆえに、制度的な問題に足下をとらわれるよりも、「開放」と呼べるような新しい批評言語を鍛え上げることの緊急な要請もあるのではないだろうか。
総じて言えば、映像という分野に抵抗がある、あるいはそれを自分がすでになじんできる領域にひきつけて語る言葉が多かったように思うのが気になる。とくに芸術文化を語るジャーナリズムは、自分自身が何を問うているのかにもっと強い意識を向けてもらいたいし、作り手(企画者)にとって新しい関心を喚起するものであって欲しい。その点で、美術ジャーナリズムに関わる人たちは、繰り返し語られ陳腐化している問いを当てはめることで文章を作り上げていることが多く、どれだけの人が自らの問題意識によって現在直面している事態を次に進めようと考えているのだろうか。
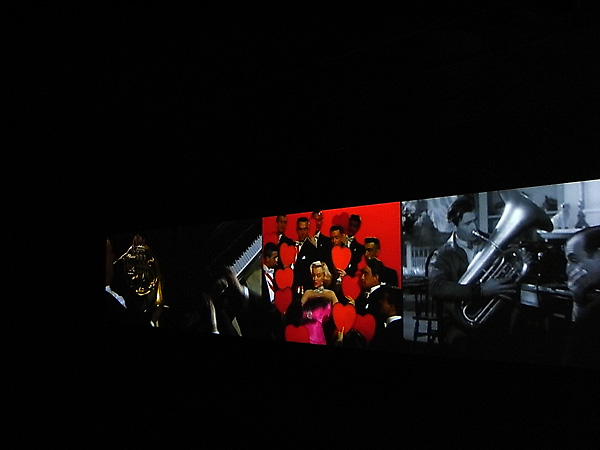
クリスチャン・マークレー《ヴィデオ・カルテット》


左=Graffiti Research Labのプロジェクト紹介展示
右=CHANNEL CREAM活動風景



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)