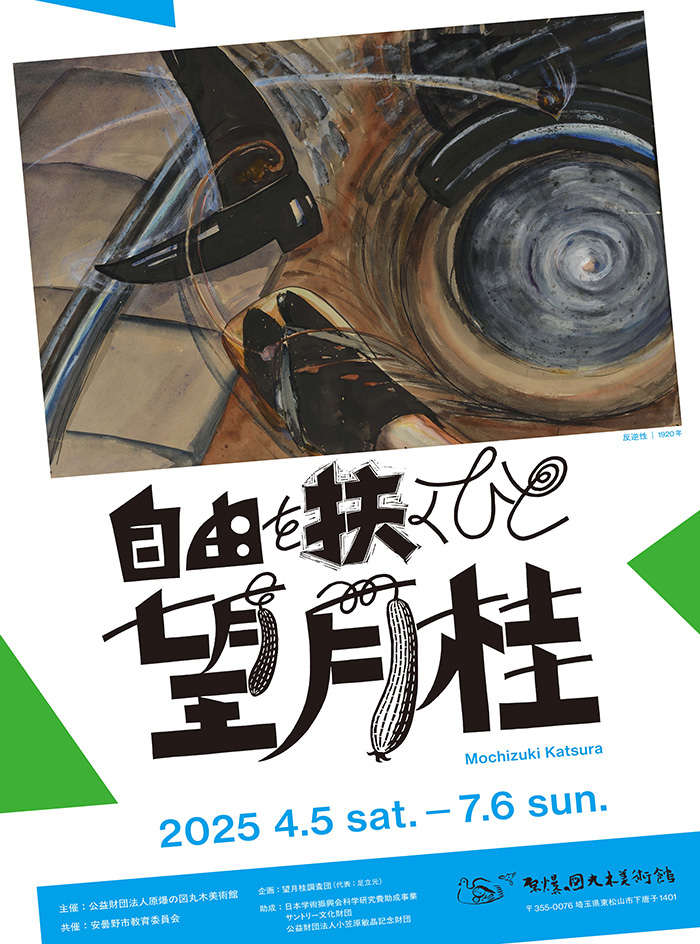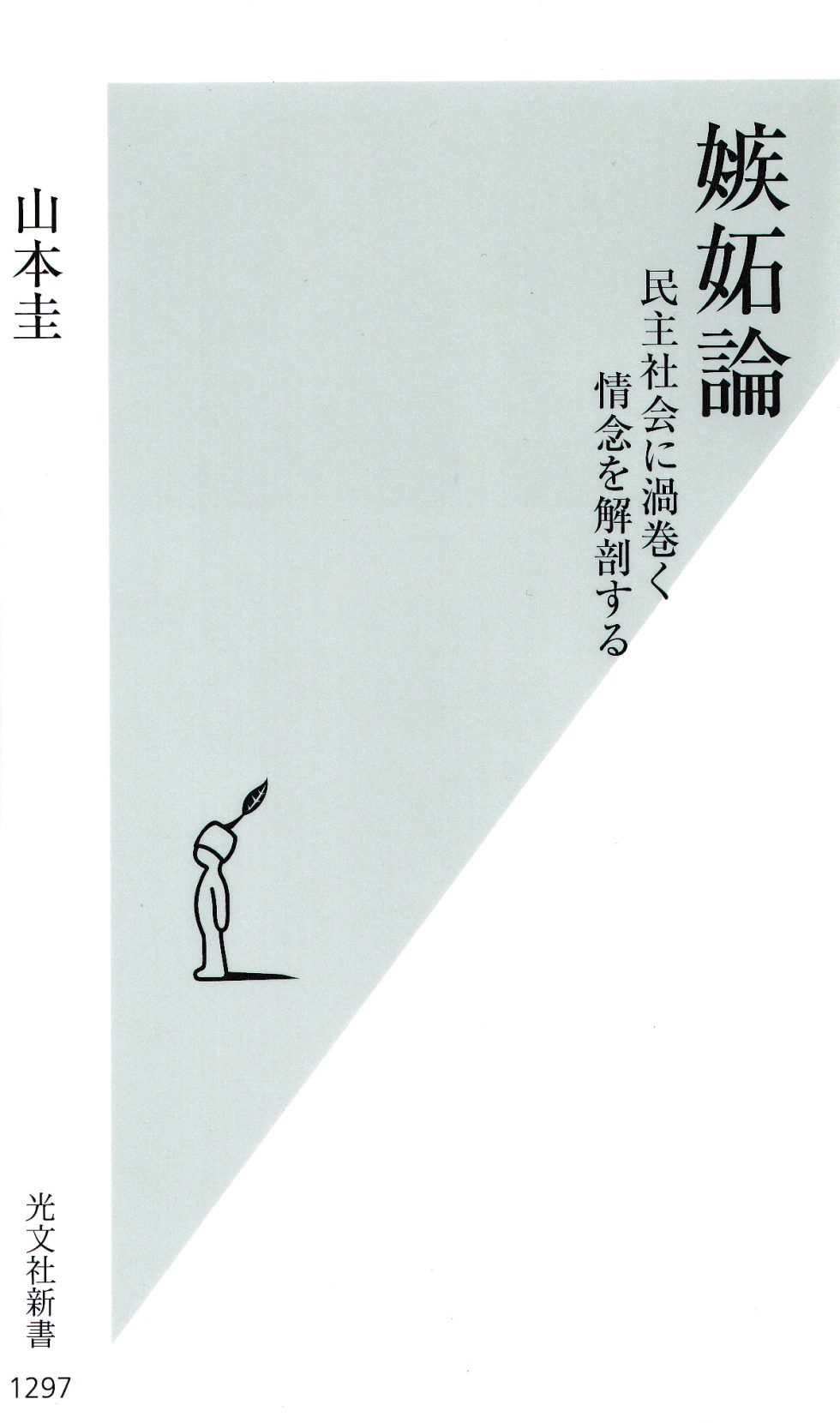
発行所:光文社
発行日:2024/02/29
嫉妬(心)というのは、おそらくほとんどの人間にとって無視しえないテーマだろう。にもかかわらず、この感情が学問的な考究の対象とされることは稀であった。人は往々にしてみずからの嫉妬心に向き合うことを、そしてそれ以上に、他人にその嫉妬心を嗅ぎつけられることを恐れる。かくしてこの厄介な感情は、これまで長らく公共の場から遠ざけられてきた。そうした状況にあって、この嫉妬というテーマに果敢に切り込んだのが、本書『嫉妬論』である。
本書は新書という体裁ながら、現代政治理論を専門とする著者の手腕が遺憾なく発揮された、読み応えのある一冊である。著者・山本圭(1981-)はこれまでにも、2017年の「嫉妬・正義・民主主義」(『ニュクス』第4号)を皮切りに、嫉妬を主題とする論文やエセーを断続的に発表してきた。それが一冊の本にまとめられることを心待ちにしていたのは評者だけではないだろうが、その成果がこうして広く世に問われたことの意味は大きい。
本書の大まかな構成を見ておこう。「プロローグ」とそれに続く第一章「嫉妬とは何か」においては、本書が問題とする「嫉妬」とはいかなるものかが明確に示される。そこでは、日常的にしばしば混同されがちな「嫉妬(envy)」と「ジェラシー(jealousy)」がそれぞれ「欠如」と「喪失」に関わるという指摘がなされるほか、「ルサンチマン」や「シャーデンフロイデ」といった隣接概念についても過不足のない説明がなされる。そのほかにも「上方嫉妬」と「下方嫉妬」の区別をはじめ、『嫉妬論』の入口を担うこのパートでは、のちの議論にかかわる交通整理がこのうえなくスムーズになされることが印象的である。
第二章「嫉妬の思想史」では、そこから一転して、人文学・社会科学の領域においてけっして頻繁に主題化されてきたとは言えない嫉妬の感情が、いわば歴史的に追跡される。古代ギリシアのプラトンから近代日本の福沢諭吉まで、過去の賢人たちが嫉妬についてどのようなことを考えていたのかを知りたい読者は、おそらくこの章にもっとも心を掴まれるだろう。
そして、本書後半にあたる第三章から第五章は、いわば理論篇である。これらの章は、むろん嫉妬を論じるものでありながら、それを誇示、正義、民主主義といったテーマと絡めることで、嫉妬という個人的な情念が政治思想に結びつくポイントを鮮やかに示してくれる。この後半のパートは、政治理論を専門とする著者だからこそ書きうる内容であり、その意味で本書最大の読みどころである。
最後になるが、本書は新書には珍しく、各節の議論のリソースとなる(多くは英語の)文献が明記されていることを特筆しておきたい。これらの書誌は、本書の学術的な信頼性を裏づけるものであるのはもちろんのこと、本書に刺激された読者が「嫉妬」をめぐるさらなる探求に赴くことを可能にしてくれる。学術的な論文作法と、一般書としての読みやすさを兼ね備えた本書のスタイルは、新書がとりうるひとつの理想的なかたちであると思われる。
執筆日:2024/04/07(日)