太田市美術館・図書館では、2024年7月13日から9月16日までの会期で「太田の美術vol.5『赭土でつながる─大槻三好・正田二郎・正田壤─』」を開催している。本展は、太田における重要な作家、作品および文化財をテーマにしたシリーズ「太田の美術」の一環として企画された展覧会で、今回は「赭土/赤土」をキーワードに3名の作家の作品や資料を紹介している。3名の作家、すなわち、大槻三好、正田二郎、正田壤のいずれも現在の行政区画における太田市出身の作家であるが、正田壤は学校や文化施設などの公共施設に作品が展示され、郷土の画家として認識されている感が強いものの、大槻と正田二郎の画家としての認知度は低いかもしれない。もっとも、大槻は太田で長年教員として勤め、小中学校の校歌の作詞もしているため、その面で記憶に残っている人は多いだろう。しかし、画家・正田二郎についての調査と評価は未だ進んでいない。
本稿では、「赭土でつながる」展についてご紹介したのち、正田二郎という画家を多くの方々に知っていただくため、彼の画業の一端について触れたい。
赭土でつながる──大槻三好・正田二郎・正田壤
 展示入口[撮影:吉江淳]
展示入口[撮影:吉江淳]
本展は、2022年度に当館に寄贈された正田壤(1928-2016)の資料のうち2点に記載された「赤土 AKATUTI」という言葉を発端に、1930年から1934年に太田に存在した洋画同好会「赭土会(あかつちかい)」と、これにかかわった太田の作家・大槻三好(1903-1987)、正田二郎(1907-1949)の作品を紹介し、その流れの先に正田壤の画業を見つめる展覧会である。
「赤土 AKATUTI」の記載があったのは、正田壤が1947年、19歳の頃に使用していた2冊のスケッチブックだ。正田壤はこの年から当時の境町立境中学校★1に勤務しており、教員としては3年目であった。それと同時に、1945年に東京美術学校(現・東京藝術大学)を受験するも失敗し、独学で画家を目指していたちょうどその頃である。その中身を見てみると、学校で働きつつ画家になるという明確な目標が滲み出ている。例えば、春休みや日曜、あるいは毎晩の日課として決めた描画訓練の内容や、自分に言い聞かせるために書き留めた絵画に邁進するための言葉。または、教務に関する記載として、生徒の評価についてのメモがあるといった具合である。
この正田壤によるスケッチブックの「赤土 AKATUTI」から連想されたのが、太田の美術グループ「赭土会」★2だ。筆者はそれまで、この「赭土会」については正田二郎の経歴のなかでのみ、目にしていた。正田壤の叔父であり、42歳という若さでこの世を去ってしまった画家・正田二郎。彼のプロフィールにある数少ない情報のひとつにこの「赭土会」で学んだということが記載されていた。壤のスケッチブックにある「赤土 AKATUTI」が二郎のプロフィールにある「赭土会」とつながるのではないか、と考え、調査に取り掛かり、展覧会企画へと至った。
 正田壤《スケッチブック》(1947)太田市美術館・図書館蔵[撮影:吉江淳]
正田壤《スケッチブック》(1947)太田市美術館・図書館蔵[撮影:吉江淳]
大槻三好と正田二郎
「赭土会」の活動を記録し、後世に残してくれていたのは、太田出身の歌人であり、教育者であり、文学研究者であり、画家でもあった大槻三好である。大槻は、群馬県師範学校で学び、在学中3年の頃に油彩画を始めた。学生同士で組織した絵画同好会「曙会」では、1921年から始まった展覧会「曙会展」において運営面を担い、自らも出品しつつ活躍。それと同時に、『上毛新聞』記者の柳芳太郎(1903-1978)と出会い、彼に請われて同紙の文芸欄「日曜文芸」に版画を提供することになった。師範学校卒業後は、太田に戻り教師をしながら郷土の文芸発展に寄与する活動を多様に展開。そのひとつが「赭土会」だった。
結果として「赭土会」とは、太田における教員を中心とした洋画同好会であった。会の活動としては、展覧会「赭土会展」の開催、裸婦デッサン講習会の実施などである。この会の発起人が大槻である確証は得られていないが、大槻は学校に勤めてからも何度か太田で個展を開いているし、絵画を学び合う同好会の結成やグループ展の開催を目論むような発言をしたりしているため、その中心的人物であった可能性は高いと思われる★3。
今回の調査にあたってもっとも参考になった文献が大槻の残した『太平楽(たっぺいらく)』(1986)と『恩頼抄』(1980)である。『太平楽』は大槻最晩年の自伝的な著書だ。そこに「赭土会」の記載を見つけたことで、会の概要を知ることができ、そこから芋づる式に新聞記事や、展覧会場であった当時の小学校の日誌を調査し、事実確認をすることができた。しかし残念ながら、結果として正田壤の「赤土 AKATUTI」と「赭土会」とのつながりは見出すことができなかった。「赭土会」が雲散霧消してから13年ののち、「赤土」がどうしてまた美術の文脈に現われたのか。それについては今後も調査を続けていきたい。
その一方で、嬉しい発見もあった。それは、大槻三好と正田二郎に画家としてのつながりがあったことがわかったことである。
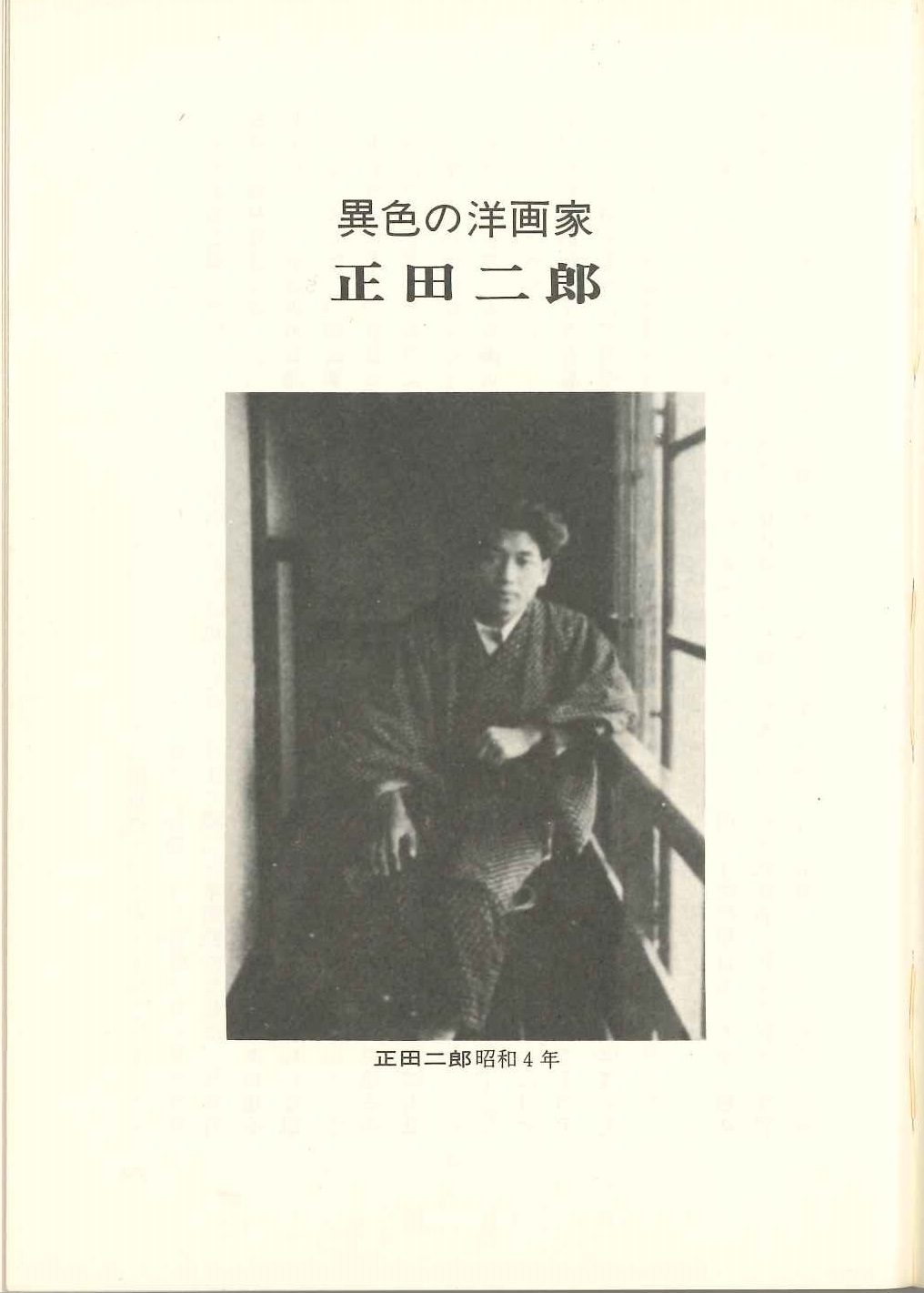
大槻三好の著書『恩頼抄』は、大槻と付き合いがあり、敬慕している作家や文化人について、彼の視点でまとめた著書である。そのなかの一人に正田二郎がいる。本展で筆者がもっとも参考にした正田二郎資料は、大槻が著した「異色の洋画家・正田二郎」★4という文章だ。両者の出会い、画家としての交流、二郎の東京での生活、作品の行方、疎開後の暮らしぶり、そして二郎が胸に抱いていた野望。そういったことが大槻の文章から明らかになった。また、それ以外にも、大槻旧蔵のスクラップブックには、二郎からの絵葉書が何枚も保存されており、絵葉書には大槻に宛てた手紙の文面が読み取れるものもあった。
ここで、正田二郎についてご紹介したい。正田二郎は正田壤の父である正田太郎の弟として新田郡綿打村大字花香塚(現・太田市新田花香塚町)に生まれ、旧制太田中学校を卒業後しばらくして前橋に転居し、群馬県庁に勤めた。油彩画は太田中在学時から始めており、県庁在勤中に出品した《M市公園》(1931)が「第12回帝国美術院展覧会」(以降、「帝展」と記載)に初入選。これがきっかけで上京を果たし、茨城県出身の画家・熊岡美彦(1889-1944)に師事し、本格的に画家としての歩みを進めた。熊岡が組織した美術団体「東光会」を主な活躍の場とし、その他「帝展」などの官展にも入選を果たした。しかし、太田中学校卒業後から患っていた病により、入院や全身を拘束されるような療養を強いられながらの制作であり、戦争により埼玉に疎開したのち1949年に42歳という若さでこの世を去ってしまった。
 正田二郎 肖像写真、個人蔵[撮影:吉江淳]
正田二郎 肖像写真、個人蔵[撮影:吉江淳]
正田二郎の画業と彼が目指していたこと
正田二郎は、大槻により「育ちのよさから備わる貴公子タイプ・温厚寡黙」★5と形容され、残されている二郎から兄・太郎へ宛てた手紙にも、いかにも慎重派で丁寧に事を進める様子が垣間見れる。戦争により多くの作品は消失してしまっているが、残された作品のほとんどが風景であり、都市の建物と木々、群馬の風景、千葉や秋田の海景などが確認されている。1939年の「第3回新文展」に入選した《農家の昼》は、当時の生活が窺える寂れた家の上り框に一人の男性が腰掛ける作品で、高い評価を受けたという★6。
さて、二郎は上京後、麹町に住みながら日比谷公園内にある東京市政会館内6階に事務所を構えていた「国政研究会」★7という組織で図書係として働いていた。当時の美術雑誌の消息欄によると、1935年まで麹町に住んでいたようだ。ここで二郎は数々の東京の風景を描いた。そのなかのひとつに、《議事堂風景》(1933)がある。
 左:正田二郎《M市公園》(1931)群馬県立近代美術館蔵/右:正田二郎《議事堂風景》(1933)豊郷町蔵[筆者撮影]
左:正田二郎《M市公園》(1931)群馬県立近代美術館蔵/右:正田二郎《議事堂風景》(1933)豊郷町蔵[筆者撮影]
本作は、当時二郎が住んでいた麹町の辺りから、国会議事堂を、我々に馴染みのある東正面からではなく、西正面から捉えた作品であると考えられる。国会議事堂の竣工は1936年11月であるが、『帝国議会議事堂建築の概要』★8によると、1930年末に本館の石積み全部が完了し、同時に外装全般の工事が進められたという。つまり、この頃には外観はおよそ現在の国会議事堂と違わぬ様子になっていたということだ。二郎は1933年に上京したと考えられるため、上京後間もなく取り掛かった作品と思われる。作品自体を見てみると、二郎の作品に特有の、視線を画面の奥に誘う構図で緻密に描かれている。高い塀が立ち並ぶ道路、瀟酒な家が描きこまれている様子からは、いかにも高級住宅街からの眺めのように見える。
一方で、同時期に国会議事堂を描いた画家として知られているのは、京都出身の画家・津田青楓(1880-1978)だろう。津田は、日本画、染織、洋画を学んだのち、日露戦争への出征を経て、その後フランスへ留学。帰国後は夏目漱石に出会い、漱石に油彩画の指導をするなどした。その後、二科会の創立に参加しつつ、油彩画、日本画、短歌など幅広く制作するとともに、プロレタリア運動に接近して関連する作品を描くようになる。それが、国会議事堂を描いた2点の作品、《ブルジョワ議会と民衆の生活》(1931年の下絵のみ現存)、そして《犠牲者》(1933)だ。津田は、できあがりつつある白亜の殿堂たる国会議事堂を社会の資本家階層の象徴として描き、その手前に民衆を象徴するモチーフ、すなわちバラック小屋や、官憲に拷問を受けて命を落とした小林多喜二に着想を得た、痛々しい人物像を描いた。
正田二郎と津田青楓が描いたそれぞれの国会議事堂。ほぼ同時期に描かれていながら、その捉え方は180度違うと言って良いだろう。すなわち、国家の中枢としての国会議事堂を都会の風景の一番目立つ位置に取り込み、自らの絵画形式の一部に組み込んでしまう二郎と、社会的な視点から国会議事堂を象徴的に取り込み、その社会告発的な思想を増強させる津田。二郎がどのような想いで国会議事堂を描いていたかは、今となっては知る由もない。しかし、国政研究会で働き、見掛け上体制側であったように見えてしまう二郎にとっては、できたばかりの国会議事堂を描くのも自然の流れだったのかもしれない。
最後に、正田二郎が残した言葉について触れたい。今回の展覧会に際しての調査では、数々の文献、書簡等を多くの方々の協力を得て拝見することができた。そのなかで特に印象的だったのが、二郎が地元群馬の風景を称賛する言葉だ。例えば、二郎が大槻三好に当てた葉書の末尾には「此の間は奥多摩へ紅葉を描きに行つて見ました。群馬の山を見てからですからさつぱり面白くもありません」と綴られている。また、1940年1月21日付の『上毛新聞』に掲載された二郎のエッセイ「故郷・個人展・顔」には、二郎が風邪をひきながら東京から前橋へ電車で移動する場面の描写として、次のように記載されている。「前橋への車窓、深谷あたり迄来て昨日あたり降つた白雪に夕陽を受けた赤城山、浅間、妙義そして奥上州の山、山、視界をさへぎる雲の形。こんな風景は何よりの妙薬で忽ち元気回復した」。
 正田二郎《榛名富士》(制作年不詳)太田市蔵
正田二郎《榛名富士》(制作年不詳)太田市蔵
二郎は群馬の風景をこよなく愛し、身体の不調をおしても制作を続けた。画家として諦めない姿勢は美術雑誌の展評でも触れられている★9。晩年は群馬にほど近い埼玉県に疎開していたため、群馬の山を眺めつつ暮らしていたことが想像される。二郎は終戦後、大槻三好に向けて、次のような言葉を送っていた。
終戦後に於ける社会的の混乱が落付きますと、吾々芸術人の使命も重要性を加えて参りますし、武力戦経済戦に敗退せる今後は、文化方面にて世界に進出せねばならぬと思って居ます。★10
二郎は世界を見据えていたが、この言葉を送った4年後にこの世を去ってしまった。絵葉書や展覧会目録に残された出品作の図版を見てみると、毎回実験をするように少しずつスタイルを変え、独自の表現を手に入れようと邁進していた様子がわかる。そうした試行錯誤のうえに、自身のスタイルを見出して画家として生きていこうとしているその最中に亡くなってしまったのだ。
本展の調査で、彼の足跡や作品の所在が少しずつわかってきたものの、まだ調べるべきことはあり、そのうえで美術史に紐づけて語られていくことが必要であると考える。今後も継続して調査を続けつつ、正田二郎という画家と太田の美術を深めていきたい。
★1──1964年に島中学校と統合し境町立境南中学校、その後伊勢崎市立境南中学校となり今に至る。
★2──それまでは「赭会」と記載されたりしていたが、このたびの調査で、当時の史料から「赭土会(あかつちかい)」であることが明確になった。
★3──1925年4月26日付『上毛新聞』の「消息」欄には「大槻三好氏 東毛在住の画家を以、近くグループを作り大展覧会開催の計画中」と記載がある。
★4──『恩頼抄』pp.73-82
★5──前掲書、p.77
★6──『日展史13(新文展編 1)』の細野正信による「総論」には、一般入選作の特筆すべき作品について触れられており、正田二郎の当該作品も「日本的風土を油彩で良くとらえた正田二郎の《農家の昼》」として言及されている。(細野正信「総論」『日展史. 13(新文展編 1)』日展、1984、p.669)
★7──国政研究会とは、中島飛行機株式会社の創業者である中島知久平(1884-1949)が設立した日本初のシンクタンクと言われる組織。1931(昭和6)年に設立され、1940(昭和15)年に廃止された。
★8──大蔵省営繕管財局編『帝国議会議事堂建築の概要』大蔵省営繕管財局、1936、p.38
★9──渡邊浩三、野口謙蔵「東光会展合評」(『美術』第12巻第4号、美術発行所、1937、p.8)に次のようなコメントがある。「渡邊──あんなに病気して、よくこれだけ描けたものだ、小さい方が特に美しい。 野口──さうだね」。なお、この時は白根山を描いたと思われる《火口》と木々を大胆に配置した《早春》を出品しているが、どちらが「小さい方」かは不明である。
★10──「異色の画家・正田二郎」『恩頼抄』pp.81-82
太田の美術vol.5「赭土でつながる─大槻三好・正田二郎・正田壤─」
会期:2024年7月13日(土)~9月16日(月・祝)
会場:太田市美術館・図書館(群馬県太田市東本町16番地30)
公式サイト:https://www.artmuseumlibraryota.jp/post_artmuseum/187612.html







