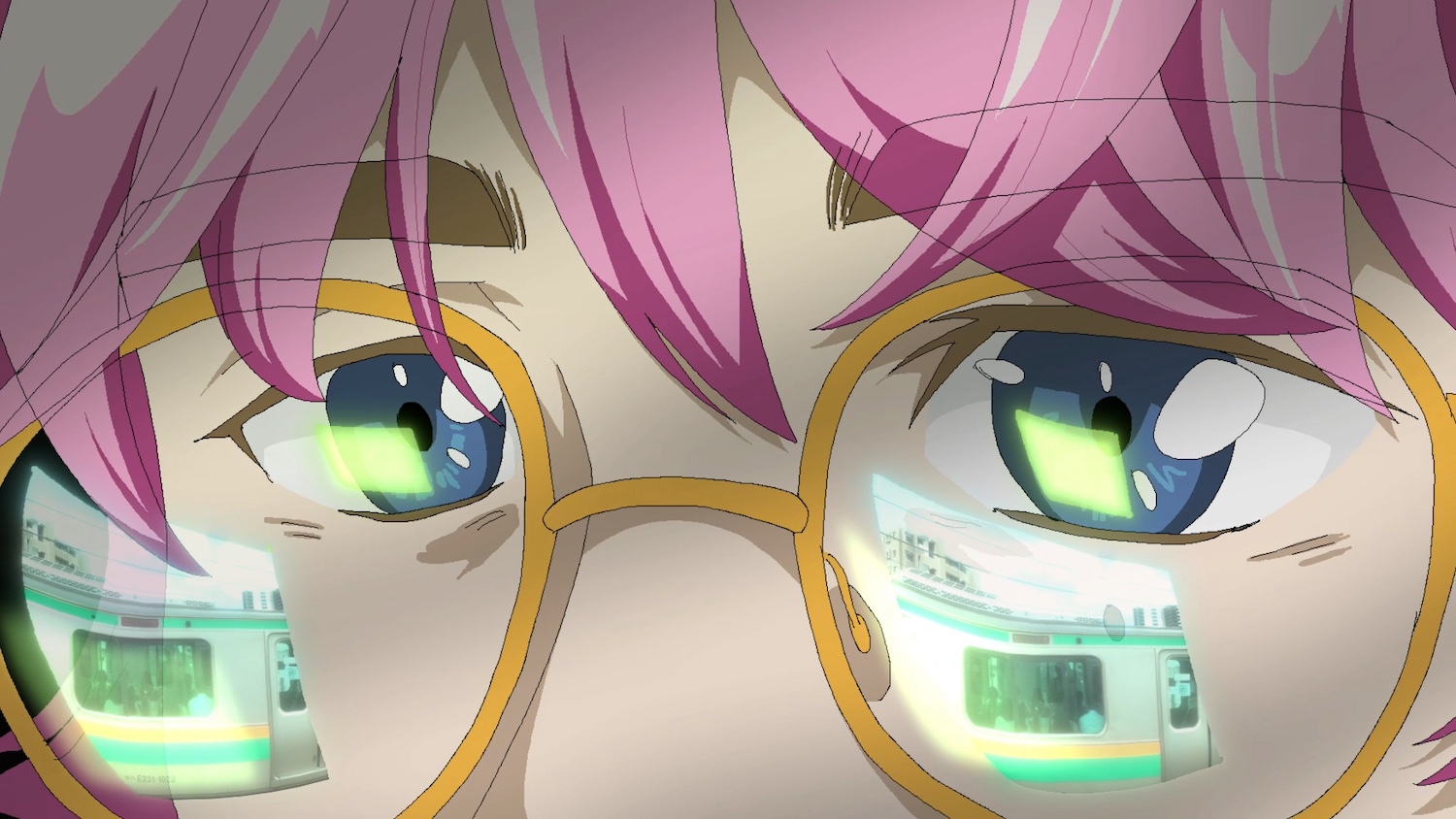会期:2024/07/13〜2024/09/28
会場:神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]
公式サイト:https://www.moma.pref.kanagawa.jp/exhibition/2024-ishida-takashi/
(前編から)
近年積極的に取り組まれている絵画やドローイングも、そうした作家の欲望の延長線上に位置付けられるだろう。大型絵画では多くの作品が制作されたであろうアトリエを舞台装置に、そこで幻視したビジョンが生々しさを保ったまま定着されている。さらに会期中公開制作が進められている新作や、初めて公に展示されたドローイングやスケッチブックからも、その描く身体を垣間見ることができ、作家にとってそれが重要なテーマであることは明らかだ。
 「石田尚志 絵と窓の間」展示風景[撮影:白井晴幸]
「石田尚志 絵と窓の間」展示風景[撮影:白井晴幸]
このたびの展覧会は、近年初めて発表された陶芸や写真作品も含め、ますます広がりを見せる作家の仕事を通覧することで、石田のそもそもの制作動機について改めて考える機会となっていたように思う。このような思考に導かれたのは、展覧会の締めくくりに、6歳の頃に描かれた《幼児期の画》(1978)が展示されていたことが大きい。石田は、線と色が予期せぬ形となることを絵を描く原体験として語っており★7、《絵馬》(1990)と並び《幼児期の画》を今回の展示で特に向き合いたい作品に挙げている★8。

石田尚志《幼児期の画》(1978)[撮影:白井晴幸]
 石田尚志《幼児期の画》(1978)[撮影:白井晴幸]
石田尚志《幼児期の画》(1978)[撮影:白井晴幸]
クレヨンで描かれたそのキャラクターたちは「かいじゅう」と呼ばれており、ここから私は、モーリス・センダックによる絵本『かいじゅうたちのいるところ』を連想した。同作はまるで石田の映像作品のように部屋が変容し、草木の生い茂る野原になってしまうところから本格的に物語が展開される。部屋とは現実の空間でありながら、虚構が入り込む不思議な空間なのだ。石田とセンダックは、そのような認識を共有している。しかしセンダックは部屋の変容以降、主人公・マックスに大海原を航海させることで、ファンタジーという彼岸へと向かい、そこで「かいじゅう」たちとの交流を描いているのだが、それに対して石田の諸作品に登場する部屋は、現実空間という此岸に留まりながら、むしろ混沌という名の「かいじゅう」を、こちら側に引きずり出そうとしている点に違いがある。
世界との先触れに、ひとりの人間として対峙し続けること。およそ10年ぶりの大規模個展で浮かび上がってきたのは、そのような作家の根源的なモチベーションであり、流行はもちろん、実験映画やアートといったジャンルや制度からも遠く離れた「ことの領域」★9で繰り広げられるそんな原初との出会いを、石田は飽くことなく今後も追求してくれるだろう★10。

石田尚志《窓-2》(2022)[撮影:白井晴幸]

石田尚志《窓-3》(2023)[撮影:白井晴幸]
ところで、『かいじゅうたちのいるところ』には別の翻訳が存在している。現在流通している冨山房版は1975年に初版が発行されたものであり、そこから遡ること1966年に、ウエザヒル出版社から最初の日本語版が出版されている。アメリカの絵本を紹介するシリーズのなかの一冊で、監修委員にはあの三島由紀夫も名を連ねている。翻訳は音読を想定したリズミカルな七五調であり、それにならって冨山房版とは異なるタイトルが付けられている。石田は《幼児期の画》を描いているとき「一人で少し喋りながら描いていたように思う」★11と回想をしているのだが、もしかしたら、その『かいじゅうたちのいるところ』の最初の邦題をつぶやいていたのではないだろうか。
「いるいる おばけが すんでいる」と。
★7──「石田尚志への質問」(『石田尚志「弧状の光」』、青森公立大学国際芸術センター[ACAC]、2020、p.68)
★8──石田尚志「ことの領域/ことばの領域」(『石田尚志 絵と窓の間』、ケンエレブックス、2024、pp.268-275)
★9──同上。
★10──その点において、前掲★1の文章で三本松も触れているように、同展初出の新作映像《夜の海》(2024)における「緩やかな時間」は、今後の制作の展開を予感させるような作品になっている。
★11──前掲★8。
鑑賞日:2024/08/24(土)
関連レビュー
石田尚志「渦まく光」|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2015年05月15日号)
石田尚志──渦まく光|村田真:artscapeレビュー(2015年04月15日号)