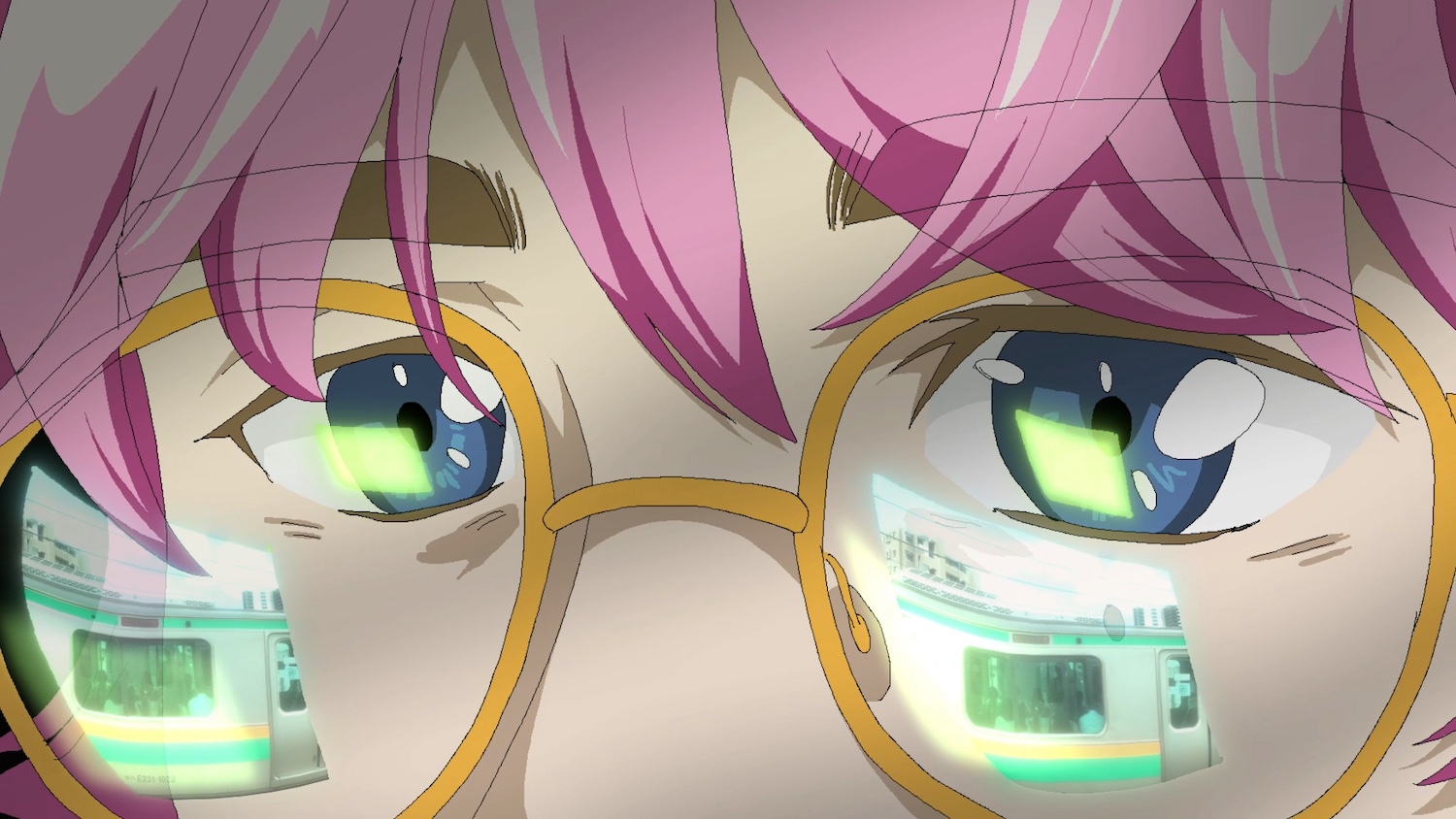会期:2024/9/21~2024/11/10
会場:岡山県立美術館[岡山県]
公式サイト:https://okayama-kenbi.info/events/event/20240921-fujiwara/
岡山県立美術館で、音の表現者である藤原和道の展覧会が開催された。藤原は1970年初頭にときわ画廊や田村画廊を通じて作品を発表し、松澤宥と交流するなど、前衛の気配を残す日本美術との関わりが深い作家である。と同時に、1988年以降はメディアアーティストとマスメディアが邂逅した時代の機運のなかで、音にまつわるコンテンツプロデューサーとしても活躍した。その両方の側面を知ることができる初めての美術館展覧会が、彼の出身地である岡山県で催された。
前半のゾーンは藤原が作曲を学んでいたことから始まり、彼の代表作である「音響標定」が記録写真とともに大きく紹介された。「音響標定」は数人がかりで巨大な「音具」を奏でるパフォーマンスコンサートである。たとえば1970年にときわ画廊で発表された「音響標定」のシリーズ「YOBOUE」は、木とコンクリートによる直径1.5メートルほどの円柱の側面に4本の棒が十字に突き出すように配され、その棒を複数人で押し回して音を出す。
「音響標定」は70年代に15回ほど行なわれたとされ、記録写真が残っている7つの展示ではすべて異なるかたちの音具が使われている。「YOBOUE」(1970年10月19日〜24日)、「音響標定〔田村画廊前〕」(1971年5月28日〜30日)、「音会」(1971年7月10日〜11日)、「音響標定 サウンド・ロケ第4」(1972年5月10日〜6月5日)、「音響標定 No.5」(1972年11月11日〜13日)、「石の歌」(1973年)、「音響標定〔渋谷山手協会隣り空き地〕」(1974年6月5日〜11日)において、「石の歌」を除くいずれもが巨大である。尋常ならざる労苦で組み立てられ、演奏されたことが窺える。
とくに西武が有した敷地で演奏した「音響標定〔渋谷山手教会隣り空き地〕」は、クレーンを用いた大掛かりなもので、数ヶ月にわたる準備ののち、予定していた展示期間の最終日を過ぎた時刻に完成し、4時間の演奏を経て解体された。このときの記録を、かわなかのぶひろが映像作品としてまとめており、会場では58分31秒の全編を見ることができた。展示記録の映像としては珍しく細かくカットが割られ、藤原が水に浮かぶ巨大な丸太を東京湾で購入するところから、音具が解体される終幕までを捉えている。この作業には畦地拓治のほか、天井桟敷のメンバーが多く協力したという★1。
「音響標定」の記録は同時代の作家によって撮影されている点も特色である。藤原の活動は田中孝道、楠野裕司、安齋重男が撮影したほか、とくに「音響標定 サウンド・ロケ第4」は同じ音具の演奏を、榎倉康二と山崎博がそれぞれに写した写真が残っている★2。
こうした「音響標定」の活動によって、藤原は1975年にパリ、76年にヴェネツィアと立て続けに国際ビエンナーレに招聘される。しかし彼のプランが大規模で準備を要する一方、急な展示場の変更や音具発注先のストライキに巻き込まれ、両展において制作は実現しなかった。彼はそのまま1988年に帰国するまで10年以上イタリアに留まることになる。
巨大な音具と並行して、持ち運べる音具の制作や乾燥させたユリの花弁構造に音具の機能を見出していた藤原は★3、イタリアでも小さな音具を作り、子供の知育玩具として展開させていく。交流のあったブルーノ・ムナーリによって、それらは鳥の呼び笛を意味する「richiami(リキアーミ)」と名付けられる。一人で奏でることができる音具は、帰国後に手掛けるイヤフォンやヘッドフォンで体験する個人型デバイスへとつながっていく。
 「藤原和通─そこにある音」展会場風景[筆者撮影]
「藤原和通─そこにある音」展会場風景[筆者撮影]
後半のゾーンでは帰国以降の活動が紹介され、来館者による撮影が可能になっていた。藤原の耳を象った、オブジェのような録音用マイク「ニューラルサウンド・システム・ダミーヘッド・マイク」(1989〜)のほか、音を左右に異なるリズムで遮断させて聴く「点滅キノコ」(1996)、音を振動に変換する《dayon(ダヨン)》(2007)といった電子的な音具が紹介されていた。
会場において90年代以降の製品が体験可能だったこともあり、やはり気になるのは巨大な音具がどのような「音」を奏でたかという点である。かわなかの映像作品は無音であり★4、音についてはいくつかの証言から推測するほかない。美術評論家の平井亮一は「ごろごろと重い音」、東野芳明は「押しつぶされたような、鈍い、低い、強い音」、ヨシダ・ヨシエは「ざあざあという、芸のない摩擦音」、日向あき子は「きしんだ音」★5、そして藤原本人は「コンサートと言っても、音が出ません」と述べて開催場所の交渉に挑んでいたという。こうした言葉や場所探しに対する藤原の熱意からは、彼の関心が聴衆にどのような音を届けるかということよりも音具を鳴らすという行為そのものにあったことが窺える。藤原の音具は展示来訪者の誰もが鳴らすことができた。音は触覚によって身体的に掴み取るものであり、「YOBOUE」から「リキアーミ」、そして「ダヨン」へと続く彼の作品群において、音における「震える運動」が彼の常なる追求だっただろう。
ところで会場の冒頭には、藤原が最初の「音響標定」を発表した頃に発行したという採譜楽曲集『唄〈東北民謡〉10』(1967)の冊子が展示されていた。これは藤原が民謡を聴き取ってまとめたもので、彼が大勢で歌う民謡という様式に惹かれていたことは、初期の「音響標定」が一人では演奏することができない形態であったことを思い起こさせる。
複数の人々によって奏でる唄や、集団の動力で鳴らすことができる巨大な音具の音は、時代の要請を経ながら個人で体験するものへと変わっていった。現代においてこの傾向はますます促進され、打ち込みによって一人で複数の楽器を操作したり、音楽のサブスクリプションサービスが推薦アルゴリズムによって個人用のプレイリストを提供してくれたりする。そうした時代において、藤原和通が70年代に手がけた巨大で重々しい音具の試み、またその協力者たちの営みにかえって強く惹かれる思いである。
鑑賞日:2024/10/14(月)
★1──『藤原和通 1 1970~1974[音響標定]』(おふね舎、2021)
★2──「音響標定 サウンド・ロケ第4」は、安齋重男、羽永光利による写真も残り、前掲書に掲載されている。
★3──★1に同じ。
★4──未発見のようだが、かわなかの映像にはカセットテープのサウンドトラックが付属したという。参照:金子智太郎「場をつくり、音と対峙する 1974年までの藤原和通の《音響標定》」(前掲書所収)
★5──★1に同じ。
参考文献:『藤原和通―そこにある音』(岡山県立美術館、2024)