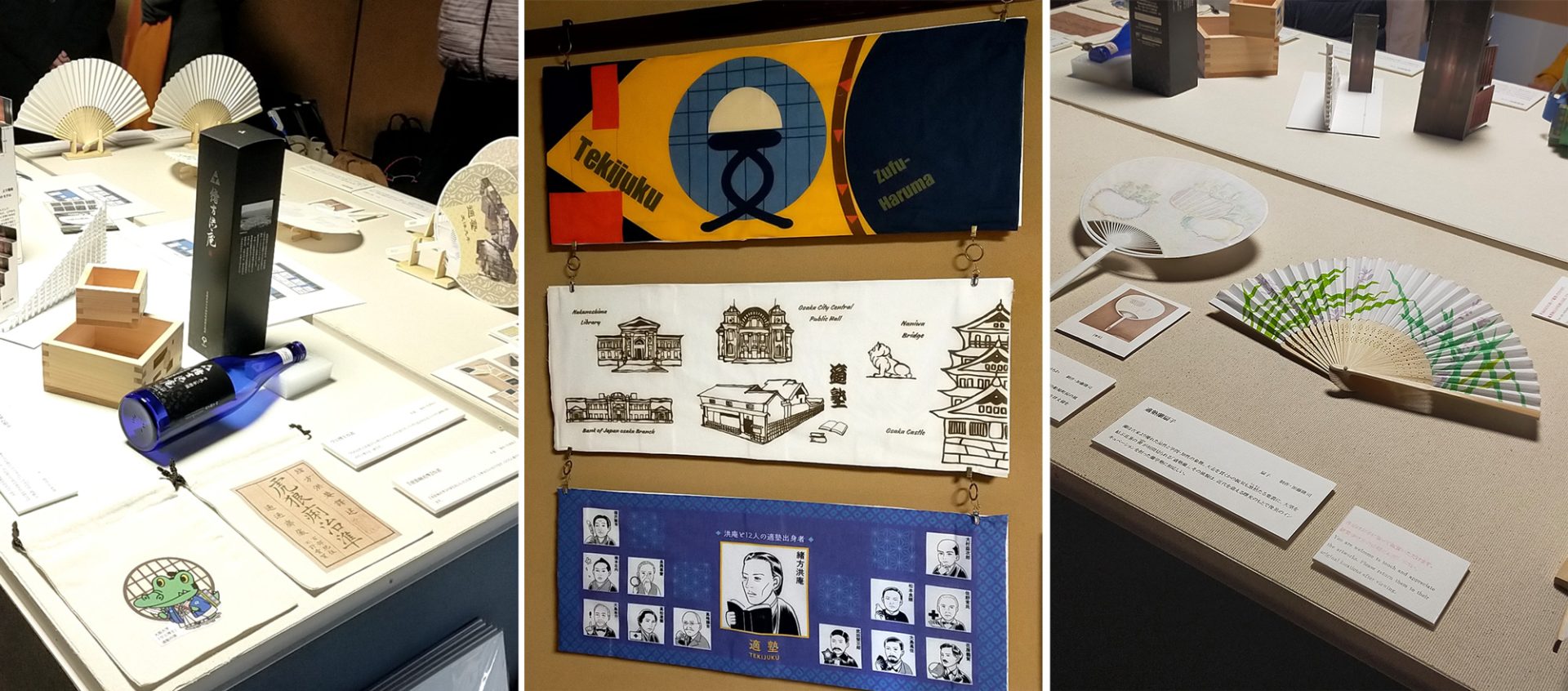2025年に開設30周年を迎えたartscapeは、アート情報サイトの新たな地平を切り拓くべく、星野太氏(美学・表象文化論)、きりとりめでる氏(デジタル写真論)、野見山桜氏(デザイン史家)の3名を特別編集委員として迎えました。今回は、そんな編集委員による座談会のかたちで、今後のartscapeの針路を探るための公開企画会議を実施しました。それぞれの専門分野の第一線で活躍する3名は、現代のアートとデザインにおける「理論」「批評」「アーカイブ」「教育」の現状をどう捉えているのでしょうか。30年の歴史を振り返りつつ、未来に向けた議論を交わしたようすを、前・後編にわたってお届けします。(artscape編集部)

特別編集委員のみなさん。左から、星野太、きりとりめでる、野見山桜(敬称略、以下同)[撮影:吉屋亮](以下同)
編集委員それぞれの活動
artscape編集部・太田知也(以下、太田)──本日はお集まりいただきありがとうございます。今回は特別編集委員のみなさまによる最初の座談会として、今後のartscapeの方向性を考えるための議論ができればと考えています。ただし、これは今後の具体的な記事制作に向けた企画会議でもあります。皆様が編集委員として、どのような問題意識を持ち、今後どのような企画を作っていきたいか、その背景にある考えをぜひお聞かせください。
まずは、読者の方々にみなさんをご紹介するという意味も込めて、お一人ずつ近年のご活動についてお話しいただけますでしょうか。では、星野さんからお願いします。
星野太(以下、星野)──よろしくお願いします。私は大学で美学を専門に研究教育に携わっています。アートやデザイン分野との関わりで言うと、20代から30代にかけては、アーティストとの対談や記事執筆など、頼まれた仕事はなんでも引き受けていました。特にリレーショナル・アートやソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)といった、海外のものを日本に紹介する仕事が多かったですね。artscapeにおいては「Artwords®(アートワード)」の項目をたくさん書かせてもらいました。
しかし、40代に差しかかったここ5年ほどは、少しフェーズが変わってきたと感じています。これまでが海外の文献を読み解き、紹介するというサイクルだったとすれば、今は自分のビジョンや考えていることを本というかたちで提示していく、まとめる時期に入っているという感覚です。2020年頃から毎年1冊ほどのペースで著書を刊行しています。それと並行してartscapeのブックレビュー執筆やトークへの出演、展覧会カタログへの寄稿なども続けています。

星野太
きりとりめでる(以下、きりとり)──特別編集委員のみなさんと対面でお会いできて嬉しく思います。私自身は批評家と名乗ったことはないのですが、ここ5年ほど、展覧会を観て、その場で出会った方から「展評を書いてみませんか」と声をかけていただく機会が非常に増えました。その流れでartscapeでもレビュアーとしてお声がけいただき、2022年から2年ほどのあいだ毎月展覧会レビューを執筆していました。
私の専門は、写真という媒体がデジタル化して以降、社会や人間をどう変えていったか、あるいは人間がそれをどう扱おうとしたか、という変遷を調査研究することです。この視点は美術に限りませんが、展覧会レビューを書くうえでも役立っているように感じます。
現在の表現全般に言えることですが、何かひとつのまとまった理論で物事を切り分けるのは非常に難しい時代になっています。ですから私は、その都度、対象となる作品や表現が、どのような理論や言説をバックボーンにしているのかを検討し、まとめて書く、というアプローチをこの5年間続けてきたように思います。
また、2017年からは『パンのパン』という同人誌も発行しています。これは、展覧会終了から時間が経ちすぎて通常のウェブメディアでは掲載しにくくなった展覧会評や長文の論考などを掲載するなど、既存の美術メディアでは扱いにくいものをすくい上げるための場です。表現者や美術関係者(アートワーカー)が考えていることそのものが伝わるような文章が生まれる場を作りたいと考えています。
野見山桜(以下、野見山)──私は大学院で近代デザイン史を学ぶためにニューヨークへ渡りパーソンズ美術大学へ入りました。帰国後、もともとインターンでもお世話になっていた東京国立近代美術館でマルセル・ブロイヤーの展覧会に携わったのがきっかけで、客員研究員として4年半ほど勤めました。
しかし、デザイン系の学芸員は非常に少なく、この状況を変えたいという思いが募りました。そして私が40歳を目前にして、グラフィックデザイナーの五十嵐威暢さんのアーカイブを石川県の金沢工業大学内に設立するという話が持ち上がり、これに参加するしかないと感じたのです。2023年には日本デザイン振興会にお声がけいただき、グッドデザイン賞のリサーチャーを務めています。
私の活動の根底には、二つの問題意識があります。ひとつは、日本のデザイン史が海外であまり知られていないという現状です。欧米で学んだ経験から、日本のデザイン史をきちんと海外に伝え、研究のネットワークに接続していく責務を感じています。もうひとつは、日本にデザインミュージアムが少ない、デザインアーカイブがほとんどないという課題です。これに対して、ただ問題を指摘するだけでなく、自ら実践する側に立ち、未来の担い手たちのために知見や経験を提供できる人間になりたい。この思いでここ5年間、活動してきました。
批評と理論の現在地
太田──きりとりさんのお話にあった「ひとつの理論で物事を切るのは難しい」という点は、星野さんの理論紹介のお仕事とも関連する部分があるかと思いました。現代における理論や批評の問題意識について、お聞かせいただけますか。
星野──きりとりさんがおっしゃる通りだと思います。かつては、批評家はジル・ドゥルーズに代表されるようなフランス現代思想など、さまざまな理論を知っていなければならない、という風潮がありました。作品と直接関係があるかわからない理論をまず持ち出す、という作法があったのです。それは一種の「空中戦」のようでした。
しかし今、多くの書き手はそうした意識を持っていません。むしろ、対象となる作品にどれだけ密着できるか、そのバックグラウンドをどれだけ深く調べられるか、という実直なアプローチが良い批評の条件になりつつあります。
もちろん、今でも理論が有効な場面はあります。個々の作品を分析するためというより、例えば「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」のように、状況全体や新しい動向を理解するためのフレームワークとしての理論は必要かもしれません。ただ、それも批評の必須条件ではなく、あくまで切り口のひとつ。主役はあくまで作品や作家に寄り添う姿勢であり、理論が前面に出ることは少なくなっています。
きりとり──星野さんが翻訳や紹介を通して築き上げてこられた言説、例えばリレーショナルアートやパフォーマンス的転回、ポストモダニズムの状況などに関する文章や対談は、インターネット上に蓄積されています。その最たるものがartscapeのアートワードだと思っています。そうした基盤があるからこそ、私たちは「では、自分はどう書くか」という次の言葉を探すことができる。理論は、いまも書き手や作り手にとっての「基底面」としてしっかりと生きていると感じます。

きりとりめでる
90年代当時のartscapeにみられる「前衛性」と「公益性」
太田──ウェブ上の議論の蓄積やアートワードについて話題提供いただきました。ここで少し、編集者である私の視点からartscapeの歴史的な経緯を簡単にご紹介させてください。
artscapeの前身は、1993年11月に発足した「美術館メディア研究会」という組織でした。会のアドバイザーは、美術批評や写真論などで知られる伊藤俊治氏が務められたそうです。この研究会が掲げた「network museum & magazine project(nmp)」のステートメントのような文章が、いまもウェブ上に残っています。そこから引用すると、「ネットワークそのものを美術館として機能させつつ、仮想世界にとどまることなく現実と仮想の両世界を連結させ、かつ 、世界の美術館、アート・サイトとリンクしつつ展覧を進める」とあります。
ここから、当時のartscapeが持っていた二つの大きな柱が見えてくるように思います。ひとつは、初期のインターネットという新しい技術に芸術界が革新的な期待を見出していたという、ある種の「前衛性」です。つまり、バーチャル空間としての美術館構想や、ネットワーク自体が芸術の生産・流通・保存全般を一変させるというビジョンは、90年代から2000年代にかけて流行していたムードだと思うのです。そうした機運のおおきな成果のひとつには、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC](以下、ICC)のオープニング企画展として1997年に開催された「海市」展があります。じつは先に名前を挙げた伊藤氏は、ICCの企画に関わるコミッティという立場でもありました。ですから、氏を中心とした芸術界の一部には、情報が流動性を持ったときにカルチャーはどう変わるのか、という大きな問いがあったのだと思います。
上記ステートメントから読み解けるもうひとつの柱は「公益性」です。その点はとくに、情報技術によって美術館同士の連携を図るという趣旨の記述に表われています。これを実践するかのように、設立当初はウェブサイトを持っていない美術館の情報を発信するポータルサイト的な役割を担い、全国の美術館を実務的に支援していました。つまり、artscapeは商業媒体としてではなくDNP(大日本印刷)のCSR(企業の社会的責任)活動として始まった経緯があるのです。じつはartscapeのウェブサイトには、芸術文化振興を通じてより良い社会づくりを目指す活動を認証する「This is MECENAT」(企業メセナ協議会認定)のロゴが掲載されています。このように、公益に資するという精神がいまに引き継がれていることがうかがえるように思うのです。
「インターネット初期の前衛性」と「ミュージアム支援に代表される公益性」という二本柱が、artscapeの原点にあったと考えています。30年が経ち、前衛性の部分はかなり薄れてきたかもしれませんが、公益性は一貫した姿勢と言えるのではないでしょうか。私が申し上げるといささか手前味噌な価値づけにはなってしまうものの、きりとりさんがおっしゃった「基底面」にあたる部分かなと。こうした原点を踏まえつつ、これからの30年を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
野見山──当時のヴァーチャルな美術館構想とは、具体的にどのようなイメージだったのでしょうか。
太田──作品をデジタルで鑑賞・収集するというよりは、もっと理念的なレベルだったと思います。「情報の集積場として美術館を捉え直す」という思考実験であり、「美術館はメディアである」という側面を強調した試みだったのではないでしょうか。
再び伊藤氏の理念を遡ってみますと、NTT出版が発行し伊藤氏が監修を務めた『テクノカルチャー・マトリクス』という書籍があります。そこで氏は「知のルービックキューブ」という隠喩を提示していました。年代、ジャンル(美術、デザイン、建築など)、思想といった複数の軸を回転させることで、これまで結び付けられてこなかった事象のあいだに新しい関係性を発見する、というデータベースのアイデアです。そして、こうした構想に基づいて、ICCでは「20世紀マトリクス」というデータベースが実装されました。

artscapeの関連文献。伊藤俊治監修、美術館メディア研究会編『美術館革命』大日本印刷、1998/森司・村田真・暮沢剛巳監修『アートスケープ・クロニクル 1995-2005──アート、ネット、ミュージアム』大日本印刷株式会社ICC本部、2005
きりとり──「知の公共化」と、プラットフォームによる「新しい視点の創出」というわけですね。
ところで、私自身、多摩美術大学のアートアーカイヴセンターで3年間レジストレーターとして働いていたことがあります。そこでデザイン関連としては批評家の勝見勝のアーカイブなどを扱っていました。アーカイブを構築することと、歴史をまとめることは両輪だと思いますが、そこに理論をまとめるという作業はどのように関わってくるのでしょうか。野見山さん、いかがでしょう?
アーカイブが拓くもの、アーカイブが問うもの
野見山──私が携わっている五十嵐威暢アーカイブで言えば、彼の制作活動の根底には、モダンデザインを支えてきたシステムやバリエーションといった「理論」や方法論が確実に存在します。彼は、グリッドシステムのような仕組みが持つ普遍性に依拠しつつも、ポストモダンの時代感覚のなかでそこから逸脱しようと試みました。その葛藤の軌跡が、アーカイブから読み取れるのです。
アーカイブをやっていて時々ふと「これは何のためにやるのだろう」と考えることがあります。未来にとってどんな意味があるのか、と。だからこそ私は、外部の人間を積極的に巻き込み、アーカイブを多様な視点から見ることで、新しい活用の方法を見出そうとしています。これまでのアーカイブは、活用が研究者にとどまりがちでした。しかし、それでは何も変わらない。お金もかかる事業だからこそ、新しい価値を生み出すきっかけになることで、もっとやりたいという人を増やせるはずだと考え、収蔵品を用いた企画展などのかたちで実験的に取り組んでいます。
ただし、勝見勝さんのアーカイブに関しては、彼の個人的な事柄に属する収集品が多いと理解しています。そのため、利活用については必ずしもいま私が申し上げたことにフィットするかどうかはわかりません。
星野──素朴な質問を二つさせてください。ひとつは、アートのアーカイブとデザインのアーカイブの最大の違いは何でしょうか。もうひとつは、個人のアーカイブはどこまでを対象とすべきか、という点です。例えば、慶應義塾大学のアート・センターにある舞踏家・土方巽のアーカイブでは、彼が本に挟んでいた「もやし」まで保存していたと聞きます。これはいささか極端な例かもしれませんが、個人を対象にするとは、そこまでやるということなんでしょうか。どこで線を引くべきか、ご意見を伺いたいです。
野見山──まず、アートとデザインのアーカイブの違いですが、相対的に考えたことがなかったので、興味深い問いです。五十嵐さんのアーカイブに関して言えば、特徴的なのは仕事の「プロジェクトファイル」が残されている点です。しかし、これはデザイナーの誰もがやっていることではありません。やはり五十嵐さんは「残す」ことに自覚的で、だからこそ残せるレベルまで削ぎ落としたものをプロジェクトファイルと呼んで蓄積していました。
プロジェクトファイルのなかには、契約書やクライアントとの手紙、FAXといった生々しいやり取りも含まれています。とくに彼がデザイナーの地位向上のために、クライアントに対して強い言葉で自身の考えを伝えていた書簡などは、作家や作品の評価とは別の次元で、非常に興味深い資料です。こうした泥臭い記録が残っているのが、デザインアーカイブの面白さかもしれません。
ほかの具体例として、グラフィックデザイナーが用いる「版下」という印刷原稿の存在があります。これは印刷会社に渡したらその後は不要とする人も多かったのですが、五十嵐さんはそういったものを手元に戻して管理していました。PCがない時代には、例えばポスターを作る時は、イラストの原稿を手描きして、それを烏口で墨入れして、その次に文字情報を写植で準備して、それらを用いてレイアウトを制作して……といろいろな工程がありました。そうした工程をある程度まで追跡できる資料がいくつも残っています。
次に、アーカイブの範囲についてですが、私たちの場合は、五十嵐さんから「これを全部寄贈する」と言われたものを、こちらで選別せずにすべて受け入れました。幸い、収蔵スペースの面積をあらかじめ想定して準備できたので、すべて収めることができました。──土方さんの「もやし」も、何か名作が生まれたときに食べていたものかもしれませんね(笑)。場所に限りがある以上、どこかで線引きは必要ですが、何が未来で意味を持つかは誰にもわかりませんからね。

野見山桜
デザイン分野における批評の困難
太田──アーカイブの利活用や後世のデザイナーの地位向上など、まさに「公益性」や「公共性」というキーワードに繋がってきたように感じます。ここからもう少し展開してみますと、アーカイブやデータベースから情報を受け取る主体は、後世の作り手のみならず、価値づけに関わる批評家のこともありえますよね。アートと比べたときにデザイン領域では批評が乏しいということを、野見山さんはかねてより問題に感じておられると事前に伺いましたが、その点について語っていただけますでしょうか。
野見山──アートの世界には、作家、作品、マーケット、そして批評といった役割分担が明確にあり、専門家による批評が価値づけのプロセスに組み込まれているのが目に見えてわかります。一方、デザインの批評は誰もができてしまう。デザインが日常生活に関わるものだからですね。つまり、ネット上の個人的な感想も、歴史的文脈や専門知識を持つ人の言説も、言ってみれば同じ「批評」という言葉で括られてしまいかねず、それぞれの発言の意義がよく整理されていません。また、アートにおける「作家と作品」という関係が、デザインでは「メーカーと製品」になり、デザイナーはその下に従属する構造になっているなど、そもそも同じレベルで語れない複雑さもあります。こうした構造がはっきりしないからこそ、「何をどう高めていけばいいかわからない」という未成熟な状態にあるのではないかと感じています。
星野──なるほど。逆に、デザインの分野には多く存在しながらもアートには少ないものとして「アワード(賞)」がありますよね。グッドデザイン賞のようなアワードが、アートにおける批評に近い機能を果たしている、という考え方はできませんか?
野見山──グッドデザイン賞は、産業界における奨励という側面が強いと思います。ですからグッドデザイン賞の受賞マークがあるからといって、消費者がその商品を選ぶかというと、あまり関係ないように思います。
ただ、非常に興味深いのは、グッドデザイン賞の審査会の場です。そこでは、驚くほど生産的でレベルの高い批評的な議論が交わされているんです。審査員は、大量の応募デザインを一気に見るなかで、デザインをめぐる問題意識を共有し、多くの学びを得ています。しかし、その豊かな議論が、応募者や一般の人々にうまく還元されていない。結果やコメントは発表されても、なぜその価値判断に至ったのかというプロセス、つまり批評の根幹部分が開示されきれていないのです。政治的な配慮や企業間の関係性もあり、ネガティブなコメントを公にしにくいという構造的な難しさがあるのだと思います。
太田──先ほど星野さんがおっしゃった「デザインにおける賞が批評の代わりなのではないか」という問いに対して、野見山さんから内部的な視点で応答していただきました。私も外側から見ているウォッチャーとして、星野さんのご意見には半分ぐらい同意できる部分があると感じています 。
例えば2010年代には、ソーシャルデザイン的なものがグッドデザイン賞を受賞する流れがありました。これは、その時代ごとの理論や言説の中心に対して、産業界の側からシーンとして応答しようという姿勢の表われに見えます。アート業界で見られるような、理論の変遷に対する直接的な反応や議論ほど刺激的ではないかもしれませんが、賞がある程度は批評的な機能を果たしている面もあるのかもしれない、と思わされました。
一方で、やはり野見山さんがおっしゃっていたような、政治的な側面や企業間の忖度といったことが、構造的に批評の困難さを生んでいることも確かでしょう。例えば文芸批評であれば、批評家が忖度なしに作品を読み解き、それを提示することが成立します。しかし、デザインの領域では、資本や産業との強い結びつきがあるために、そうした切れ味の鋭い批評が難しくなっているのだと、いまのお話から受け取りました。
審査会の内部ではそれほど豊かな議論が行なわれているという雰囲気は存じ上げなかったので、非常に面白そうだと感じます。そうした審査の裏側など、普段は閉じられている場所での議論を、artscapeのようなメディアが取材し、コンテンツにしていく、という可能性はありそうですね。
artscapeの「インフラ」としての価値
星野──関連しそうなこととして、artscapeという媒体の性格について議論してみたいと思います。私がartscapeの大きな価値だと感じているのは、「インフラ」的な側面です。他のアート系ポータルサイトではなかなか読めないタイプの記事が数多くありますよね。例えば、長年続いている「キュレーターズノート」や、きりとりさんも参加されているジャンル横断的な「レビュー」、「もしもし、キュレーター?」などは、定点観測としての価値が非常に高く、後から振り返る際に有益な情報源となります。また、美術館の裏側に光を当てた「スタッフエントランスから入るミュージアム」や、地方の小規模なアートセンターなど、普段あまり表に出てこない人々を取り上げた「Dialogue Tour」といったものもありました★。
これらに共通するのは、いわゆるスターキュレーターだけでなく、地方の美術館で地道に活動されている学芸員の方や、レジストラー、インストーラーといった、アートやデザインの世界を下支えしている方々の率直な言葉が読める点です。30年分の蓄積があるおかげで、10年以上前の小さな展覧会について調べたいときにも、レビューが見つかって本当にありがたい。私がartscapeを「インフラ」と表現したのは、こうした背景があるからです。これからも、そうしたコンテンツを読み続けたいと願っています。
太田──ありがとうございます。媒体の公益性に関する全国のミュージアム支援という点を掘り下げていただけました。
星野──じつは、いくつか企画を考えてきました。
ひとつは、インストーラーや展示照明の専門家、あるいはプロデューサーなどへの取材記事です。とくに、特定の機関に属しておらず、アートとデザインの業界で活動なさっている──まさにインフラを担っている方々にインタビューのかたちでお話を伺ってみたいです。これは実現可能性も高いでしょう。
もうひとつは、より挑戦的ですが、美術館のなかで見過ごされがちなセクションに光を当てる企画です。個人的な話ですが、私が高校生の頃、茨城にある水戸芸術館のミュージアムショップ「コントルポアン」によく通っていました。ここはNADiff系列のショップなのですが、地方で暮らす自分にとっては、東京にしかないような雑誌やカタログを知ることのできるほぼ唯一の窓口でした。このように、地方におけるミュージアムショップが果たしてきた文化的な役割は、もっと注目されて良いはずです。
また、金沢21世紀美術館の託児室も前々から気になっています。このような託児室がどういった理念やオペレーションで運営されているのかなど、取材してみたいと思いました。あるいは、東京都現代美術館内のレストラン「100本のスプーン」のように、離乳食を無料で提供している施設の取り組みなど、企業が関わるものも含めて取材できると面白いなと考えています。
太田──非常に具体的な企画案をありがとうございます。とくにミュージアムショップの話は、東京一極集中という問題の裏面として捉えることができ、とても興味深いです。地方部のティーンエイジャーが文化に触れる場所として、ミュージアムショップが重要な機能を果たしてきたという視点は、ハッとさせられました。

(後編へ)
★──2024年3月以前の記事については「アーカイブ」をご覧ください。