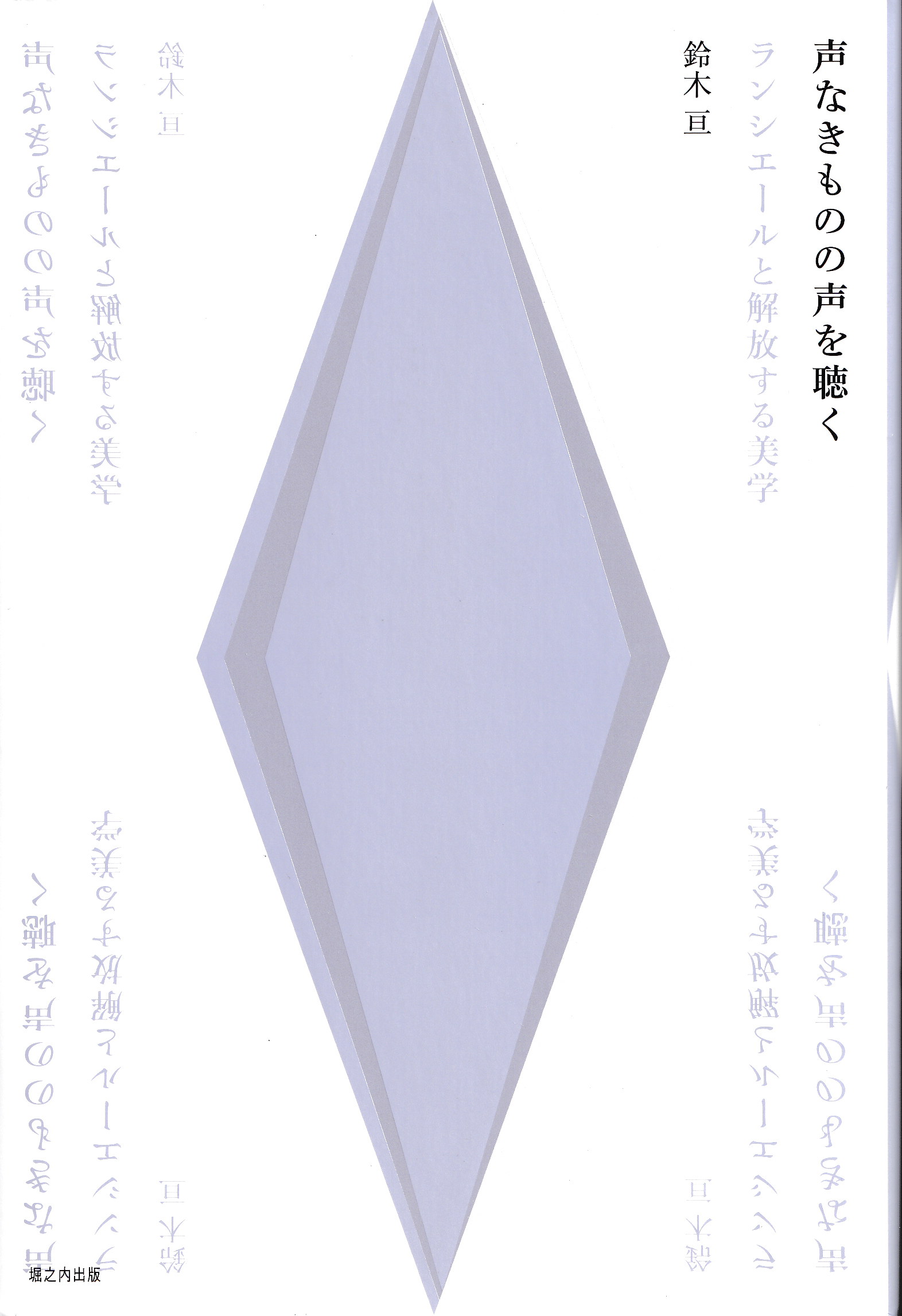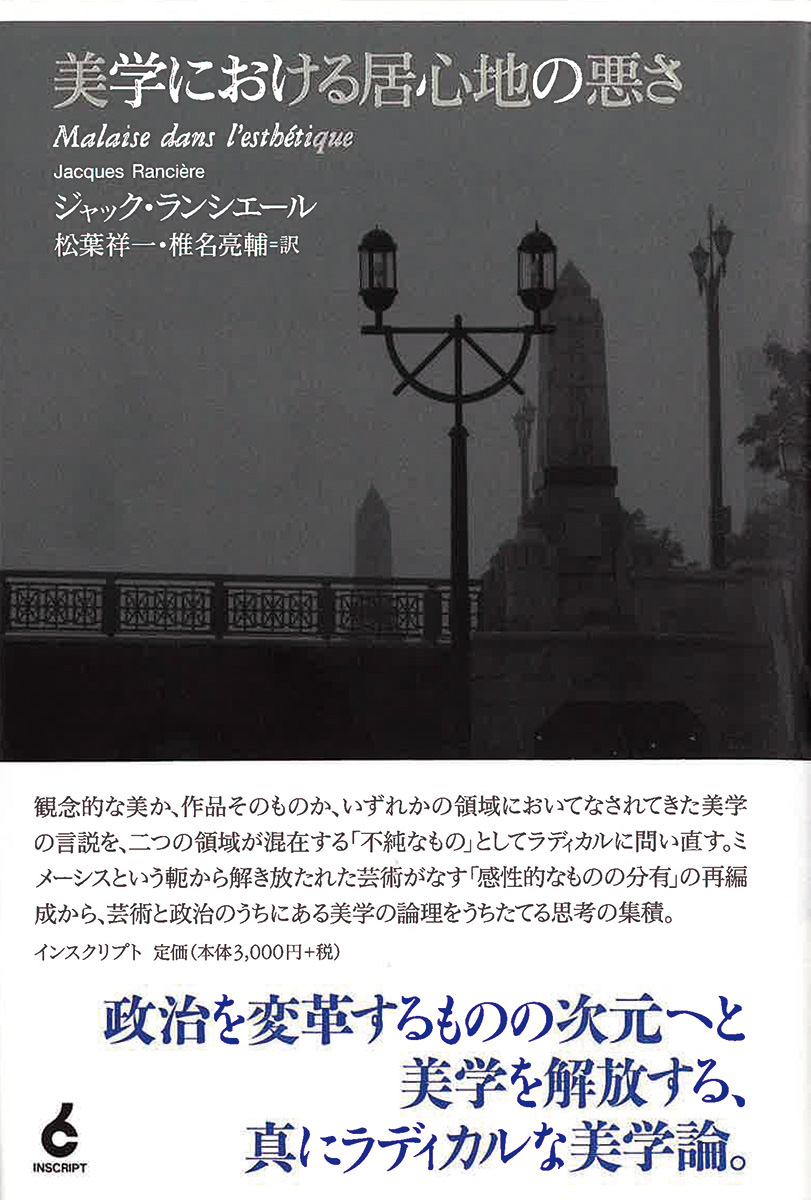
翻訳:松葉祥一、椎名亮輔
発行所:インスクリプト
発行日:2025/06/30
公式サイト:https://inscript.co.jp/b1/900997-79-0
(前編から)
ランシエールの思想において政治と美学は分かちがたく結びついているのであるが、それをギリシャ哲学までさかのぼった思想史的な系譜のなかで思考し、論述する射程の長さがランシエールにはある。だからこそ、個別のトピックに対する申し立ても再考を促すだけの説得力を持っているのだ。
例えば「観客を世界変革の意識をもった行為者に変えるため」のある種の現代美術「クリティカル・アート」について述べた「クリティカル・アートの諸問題と変容」において、そういったアートの変質を「遊び、一覧、出会い、神秘」に整理している。しかし注目したいのは、その前提としてポストモダン的な切断をランシエールが想定していないことである。彼はバルザック『幻滅』(1837-43)の一場面を取り上げ次のように述べる。
落ちぶれた詩人リュシアン・ド・リュバンプレは株の裏取引と売春にまみれて自らの文章と魂を売ることになるのだが、ここが突然新しい詩の場所となる。商取引の日常と芸術の非日常の境界を取り払った架空の詩である。★
ランシエールは他の箇所ではブレヒトを根拠に、「境界をかき乱すことは『モダン』そのものと同じぐらい古い」と述べ、ポストモダンというテクニカルタームへの過剰評価から距離を取る。こうした言説との駆け引きもまた「権威簒奪者」としてのランシエールの面目躍如だろう。
先にあげた二コラ・ブリオーへの批判はもちろんであるが、こうした面は同書のなかでは「モダニズムの二律背反」のなかでも見ることができる。ここではアラン・バティウのモダニズム観が、諸芸術の言語の特異性ではなく「観念の特異性」であると指摘し、それを「ねじれ」と表現し、バディウの記述を近代という時代の混乱へとスケールアップさせている。また、ジャン=フランソワ・リオタールに対しては彼のカント理解などを補助線として引き直しつつ、ポストモダンというキャッチコピーを再点検している。最後に収められた「美学と政治の倫理的転回」では倫理をキーワードに表象不可能性に疑義を提示し、同書は締めくくられる。
『美学における居心地の悪さ』は前半で感性学としての美学の不純さが呼び込む政治に向き合い、後半でバティウやリオタールらをターゲットとして明確に掲げながら、より大きな主題へと向かっていく。こうした構成は、ランシエールの政治と美学の哲学と、卓越したテキストの批判者としての特徴をくっきりと浮かび上がらせている。もちろん各人の関心に従って、他の著作や解説的なテキストに当たるという選択肢もありえるが、ランシエールの芸術論に直接触れるという意味においては、同書は入門的な一冊と言っても良いだろう。
★──ジャック・ランシエール『美学における居心地の悪さ』松葉祥一、椎名亮輔訳、インスクリプト、2025、70-71頁
参考資料
・星野太「ブリオー×ランシエール論争を読む」『Contemporary Art Theory』イオスアートブックス、2013
執筆日:2025/07/31(木)