Dialogue Tour 2010
「現代美術2.0宣言」にまとめられている「Dialogue Tour 2010」参加スペースの活動の特徴は、東浩紀氏が『動物化するポストモダン』(講談社、2001)で描いた後期ポストモダンの時代を生きる「おたく」たちの消費行動にきわめて近い。両者はともに、公的に共有される「大きな物語」を失い、ばらばらな個人が「小さな物語」を信じ、それでも情報技術の革新によって私的な欲望をフックにしてつながることが可能な世界を背景に生まれている。筆者はこのような状況自体は肯定的なものだと考えている。一方でこのイベントの監修者であり「現代美術2.0宣言」を書いた鷲田めるろ氏は、そのような背景から生まれた「Dialogue Tour 2010」参加スペースの活動を、美術史という「大きな物語」に接続するという欲望を口にしてもいる。それははたして可能なのだろうか。可能だとすればどのようにしてか。
コミュニケーションの形式化
イベントに先立つ筆者とのtwitter上のやりとりで鷲田氏は、「現代美術2.0」的な活動が生み出すものは〈パーティ〉のようなもので、それは「ワークショップと作品のあいだ」のようなものであるとしていた。これはコミュニケーションの形式化ということができるだろう。「Dialogue Tour 2010」参加スペースの活動は、「形式化されたコミュニケーション」を体験する場を提供しているということだ。そこでは送り手も受け手もアーティストもそれぞれの役割は流動的で交換可能であり、匿名的な存在となる。「現代美術2.0」を象徴する「ユルさ」とは、匿名的な個人が「大きな物語=組織、価値」を必要とすることなく、それぞれの欲望=関心にしたがってつながることを意味している。「現代美術2.0」はそのような形式に与えられた名前なのだ。
鷲田氏は「現代美術2.0」を美術史に接続させるための中継役として、「関係性の美学」を想定しているようだ。「関係性の美学」はフランス人の批評家兼キュレーターであるニコラ・ブリオーが提案したコンセプトである。ブリオーは1998年に出版された同名の著書のなかで、90年代におもにヨーロッパで多く見られるようになった作品の傾向を「リレーショナル・アート」と名づけ、それを支える形式的原理として「関係性の美学」を設定したのだった。その特徴は、先行する時代の美術作品のように強固な造形的な理論をもたず、「作品」を媒介したコミュニケーションの場を開くことを一義的な目的とするものであり、それによって閉塞したモダニズムの状況を突破し、美術の実践を社会的実践と結びつける可能性を開くものとして広く受容された。そのように美術作品をとらえることは、アーティストを特権化することからは距離を置くものであるし、「作者=送り手」と「鑑賞者=受け手」との「関係の流動化」にも繋がるだろう。
だがブリオーが「社会的なつながりが画一的な商品に代わり、労働の分化が進み、極端に専門化され機械化されて市場原理に支配される規律社会」のなかで分断されてしまった人間の諸活動の横断を実現することが美術作品の意義であると書くとき、彼はそのような場を生み出す人々が主体性を解体された匿名的な存在であるとは見なさなかったし、美術作品が生み出す象徴的な価値を信じてもいた。実際彼が想定する「コミュニケーション」は対面的な対話を前提としており、それは〈ユルい〉つながりとは言いがたい、むしろはなはだ〈面倒くさい〉関係だろう。ならば「現代美術2.0」が提案しているのは「関係性の美学」を批判的に継承したモデルということになるのだろうか。
〈面倒くさい〉コミュニケーション
そうでもなさそうだというのが筆者の感想である。artscapeのサイト上で公開されている「Dialogue Tour 2010」の記録に目を通すと、「現代美術2.0」でのまとめとは異なり、そこにはいかにも〈面倒くさい〉コミュニケーションの事例が散見される。山口のMaemachi Art Center(MAC)で地域の主婦との信頼ベースの関係性を築くプロセスは長い時間と細かな配慮を必要とするものであることは容易に想像がつくし、かじこで宿泊客にイベントの企画を求めるというのも非常に面倒くさいものだ。これらの手法は主催者にとっても参加者にとっても、お互いにとって圧倒的に高コストなのだ。それでも参加者はそれを喜んでいるようであり、主催者にとっては活動の目的を共有するのに効果的な手法に思われる。情報技術の進化によって圧倒的な低コストで個人同士がつながり、文化の消費が可能になった状況において、このようなコストのつり上げは美術の実践が受容される際の手法として合理的な選択なのかもしれない。
批評家の福嶋亮大氏は「セレブリティとオタク──ポップアートの新しい資源」(『思想地図β』Vol.1所収)のなかで、瀬戸内国際芸術祭の成功は「身体とカネと時間を無駄遣いする『巡礼』」モデルを取り入れ、体験を高密度化したことによるのではないかと見ている。これはおたくによる記号的消費が過度に進行したことに対する反動として生じた価値観なのだが、山口MACなどの活動に見られる〈面倒くさい〉コミュニケーションが喜ばれるのもこれと同様の現象だろう。福嶋氏は同じ論考の冒頭で、断片化が進んだ現代社会を統合するためには「二重のガバナンス(統合)」が求められるとして、コミュニケーション技術の発達による《機能的統合》と、「感情的な分断状況を一挙に束ねる」強度を持った《象徴的統合》の必要性を指摘している。美術作品は個人の「欲望と社会の中間的なインターフェースとして」後者の役割を担うのだ。
ソシエテ・アノニム──具体的で日常的な私的ネットワーク
とはいえ、このようなコストの釣り上げの手法は受容者のコストを上げるだけではなく、送り手側のコストも増大させる。「Dialogue Tour 2010」に参加しているいわゆるオルタナティブ・スペースのような小さな組織では、その統合作用が働く範囲は狭い地域に限定されざるをえないだろう。瀬戸内国際芸術祭に明らかなようにそれが有効に働くためには大企業のスポンサードと大規模な組織づくり、そして洗練されたマーケティング戦略とマネージメントの技術が欠かせない。しかし、「現代美術2.0」が標榜していたのは「マネージメントや組織すら必要ない」ことであったし、そこにはマーケットやコマーシャリズムに対する否定的な立場が見て取れる。
筆者は「Dialogue Tour 2010」参加スペースの活動や「現代美術2.0」に対して両義的な思いを持っている。主体性を持たないことにこだわり、同時に匿名的なマーケットに対して否定的な態度を取り続けるのではやはり限界があるのではないだろうかと思う。一方で大きな組織を前提としない、個人の欲望が歴史を作り出す可能性に期待したい気持ちもある。
可能性のひとつは〈ネットワーク〉にあるかもしれない。YouTubeなどのネットサービスは仲間内でのコミュニケーションを効率化することを目的としてつくられたシステムだったが、現在では世界中の人々が利用しており、メディアとしての公共性を持つものとなった。また、ここでいうネットワークは必ずしもインターネットのことに限らない。たとえば1920年にキャサリン・ドライヤー、マルセル・デュシャン、マン・レイの3人のアーティストによって設立された非営利のオルタナティブ・スペースであるソシエテ・アノニム(フランス語で株式会社の意味だが、字義通りには匿名組織を意味する)は彼ら三人の中心メンバーに協力する多くのアーティストとの私的なネットワークに支えられて活動した。最近の研究(Jennifer R. Gross ed., The Société Anonyme: Modernism for America, Yale University Press, 2006)では、1920年代と30年代にモダン・アートがアメリカに根ざしていく過程で、彼女たちの活動が大きな影響を及ぼしたことが明らかになっている。その活動は、モダン・アートの国際的なネットワークの形成と、アメリカの観客にモダニズムの理解を広めることを目指し、展覧会の開催だけでなく、出版活動や展覧会に付随した講演会やシンポジウムに加えコンサート、ダンスなどの普及事業を行なうなど多岐にわたっていた。加えて、大学ギャラリーなどにソシエテ・アノニムのコレクションのレンタルなども実施している。特筆すべきは後にニューヨーク近代美術館(MoMA)館長となるアルフレッド・バーがパリのモダニズムを中心にアメリカへのモダニズムの導入を行なったのに対し、彼女たちはドイツ、ロシアをはじめとした幅広い地域のアーティストを有名無名に関わらず紹介することで、モダニズムの現在をできるかぎり反映しようとしたことであり、そのネットワークの肌理の細かさである。彼女たちにとってネットワークとは理念的なものではなく、具体的で日常的なものだった。たんに多くのアーティストを展覧会に招聘するだけでなく、彼らが学生とともに研究旅行を行なう際のビザの取得や、滞在場所の提供、経済的な援助、はてはキャリアの相談や友人関係、結婚問題へのアドバイスまで行なっていたという。バーとも緊張状態にありながら、その関係を断つことはなかった。さまざまな要因の結果として美術史はMoMAを中心とするパリのモダニズムを軸に書かれることになるわけだが、ソシエテ・アノニムの活動はモダニズムの多様性を見せることでその基礎作りに役割をはたした。
ネットワークの可能性
これらがそのまま現代のオルタナティブ・スペースの活動のモデルになるわけではないだろうが、それでもネットワークは大きな鍵になるのではないか。それも「現代美術2.0宣言」がいうようなネットサービスの広報利用や、同じ名前のスペースを各地につくることにとどまらない、強度を持ったネットワークの形成が必要だろう。筆者がカオス*ラウンジに期待するのはその点にある。彼らはネット上の匿名的な想像力の流通にコミットしつつ、マーケットへのアクセスの戦略にも意欲的だ。そして、ファッションや演劇、建築など幅広いジャンルの実践に同時代性を認めながら、それらを横断する活動を行なっている。またそれに平行して、彼らの展覧会に作品を提供する「絵師」たちとの密なコミュニケーションによるネットワークの形成に尽くしてもいる。彼らの活動は、まだその可能性を十分に形にしているとは言えないかもしれないが、匿名的な想像力が隆盛する現在の状況に、アーティストの実存と切り離すことができない美術の実践をどのように位置づけていくのかを問うこうした試みに期待したい。

Dialogue Tour 2010最終回を収録した大阪市此花区のオルタナティヴ・コマーシャル・ギャラリー「梅香堂」

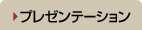

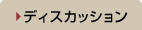
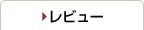
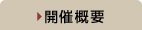
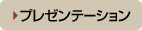
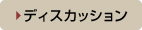

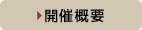




![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)