Dialogue Tour 2010
自分たちの問題でもあり、ユニバーサルで共有可能な問題でもある
須川咲子──私たちはこのSocial Kitchenというものを始める前に「喫茶はなれ」といって、毎週1回月曜日だけ家を開いて喫茶店をするということを2006年から4年間やっていました。そこも、いまの話と同じように、外から見たら「あんたんとこなにやりたいの?」と言われるようなところでした。でも毎週とにかく1回喫茶を開いて、ご飯を出して、いろいろな人たちが集まる場所をつくることをやっていました。「喫茶はなれ」の場合は、世の中のいろいろな社会状況を考えたときに、職業や年齢、ハンディキャップがある/なし、などいろいろな分断があるなかで、そういう人たちが集まれる場所になればいいなと。けれど、そういう目的がありながらも、なんとなくやっている自分たちも「なにがしたいの?」という答えには明確に答えられないという現状がありました。そういう4年間があって、Social Kitchenをつくりました。Social Kitchenは「21世紀型の公民館になる」ということで始めました。公立の施設ではなくて、私たち「hanare」というグループがお金を出しあって、つくった場所です。ここでは、「喫茶はなれ」で「自分たちはどうしていきたいんやろ?」「あまりカテゴライズされたくない」と思っていた部分をちょっと一歩脱出するきっかけをつかみたいと思っています。
そういうことを考えているときに、たまたま坂東昌子さんの「保育所設立運動」のことを知って、「なにかここに鍵があるんじゃないか」ということを感じたんですね。私たちがやってきた活動というのは、同じような年齢層でなんとなく同じような興味や関心を持った人の集まりになりがちで、なかなか広がりとか、もっと大きなものへの挑戦とか、ユニバーサルなものに対しての挑戦がないなと感じていたときに、この「保育所設立運動」のことを知りました。当時の女性研究者が、「自分たちの子どもを預ける場所がない」という自分たちの問題解決を目指した運動でありながらも、同時に「女の人があたりまえに働きながら、あたりまえに子どもを育てる権利」や「子どもたちが学びながら育ち、発達する権利」も主張されていた。なにかその展開の仕方にはユニバーサルなものというか、自分たちだけでなく、世界中に働いている女性全般に対するアプローチがある。そこが、「喫茶はなれ」をやっていた私たちとの根本的な違いであり、足りてないところだと思いました。それで、坂東さんたちの活動を本当に「格好いい」と思ったんです。これから私たちが格好良くなるためには、そういうユニバーサルなアプローチみたいな態度をどこかで身につけたり、政治への接続の仕方を考えなくてはいけないのではと思い、今日は、当時のことを坂東さんに聞いて、今後のヒントにできたらと思っています。
「社会は変えられる」/ネットワークの大切さ
坂東昌子──私が大学へ進学しようと考えていたころは、女性は大学に行くような時代ではありませんでした。仕事をしていても結婚退職といって結婚したら辞めるというのが普通でしたね。そんななか、大学進学について高校の先生に相談しました。すると先生は、「社会いうものは変わるもんや」とおっしゃったんですね。「戦後になってはじめて女も大学に行けるようになったんやで。それまでは行けなかったんだ」と話されたんです。つまり、「いまここにある社会は、ずっとそのままなのではなくて、自分も含めて、主体的に社会を変えながらその一員になるということが必要なんや」と教えてくださいました。そんな言葉の後押しもあって思い切って大学進学を決意したわけですけど、振り返ってみると、「社会を変えながら……」という言葉は「保育所設立運動」のきっかけのひとつといえるかもしれません。
もうひとつ。私は小学校から一緒だった同級生と結婚しました。大学院に進学してドクターに入るときですね。そのあとドクター2年の夏、子どもが生まれました。そのとき先生が、「女でいままで子どもを育てながら研究を続けた人はほとんどない。あの人、見てみいな。冷たいお母さんやろ」なんてことを言うわけです。「研究をやめるか、良い親になることを諦めるか、どっちかやな」と。でもそれは、論理的に考えたらおかしいわけですよね。良い親になりながら研究をやれる道も残されているのではないか。第三の道があるはずだと。これも運動の動機のひとつになっていますね。
それから、はじめに伝えておきたいのは、こうした運動をするにあたって、ネットワークというものがいかに大事かいうことです。私は、湯川研究室に所属していましたが、湯川秀樹さんは日本で一番最初にノーベル賞をもらった方で、「先進的な研究をやるためには、みんな仲間やぞ」という研究室の空気があったんですね。大学院に入ったら、「○○先生」とか呼ばない。益川敏英さんや小林誠さんと私は同期で助手をやっていましたが、研究室では「益川さんと呼べ」というように、上も下もない。そういう「真理の前にはみんな平等」というところで育ってきて、そういう空気のなかで仲間がいろいろ助けてくれて、「それやったら頑張って、どうやったらええか考えよう」ということで一緒に頑張ることができたんです。
須川──まず、坂東さんの自宅を開いて共同保育を始められたあたりからお聞かせいただけますか。当初は、何人くらいではじめたのですか。
坂東──最初は、6人くらいです。もともと子どもを預けてたのが「ベビールーム」という施設でした。そこはお医者さんがやっているということで入れたのですが、子どもが家に帰ってくると毎日すごくお腹をすかせているんです。おかしいなと思って「今日はなにを食べさせてもらいました?」と毎日しつこく聞いてたんです。そうしたら、ある日、保母さんが帰り際に追いかけてきて、「じつはあまり食べさせていないんです」「お風呂も、水をぺちゃぺちゃとつけて終わりなんですわ」と言うんですね。そこも営利主義でやらざるをえませんからね。でも、「営利目的ではあかん、公的な施設が必要や」という話になって、いろいろと勉強しました。そして家を開放することにしたんです。そのころ、夫の親が小さい家を買ってくれたんです。本当に小さい家で、共同保育をすると私らが住むところがないんですけど、ともかく「その家で共同保育をやろう」という話になって、みんなで集まっていろいろ相談して、保母さんも自分らで見つけてきてとにかく始めました。
子どもを抱えてるお母さんの運動というのは、昔から京大のなかになかったわけではないんです。女子職員もいたので「保育所をつくってほしい」という運動もありましたが、お腹の大きいあいだはみんな一生懸命なんですけど、生まれたら毎日の生活が大変でそんな暇ないでしょ。だんだんバラバラになって、ネットワークが継続しない。私たちは子どもが生まれてもネットワークが続くような運動にしないといけないということで、自分らで保育所をつくろう、そのための共同保育をやろうということになりました。そのまえから地域で子育てをやっていくために、共同住宅をつくりたいなと思っていたんです。それぞれの家庭があるなかに、みんなでご飯を食べたりするルームがあるような……、ちょっと「喫茶はなれ」に似てますかね。そんな経緯もあって、さきほども話しましたが、ネットワークをつくりながらというのは、いつも私の人生の柱であったことは確かなんです。

坂東氏プレゼン風景

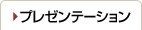

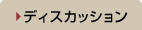
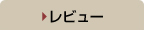
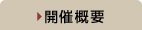

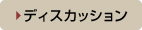
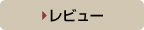
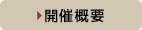





![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)