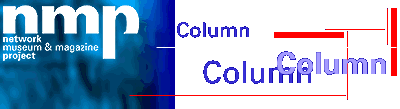
|
|
Nov. 5, 1996 (c)
|
Column Index - Nov. 5, 1996
|
|
▼

『Painting with Light』表紙
フィルム・ノワール
フィルム・ノワール
『パリのアメリカ人』
Hollywood Online
|
フィルム・ノワールの光と闇 ●森田祐三
光で描く
映画が光から出来ていることはいうまでもないが、トーキーになって付け加えられた音にくらべると言及される度合いが低い。理由は容易に想像でき、音ならば、台詞はもちろんの事、効果音、背景音楽という言葉が示すように、映画の背後に隠れている「意味」と関連づけて論じやすいのである。この場合、忘れられているのは、ロラン・バルトのいう音の「粒」ということになるが、おなじく「粒」子でもある光についても、 バルトが音の、あるいはエクリチュールの「粒」について寄せる思いと同様な関心を寄せなければならないだろう。 『Painting with Light』の魅力 ハリウッドという「工場」が集積した膨大な技術、あるいはその技術を正当化する意味の習得と伝達を目指したものではないとは、学習とは常に事物の先端において生じる出来事であり、素材と素材を扱う手つきの新たな関係の発見であると理解させてくれる本だということだ。キャメラを廻せば撮れてしまう映画には、予想に反してというか当然の事ながら、画布に絵筆が接触するときの物質の抵抗感にも似た、逡巡と決断に充ちた光との接し方が必要である。だから、キャメラと肉体の距離が、絵筆と手先の距離より遠いと感じられるなら、それは映画への感性の問題なのである。例えば、雨のシーンの撮影法をアルトンが解説した箇所を参照してみると、次のような記述がある。「お金を倹約したい人、貧乏人が雨の効果を出したいと思うなら、レンズの前に水を降らせ、奥に雨傘をきらきら光らせながら歩き回っている人を配置するだけで全体に雨の効果を出せる。」傘の濡れた表面に反映する光の戯れとは、もちろん映画の「意味」とは何の関係もないが、それだけで人が映画の雨を求め、「愛する(アルトン)」に足る十分な理由である。 「波」は絶えず新たによせる だが、いささか斜陽気味だったとはいえ、ヌーヴェル・ヴァーグよりも早く「貧乏人」の映画撮影に思いを至らせる人がハリウッドに存在し、しかもそれがスタジオ・システムの第一級の撮影監督だったということは感慨深い。もっとも、映画を撮ることはそもそものはじめから予期せぬものを求めての学習の反復だったといえるのかもしれないが、そういった態度が、やがて繁栄と引き替えに凝固した意味を担う慣習の体系へと変化した‘ハリウッド’で、如何に困難なものになっていったかということは、マッカーシーによる解説を読めば良く分かる。ロマネスクという形容がてらいもなく相応しい経歴をもつアルトン「再発見」の詳細は、この感動的な解説を参照していただく他はないが、エルンスト・ルビッチに就いて修行し、30年代のアルゼンチン映画産業をほとんど一人で興したばかりか、早撮り低予算のB級映画でアンソニー・マンの初期作を強力に支援してフィルム・ノワールの光線を確立したかと思えば、ヴィンセント・ミネリお気に入りのキャメラマンでもあったというアルトンの傑作として挙げたいのは、やはりジョセフ・ルイス監督の『暴力団』("The Big Combo", 1955, Hollywood Attic, Burbank, California)である。物質としての光と闇を極限まで探究したこの映画は、現在の日本ではスクリーンの上でみることが出来ないが、ビデオの形で手に入れることが出来る。 [もりた ゆうぞう/映画批評]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nov. 5, 1996 (c)
|
[home]/[Art information]/[Art Watch]
Copyright (c) Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1996
Network Museum & Magazine Project / nmp@nt.cio.dnp.co.jp
