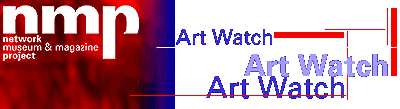
|
|
Sep. 10, 1996
|
Art Watch Index - Sep. 3, 1996
|
………………● 熊倉敬聰
|
▼
|
ナルシスの変貌 伊藤キム+輝く未来
《生きたまま死んでいるヒトは、死んだまま生きているのか?》を踊る伊藤キム Salvador Dali http://pharmdec.wustl.edu/ juju/surr/images/ dali/dali.html
A Docent's Tour of Salvador Dali Resources
|
《ナルシスの変貌》 ●熊倉敬聰
舞踏の現在
「舞踏」─人類の舞踊史においても、最重要な身体表現・哲学のひとつを生み出した土 方巽、大野一雄以後、舞踏は今や、ポスト産業資本主義の世にあって、新たな変貌を遂げられぬまま、ますます失速状態にあるように思われる。 伊藤キムの試み
そんなキムが、今年の7月、東京両国のシアターX(カイ)で、芸術文化地域活動「楽(らく)の会」のプロデュースの下、《ナルシスの変貌》(改訂版)を踊った。 舞踏の未来
東北の田圃の泥が育てた身体と、西洋近代の舞踊表現のズレを限りなく鋭敏に生き、それ自体を独自の身体創造に結晶させた土方。これからも「舞踏」が存続しうるとすれば、それは、現代の「ハイパーリアル化」されながらもさまざまな「リアル」な暴力を抱え込む「ポストモダン」社会に、いかに身体を闘わせ、それを新たな表現に作り上げていくか、そこにしかないだろう。
[くまくら たかあき/
|
|
|
|
篠山紀信写真展「食」

篠山紀信写真展「食」、会場風景
|
篠山紀信写真展「食」 ●椹木野衣
「食材」がひしめく閉鎖空間
会場に一歩足を踏み入れた瞬間から、はっと息を呑む展覧会というのは、なかなかな い。たとえあっても、その驚きが最後まで持続するということになると、ほとんどお目にかかれないといってよい。ところが本展では、一見したとき受けたショックが、会場を出るまで途切れることがない。最初に受けた驚きが、これらの写真を見るためのたんなる導入なのではなく、これらの写真の本質にかかわることだからだろう。 恐怖を呼び起こす和食のやさしさ、上品さ
いまひとつ注目すべきなのは、ここで篠山が被写体に選んだ「食」の数々が、すべて和食に限定されているということだろう。 [さわらぎ のい/美術評論家]
|
|
|
|
ガブリエル・オロズコ展@ICA
Gabriel Orozco Reference Page http://www.artincontext.com/ listings/pages/artist/r/ 6ge40xmr/menu.htm
The Institute of Contemporary Arts (ICA), London
The Institute of Contemporary Arts (ICA)
|
ガブリエル・オロズコ展@ICA ●毛利嘉孝
「都市」を書き換える悪戯
夏の間は、ロンドンのアートシーンはそれほど大きな動きがあるわけではない。実際に各ギャラリーや美術館のスケジュールを確認してみても秋に向けての小休止といったところだろう。その中で目立っているのはICAで開かれているガブリエル・オロズコの展覧会である。 「移民」として考える
オロズコはもともとメキシコ出身の作家。最近はマドリード、ベルリン、ニューヨークと転々としながら作品を製作している。シトロエンにしてもタイヤのようにも見えるゴム製のオブジェにしても、何よりもオロズコのセルフ・ポートレートであり、それは都市にとっては不可欠で有益なものでは必ずしもないかもしれない。しかし、だからといって、これらは完全なゴミとして捨てるには美的すぎるもの、何かひっかかりのあるものなのだ。
[もうり よしたか/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sep. 10, 1996
|
[home]/[Art Information]/[Column]
Copyright (c) Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1996
Network Museum & Magazine Project / nmp@nt.cio.dnp.co.jp

