先ごろ3月半ば、勤めている武蔵大学で平日5日間だけの小さな展覧会を企画した。ある美術品を気に入って買ったので、多くの人に見てもらいたいと考えたのである。私たちは、いいなと思ったものを購入し、家族や友人や不特定の誰かに見せる(とか、見せびらかす)ことをとても日常的に行なっている。例えば、着飾って街を歩いたり、レストランで料理を美しく撮影してSNSに投稿したり。私たちに馴染みのこうした「何かを購入し、自分のものにして、それを“展示”すること」と、美術品との距離はなぜだか遠い。「展示」は美術の得意分野のはずなのに。思い立ってちょっと道筋をつけてみたくなった。
展覧会のタイトルは、「美大じゃない大学で美術展をつくるvol.1 藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」。たまたま勤務先の大学内に使えそうな展示施設がなかったので、ホールを無理矢理展示室に改装した。ついでだから、大学やいろんな場所でも展示はできると周りに示すことも目指そうということで、シリーズタイトルにした。
この小論は、そこで展示した藤井光さんの作品《日本の戦争美術》について、展覧会を企画するより前に書いたものである。作品の意義、つまり、なぜどのように価値があると思うのかを文章にしたためて考えながら、この作品が、自分のところまで渡ってきた経緯を記録したものである(ただし文章は事後的に調整をしています)。

「美大じゃない大学で美術展をつくるvol.1 藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」(2024)[筆者提供]

「美大じゃない大学で美術展をつくるvol.1 藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」(2024)[筆者提供]
「パブリック」ミュージアムから歴史を裏返す──「再演」としての〈日本の戦争美術 1946〉(東京都現代美術館、2022)
藤井光〈日本の戦争美術〉は、2022年東京都現代美術館で開催された「Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022 受賞記念展」で初めて発表された。この展覧会は、そこからオンライン版展示・販売へと派生し、その結果、筆者が企画した展覧会へとつながった。本稿では、2022年の美術館での展示とその翌年のオンライン版展示について考えてみたい。
まず、東京都現代美術館での展示から解題していこう。
会場のキャプションを読む限りでは、〈日本の戦争美術〉(のちにタイトルが〈日本の戦争美術 1946〉となったため、本稿では主にその名称で表記する)という展覧会は、動画音声インスタレーション《日本の戦争美術》(2022)をあいだに挟み、二つの絵画展〈日本の戦争画〉で構成されている。
絵画展は、1946年に開催された戦争画展を再現したものである。46年展の会場は、「東京都現代美術館」の前身とも言える「東京都美術館」であり、主催はアメリカ合衆国太平洋陸軍である。「入場 占領軍関係者に限る」とあり、公衆へは開かれていなかったとわかる。この展示は、戦時中に描かれ接収されたこれらの絵画が、保存すべき「芸術」なのか廃棄すべき「プロパガンダ」なのかを検収するために開かれたものであった。
展示室には、画家たちが描いた戦争画が実寸大で再制作され、高密度で展示室に敷き詰められている。キャプションを読むと、1946年に「ここ」に展示されていた作品のタイトルや作者がわかる。ところが作品には何も具体的なイメージは描かれていない。資材が剥き出しで、布やシートが貼られた枠組みだけがディスプレイされている。抽象絵画のようで、かなり大型であるところも含め、同時代のアメリカ・ニューヨークで盛期を迎える抽象表現主義を思わせる。
室内はまるで収蔵庫のようである。再現に使われている素材は、ベニヤ板など美術品の運搬や保管・展示資材として使われたものの廃材だ。照明に着目すると、スポットライトは弱く、展示室はまるで事務室のように蛍光色で全体が明るく照らされている。とくに後半の絵画展では、ところ狭しと大きな絵画が二段に展示され、二つの列に挟まれた通路の幅は、このサイズの絵画を鑑賞するにはあまりにも狭い。こうしてディスプレイに着目してみれば、「舞台裏」をひっくり返して表に出しているようにも見えてくる。普段展示室で作品を鑑賞するときには整然と見える、美術館や美術品の「顔」には裏側がある。そのような想像へと導かれる。

「Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022 受賞記念展」(2022)[撮影:木奥惠三、提供:藤井光]
さらに本作は、美術史についても「表の顔」を見つめなおすよう促してくる。二つの絵画展のあいだの回廊に設置されたインスタレーション《日本の戦争美術》では、第二次世界大戦後の占領期、アメリカ軍が戦時中に日本軍を喧伝するために描かれたプロパガンダ絵画について議論する音声が掲示される。黒色の背景に台詞の字幕のみが映し出された画面は、鑑賞者に考える余白を与える。議論の中身は例えばこのようなものだ。この押収品は、「芸術品」なのか「政治の道具」なのか。もし高名な芸術家が創ったものならば、どう扱うのが適切なのか。ここにはあのパリの藤田嗣治も入っているが、彼は戦争画であれ自身の作品がアメリカ国内で展覧されると聞いて大喜びらしい……などと、米国陸軍通信隊の高官が極めて興味深い会話を展開している。
「美術館の裏の顔」のごとく再現された絵画群は、この音声・字幕映像と併せて展示されている。誰が芸術とそうでないものを決めるのか。私たちが見ている「芸術」はどのようなふるいにかけられているのか。社会にとって芸術とはどのような存在なのか──次々と頭に浮かぶ問いが鑑賞者に揺さぶりをかける。こうして藤井は、「敵/味方」や「虚/実」などと二元論的に語ることはできない、芸術やその歴史の複雑さについて提示してみせる。
作品の素材は、史実の痕跡を残す史料である。本作はアメリカの国立公文書館で保管・公開される一次資料をもとに描かれたドキュメンタリーなのである。映像は2種類あり、5,000カット以上の文書資料をマイクロスコープで撮影したもの、そして、前述した音声字幕のみを映した映像だ。後者のもとになった資料は、じつは音声ではなかった。戦時中の暗号を含む機密情報には、興味を誘われるような「演劇的な」やりとりが残されていたわけではなかった。
それは藤井の手によるシナリオなのである。ただし、その実証性とリアリティのために藤井は次のような手続きを採った。戦争画研究者の河田明久に脚本を依頼し、別の占領史家にも重ねて内容の妥当性を確認した。さらに、英語音声と日本語字幕で表現されるシナリオは、言葉のニュアンスまで表現できる字幕専門家ディーン島内の手で最終的なかたちに整えられた。このような映画監督(ディレクター)とも呼びうる過程を経て当時の証言を再現している。
この戦争画が辿った歴史は、これまで美術館ではあまり語られてこなかったものだ。この歴史を日本国籍の表現者が再構成するに至ったのは、戦勝国アメリカが、その史料は公益性を持つ公共財であると見なして保存し、そして、アメリカ市民及び米国と外交関係がある国の市民へと公開したことによるものである。絵画が辿った歴史の顛末について言えば、藤田嗣治をリーダーとする著名な画家たちによって描かれた153点の戦争画は、精査の結果1951年アメリカへと送られたあと、1970年に「無期限貸与」という名目で日本政府に返還されたあと、東京国立近代美術館へと収集された。
「アメリカ」の声を通して、加虐の歴史を修正するために日本軍によって廃棄されたいくつもの「不在の資料」もまた想起される。忘却への欲望、あるいは、見ないふりや忘却という所作ですらない、公文書への頓着がまるで感じられない無関心。現代日本社会へも続く病への想像力もまた喚起される。「見える」歴史とは、いかに視野が限られ、整えられたものなのか。藤井は、「裏側」を見せることで「見えないもの」を描こうとし、なぜそれは不可視なのかを浮かび上がらせる。
このように本作は、「公共の」「美術館」「展示室」で再構成されることそれ自体に意味が読み込める、自己言及的なミュージアム批評作品である。

「Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022 受賞記念展」(2022)[撮影:木奥惠三、提供:藤井光]
その演出に見られたように、本作はまた、《日本人を演じる》(2017)、《帝国の教育制度》(2016)、《無情》(2019)など藤井が近年とりわけ力を入れる「再演」の手法を取り入れたシリーズの一環であると見立てることもできる。
演劇用語で「再演(re-enactment)」とは、過去の出来事を再現するパフォーマンスの表現様式のことである。美術の文脈では、マリナ・アブラモヴィッチなどがよく知られている。同時にこの言葉は、野外で行なわれる参加型の大衆演劇や、学校や教会で実施される教育的史劇、また“歴史ガチ勢”が本格的なコスプレをするファンカルチャーのことも指す。例えば、アメリカ独立戦争や南北戦争など有名な戦闘の一場面を、史実に基づき再現した衣装や隊列、順序などで演じるものだ★1。幼年期から教育に広く採用されていることにも明らかなように、一般市民が自らの歴史を追認し再認識する再演には、演じることを通して「正史」を再強化する政治的機能がある。
藤井はこの再演の手法を、美術館で催されるワークショップへと転用する。2017年の作品《日本人を演じる》は、「人間動物園」と呼ばれる博覧会の上演展示をモチーフとしている。これは、朝鮮、台湾、中国本土やアイヌ、沖縄などから人々を連れてきて展示することで植民地における「人種」の差異や優劣を示すというグロテスクなもので、100年ほど前の日本や、植民地を持つ諸国で行なわれていたものである。人類館と呼ばれたパビリオンで人類学者が「『日本人』とはどのような特徴があるのか」と問うた、帝国主義的な支配の欲望をむき出しにした問いを、藤井は現代日本で再演してみせた。
また、2016年韓国の国立現代美術館ソウル館で発表された《帝国の教育制度》で日本の朝鮮植民の歴史を再演している。本作は、太平洋戦争中にアメリカ陸軍が軍内で作成した大日本帝国の教育制度に関する資料映像と、現代の韓国籍の学生が参加したワークショップ映像で構成される。ワークショップで参加者が見ている映像自体は映されず、日本人作家が専制的にその場を制御していることへ意識が向けられるしかけが施されている。あいちトリエンナーレ2019のために制作された《無情》では、日本統治下の台湾で行なわれた「日本人」への同化教育プロパガンダ映画『国民道場』がワークショップ映像と併置される。映画で示される「皇民」としての身体動作を、中京地区の自動車工場などで労働者として働く外国籍移民に寸分違わずシンクロさせるように演じさせている。
これらの作品で監督を務めた藤井は、「日本人」という強固な概念が「正史」から弾き出した存在をその歴史に取り込む演出で「再演」したのである。藤井による、身体への教化という政治力学を伴う「演じる」という行為の導入は、美術史のパフォーマンス表現の文脈というよりも歴史教育の「再演」の系譜に近いものである。しかし、この歴史力学への批評性は作品として美術館に展示される。歴史から消されたものを美術館からもう一度美術史へと導入するように。
〈日本の戦争画〉展もまた、再演作品のひとつの変奏である。それは先に挙げた映像での再演だけではない。日本の現代の公立美術館を「再演者(re-enactor)」としてキャスティングし、語られてこなかった「日本の美術(館)史」の出来事を「再演」したものでもある。
同館を管轄する東京都の行政機関では、近年歴史否定論者・修正主義者による検閲的事態が目立っている。首長の小池百合子都知事は、関東大震災時のデマが引き起こした朝鮮人虐殺という史実を相対化する言説を公人として発信し続けている。東京都総務局人権部は管轄するミュージアムの人権プラザで、虐殺の史実であるという歴史家の証言を含む、アーティスト飯山由貴による映像作品《In-Mates》(2021)の展示を拒否した。こうした文脈において、東京都管轄かつ現代美術界有数の東京都現代美術館において藤井が行なった歴史の再演は、〈歴史〉を語る力学において大きな意義を持っている。
のちに作家本人から、極めて興味深い事実を聞かされた。
〈日本の戦争美術 1946〉には、普段は埼玉の工場で働く4名のクルド人難民が展示の現場制作者として参加していたという。じつは展覧会にクレジットもされている。彼らは中学生の頃に両親と移住してから日本に住んでいる。あえて記すのだが、彼らはわれわれの社会を構成する一員である。しかしながら、法務省・入局管理局によって「仮放免者」として扱われ、同じ社会に暮らしながらも、就労し日々の糧を得ることと、そして、生きがいを感じる権利を疎外されたものたちである。
つまり藤井は、「公的な」エコシステムから排除されたものたちを「再演」芸術という形態を流用してエコシステムに再び包摂し、不十分な日本の「公共性」を補ったのである。「公立の」美術館がただしく「公共的な」役割を果たしたと言える。これは当然、同時代の「正史」へ挑戦するものである。この意味で〈日本の戦争美術 1946〉は、プロジェクト型の「パブリック」アートであり社会彫刻でもあったのだ。
美術品をポチって戦争の記憶に参加する──アートの通販〈日本の戦争美術1946 Cloud Exhibition April 26 – May 31〉(オンライン、2023)
二つ目の展示も見ていこう。本作は翌年2023年4月になって、さらに〈日本の戦争美術1946 Cloud Exhibition〉と題したオンライン版でも発表された。
藤井は、東京都現代美術館の〈日本の戦争美術 1946〉で制作した各作家の再演絵画を統一された寸法の小型のオブジェ作品へと作りかえた。これをウェブ上のバーチャル展覧会で展示して販売を行なった。一日限定で会場での展示も行ない、その日は藤井自身も参加した。
こうした方法で展覧会を実施した藤井のねらいは何か。新型コロナ禍におけるパンデミックという社会背景があるのはおさえたうえで、ここではその意義を、「販売・購入」と「参加意識」という点から考えてみたい。
アンディ・ウォーホルを例に挙げるまでもなく、展覧会や芸術祭、アートフェアやギャラリーでの販売、美術史研究や美術批評・ジャーナリズムといった言論や各種メディアでの露出など、アーティストは広い意味でのマーケットバリューに引っ張られながら歴史にその名を残すことになる。何が残り何が残らないのか。どの作品が、どの作家のどのエピソードが語られ、そして何が語られないのか。資本主義社会において歴史語りの強弱はこうした市場構造のなかに組み込まれている。現代美術の領域には、そのなかにいながらにして、こうした〈歴史〉の課題を暴き批評することに優れたアーティストが多いということは言うまでもない。
現代美術の批評性は極めて鋭い。鋭いが、映画やポピュラーミュージックなどに比べてそのターゲットは極めて限定されているようにも見える。美術も社会から自由ではない。人種主義や優生思想、家父長制、後期資本主義や「正しい」心身のイデオロギーなど、ある社会が過去に根ざす特定の構造、つまり〈歴史〉が支える価値観や序列に支配されているならば、美術もまたその構造のなかにある。
〈日本の戦争美術〉展は、こうしたミュージアム界や美術界の「歴史の磁場」自体を問うものであった。この販売プロジェクトは、さらにその問いを別のところにいるオーディエンスへと開くための具体的な試みではないだろうか。それは物理的にも、制度的な意味でも「美術館の外」へと開こうとしたものである。
藤井はSNS上で、このバーチャル販売展について次のような趣旨の発言をしている。展示物のうちいくつ売ればアーティストフィー(制作活動自体への報酬)を除く制作経費が回収できる、さらに何点売れれば「ベトナム戦争が始まる1965年の冷戦時代」についての次回作の制作費に充てる……。作家はその行為が持つパフォーマティヴな意味に極めて意識的である★2。上がった収益の使途を公開して透明性を高めながら、芸術制作への参加者を募っているのだ。
恒常的に活動がまわるエコロジーのための作品販売。上記の理由で設定された69,300円(税込約7万円)という価格は決して安価ではないが、うん100万円というような、購入にローンを組まざるを得ない値段ではない。ちょうど誕生日も近いし、自分へのプレゼントだと思い切ろう。「購入する」というよりも、このプロジェクトに加わり「参加する」という感覚でポチった。
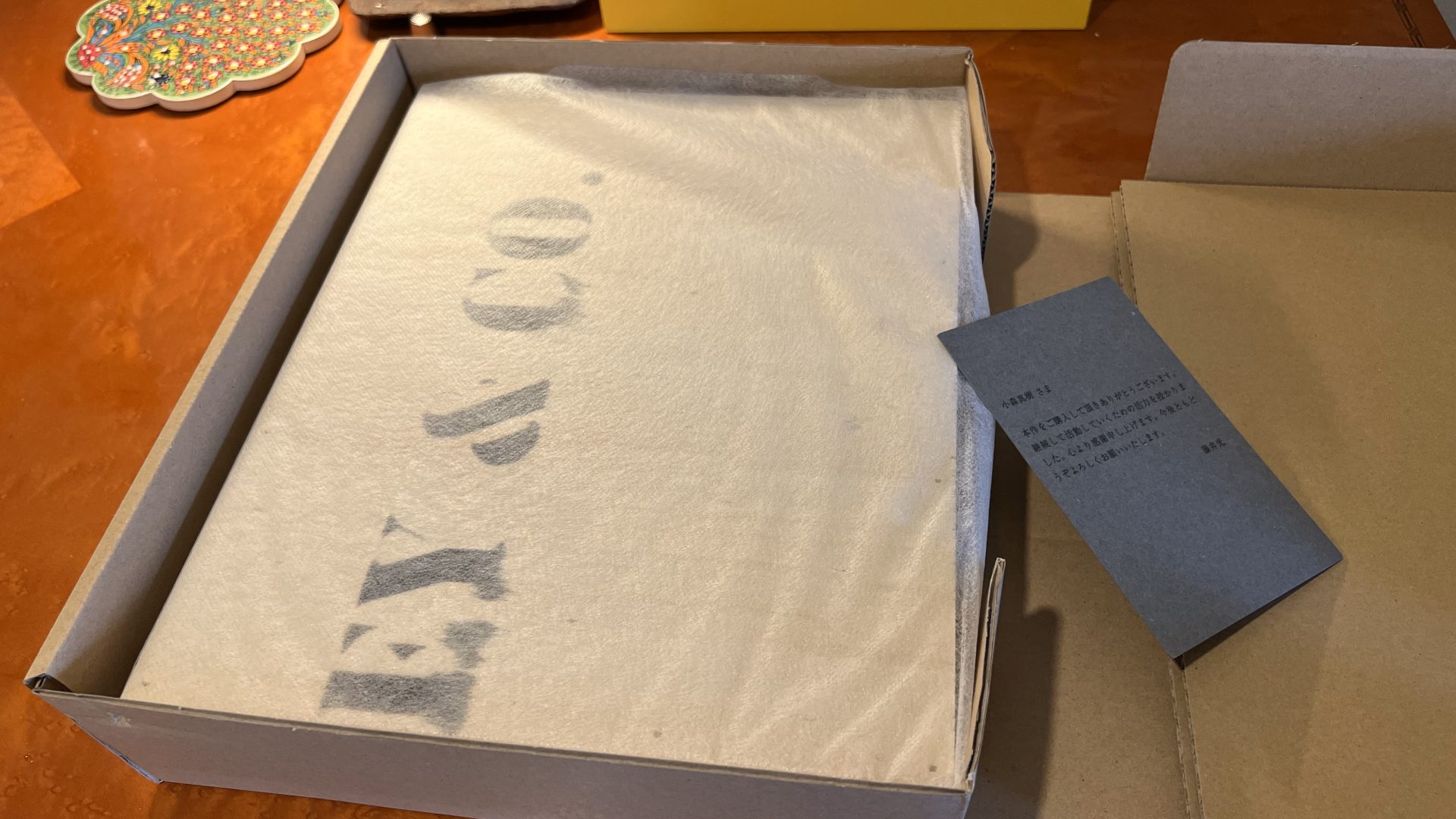
届いた作品の梱包を解くと丁寧に包装されたボックスセットがお出まし[筆者撮影]

私家版〈日本の戦争美術1946〉展(2023年5月19日-2024年3月14日、於都内某所)[筆者撮影]
しばらくすると、藤井本人の礼状が添えられた作品が届いた。美術館での絵画作品を小さく加工した、ラップトップ大の大きさのベニヤ板の箱型オブジェ。それは、マルセル・デュシャンよろしくボックスセットになっていた。包装され、上映権付の作品証明書、SDカードに入れられた映像・音声作品、音声スクリプトや作品リスト、作品インストラクションなどがボックス内に封入されている。オブジェとして自室の一角に展示してみたが、展示室と手狭な自宅では空間把握が異なり巨大な感じがする。手に取ると想像以上の物量を感じ、作品が運ぶ「歴史=物語」の重みを伝えている。
成功するクラウドファンディングの現場には、いつも「祭り」としての盛り上がりがある。それと同様に、「われわれ」意識がうまく働くことが、美術品の販売においても肝要だろう。藤井はステートメントでこう述べている。「現時点ではまだ理想のエコシステムですが、この機械仕掛けのシステムを動かし命あらしめるのは皆様の『参加する』という意識に他ならない。」★3
日本社会は展覧会を観ることへの関心が高い一方で、美術品の購入にはそれほど関心を持たない傾向があると言われている★4。「購入」という行為は、この国に極めて馴染み深いものでありながら現代美術界にはなぜだか広がらない★5。〈日本の戦争美術1946 Cloud Exhibition〉は、売買という消費活動を媒介にコミュニケーションを生みだし、未だ見ぬチャンネルから歴史をこじ開けようとする作家のアクションと受け取った。
オンライン展タイトルに冠された「クラウド」とは、クラウド・ファンディングのことであり、同時に、ネットワークのクラウドのことも指すのだろう。ウェブ上でデータが断片化され、使用する都度再構築する形で仮想化された、現代的な「モノ」のありかた。それは、所有欲から「購入」して人とつながり、薄い意識で社会に「参加」する、ふわふわした「われわれ」意識のようでもある。
ウェブサイトから、このプロジェクトに「参加する」きっかけをオーダーした。そして、どうやってこの作品を公に展示しようか、展示の企画へと思いを巡らせはじめた。
本作は上映権付だと、作品証明書に記されていた。金銭を介して、モノだけでなく展示する権利も譲渡されていた。本作が映像作品も含んでいることは、「展覧会」だけでなく、「上映会」といったかたちで作品が広がる可能性もある。
こうして本作は、美術史や美術館の歴史性を問い直す物語を、「販売」という方法で〈パブリック〉へと開放していく。「作品を購入する」という行為が、グランドセオリーとしての〈歴史〉を批評し解体する方法を提案している。

「美大じゃない大学で美術展をつくるvol.1 藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」(2024)[筆者提供]
2024年3月、購入した本作を主軸に据えた展覧会「藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」を実現することができた★6。(忙しいなか手伝ってくれた学生さんをはじめ各方面のご協力のおかげである。感謝したい。)「所有したい」というエゴと「参加したい」というちょっとした社会意識でたまたま作品を「購入」したが、これが展覧会をミュージアムの外へと拡げて〈歴史〉を語り継いでいくきっかけとなったのである★7。
★1──そのほか、この再演手法をミュージアムで採用したものにリビング・ヒストリー・ミュージアムがある。例えば米国ヴァージニア州にあるコロニアル・ウィリアムズバーグは、18世紀米独立期植民地時代の村を博物館学や演劇論などのトレーニングを受けた人々が演じる野外博物館である。こうしたミュージアムやイベントなどの再演行為は、非専門家が自ら語る歴史、つまり、パブリック・ヒストリーの典型例である。参照:菅豊・北條勝貴編『パブリックヒストリー入門』(勉誠出版、2019)。
★2──藤井光、Facebook投稿、2023年5月1日12:10。
★3──藤井光、Facebook筆者へのリプライ投稿、2023年5月21日。
★4──近年の市場調査でも以下などがこうした結果を示している。『日本のアート産業に関する市場レポート2020』(文化庁・一般社団法人アート東京、2020)における「『美術品購入』と『博物館・美術館訪問』の状況」を参照。
★5──筆者が行なった戦後期の現代美術を扱う雑誌言説を対象にした調査に拠れば、古参の美術専門雑誌の言論が非美術画廊以外の市場へ美術品が拡がることを忌避する一方で、新興の非美術系サブカルチャー誌ではむしろそれをアートの民主化として賞賛するといった一種の対立構造が1980年前後の時期に現われていた。美術に関わる消費行動の理解には、このような美術品に対する価値観の構築過程の分析も有効であろう。参照:小森真樹「日本における『アート』の登場と変遷」東京大学大学院総合文化研究科修士号取得論文、2008年度。
★6──200名以上の来場者に恵まれて閉幕した。現在、書籍版+ウェブ版の二つで記録集を編集中。以下で、展覧会の制作プロセスとアーカイブを更新中。展覧会資料アーカイブ:「美大じゃない大学で美術展をつくる vol.1 藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」公式サイト(https://masakikomori.com/)、制作プロセス(https://www.instagram.com/phoiming0422/)※SNS投稿のまとめ機能が停止されたようなので、お手数ですが3月頃の投稿へ遡ってご覧ください。
★7──「美大じゃない大学」で展示する試みは嬉しいことに好評をいただき、他大学や本学の別学科の教員などへも広がりつつある。2024年9月には武蔵大学図書館で「vol.2」が行なわれることが決定した。どなたでもこのシリーズ名を使って企画していただければと思っています。
関連レビュー
村田真|Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022 受賞記念展:藤井光:artscapeレビュー(2022年05月15日)
高嶋慈|Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022 受賞記念展:藤井光:artscapeレビュー(2022年04月06日)







