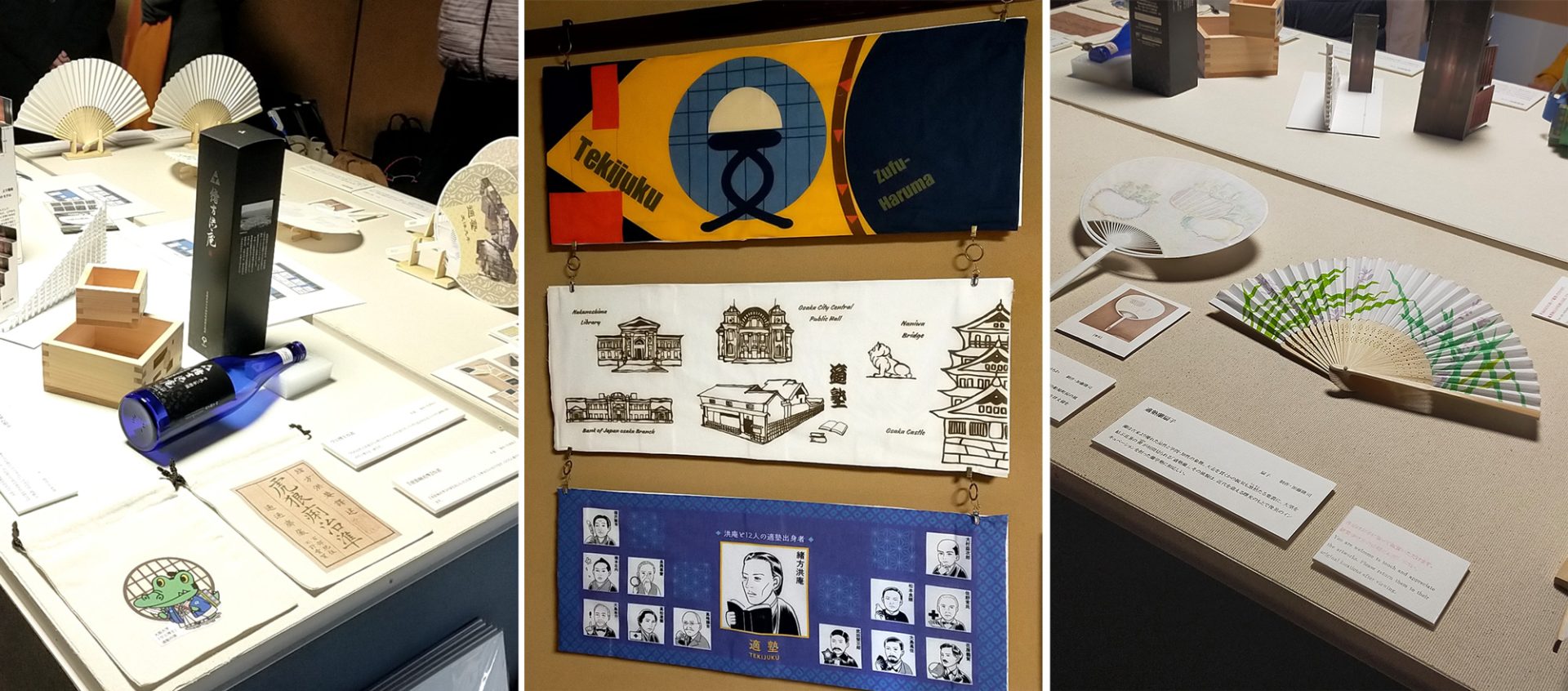鳥取県立美術館の開館まであと2カ月という時期にこの原稿に向かっている。artscapeに執筆を始めたのが2021年6月だったことを思うと、本当にあっという間の4年間であった。読者の方々はきっと、新しい美術館やその準備状況を期待されているだろうし、学芸一同新しい美術館に期待を膨らませていることを想像されるかもしれない。個人的には、その実、慣れ親しんだ、そして思い出深い県立博物館から離れることの方が寂しくて切ない。ある意味「区切り」とも言えるこのタイミングに、あえてこの古い館での活動を振り返ってみたいと思う。
 梅田哲也によるライヴ・パフォーマンス(2018年12月23日、鳥取県立博物館エントランスホール)
梅田哲也によるライヴ・パフォーマンス(2018年12月23日、鳥取県立博物館エントランスホール)
いかに時代を共有するか
筆者が鳥取県立博物館に勤務した期間は、2002年7月から2008年6月、2013年10月から現在までと、およそ17年間にわたる。近現代美術と写真分野を担当し、十数本の企画展に携わってきた。第一期美術館建設構想が凍結となってまもなく、学芸員の増員施策が取られたタイミングでの採用であり、これはその後の博物館の活動方針をある意味示していたと言えるのかもしれない。初めて手がけた企画展は、「現代の表現 鳥取」というシリーズで、鳥取にゆかりのある現存作家あるいは近年物故の作家を取り上げ、同時代の美術表現を紹介するという趣旨であった。企画を立ち上げる段階で、顕彰というよりも、奨励や支援といった、いまの芸術活動を活性化したり、あるいは新たな価値の創造の現場としてのミュージアムという、社会的な役割を拡充させたりすることを企図していた。当時、作家のリサーチ、インタビューなど準備を進めるなかでしばしば出会ったのは、「死んでからでないと作品は収蔵されない」という皮肉めいた言葉であり、開館から35年が経ち、いよいよ別のフェーズに入ることが期待されていると感じたものである。
地方自治体がミュージアムを設置する目的は、その地域の歴史を記述し、モノや情報を蓄積していくことを第一義としてきたことは言うまでもない。「鳥取の美術」の姿は、諸先輩方の弛まぬ調査研究、収集作業により輪郭を与えられてきた。一方で、現在の美術については分野別の公募展「鳥取県美術展覧会(県展)」が担い、現代美術をはじめとする多様な表現への対応が困難な状況であった。それを踏まえたうえでのこの新たなシリーズは、ミュージアム/博物館としての活動にギャラリー的な機能を付け加えた、という格好である。広報物のデザインもグラフィック・デザイナーを入れ、一新したのだが、「博物館らしくない」として苦言を呈されたこともあった。しかし、時代を共有するヴィヴィットな表現は、アートを身近なものとして捉える効果を生み、新たな観客への回路を開いたように思う。筆者の知る範囲の事例で恐縮ではあるが、展覧会に来場したことがきっかけでアートの道に進んだ高校生の話や、「同世代の活動に刺激を受け、励まされた」といった声も、時を経て届けられたこともある。
このシリーズ展は、ジャンルを現代美術に絞ったものではなく、工芸や写真なども射程に入れていた。単に作品を借用し展示構成を学芸員がすべて行なう物故作家の展覧会のやり方ではなく、作家とともに作り上げることに主眼を置いた。上述したように、作品の形態が多様化したことから、インスタレーションやワーク・イン・プログレスといった、動的で変化を内包するスタイルの展示も行なわれた。
その第4回目、2007年に開催した「中ハシ克シゲ展 ZEROs──連鎖する記憶」では、サイトスペシフィックな新作に挑戦したのだが、困難も多く、とりわけ印象に残っている。第二次大戦中に県内で訓練していた特攻機とその乗組員に関するリサーチから、制作ボランティアの募集、作品の焼却場所の交渉、展覧会の賛否についての意見への対応など、プロジェクトの実現のために必要なありとあらゆることを担うなかで、アートと社会の関係性、そしてミュージアムという場について考えを巡らせるようになった。ある時はアートの自明性を支える強力な装置として、またある時は来場者やスタッフ、協力者の方々と沢山の言葉を交わす場として、ミュージアムが変容する様子を間近で目撃したのである。
 「中ハシ克シゲ展」 制作ボランティアと作品を輸送する様子(2007年5月27日、鳥取県立博物館 正面入口付近)
「中ハシ克シゲ展」 制作ボランティアと作品を輸送する様子(2007年5月27日、鳥取県立博物館 正面入口付近)
 「中ハシ克シゲ展」バーニング・イベント(2007年5月27日、協力:航空自衛隊美保基地)
「中ハシ克シゲ展」バーニング・イベント(2007年5月27日、協力:航空自衛隊美保基地)
現代アーティストが提示する「ミュージアム」の新しい意義
もうひとつ、「ミュージアムとの創造的対話」というシリーズ企画展を紹介したい。これは2017年から2023年にかけての6年間で4回開催された現代美術の展覧会である。初回の開催は2016年度末であったが、本企画もまた、美術館構想と深く関わっている。というのも、その2年前に「鳥取県立博物館現状・課題検討委員会」が立ち上がり、今後の館のあり方が議論され始めたのと並行して、構想を練っていったという経緯を持つからである。
企画の主軸となるコンセプトは2つあった。ひとつは、鳥取にゆかりのある作家という枠を超え、国内外から多彩な現代美術作品を紹介すること。もうひとつは、博物館の建物の内外を活用し、オフ・ミュージアム的な視点を取り入れることであった。これにより、博物館や美術館を相対化し、新しい視点からその意義を再考することを目指した。2010年代に全国的に地方芸術祭が盛り上がりを見せ、展示施設以外で展開されるサイトスペシフィックな作品が注目されていた時代背景も、この試みに影響を与えている。一方で、地方芸術祭のような一過性の「祭」と、永続性を基本とするミュージアムとの差異を見つめ直すことも重要なテーマであった。
そうしたことを考えながら付けたタイトルは、とりたててキャッチーなものではなく、どちらかというと地味で堅苦しい印象を与えていたかもしれない。なんらかの強いメッセージを発するようなものというよりも、むしろ多様な解釈や展開の可能性をもつ、良い意味での「曖昧さ」を残すことにより、シリーズごと、アーティストごとに「ミュージアム」に対してさまざまにアプローチする余地や余白を用意しようと考えた結果である。各回のテーマおよび参加作家は、以下の通りである。
- 01 Monument/Document 誰が記憶を所有するのか(2017年2月25日〜3月20日)
出品作家:西野達、中ハシ克シゲ、白川昌生 - 02 空間/経験 –そこで何が起こっているのか(2018年11月23日〜12月24日)
出品作家:梅田哲也、小山田徹、田口行弘 - 03 何が価値を創造するのか(2020年11月28日〜12月27日)
出品作家:渡辺英司、大塚泰子、竹川宣彰、藤原勇輝 - 04 ラーニング/シェアリング──共有から未来は開くか(2023年11月26日~12月28日)
出品作家:小沢剛+ヤギの目、高山明、リクリット・ティラヴァニ
「ミュージアム」というお題に対し、作家の応答はさまざまであった。各回ともミュージアムを巡る問い立て、3〜4名(組)の作家によって展覧会を構成した。
「コレクション」の再解釈に挑んだのは梅田哲也、小山田徹、西野達である。西野は収蔵品のブロンズの胸像に発泡スチロール製の下半身を付け加えて全身像に作り変えたり、前田寛治の絵画作品4点を組み合わせて椅子型のオブジェに仕立てたり、と、モノの意味や文脈を無効化する常套手法で衝撃的な作品を制作。小山田は石器や土器、須恵器といった考古資料の実測図に「創造の契機」を見出し、自作の実測図とともに「ドローイング」として展示した。梅田は動物の剥製や植物のレプリカ標本といった自然資料を用い、水や光と組み合わせた生命を思わせるインスタレーションを発表したが、そのリサーチの過程で美術、歴史民俗、自然資料の価値の作られ方の違いに興味を持ち、全分野の学芸員とともに「コレクション」をテーマにしたオープン・ダイアローグ「梅田哲也×学芸員たち」を企画するに至った。
 小山田徹 展示会場より ケース内:《尖頭器》縄文時代、鳥取県西伯郡大山町羽田井にて出土、個人蔵
小山田徹 展示会場より ケース内:《尖頭器》縄文時代、鳥取県西伯郡大山町羽田井にて出土、個人蔵
壁面左:《尖頭器 実測図》記録者:北弘明、個人蔵 壁面右:《尖頭器 実測図》記録者:亀井熙人、鳥取県立博物館蔵
 小山田徹「小さな火床に集う」in 岩戸海岸海水浴場(2018年11月25日)
小山田徹「小さな火床に集う」in 岩戸海岸海水浴場(2018年11月25日)
 オープン・ダイアローグ「梅田哲也×学芸員たち」の実施風景(2018年12月22日、鳥取県立博物館講堂)
オープン・ダイアローグ「梅田哲也×学芸員たち」の実施風景(2018年12月22日、鳥取県立博物館講堂)
「ミュージアム空間」に対して意識的にアプローチしたのは、中ハシ克シゲと小沢剛率いる「ヤギの目」である。いずれも公開制作を行ない、来場者と交流したりワークショップを実施したりと、展示室を創作の現場に作り変えた。県立美術館を模したヤギ小屋を制作していた「ヤギの目」は、約1カ月間の制作期間を経て完成した小屋を前庭に運び入れ、2匹のヤギを迎えて飼育を通じたコミュニティづくりの実験を行なった。また、エントランスホールを使ったライブ・パフォーマンスに加えて、普段閉鎖されている地下室にある考古資料の特別収蔵庫へのツアーパフォーマンスを2日間限定で上演し、バックヤードを含めて劇場化した。
 ヤギの目プロジェクトでは2匹のヤギが博物館に滞在した
ヤギの目プロジェクトでは2匹のヤギが博物館に滞在した
また、「観客/来場者」に焦点を当てると、いわゆる参加型の作品形態も多くあった。小山田は、「握り石」と呼ばれる触り心地の良い石を並べたテーブルと椅子による対話空間を会場中央に配置し、新しい鑑賞体験を提供した。田口は砂を用いた巨大アニメーション・スタジオを設置し、来場者もストップ・モーションの映像を制作できるという趣向をとった。リクリット・ティラヴァニの卓球台のインスタレーションでは、来場者たちは思い思いにピンポンを楽しみ、時折看視スタッフもジョインしてプレイしていた。小沢の《あなたが誰かを好きなように、誰もが誰かを好き》(通称「布団山」)は、子どもたちが好きな人の似顔絵を描いてポストに投函し、誰かの元へ届けられ、また自らも誰かの顔が描かれたポストカードを1枚もらって帰るプロジェクトとして実施した。
そして、やはり最も刺激的だったのは、館外での展示やプロジェクト展開である。白川は駅前の地下街を通る人々の痕跡をテーマにサイトスペシフィックなインスタレーションを展開し、土地の記憶を視覚化した。西野の空き家を使った交換プロジェクトや小山田徹の焚き火プロジェクト、高山明の「マクドナルドラジオ大学」は、その作品のコンセプトの根幹から「公共空間への介入」という要素を持っている。さらに、リクリット・ティラヴァニのテキスト「SMALL DROPLETS OF WATER MAKE A BEAUTIFUL OCEAN」がプリントされたエコバッグを配布するプロジェクトでは、日常のなかにアートが入り込み、拡散していく様を目撃することとなった。また、2020年のサテライト会場では、工業団地の空き倉庫に《Oil and Water》ほか原口典之の2作品を展示した。その後、この倉庫は改装され、ギャラリースペース「アート格納庫M」として昨年3月にオープンし、原口作品の常設展示と若手作家の企画展が楽しめる、新たなアート・スポットとして活動が始まった。
 小山田徹「握り石」の空間で実施したイベント「学芸員との創造的対話」(2018年12月1日)
小山田徹「握り石」の空間で実施したイベント「学芸員との創造的対話」(2018年12月1日)
 田口行弘によるアニメーション・スタジオ
田口行弘によるアニメーション・スタジオ
 リクリット・ティラヴァニ《Untitled 2012(who if not we should at least try to imagine the future, again)》(公益財団法人石川文化振興財団蔵)展示風景
リクリット・ティラヴァニ《Untitled 2012(who if not we should at least try to imagine the future, again)》(公益財団法人石川文化振興財団蔵)展示風景
 高山明「マクドナルドラジオ大学」イントロダクション(2023年11月23日、マクドナルド鳥取駅南店 協力:マクドナルド) 手前の椅子の背にはリクリット・ティラヴァニのエコバッグがかかっている
高山明「マクドナルドラジオ大学」イントロダクション(2023年11月23日、マクドナルド鳥取駅南店 協力:マクドナルド) 手前の椅子の背にはリクリット・ティラヴァニのエコバッグがかかっている
「創造的対話」の生まれる場
こうして振り返ると、このシリーズを通して、多様な「鑑賞」体験、なかでもコミュニケーションの前景化とアートの日常への介入という特徴が浮かび上がってくる。単なる美術品や歴史資料の保存・展示の場に留まらず、観客・地域・社会とのつながりを築き、新しい価値や体験を生み出す場としての可能性にさまざまに挑戦してきたのが、この「ミュージアムとの創造的対話」であったのかもしれない。時代とともにミュージアムが持つ役割が変容し続けるのは、歴史を鑑みても必然であるだろう。またそうすることによって、ミュージアムは活性化し、新たな社会的役割に開かれる。「OPENNESS」を掲げる新しい美術館の開館を目前に控え、これまでの試みを基盤としながら、さらに豊かな「創造的対話」が生まれる場をつくっていきたい。
関連レビュー
シリーズ ミュージアムとの創造的対話01 Monument/Document 誰が記憶を所有するのか/イノビエンナーレ|川浪千鶴:キュレーターズノート(2017年03月15日号)