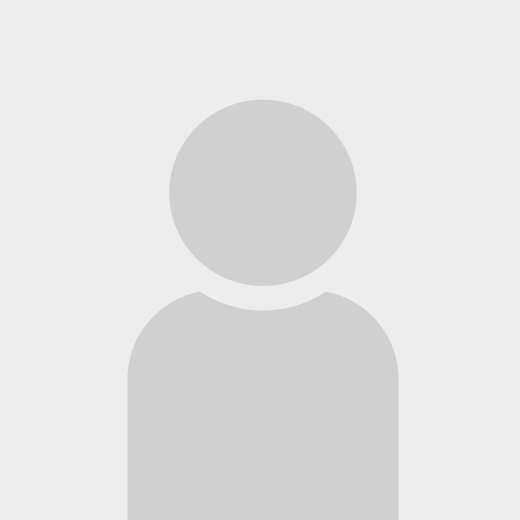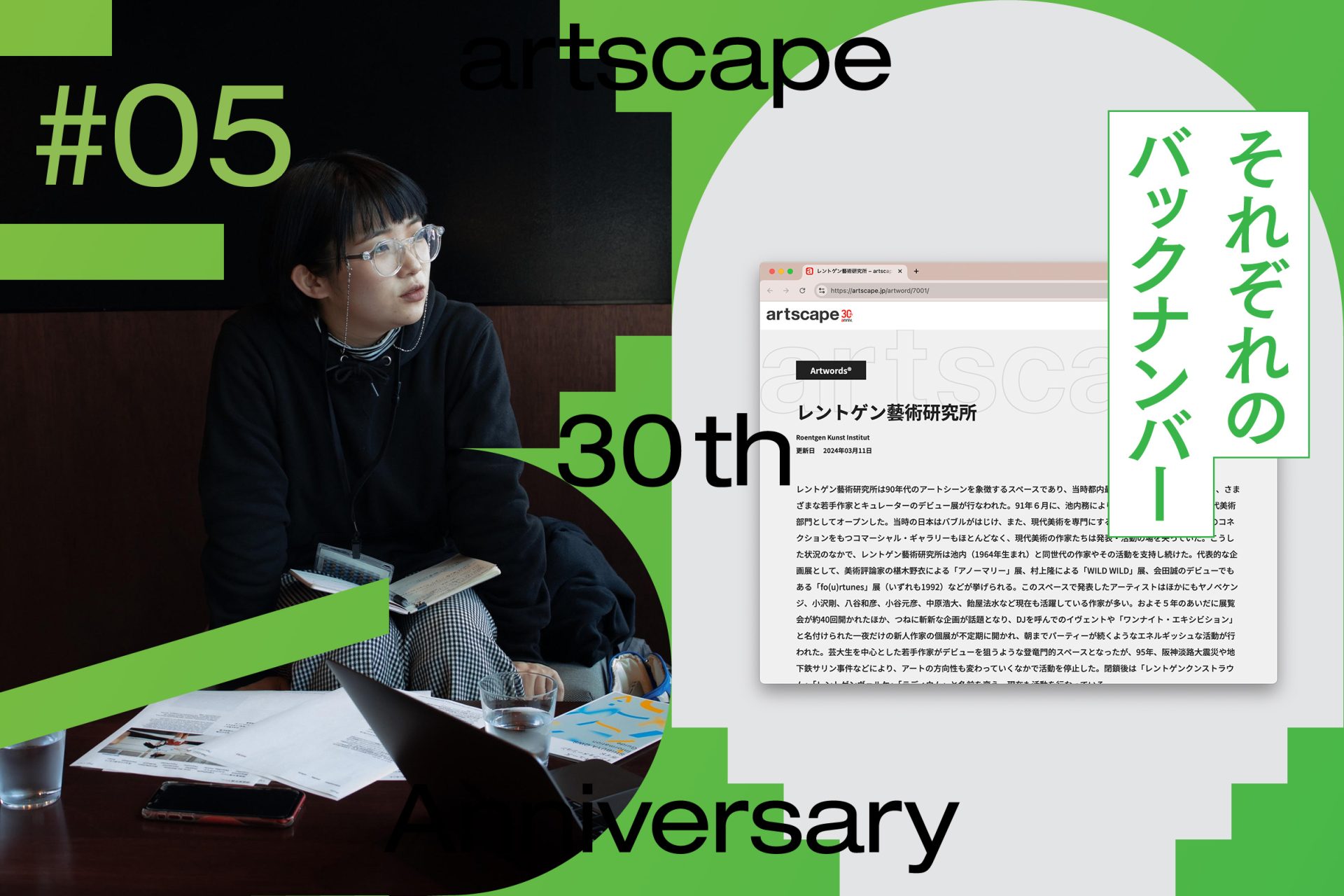日本の民家を描き続けた向井潤吉★1という画家がいる。2021年に担当した展覧会「映えるNIPPON」において作品を取り上げた際に、この作家について語る言葉がことごとく「郷愁」「なつかしさ」であることに、ある種の驚きを感じた。「郷愁」「なつかしさ」といった言葉は、絵画作品を物語るものとしてしばしば用いられる。けれども、あらためて考えてみるとその「なつかしさ」は必ずしも実体験に基づいた記憶だけが喚起するものではなさそうだ。
1901年に生まれた向井と同時代を生きた人々にとっては、確かに暮らしのなかに藁葺き屋根の民家は存在したであろうし、それが失われてゆくことに喪失感を抱き、描かれた民家を懐かしく感じることができるだろう。しかし、今日向井の作品を見る我々のどれだけが、自分史のなかに藁葺き屋根の民家の記憶を持っており、それを懐かしく感じるだろうか。もちろん、民家=懐かしいということ自体に疑問はない。むしろ疑問なく受け入れられてしまうことに驚きを感じたのだ。
昨年11月から今年の1月にかけて、東京都美術館で開催された「ノスタルジア─記憶のなかの景色」は、上述のようなひねくれた疑問を感じていた私にとって非常に気になる展覧会であった。「ノスタルジア(nostalgia)」とは、もともとギリシャ語の「nostos(家に帰ること)」と「algos(痛み)」の合成語であるという。故郷へと帰りたいが決して帰れないときに感じる心の痛み、望郷の念。移動が頻繁となった現代においては、戻ることができない過去の記憶を、現在の風景などに重ね合わせて味わう、切なくも複雑な感情をいう、と解説されている★2。
 「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第1章 街と風景(阿部達也) 会場風景 [写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第1章 街と風景(阿部達也) 会場風景 [写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
展示においては、街と風景、子ども、道という3つのコーナーが設けられ、8人の作家の作品が紹介されていた。なかでも印象的だったのは、無人の風景を描いた作品が展示されていた阿部達也と、幻想的な絵画空間が展開されていた近藤オリガだった。
「ノスタルジア」はどこまで拡張可能なのか
阿部の描く無人の風景からは、あまり音が聞こえてこない。風景のなかに、そこで暮らす人の存在は非常に希薄であり、それゆえに自分以外の人類が滅亡してしまった後の世界を見る様な、寂しさすら感じるのかもしれない。また、描かれる対象は海岸や河岸といった水辺の風景が多く、そのことも「ノスタルジア」と密接に結びついているように感じた。私自身は通学路に水辺はなかったにもかかわらず、実在しない学生時代の甘酸っぱかったりほろ苦かったりする思い出が喚起される様な気持ちになった。冷静に個人史を振り返ると、新型コロナウイルスが猛威を振るい、外出がままならなかった時期に出かけたのは川辺だったことを思い出した。暮れなずむ多摩川で家族と眺めた夕日。確かにこれは私個人の記憶のなかにしっかりと刻まれた1頁だ。しかしその前に感じた存在しない記憶はいったいどこからやってきたのだろうか。もしかしたら、小説やアニメ、ドラマといったフィクションのなかで学生時代の帰り道と水辺は強固に結びついているのかもしれない。それでは、そういった文脈を共有しない人、例えば異なる文化的背景を持つ人や幼い子供はこの絵を見て「ノスタルジア」が喚起されるのだろうか。
 「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第1章 街と風景 阿部達也の作品の展示風景[写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第1章 街と風景 阿部達也の作品の展示風景[写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
 「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第1章 街と風景 阿部達也の作品の展示風景[写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第1章 街と風景 阿部達也の作品の展示風景[写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
近藤オリガの作品を見ることでこの疑問はさらに私のなかで大きくなった。近藤はベラルーシに生まれ、同国の国立美術学校を卒業し東欧やドイツで活動してきた画家である。その後日本に拠点を持ち制作しているが、描かれているのは彼女の「記憶のなかの景色」だ。父親が子供時代の古い写真、我が子、そしてひまわりやざくろなどがモチーフとされる。これらはすべて、私の個人史とは交差しないにもかかわらず、彼女の作品を語る言葉が「ノスタルジア」であることに異を唱えることはできないと感じたのだ。もちろん、モチーフの描かれ方はひとつ大きな要素であるだろう。ひまわりが鮮やかな色彩を纏って青空の下に描かれるのと、セピア色の風景のなかに枯れたひまわりが描かれるのとで、喚起される印象は大きく異なる。ではある一定の描き方を採用したら、文化的背景を超越して人類に普遍的な「ノスタルジア」が喚起されるのだろうか。
 「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第3章 道 近藤オリガの作品の展示風景[写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第3章 道 近藤オリガの作品の展示風景[写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
 「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第3章 道 近藤オリガの作品の展示風景[写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
「ノスタルジア─記憶のなかの景色」 第3章 道 近藤オリガの作品の展示風景[写真提供:東京都美術館 撮影:坂田峰夫]
「個人的ノスタルジア」と「歴史的ノスタルジア」
心理学的には「ノスタルジア」には自分が直接経験した過去への思慕である「個人的ノスタルジア」と、直接経験していないものごとへの思慕である「歴史的ノスタルジア」とが存在するという。「個人的ノスタルジア」は自分が体験したことを確かに思い出しているという、自己内省的意識と結びつくものでエピソード記憶と関連していると考えられている。一方の「歴史的ノスタルジア」は小説などのフィクションによって形成され、知っているという感覚とむすびつく意味記憶との関連が指摘されている★3。
この観点を導入すると、向井潤吉、阿部達也、近藤オリガは「歴史的ノスタルジア」という一本の線で結ばれる。いずれの画家が描くモチーフも私の個人史とは関わりがないものが多いが、私がこれまで蓄えてきた正しく「記憶のなかの景色」に結びついてくるが故に「郷愁」や「なつかしさ」を覚えるのだ。そしてこの「記憶のなかの景色」は私に限定されるのではなく、同じ文化的背景を持つ人には広く共有されるものである。さらに、例えば昭和の「レトロ」な街並みがインバウンドで多くの海外からの観光客を集めているように、ときとして文化的背景を超えて共有されることもある。それゆえに近藤オリガの描くセピア色の風景も、その描かれ方ゆえに文化的背景の異なる私たちの「ノスタルジア」を喚起するのだ。
一方で展覧会を見終えて考えていたことは、私が今感じているこの「ノスタルジア」は、果たしてどこまで共有可能なものなのか、ということだった。同じ展覧会を見てもどの作品にどのような「ノスタルジア」を感じるのかは人それぞれだろう。ある作家にはまったく「ノスタルジア」を感じないということも当然起こりうる。そもそも展覧会のタイトルに「ノスタルジア」と銘打たれているからこそ、「ノスタルジア」と結び付けて作品を見てしまうのであって、まったく別の文脈で提示された場合には、そもそも「ノスタルジア」を感じないということもあるはずだ。展覧会とは多かれ少なかれ、ある特定の見方に沿って作品を提示することで、観覧者にその見方を伝えるメディアであり装置である。本展覧会においては、これまで作家を語る言葉として折々で集積されてきた「ノスタルジア」をひとつの軸として示すことで、作品・作家の見方に新しい光を当てている。「ノスタルジア」という、鑑賞体験を通じて想起される感情をあえて前景化して見せることで、本来個別のものである鑑賞体験が共有される場が形成されたのだ。さらにこの「ノスタルジア」という感情自体が、一個人の感傷ではなく、人の持つさまざまなカテゴリーを超えて共通言語として作用しうるということをも示しているのである。
★1──向井潤吉(1901-1995)は、京都市立美術工芸学校を中退したのち関西美術院、川端画学校、信濃橋洋画研究所と学びを重ねた。1927年には渡仏、パリ・ルーヴル美術館で名がの模写に励んだ。1933年以降は世田谷区弦巻にアトリエを構え、二科会を中心に出品を重ねた。1937年以降はたびたび戦場に赴き、作戦記録映画やポスターなどの制作に携わった。戦後ふと目にした民家の美しさに心惹かれて以来、民家を自らの画題として障害をかけて描き続けた。弦巻のアトリエは現在、世田谷区立美術館分館向井潤吉アトリエ館として、向井の作品が展示・公開されている。詳細は
世田谷区立美術館分館向井潤吉アトリエ館 http://www.mukaijunkichi-annex.jp/を参照。
★2──山村仁志「ノスタルジア──街と風景、子ども、道」(『上野アーティストプロジェクト2024「ノスタルジア─記憶のなかの景色」』図録8頁、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、2024)
★3──日本心理学会編『なつかしさの心理学─思い出と感情』(誠信書房、2014)
上野アーティストプロジェクト2024 「ノスタルジア─記憶のなかの景色」
会期:2024/11/16(土)~2025/01/08(水)
会場:東京都美術館 ギャラリーA・C
公式サイト:https://www.tobikan.jp/2024_uenoartistproject/