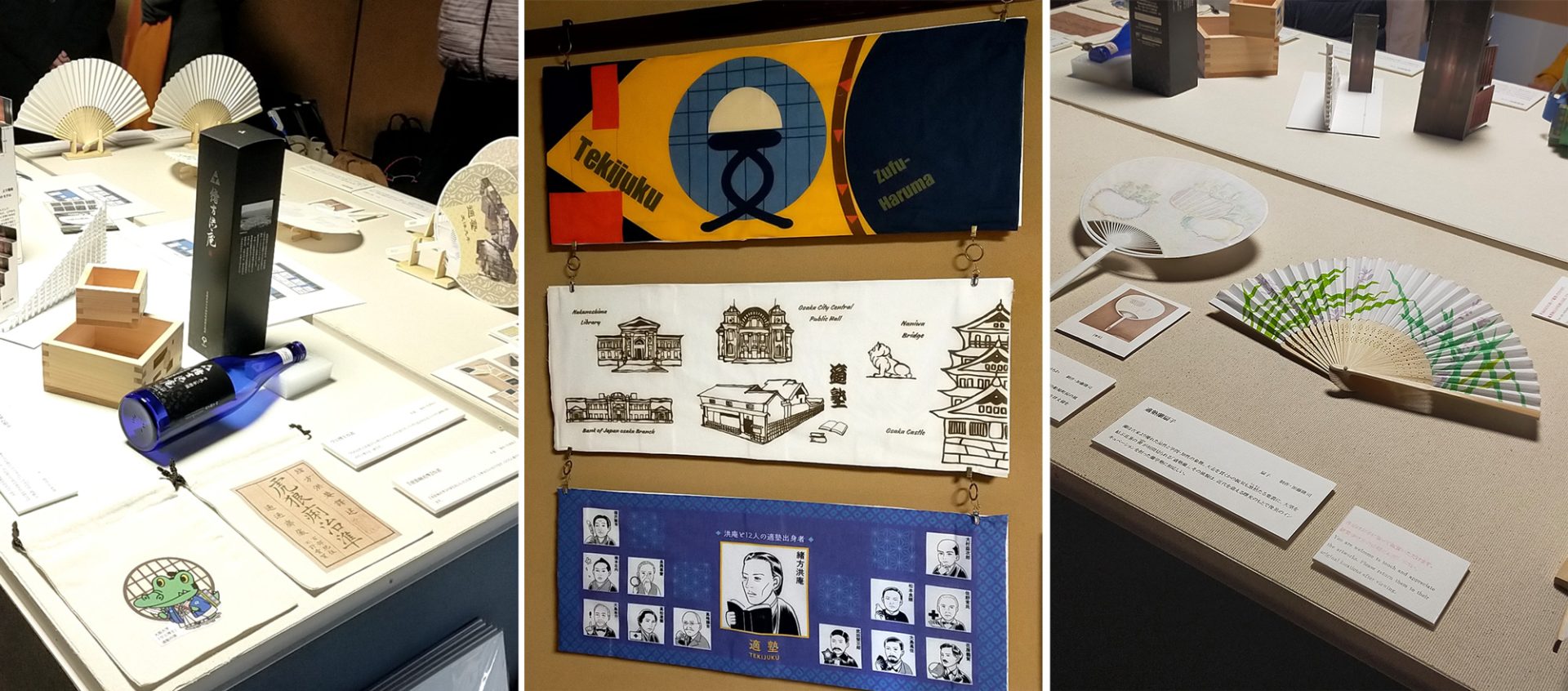5月28日、「スタッフエントランスから入るミュージアム」第9回の取材に行ってきました。今回おたずねしたのは、安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄です。札幌から車で40分ほど(道央自動車道利用)行った美唄市の、かつての炭鉱の町の小学校の跡地を利用した、地元出身の彫刻家、安田侃の作品を展示する美術館です。わっと芽吹いた新緑があざやかで、目にもまぶしいほどでした。

実は以前、同シリーズで野外彫刻の保全をテーマにしたとき、この美術館は取材先の候補にあがっていました。
広大な公園になかに野外彫刻が点在し、冬は雪のなかにあるという、いかにも作品の保存やメンテナンスが難しそうで、この館ならではのお話が聞けそうです。しかし、検討の結果、箱根の彫刻の森美術館を取材させていただいたのですが、この美術館はいつか訪ねたいと思っていました。
そうこうするうちにモエレ沼公園の宮井和美さんが今年の2月に「キュレーターズノート」で取り上げてくださいました。モエレ沼公園を設計したイサム・ノグチと安田侃は親交が深かったのですね。そして、雪のなかの美しい彫刻やアートスペースとなった小学校の写真を何点も掲載していただきました。また、「こころを彫る授業」と名付けられた彫刻のワークショップに全国から参加者が集まっていることや炭鉱の町の記憶を美術館という場所で継承されていることも、このレポートで知ることができました。ますます興味はつのりました。
ライターの坂口千秋さんと最初は、ワークショップと炭鉱の町の記憶の伝承のどちらか、あるいは両方に焦点をあてようか、と話していました。ところが、実際に取材を申し込んで広報の方とやりとりしたところ、私たちはこの美術館に思いがけないテーマが潜んでいることに気づいたのです。それが何かは、ぜひ7月公開予定の記事でお確かめください。
 そらち炭鉱の記憶マネジメントセンターの展示
そらち炭鉱の記憶マネジメントセンターの展示
「炭鉱の記憶」といっても、そもそも私自身が「炭鉱」についてほとんど何も知らないことに気づき(映画『幸福の黄色いハンカチ』くらい?)、美唄に行く前に「そらち炭鉱の記憶マネジメントセンター」に立ち寄りました。1927(昭和2)年に建てられた石造りの建物のなかに、炭鉱夫たちが鉱山に持って入ったバッテリーやヘルメット、石炭の塊、当時の写真や地図、後世に残そうとつくった模型などが展示されています。いくつか本も出版されていて、それは炭鉱夫の家族の厳しい生活、労働運動、盛んだった文化活動、大事故という悲劇、そして閉山とコミュニティの離散……が書かれています。ここはいまも、家族や親戚のなかに炭鉱で働いていた人がかならずいるという土地柄なのです。
日本の戦後復興期を支えた石炭というエネルギーの盛衰、家族、生活、コミュニティの変化。これらは、すべて過ぎ去った過去のこと、炭鉱のあった限定した地域だけの話でしょうか。私には、現在の原子力や再生エネルギーなどのエネルギー開発と私たちの生活との関係を重ねて見ることができるように思えました。
人口減少の町の記憶を誰に、どのように引き継ぐのか。この美術館の活動を次の「スタッフエントランスから入るミュージアム」でご紹介できればと思います。(f)
 アルテピアッツアの近くの炭鉱メモリアル森林公園に残された旧三菱美唄炭鉱の立坑。ここにも安田侃の彫刻が設置されていますが、歩道がわからず近くに行けませんでした。
アルテピアッツアの近くの炭鉱メモリアル森林公園に残された旧三菱美唄炭鉱の立坑。ここにも安田侃の彫刻が設置されていますが、歩道がわからず近くに行けませんでした。