2025年に開設30周年を迎えたartscapeは、アート情報サイトの新たな地平を切り拓くべく、星野太氏(美学・表象文化論)、きりとりめでる氏(デジタル写真論)、野見山桜氏(デザイン史家)の3名を特別編集委員として迎えました。今回は、そんな編集委員による座談会のかたちで、今後のartscapeの針路を探るための公開企画会議を実施しました。それぞれの専門分野の第一線で活躍する3名は、現代のアートとデザインにおける「理論」「批評」「アーカイブ」「教育」の現状をどう捉えているのでしょうか。30年の歴史を振り返りつつ、未来に向けた議論を交わしたようすを、前・後編にわたってお届けします。(artscape編集部)

特別編集委員のみなさん。左から、星野太、きりとりめでる、野見山桜(敬称略、以下同)[撮影:吉屋亮](以下同)
(前編から)
ヒエラルキーを解体するメディアの役割
野見山──美術館もそうだと思いますが、アートやデザインの世界は作り手以外の職種での人材不足が課題です。その背景には、専門的な知識を持っているからこそ活躍できる場がほかにもあるのに「そうした仕事があること自体を知らない」という問題があるのではないでしょうか。「美術を学んだら作家になるか、文章を書くか」といった固定観念はいまだに根強いですが、実際にはもっと多様な関わり方があるはずです。
業界内に存在する固定観念やヒエラルキーを解体していくことは、artscapeのようなフラットなメディアだからこそ担える役割なのではないかと感じます。
太田──美術には「アートワーカー」という概念があり、アート分野での多様な活動主体を名指すことができますよね。これに倣って、デザインの分野でもある種の「デザインワーカー」に取材するような企画を立ち上げていきたいですね。
きりとり──ヒエラルキーを崩すという点で言うと、「どういった言葉を登録しておくか」は非常に重要です。「アートワード」や「キュレーターズノート」の蓄積は、ときに既存の価値観を再生産してしまう可能性もあれば、逆にそれを突き崩す力にもなり得ます。今回の30周年企画を通じて、ヒエラルキーを突き崩すためにどのような言葉を増やしていけば良いか、皆で話し合っていきたいです。
例えば、地方美術館の収蔵作品や、そこで活動した作家たちなど、今のアートワードにはまだ載っていない美術史の側面を開拓していく、というイメージです。そのために、まずアートワードの項目を見直し、さまざまな分野の方々に「何が足りないか」と意見を求める。過去に「キュレーターズノート」を執筆された方々に、「もしいくつか項目を足すとしたら何ですか」と具体的に聞いてみるのも面白いかもしれません。
「ローカリティ」の再発見へ
太田──お二人からも重要な問題提起をいただくことができました。星野さんの先ほどの企画案とあわせて考えてみると、解体されうるヒエラルキーとして、都市部と地方部の文化的格差というものも挙げることが可能かもしれません。その意味で、artscapeが設立当初から持っていた「全国のミュージアム支援」という柱は、現代において「その場所独自の文脈を伝える」というかたちで再解釈できるかもしれません。かりに90年代インターネットの前衛性が「場所から情報を引き離す」ベクトルだったとすれば、今はむしろ「情報と場所性の一致」にこそ重要な価値が見出されているように思います。
これに関連したトピックとして、皆さんが「どこで活動するのか」という、それぞれのローカリティについてお話を伺っていければと思います。野見山さんと星野さんは金沢で長らくお仕事をされていますし、きりとりさんは海外にも滞在されていますね。
野見山──仕事の縁で金沢に移住しましたが、当初は正直なところ不安でした。というのも、街がコンパクトな分、仕事圏と生活圏の境目があまりなく、私的な時間の行動も常に気を配らねばと考えていたからです。東京の匿名性がいかに心地よかったかを痛感しました。しかし、いざ住んでみると、とくに子育てをするうえでは、あらゆるものが身近にある生活の素晴らしさを実感しました。その時々の状況や立場で、場所の意味合いは変わるものですね。いまは東京と金沢を行き来する二拠点の距離感が、現場から離れすぎず、かつ冷静な視点を保てるので心地よく感じています。
星野──その感覚、非常によくわかります。私も金沢に4年間住んでいたのですが、当時を思い出してみると愛憎入り混じる感情が湧き上がってきます(笑)。大学の教員として一挙手一投足を見られているような身動きの取りづらさと、小さなコミュニティに特有の居心地のよさがありました。ちょうど私が居た頃、キュレーターの長谷川新さんも金沢に滞在されていたり、金沢美術工芸大学の学生が始めた「芸宿」が盛り上がったりしていたんですね。
きりとり──私は仕事柄わりあい場所の成約を受けづらいので、展覧会やイベントが多い東京の周辺でありつつ、地価の面で比較的住みやすくもある横浜を拠点にしています。ところで、意識的に取り組んでいるのが「移動」です。最近はコンテンポラリーアートにおける現代性は、一定の作家が世界を還流することと関係しているのではないか、と考えています。それはヒエラルキーの問題──世界を移動できるグローバルエリートと、地域から出づらい人々とのあいだの経済的・文化的格差──もはらんでいますが、まずは私自身その流動性に身を置いてみようと。そのため、アーティスト・イン・レジデンス関連の仕組みなどを利用して、オーストラリアや台湾を転々としながら活動しています。じつはアーティスト・イン・レジデンスをやっている施設のなかには、作家のみならずアートワーカーに安価で場所を提供している例があるんです。今後はタイにも足を伸ばしてみたいと考えています。

星野──流動性の議論は重要ですね。世界中を移動できるアーティストが国際的に評価され、そうでない人は取り残されてしまう、という構造があります。私自身、ここ数年は家庭の事情で以前のように海外へ行くことが難しくなり、そのような状態に葛藤がありました。しかしいまは、その「流動性が高い=活躍している」という価値観自体を変えていきたいと考えています。それでもなお、マストで観ておきたい展覧会があれば、頑張って遠征しています──平日の朝5時に家を出て、京都で「アンゼルム・キーファー SOLARIS」展を2時間だけ観て直帰する、というようなこともできなくはないので(笑)。無理できるところは無理しつつも、やはり特定の場所から動きづらい人をすくい上げたり、その人たちの仕事に注目したりといった視点を、私たち自身が持たなければならないと感じています。
野見山──デザインの領域でも、日本各地の地場産業に根差した独自の活動がたくさんあります。最近では、Instagramなどを通じて、地域の歴史資料などを掘り起こし、発信する人たちも出てきています。例えば香川の高松市屋島山上交流拠点施設「やしまーる」の館長をされている中條亜希子さんのような方です。そうした学術的なデザイン史とは違うラインで活動している人たちとともに、それぞれの地域・それぞれの人たちのデザイン史を紡ぐといったことができれば面白いなと思いますね。これは星野さんが提起された「インフラ」の議論ともつながるところでしょう。
日本各地で行政などの意向で「古いものを壊して、新しいものを作ろう」という考えが先行してしまい、価値ある建築が失われてしまうケースが少なくありません。しかし、そうしたもののなかには、じつは観光資源やデザイン資源として活用できるものが多く眠っています。そうした地域的な資源の利活用の可能性について、行政や政治に関わる人々へ向けてメディアが発信していくことには、大きな力があるはずです。これも、今回私たちがartscapeで実現できることのひとつではないでしょうか。
美術とデザイン──その並行的な教育上の課題
太田──座談会も後半にさしかかってきまして、やや抽象的で大きなテーマについてみなさんに伺ってみたいと思います。現代のアートとデザインのシーンや動向に関して、どのようにご覧になっていますか。こうした質問の背景として、デザイン史家の野見山さんを編集委員にお招きしたことにも明らかなように、アートのみならずデザインの分野についても今後のartscapeではより幅広く取り上げていきたいという編集部の意向がございます。
野見山──2000年代以降、美術とデザインはさまざまな側面で近しい動きを見せていると感じます。例えば「日常性」への関心の高まりは両者に共通するテーマですし、マイクロポップのムーブメントと、深澤直人さんのような「普通」を目指すデザインの仕事も、バブルの頃の華やかなものから身近なものに価値を見出すようになったという点で、じつは地続きに捉えることができるのではないでしょうか。
そしてデザイン業界自体は、グラフィックやプロダクトといった垣根を越えた「統合」に向かっており、第一線で活躍するデザイナーは領域を横断するのが当たり前になりました。しかし、美大もその流れを追随してしまっている状況が気になっています。本来、ひとつの専門領域を深く学んだうえで応用として範囲を広げていくのが王道ですが、最近の教育は最初から統合的なアプローチを教えることに向かっています。それを従来の4年間という限られた時間で行なうのは簡単ではありません。実際に教育現場に身を投じて考察しているところですが、学生たちが主体的に学びを深めなければ、専門性という幹がないままになってしまい、「この人にしかできない」という強みを取得するのは難しいと考えます。
星野──いまのお話は、美術教育の現状についても当てはまると思っています。かつてのアーティストは、絵画や彫刻といった専門を身につけてからインスタレーションなどへ展開していくケースが多かったですが、昨今の美大のカリキュラムは、写真も映像も一通り扱うけれど個別の専門性は身につけづらい、というかたちに変わってきています。
きりとり──私もおおよそ同意見です。 美術の世界では、そうした「統合」の結果、それぞれのアートフォームが担ってきた歴史的意識が切断され、学生たちはその「残余」だけを中途半端に知っている、という状況が生まれているように感じます。その残余がどこから来たのかを、歴史を遡って理解するのが非常に難しくなっているのです。デザインにおける「統合」も、同じような課題を抱えているのではないでしょうか。
野見山──デザイン教育は、より根深い問題を抱えています。やや批判的な物言いになってしまいますが、多くの美術系大学では「デザイン史」が必修科目ではないことに問題を感じています。美術の教育課程で美術史が必修であるのに対し、デザインを学ぶ学生は、自らの制作を歴史のなかに位置づけるための体系的な知識を得る機会が──主体的に選択することなしには──用意されていません。そのため、歴史的な観点ではなくSNS上のコメントや「いいね」の数などが評価の指標になってしまいます。
きりとり──教育の構造的な問題に、メディアとして光を当てることはできるかもしれませんね。そうした構造のなかで、私たちは個別のデザインの動向とどう向き合えば良いのでしょうか。デザインに関連するとしたら例えば、最近私は上野学『モードレスデザイン──意味空間の創造』(ビー・エヌ・エヌ、2025)という本を読んだり、八木幣二郎さんの展示「NOHIN: The Innovative Printing Company」を拝見したりしました。それぞれ非常に刺激的ですし、『モードレスデザイン』においてはアプリ内でタップしないと次にすすめないモーダルにあふれた現在の使役的システムを考え直すことができます。また、八木さんの展示では、グラフィックデザインの個別のディシプリンによって架空の企業活動を捏造するといった総体的な力が示されていました。どちらも個別的な問題設定やディシプリンに根ざしつつ総合性を志向するお仕事であったように思います。ともあれ、こうした個別の動きがデザインの全体像のなかでどのような意味を持つのか、デザインの動向というものを把握するのが難しいと感じます。どうしたらそのようなことを考えられるようになりますか。
野見山──普段の生活で接するあらゆるものが、誰かによって企画・デザインされているという前提に立ってみることが第一歩だと思います。優れたインターフェイスデザインは、私たちが悩まずに目的を達成できるよう、巧みに誘導していますよね。そうしたものの実態や隠された意図を、自身の無自覚な行動を分析することで剥ぎ取っていく。それは、私たち自身の、あるいは社会全体の欲望やニーズを読み解く「自己批評」や「社会批評」にも繋がります。
星野──私のような美学の研究者は、デザインを扱う際、どうしても建築やファッションの歴史的なプレイヤーや事象を分析することに向かいがちです。そこと批評にはやはり距離があり、デザイン史がわかれば即座に批評ができるようになるとは言えません。
また、私自身のデザインへのリテラシーも、正直なところ本をはじめとする印刷物に大きく偏っているなと思わされます。仕事柄、書籍のデザインについては考える機会が多く、自分の本の装丁にもいつもわがままを言わせてもらっています(笑)。個人的な実感になってはしまうものの、一口にデザインと言っても、建築、家具、本と多岐にわたっており、統一的な視点で語ることの難しさを感じます。
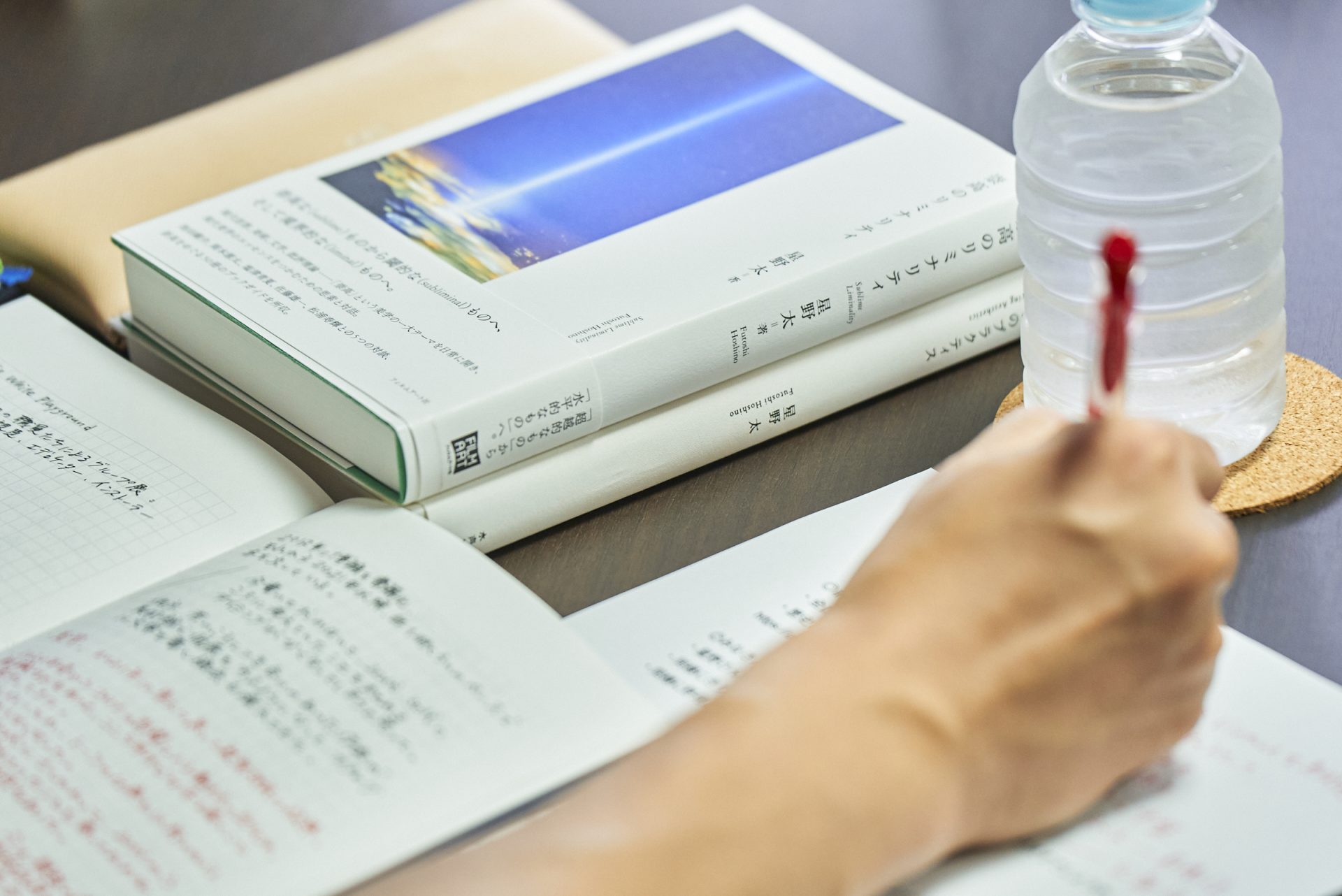
インディペンデント批評誌のシーンと方法論の模索
きりとり──少し私の視点でシーンの話を続けてみますと、近年、インディペンデントな美術批評誌の創刊が非常に活発です。ここに持ってきただけでも、『ドリーム・アイランド』『だえん2024』『Padograph雑誌』『Layers–セキソウ』などがあります。これらすべてがインディーという自覚をもって刊行されているとは言い切れないものの、版元をもつ商業出版ではない点で共通しています。
一冊ずつ紹介していきます。まず『ドリーム・アイランド』の方向性としては、「切断」の時代における「コモングラウンド」をいかに形成するかという問題意識が示されています。みんながひとつのものについて議論できる出発点を作る、というものですね。もうひとつの例である『だえん』は「美術年鑑」を銘打っており、一年間のアートの動向を記録すべく、アーティストやアートワーカーが話し合う「クロストーク」や論考が収録されています。また、30個のギャラリーとミュージアムを選出し、そこで行なわれた展覧会をすべてリストアップするとともに、アート系の事象を年表形式でまとめています。つぎに『セキソウ』ですが、これは「半匿名」のかたちを取っており、執筆者の一覧は示されつつも誰がどの記事を書いたかは伏せられているというものです。批評やコメントのかたちで価値判断することが時代状況として難しくなりつつあるなかで、半匿名という方法でそれに応じようという試みです。『Padograph』は「アジア現代美術」のタグラインを持っており、韓国や日本、ベトナムなどの動向が扱われています。これは政治的・学術的な「境界線を引く」、そしてそれを見直すというステートメントのもとで編まれた一冊です。
このように昨今の美術批評のシーンというのは、語るための方法や境界策定それ自体から始めなければならないという問題に直面しているかのようです。
とりわけ『だえん』に掲載された中村融子さんの論考「文明を洗練させる美術の『力』に抗して──関西から2024年を複数化する」を、私はたいへん興味深く読みました。美術が文明を洗練させてきた一方で、イスラエルによるパレスチナでの虐殺を止められていないという、美術「が」問題だと提起する論考です。美術という営みは周縁を「発見」することで美術を「豊か」にしてきましたが、それを解呪し、権力を分散させる美術があるということを、奥誠之が逡巡する「いま絵を描くこと」やKOURYOUの人との出会い方、松平莉奈の画面構成での選択、国立ハンセン病資料館での「絵心でつながる」展などを通して議論しています。その意味で中村論考と『Padograph』での「日本現代美術業界マップ」は対照的で、平たく言えば分類という美術での批評の質、評価基準自体が問われているのが現在といえます。
星野──ご紹介ありがとうございます。たいへん勉強になります。2010年代にも同じように志の高い雑誌がたくさん生まれましたが、数号で休刊してしまったものも多くありました。そういった試みは同時代への介入という点では有効でも、15年ほど経つと忘れられてしまいます。その種の蓄積のされなさにもどかしさも感じますね。
他方、画家・批評家の松浦寿夫さんが前に言っていたのですが、雑誌は続けることが偉いわけじゃない。数号出して終わってもよいのであって、惰性で続けることがベストであるとも限りません。
きりとり──読者の受け止め方が問われているのでしょうね。数号で終わるのだとしても、きちんと価値づけることができるでしょう、と。

30年後のartscapeへ
太田──では最後に、artscapeの未来について、探っていきたいトピックや企画のアイデアがあればそれぞれお聞かせください。
野見山──「書き手の発掘」は大きな課題です。とくにデザイン分野で、紹介記事を書くだけではない、批評的な視点を持つ書き手をどう見つけるか。私自身、最近2000年代のデザインについて執筆した際、当事者が多く存命であることや企業の評価など、さまざまな制約から深く踏み込めず、「解説的」な文章になってしまう難しさを痛感しました。artscapeならではの価値観や批評性を、より強く打ち出していく必要があると思います。それを基軸にデザインを語るチャンネルが増えれば、「デザインについて書くこと」に関心を寄せてくれる人が増えるのではないでしょうか。
きりとり──私は、「30年後のウェブマガジンのUI/UXを構想する」という企画を提案したいです。360度ビューの展覧会やデジタルツイン、あるいはVR空間で身体とインタフェースの関係性から作り直すといった動向を踏まえつつ、HTMLのブラウザベースではない未来の媒体のあり方を、ウェブデザイナーや専門家とともに探ってみたいです。
星野──私は純粋にコンテンツのことを考えてみました。ひとつは、展覧会レビューのような蓄積型のコンテンツを今後も継続していくこと。展覧会というのはどこまでいっても一過性のエフェメラルなものです。それがどのように鑑賞されたかを記録し続けることは、artscapeレビューの重要な責務ではないでしょうか。そこは、ぜひやり方を変えることなく続けていって欲しいと思います。もうひとつは──「インフラ」の議論でも申し上げた通り──批評家でもライターでもない人の文章をもっと載せること。例えば、アーティスト自身が綴るエッセイなど、批評家的な「構え」から自由な、もう少し緩やかな連載があっても面白いと思います。
きりとり──コンテンツについては、テキスト以外の形式で展覧会などについてレビューすることも考えてみたいです。漫画ですとか、それが大変であれば、例えば一枚絵の「イラストレーション」で展覧会や何らかの事物との向き合いについての記録を描いてもらうのはどうでしょう。1枚のタブローを描き手に渡し、テキストを入れるも入れないも自由にする、など。これなら継続性も担保しやすいかもしれません。
野見山──ウェブで公開しつつ、実物を展示することもできますね。
太田──大小さまざまな企画案をいただけました。座談会でいただいたトピックをもとに、今後もみなさんと企画会議を進めて具体化していきたいと思います。本日はありがとうございました。

収録日:2025/07/01(火)











