2011年から地上デジタル放送が本格的に始まります。デジタル画像となった作品をモニターで見る機会が増えると思いますが、絵画の美をデジタル画像はどこまで表現することができるのでしょうか。デジタル画像への審美眼はすでに求められています。高精細画像やX線画像など、工学と光学の新技術であるデジタルアーカイブの成果を活用する、新しい芸術表現と鑑賞の時代。デジタル画像を、よりよく鑑賞し、あるいは作品を創作するイメージの源とするためにも、改めてオリジナル作品の鑑賞方法を検証してみたいと思います。絵画を研究する専門家に、鑑賞の視座や注視点など、美の探究に必要な知識や、絵画の鑑賞方法をインタビュー。また実際に、絵画のデジタル画像を利活用することにより、著作権とどのような関連が生じてくるのか、チャレンジングな試みにもなりそうです。古典と現代をつなぐ日本の優れた絵画を、毎月一点ずつ12回選出し(古典6作品・現代6作品)、世界的な文化資源ともなるデジタル画像を鑑賞しながら、日本絵画の美を探求していきます。新たな役割を担いはじめたデジタル画像は、オリジナル作品の代用の領域をはるかに超越しています。アート分野におけるデジタルアーカイブ「アート・アーカイブ」の独自性と可能性を発見する、オリジナルとデジタルのはざまを行く新連載です。
|

 |
|
長谷川等伯《松林図屏風》(上:右隻/下:左隻)
安土桃山時代(16世紀)、紙本墨画、六曲一双、各156.8×356.0cm
東京国立博物館蔵
[出典:ColBase]
無許可転載・転用を禁止 |
|
デジタルで古典を観照する
コンテンポラリーアートに長年興味を抱きながらも、日本の古典美術に関心が向いてきたのは先端的なデジタル技術のおかげである。美術作品のデジタル画像を、現代から古典へジャンルも地域性もなく大量に見ていくうちに現代美術から古典美術へ、一気に視界が開けていった感じがしている。現在から過去へと、美術の世界を遡る感覚はとても新鮮で、時を得てアウラを宿した古典作品のなかに、古色がからない現代美術の遺伝子を見つけ出す楽しみも加わってきた。美術のようなもしかしたら無用ともいえるものに関心を抱き、心血を注いできた先人たちが作り上げた作品を改めて見ていると、現代美術家に通じる鋭い感性が伝わってきて感動を覚える。古典美術と現代美術がデジタル画像を通して、私のなかで躍動し始めたのだ。「デジタルアーカイブ」という和製英語が、一般的に普及していった頃、2002年東京・出光美術館で『開館35周年記念 長谷川等伯 国宝 松林図屏風展』が開催された。《松林図屏風》を所蔵するのは東京国立博物館である。何度かこの作品を見ていたが、このときの展示はいつもと何かが違っていた。松林から霧が立ち渡り、細霧はもやもやと動き出し、絵のなかの自然に鑑賞者を没入させた。東京国立博物館蔵の、門外不出の作品と思い込んでいた《松林図屏風》の静かな迫力に、誰もが感動しているように見えた。現代日本人の最も好む絵画というだけではなさそうな気配を漂わせていた。この展示が記憶に残らないわけはなく、きっと何かがありそうだと感じていた。この展覧会を企画した出光美術館学芸課長の黒田泰三氏(以下、黒田氏)に会いたいと思った。黒田氏は日本近世絵画史が専門で長谷川等伯(以下、等伯)の新見解を打ち出している研究者である。
|
黒田企画の展覧会
安土桃山時代から江戸時代にかけて、300年間の絵画史を研究する黒田氏。等伯の絵を見て25年、研究を始めてから15年ほど経つという。黒田氏が勤務している出光美術館のコレクションのなかで、等伯による情感豊かな動物の表現に触れたこと、また等伯の不思議な人間性にも惹かれ、その生涯を追って調査研究ができるほど多くの作品が残っていたことが等伯を研究する決心につながったそうだ。代表的な黒田氏の展覧会企画は、『開館35周年記念 長谷川等伯 国宝 松林図屏風展』(2002)、『伴大納言絵巻展』(2006)など。私はデジタルアーカイブの視点で両展を見ていた。1日あたり通常の約3倍の平均1,600名の入館者があったという松林図屏風展は、特に照明が良かったが、黒田氏自身が展示を工夫し行なったと聞いて納得した。来館者からもこれは東京国立博物館の作品とは違うものですか、という質問があったそうだ。黒田氏によると、見え方が異なる一つの要因には東京国立博物館は展示ケースが高いため、見上げて作品を鑑賞することになるが、出光美術館は施設の構造上天井が低いため、展示ケースも必然的に低くなり、本来屏風を見る目線で作品を観賞することができたと言う。この展覧会前年の2001年、スイスのチューリッヒにあるリートベルグ美術館(Museum Rietberg)で、持ち出しはできないと思われていた《松林図屏風》を展示して長谷川等伯展が開催された。黒田氏は、作品を2、3点貸し出した関係からチューリッヒに行き、展覧会にクーリエとして立ち会った。「ひとことで言うととても悔しかった」と黒田氏。美術館の外はまるで絵葉書のような南アルプスの山並みが美しく、彩りのある季節で天気もいい、墨一色のモヤッとした作品ではいい反応がないと思っていたのだ。ところが若い人が作品に張り付いて見ており、連日展覧会は好評だった。本家本元である日本でも《松林図屏風》のよさを再認識する展覧会を開催すべきだと思い、実現させたのが、35周年と銘打った松林図屏風展であった。もう一つの代表的な展覧会である『伴大納言絵巻展』は、日本美術の展覧会のなかでもデジタル画像の特性を十分に活かした展示として印象的であった。東京文化財研究所の情報調整室で画像形成を専門としている城野誠治氏のアイディアが発端となり実現したそうだが、「伴大納言絵巻(国宝)」は、源氏物語絵巻に負けず劣らずの面白さがあり、それを学芸員として伝えたかったと言う。つねに作品を見ている所蔵館ならではの見せ方を考えた。ディテールを拡大し、表情や動き、着物の柄や色など、肉眼で見る以上に伝えられないかと。デジタル画像を活用し、絵巻の細部に描かれた人物を大胆にも等身大まで拡大した展示は、新たな展覧会のスタイルを具体化し、古典絵画とデジタル画像の相性の良さを印象づけた。
|
風俗画と英雄好みの時代
日本のルネサンスといわれる16世紀の桃山時代(美術史上では安土桃山時代から江戸初期を含める)、すでに絵画を日常で楽しむ風潮ができていた。それ以前の室町時代は戦乱に明け暮れた時代。桃山時代は織田信長が出てきて世のなかを治め、安定し様子も変わり、絵も変わってきた。いちばん変わったのは自分たちの生活を絵にしたということ。生活が安定すると安定した生活を見つめ追体験しようと風俗画が誕生した。もう一つは英雄ごのみ。城、書院造り、絵の巨大化、ダイナミズムが展開していく時代。広い空間に花や木、樹木を描いた。巨大な樹木をダイナミックな構図でエネルギッシュに描く巨大な画面の絵が誕生した。狩野永徳の絵は、桃山時代前半の様式を決定づけている。この大きな流れのなかで英雄の好みも変わり、同時進行して千利休が登場してくる。茶の湯が広まり、茶道を確立し、狭い空間に掛ける自然を凝視した小画面の絵が求められた。書院造りのように大きく金色や原色の豪華な空間と、かたや茶室のように狭く質素な空間と、両極端な作風が同居している時代であった。両極端の間では入り混じることによって、いろんなタイプの不思議な絵が現われた。例えば金箔の地には本来なら色のついたモチーフを描くが、墨で描くなど考えられないことをしている。
|
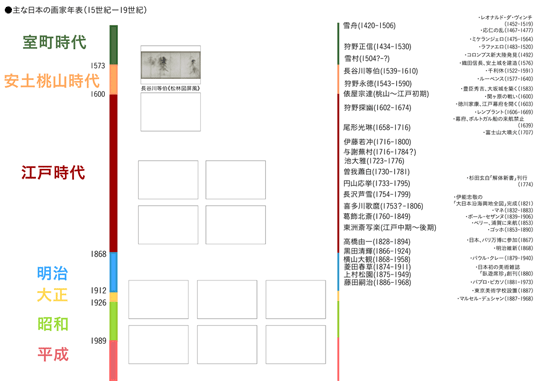 |
|
| 主な日本の画家年表 作成:筆者 |
|
百花撩乱に松林
日本の美術史上最高峰の水墨画と評価される、国宝《松林図屏風》は、豊臣秀吉が政権を握っていた桃山時代に制作された。木枠にこうぞ紙を貼り、6枚つなぎ合わせたものを一隻とし、左右組み合わせ一双としている。現代人の普通の暮らしには聞き慣れない語だが、右隻と左隻二つの屏風を一作品とする6曲1双(各縦156.8cm×横356.0cm)の紙本墨画である。桃山時代から江戸時代の絵画は、永徳や探幽をはじめとする狩野派を中心に、宗達・光琳らの琳派、大雅・蕪村らの南画派、応挙を祖とする円山派、若冲・芦雪・蕭白らの個性的な画家たちを輩出し、百花繚乱の相を呈していた。「この何でもありの時代だからこそ、等伯は『松林図屏風』を描けた」と黒田氏は時代を振り返る。「この絵のようにどこを描いたのかわからない山水画のような松林だけを描いたのは、この絵が始めてで後にも先にもない。室町時代では松林だけを屏風に大きく描く発想がないし、江戸時代には一つのテーマを墨だけで表現することはないと思う」。書物が残されており研究が進んでいるといわれる等伯であるが、《松林図屏風》の制作年代は不明なうえ、伝来がわからないというのも不可解であり、これも名作がもつ謎と魅力となっている。黒田氏は、ディテールの微妙な墨の濃淡を拡大し、全体像をイメージして把握するのが、この名作を見る最大の楽しみと語った。具体的に《松林図屏風》の見どころを下記のように教示してもらった。
|
【松林図屏風の見方】
 |
 |
 |
|
|
|
右隻4扇:松の葉
《松林図屏風》(部分) |
|
|
|
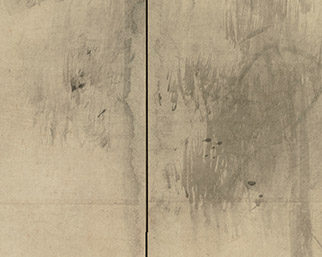 |
|
|
|
右隻5扇・6扇:飛び散る墨《松林図屏風》(部分) |
|
|
|
 |
|
|
|
左隻5扇:下に溜まる墨《松林図屏風》(部分) |
|
|
|
 |
|
|
|
左隻1扇:山
《松林図屏風》(部分) |
|
|
|
  |
|
|
|
右隻1扇:印影(左)、
左隻6扇:印影(右)
《松林図屏風》(部分) |
|
|
|
 |
|
|
|
左隻6扇:左端の松
《松林図屏風》(部分)
部分画像はColBaseをもとに作製 |
|
|
 |
|
(1)墨の筆致
ディテールを拡大して見てみると、タッチが激しい部分や墨の薄いところと濃いところが無造作ではなく、事前に計算されて描かれたことがわかる。何種類かの筆を使っているようだが、特に連筆といって4本ほどの筆を指などに挟んで同じように描いた松の葉の表現は迫力がある(右隻4扇:右手の作品の右から4枚目)。また中国の牧谿(もっけい)の影響により墨を線でなく、面的に使う筆様で、手前は線、奥は面、しかも墨の濃淡で表現する特徴がある。
(2)墨が飛び散っている・墨が垂れて下に溜まっている
一気呵成に描いた痕跡ではないだろうか(右隻5扇・6扇)。屏風として立てかけて描いたのかもしれない(左隻5扇)。また公的に完成された作品を描いたというよりも私的な作品と考えられるところである。
(3)松と霧(空気)
実際には松だけが描かれ、霧を描いてはいないが、目の補完機能が働き霧が実在しているように見える。松の絵とも言えるが、空気の絵でもある。松と松との間に空気が描かれ、しかも朝の光が差し込んできて、一瞬空気が光輝くようなその瞬間をとらえている。
(4)山
左隻の右上に、うっすらと能登の心象風景か、山が見える(左隻1扇)。山はロマンチック、センチメンタルでもある。桃山時代の風景画の構図というのがある。元々室町時代は山水画を巨大な画面に仕立てていたが、広い範囲を描く山水表現から、だんだん花や樹木など手前にあるモチーフをきちんと描く流れになっていた。花鳥画はその手前にあるモチーフをピックアップして出来上がったもので、山水画のディテールにしかすぎなかった。桃山時代に狩野派は花鳥画の背景を完全に描かなくなり、奥行きが乏しくなっていく。この松林図屏風の山は、奥に描いた室町時代の山水画の名残を留めていると考えられ歴史的に貴重である。
(5)印影
右隻と左隻に「長谷川」「等伯」の印がある(右隻1扇・左隻6扇)。描いた最後に捺すのが普通だが、これは等伯が亡くなった後に長谷川派の誰かが捺したのであろう。等伯自身が捺した印影ではない。同形のいわゆる基準印とは異なる。
(6)紙
下描き用に多く使われる粗いこうぞ紙。完成のために使う紙ではないといわれている。
(7)継ぎ目
1枚(1扇)を上から下へ、紙を5枚から6枚継ぎ合わせてあるが、ところどころ段差ができている。右隻の第1、2扇と第3〜6扇の間。左隻では第1〜3扇と第4〜6扇の間にずれがある。継ぎ目で分けると4つの作品になる。
(8)サイズ
描かれた当時は天地左右のサイズが今より大きかったと推察されている。左隻6扇左端中程に、松の葉と思われるモチーフが見られ、画面はさらに左方に広がることを予想させる(左隻6扇)。
(9)屏風の形式
元々屏風の形式で作られたかどうかが問題点である。紙質が粗く、紙継ぎが不連続であり、障壁画のための下描きの絵を屏風に仕立て直したのではないかなど、屏風ではなかったと多くの研究者は言っている。しかし、黒田氏は初めから屏風だったと考えている。屏風の形を見ると向こう側へ折れた谷折り、手前に折れた山折りに合わせた描き方に表れている。右隻の右端の松は向こう側(谷折り)へ向かっており、谷に向かっているのは色が薄い木。色の濃い木は手前の山折りにある。濃淡と木の角度が屏風の形式に合っており、屏風で絵を立体的に鑑賞してもらう意志がはっきり見て取れる。桃山時代から日本人は屏風で絵を鑑賞する態度があった。屏風は元々中国の実用品、そこに絵を描くようになったのは日本に屏風が入ってきた鎌倉時代から。鎌倉時代の屏風は現在残っていないが、鎌倉時代の絵巻物のなかにはその様子が描かれている。松林図屏風はフラットな状態ではなく、ジグザグに折られた形で鑑賞するのが正しいのだろう。ただ、初めから屏風だったと説明がつかないところもある。
(10)引いて近づく
離れて見ると静かな絵だが、近くで見ると激しい筆使いに驚かされる。
(11)鑑賞するときの光
夜ろうそくで見るのではなく、障子越しの太陽光だろう。
(12)音
静かなる絵といわれている。一つの楽器の音色の美しさを伝える音楽が得意なキース・ジャレット(Keith Jarrett)のアルバム『The Köln Concert』(1975)や『La Scala』(1995)などの、ピアノソロのイメージ。《松林図屏風》など等伯から感じる音は楽器一種類。それに対し狩野派はオーケストラの交響曲がイメージされる。
(13)その他
日本人なら松林を見て自分の体験を重ね合わせて鑑賞できる。おそらく描かれたのは秀吉の特命により祥雲寺(智積院)の障壁画を制作する時期と同じであり、心の安泰した時期に描いたものとは思えない。
(拡大した部分画像は色調整をしていません)
|
スケッチとデジタル画像
日本画の場合、細部を拡大すると画家の力量がわかり、ディテールで全体像を把握するのは可能だ、と黒田氏は次のように続けた。「墨や紙の成分など、肉眼ではわからないデータが出てくる。それが新たな解釈の証明または否定のために使えると思う。作品研究は、まずオリジナル作品を直接見ることだ。よく見るためには作品をスケッチし、自分の目で見たというイメージの記憶が大事である。写真はメモとして補助という程度であったが、写真技術が発達して徐々に逆転してきている。実物を見ると言っても全部を見ているわけではなく、デジタル画像で気付くこともある。デジタル画像の一番のメリットは拡大にある。デジタル画像は研究にとっては最高の武器であり、研究は進歩した。江戸時代の絵画で意味を書き込んだ絵解きを研究している人など、映画『ダ・ヴィンチ・コード』のように絵を解読する研究者もいる。また知識で鑑賞するのならば、デジタル画像で十分だが、本物にしかない迫力や微妙な質感はデジタル画像では再現できないのかもしれない」。
|
職人画家からアーティストへ
等伯は、日本の水墨画を目指すべきだという思いをはっきりと持っていた。「室町時代は中国の水墨画を真似るというレベルだ。桃山時代に入っても水墨画を日本人に理解できるようにする発想はほとんどなかった。日本の水墨画を自立させる発想自体が桃山時代である。当時は黒い鳥を水墨画で描くときは中国に生息している叭々鳥(ハハチョウ)が常識だったが、『等伯画説』(日通上人, 本法寺)を読むと、等伯はこれに疑問を投げかけており、等伯の黒い鳥は日本に生息しているカラスで描かれていた。狩野永徳は叭々鳥を描いている。アカデミックな狩野派との教養の差はあると思うが、等伯は日本で見られるモチーフを見て描くべきだと考えた。松林図屏風で松を選んだのも、日本人は昔から松が好きだし、松林は当時日本の海にはどこでも見られ、正月には必ず出てくる日本人にとって一番親しみのある植物だからだ」。水墨画を日本独自の表現として自立させようとした等伯は、個性的な表現を考案し、職人的な絵描きではなく、自立したアーティストとなっていったと黒田氏は言う。「等伯が牧谿(もっけい)の《瀟湘八景(しょうしょうはっけい)》を見たという記述などから、等伯の師は牧谿だと思われる。牧谿との出会いは大徳寺。天正17年(1589)頃に牧谿の《観音遠鶴図》(大徳寺)を見ている。画家が見たというのは模写をすることだ。等伯は、絶対かなわないと完全に打ちのめされたのだろう。牧谿の絵を見て当時多くの画家が動けなくなってしまったとすれば、等伯は残された可能性を模写から見出していったのではないか。模写というのは自分の実力の限界を知ること、同時に自分の可能性を模索するために大事なこと。等伯はそれに気づいた。牧谿が、猿や鶴を哲学的なロジックとして描いても、その意味が理解できなかった等伯は、猿や鶴の肌のぬくもり、情感を表現しようと思ったのだろう。その後の等伯の作品を追ってみると、鶴や虎のカップル、猿、カラスなどを描くようになっている。等伯は自分でもこれなら描けるし、日本人なら分かってもらえると思ったのではないか。その延長線上にこの松林図屏風が出てくる」。72歳で亡くなった長谷川等伯が、注目されてきたのは近年である。《松林図屏風》が描かれて300年間は所在不明であったのだ。この作品が発見されてからまだ100年も経っていない。
|
余白の風景
《松林図屏風》が描かれた背景を黒田氏は「等伯の息子の久蔵が26歳で亡くなったことの影響もあるが、考えられるのは桃山時代の、何でもありの時代的特徴のなかで、等伯は不安定であったのだろう。祥雲寺(智積院)の仕事が無事に終わり、心の平穏があって描かれたと今まではいわれていたが、当時祥雲寺障壁画制作に携わっていた等伯自身の、自己の居場所を探した結果の原風景を映し出していると思う。絶大な勢力を誇っていた狩野派に対して、一匹狼の等伯は芸術生活が一時的に成功したとしても不安定であった。等伯は現在の石川県の七尾から出てきて上手にサクセスストーリーを歩んでいる。千利休と知り合い、豊臣秀吉の庇護を受けるようになっていった。等伯にとって秀吉が唯一の拠り所だった。秀吉の子供が亡くなり、三回忌の法要のため祥雲寺の仕事を引き受け絶頂だったろう。その頃、秀吉によって千利休は自刃。等伯もいつそうなるかわからない不安、また将来の不安もあったろう。祥雲寺の仕事はそういうプレシャーのなか、命がけで描いたはずである。一番のプレッシャーは締め切りだったと思う。ほぼ2年間の制作期間に96枚の絵を描くことになっていた。文禄二(1593)年8月の祥雲寺障壁画完成前の6月、息子の久蔵が亡くなってしまう。大成功は収めたが、等伯は秀吉の仕事をしている自分は本当の自分なのか、自分探しをしたのではないか。画家は絵を描いて自己を確認する。おそらく何の準備もせずに、もがくような気持ちのなかで故郷能登で見かける松林の原風景を一気呵成に描いたのではないか。その証拠に墨が飛び散っていたり、墨が垂れて下に溜まっている。たぶん屏風を立てかけて一気に六曲一双を描いたのだろう。そして、《松林図屏風》の制作年代は確定していないが、私は祥雲寺完成直前の文禄二年7月を制作年月と見ている」。黒田氏は画題の解釈と構図の斬新さを等伯の特質と語った。ますます等伯への疑問は多くなってきていると言うが、今後新しい等伯の全体像を我々に見せてくれるはずだ。墨一色で描かれた松と、描かれていない余白を同時に見せるこの感覚は、400年経った今も新鮮に伝わってくる。
|
【画像製作レポート】
個人でできるデジタルアーカイブの活用を試みた。東京国立博物館 のホームページには、40数点の長谷川等伯《松林図屏風》のデジタル画像がある。そのなかには全体像の見える6曲1双の一発撮り画像はなく、2枚(2扇)ずつ分割して撮影したものが多い。そのため作品全体を見ようとすれば画像を合成しなければならない。また、色調整も必要であった。一般的な家庭にあるPCとスキャナでデジタル画像の加工にトライしてみた。東京国立博物館が所蔵している画像を販売する(株)DNPアーカイブ・コムへ画像番号C0060804〜C0060809を依頼し、作品番号 TNM000683・TNM000684・TNM000685とTNM000688・TNM000689・TNM000610の6点を入手した。ホームページよりインターネット経由で画像をダウンロード、簡単にデジタル画像を入手することができた。依頼した画像番号と送られてきた作品番号が異なっていたので、はたして同一のものか少々不安にはなった。使用目的に応じてTIFFとJPEGの2通りから選べる。今回はWebサイトに使うためJPEG画像を利用した。右隻と左隻、それぞれ3画像ずつ分割されているので、まずは画像の色調整と画像合成。事前にカラーガイド・グレースケール(以下、カラーガイド。Kodak Color Separation Guide and Gray Scale Q-13)をスキャニング(brother MyMiO MFC-620CLN,8bit,600dpi)し、モニターに表示しておく。iMacの17インチモニターはD65に色温度調整、ColorSyncでsRGBプロファイルを確認、カラーマネジメントに備える。右隻と左隻の画像は色の違いがあるが、極力モニターに表示してあるカラーガイドと、画像に写っているカラーガイドの色調を合わせていく。微妙な色を合わせるために2日ほど時間をかけた。その後、色合わせを済ませた6点に分割された作品画像を合成していく。画像を合わせてみると色の違いだけでなく、作品が少しゆがんで写っていることもあり、ジャストフィットしない。その形の誤差をフォトショップのコピースタンプツールなどを使い修正した。この時なるべく作品に手を入れないよう修正を最小限にする。今回は屏風の2枚(2扇)を3画像つないで一隻の屏風を製作した。当初カラーガイドに忠実に作業をしていたが、出来上がった右隻と左隻を並べて比較すると、金壁画のように発光した屏風絵に見えたため、最後は画集と記憶をたどり色調整した。実物の作品が身近にない場合、記憶にある作品の色や印刷物をたよりに作ることになる。カラーマネジメントの知識と技術が必要だ。右隻と左隻の色差は元々の写真の色の違いでもある。仕上がった画像は実物ともフィルム写真とも異なる、自立した新たなイメージであった。実物を見ている人が画像を見ればその違いを補完して見ることもできるが、見ていない人は実物と画像の差を感じてしまうかもしれない。公共財である美術館の収蔵品資料の活用へ向けて、画像の価値について再認識し、画像を評価する基準というものが必要か、検討する余地はありそうだ。
※《松林図屏風》の画像は、東京国立博物館の所蔵作品掲載期間終了のため削除し、2024年10月31日より、ColBaseの画像に差し替えました。そのため画像の拡大はできません。
|
■黒田泰三(くろだ・たいぞう)
出光美術館学芸課長。日本近世絵画史専門。1954年福岡県生まれ。1978年九州大学文学部哲学科美学美術史専攻卒業。同年出光美術館学芸員となり、現在に至る。近年の主な研究テーマは、長谷川等伯・狩野光信・狩野長信の3人の関連や「伴大納言絵巻」など。主な著書は、『新編名宝日本の美術(伴大納言絵巻)』(1991, 小学館)、『新潮日本美術文庫(長谷川等伯)』(1997, 新潮社)、『狩野光信の時代』(2007, 中央公論美術出版)など。
■長谷川等伯(はせがわ・とうはく)
桃山時代の画家。1539年〜1610年。能登国(石川県)七尾生まれ。長谷川派の祖。当初「信春」を名乗り、仏画などを描いた。30歳を過ぎて上洛、当時の主流であった狩野派に対抗し、独自の画風を確立。千利休と親交を持つ。一門による祥雲寺障壁画(智積院蔵)は金碧画の代表作。松林図屏風(東京国立博物館蔵)により日本における水墨画を自立させた。
■松林図屏風(しょうりんずびょうぶ)デジタル画像のデータ
タイトル:松林図屏風 右隻 左隻。作者:影山幸一 。主題:日本の絵画。内容記述:長谷川等伯, 桃山時代制作, 6曲1双(各縦156.8cm×横356.0cm), 紙本墨画, 国宝。公開者:(株)DNPアーカイブ・コム。寄与者:東京国立博物館。日付:2008.6.4。資源タイプ:イメージ。フォーマット:JPEG, 各12.3MB。資源識別子:C0060804〜C0060809。情報源:─。言語:─。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:http://www.dnparchives.com/
■参考文献
橋本綾子 編『日本の名画──3長谷川等伯』1974.3.20, 講談社
『日本美術館』1997.11.20, 小学館
橋本治「ひらがな日本美術史【連載】その五十……ジャズが聞こえるもの長谷川等伯筆『松林図屏風』」『芸術新潮』第49巻第5号 通巻581号,p.129-p.135, 1998.5.1, 新潮社
黒田泰三「松林図屏風の制作年代に関する一考察」『出光美術館研究紀要』第7号pp.45-65, 2001.12.31, 出光美術館
黒田泰三「【特集】長谷川等伯の画業 松林図屏風小考──長谷川等伯の芸術と軌跡」『淡交』No.683 第56巻第2号, pp.35-40, 2002.2.1, 淡交社
図録『開館35周年記念 長谷川等伯 国宝 松林図屏風展』2002.2.26, 出光美術館
佐藤康宏編『講座日本美術史 第1巻 物から言葉へ』2005.4.26, 東京大学出版会
黒田泰三「第二節 松林図屏風」『狩野光信の時代』pp.115-131, 2007.9.25, 中央公論美術出版
■関連記事
美術家のための公益著作権管理団体──(社)日本美術家連盟事務局長「梅 憲男」
|
|
|
| 2008年6月 |
 |
| [ かげやま こういち ] |
 |
|
 |
|
 |
| ページTOP|artscapeTOP |
 |
 |

