| 木藤純子展/大西康明展/池田朗子展 |
 |
| 大阪/国立国際美術館 中井康之 |
 |
6月、7月、8月と各月にひとつずつ記憶に残る個展を見た。いや、より正確に記すならば、それぞれの作家の勝れて感覚的な造型空間の中に身体を浸透させるような体験を重ねることになった、とでも言えばよいのだろうか。
|
|
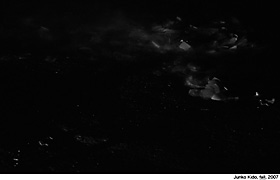 |
|
木藤純子、作家によるイメージ図版 |
 |
そのような実感をもたらしたのは、このレポートが公開される時期にはまだ開催している木藤純子による東京での個展である。作品を見る以前に、強烈な日射しを投げかける街角から薄暗いビル空間に吸い込まれるように入り込み、さらにその画廊空間内に設けられた暗闇に身を浸すような舞台設定だけでも、また、そのようなシークエンス空間を体験してきただけでも、鑑賞する者の意識というのは異次元にでも貫入するような認識を持つものであろう。例えば、少年期に暗い洞穴へと(その多くは防空壕であったりするのだが)恐怖心を抱きながらもその暗闇に誘われるように潜り込んでいったような記憶を呼び起こすものであり、あるいは古代の人々が暗黒の洞窟壁面に恐らくは厳粛な精神状態で躍動的な動物を描いた記憶が遺伝子に刻み込まれたようなものであろう。木藤の個展会場に至るまでに、そのような舞台装置がはからずも用意されていたのである。実際、展示空間の入口に設けられた暗幕をくぐると、その内部はほとんど暗転した状態であった。暗闇に目が慣れるまで作品が見えない、最初はそのような仕掛けを持つ作品のひとつかと思った。しかし、しばらくすると、壁際や室内に置かれたいくつかのベンチの下などに設置された僅かなペンライトほどの照度を持った明かりがゆっくりと点灯し、床に紙吹雪に用いられるような紙片が一面に敷き詰められていることに気付くのである。そうしているうちに、一陣の風が吹き、とでも形容できるように床に設置されたライト付近に併置された送風機によって不意に風が吹き始め、その風に舞う紙片の微かな影が対面の壁に幽かに映し出されるのである。この段階に至り、ようやく、その作品から作家の息づかいを感じたのである。しばらくその空間に身を預けるかのように、設置されたベンチに腰を掛けていると、極めて抑制された光と風の微視的な変化が、まるでロバート・ライマンの絵画空間を体感しているような、ある研ぎ澄まされた精神状態になっている自分に気付かされるのである。
|
| 異空間へ入り込んでいくような感覚を、じつは2カ月ほど前にも体験していた。大阪駅から歩いて15分もかからない、戦後あたりからまったく風景が変わっていないのではないかと錯覚するような地域に設けられた画廊PANTALOONでの個展である。そのレトロな場所を、ちょうど2年程前にも、このコーナーでレポートしたことがある(学芸員レポート05年8月号)。時間が止まったかのような周辺の雰囲気はそのままであったが、PANTALOON自体は隣の住宅にまで拡大して見事な空間を生み出していた。2年振りにそこへ足を運ばせるきっかけとなったのは大西康明の個展が開催されているという情報を得たからである。彼の作品は、2005年12月に東京のINAXギャラリーで見る機会があった。その時はキネティック・アートに有機的な要素を強化したようなところに興味を持った。それから1年余経過してから、岡本太郎記念美術館で初めて大賞を受賞した作家として、再び大西の蠢く光による立体作品と再会していたのである。であるから正直な話、その手法をどのように展開しているのか、という程度の期待度であったのである。しかしながら、先にも述べたようにPANTALOONは拡大し、天上の開口部から光が降り注ぐようなあたらしい画廊空間を生み出していたのである。この時、私の意識は一瞬ホワイト・アウトした。薄暗闇に浮かぶ光をイメージしていただけに、昼行灯よろしく、天上から降り注ぐ光に対して床に設置された蛍光灯がぼーっと光り、それを半透明のシートによって見え隠れするような装置を眼にした時には、思考が停止したのである。落ち着いてその作品を観察すると、その巨大なシートはヘリウムガスの詰まった風船によって空中に浮かび、その下辺は鉄道模型につながれて半円を描きながら展示空間をぐるぐると回っているのである。大西はその作品の前で懸命に調整をしていた。システムとしては未完成のようであった。しかし、大西によれば、今回の個展の話があったときに、この新しい展示空間を見てから作品のアイデアを考えたのだという。確かに、2階の屋根裏まで吹き抜けとなったその空間の解放感は、とらえどころのない半透明のシートが緩やかに回転して生み出される柔らかな光の乱反射によって異空間に変質させられていたのである。であるから、私が先に意識が飛んだというのは、予期していた作品が見られなかったことばかりでなく、大西の作品によって変容させられた空間に紛れ込んだような感覚を無意識に感じていた査証であったとも言えるのである。 |
|
|
|
異質な空間ということではなく、現実的な空間の延長線上に、ポカリと口を開けて異次元が待っているような、というとまるでルイス・キャロルが著した「不思議の国のアリス」のようなお伽噺になってしまうが、われわれの日常空間に、最低限の加工を施すことによって異空間を生み出す作品を、大阪のギャラリーで見たのは7月のことであった。その作家、池田朗子は、同じ画廊でミニチュアの飛行機を電車や飛行機などのガラス窓に貼り付けて、窓景が動くことによってミニチュアの飛行機が移動しているように見える光景をビデオで撮影した作品によって知っていた。今回は映像作品では無い、ということをその画廊主に以前から聞いていたが、その作品をスティールにしたようなものではないだろうな、という程度の予見を抱いていたに過ぎなかった。その画廊の扉を開けると、作業机に雑誌が並べられ、その横に観葉植物が置かれているような、ありふれた光景が待っていた。しかし、その無造作に置かれた雑誌に僅かな仕掛けがほどこしてあった。雑誌の中にある写真の人物が切り立てられているのである。それだけのことに過ぎないのだが、その作業机には主人は存在しないために、その机の各所に開かれた雑誌から立ち上がる、無数の小さな人型を見る観察者自身は、まるでガリバーが小人の国に迷い込んだかのような錯覚に陥るかのような不思議な感覚に囚われる事になるのである。後から知った事であるが、池田はこの手法を2001年頃から始めていたようである。しかし今回の個展で用意された装置は、日常空間に置かれた雑誌というファクトと、そこから立ち上がってくるフィクショナルな世界が、見る者の意識の中で自然に往還するようになっていたところに、ヴィデオ作品で展開されていたフィクショナルな世界とキッチュなファクトの交錯する世界が反映されていたように感じた。 |
|
|

