バックナンバー
2024年01月15日号のバックナンバー
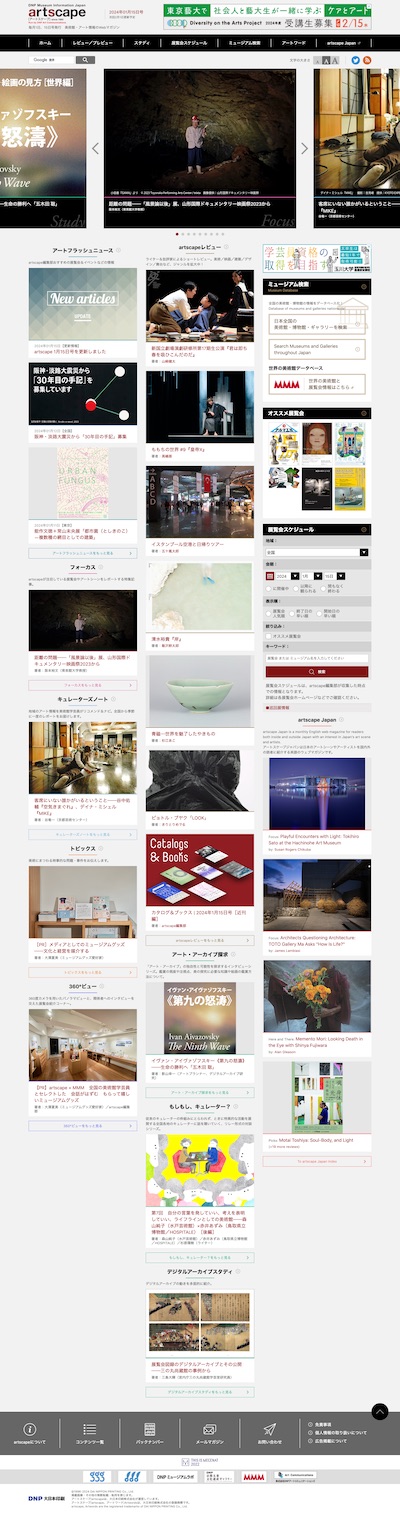
フォーカス
距離の問題──「風景論以後」展、山形国際ドキュメンタリー映画祭2023から
[2024年01月15日号(阪本裕文)]
近年の国際映画祭のストリーミング配信を見続けていると、ある風景や場所に付随する社会性・歴史性を主題とした映画に少なからず出会う。このような映画は、実験的なドキュメンタリーや実験映画の文脈に位置付けられていることが多い。それらは何の変哲もないある場所を対象としながら、カメラワークや演出、切り詰められたモノローグや字幕を利用することで、その場所のイメージに別のレイヤーを付与し、意味を分析し、操作する──それによって観客の意識において、対象とされている場所が異化される。このようなアプローチは、過去に何人ものドキュメンタリー映画や実験映画の作家によって試みられてきたものであるが、それはいまも広がりをもって展開されているということだろう(代表的な映画として、ジェームズ・ベニングの『ランドスケープ・スーサイド』[1986]や『ステンプル・パス』[2012]を挙げておこう)。
2023年秋に筆者が観た二つの催しである「風景論以後」展(東京都写真美術館、2023年8月11日~11月5日)と山形国際ドキュメンタリー映画祭2023(山形市中央公民館/山形市民会館/フォーラム山形ほか、2023年10月5日~12日)でも、そのような作品にいくつか出会った。ここではそれら作品を通して、風景や場所についての映像作品について考えてみたい。
キュレーターズノート
客席にいない誰かがいるということ──谷中佑輔『空気きまぐれ』、デイナ・ミシェル『MIKE』
[2024年01月15日号(谷竜一)]
「本公演は、『リラックス・パフォーマンス』です。客席に長時間じっと座っていることが難しいお客様(例えば、自閉症、トゥレット症候群、学習障害や慢性的な痛みなどがある方)を歓迎します」
これは、Co-program カテゴリーA採択企画である、谷中佑輔『空気きまぐれ』に関する公演に際した、アクセシビリティについての記載の一部である。
本公演はアクセシビリティについての思考を促すものであり、またそれは多様な観客や、観客以外の存在への思考をも促す公演だったといえるだろう。
アート・アーカイブ探求
イヴァン・アイヴァゾフスキー《第九の怒濤》──生命の勝利へ「五木田 聡」
もしもし、キュレーター?
第8回 美術を辞めて日常に戻る人の背中が、もっと見たくなってしまって──奥脇嵩大(青森県立美術館)×森山純子(水戸芸術館)[前編]
[2024年01月15日号(奥脇嵩大/森山純子/杉原環樹)]
学校と連携して教育普及事業を展開したり、地域と美術館をつないだり──従来の「学芸員」の枠組みにとらわれずユニークな活動を展開する全国各地のキュレーターにスポットをあて、リレー形式で話を聴きつないでいく対談連載「もしもし、キュレーター?」。今回と次回は、水戸芸術館で長らく教育普及事業に携わる森山純子さんが、青森県立美術館の奥脇嵩大さんを訪ねます。
美術と農業の接続を試みる「アグロス・アートプロジェクト2017-18 明日の収穫」や、青森県内の美術館から離れたエリアでの制作と展示を通した「美術館堆肥化計画」など、人の生活や営みの目線からさまざまな独自の企画を立ち上げてきた奥脇さん。美術館が人々の「肥やし」として長く続いていくもっと自由なあり方を想像し、そのための土壌を耕していく様子を、2023年の「堆肥化計画」開催地でもあった本州最北端・下北半島をはじめ青森県の各地で探ってきました。(artscape編集部)
[取材・構成:杉原環樹/イラスト:三好愛]
※対談の後編(第9回)「美術館を出て考える、人が「ここ」で生きている意味」はこちら。
※「もしもし、キュレーター?」のバックナンバーはこちら。






![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)