キュレーターズノート
非力さを再考する
田中みゆき(キュレーター)
2020年01月15日号
対象美術館
アート&カルチャー情報サイト「Hyperallergic」が毎年行なっている「The 20 Most Powerless People in the Art World(アート界で最も非力な20人)」の2019年版★1に「障害のあるアーティストとアートファン」が選出された。このリストは、20人の存在を通して限られた既得権益が支配するアート界の構造を批判するものだが、ある意味、障害のある人たちの存在がアート界に関わるものとしてようやく認知され始めたことを表しているとも言えるだろう。障害のある人の表現を展示する、あるいは障害のある人と共に作品を鑑賞することにおいて、ハード面とソフト面の両方において課題があるとわたしは思う。いずれも従来の美術館や劇場という制度、そして作品における作家や鑑賞者の位置付けに挑戦するものである。しかし、障害の問題に限らず、人間を世界の中心に据える思考や行動を再考せざるをえない出来事が現実世界では起こっている。それに対し美術館や劇場はどう反応できるのだろうか。

IF THE SNAKE, Okayama Art Summit, 2019
Fernando Ortega Untitled, 2003
[Courtesy of the artist and kurimanzutto, Photo: Ola Rindal]
「世界」には誰が含まれるのか
昨年夏にテート・モダンで開催されたオラファー・エリアソンの展覧会「In real life」は、多くの展示物が障害のある人にとって体験できない/しづらいものになっていたことで、当事者から批判が寄せられ物議を醸した★2。とりわけ、作品のひとつである『Spiral View』において、入り口に階段が数段設けられていたにも関わらずスロープが用意されていなかったこと、尋ねられた監視員がそのことを「キュレーターの選択」と答えたことに批判が集中した。当事者であるCiara O’Connorのツィート★3にオラファー本人も返答し、テートとの協議が行なわれたようだが、「車椅子ユーザーに安全が確保できない」との理由で要望が叶うことはなかった。O’Connorは展覧会に寄せられたオラファーのテキストについて言及している。そこにはこう書かれていた。「美術館において、わたしたちはまるで体を持たないかのように動く──あるいは少なくともアートを見る際に身体的な動きを共に(作品を)作り出すための要素として参照しない」 。それに対しO'Connorは憤慨する。「過剰に知的に見せ大きな話をしているけれど、自分たちが作り、キュレーションし、展示するのは、限られた身体に対してのみだという事実を曖昧にしているだけ」と。
このニュースは少なからずわたしを落胆させた。自然環境や社会に対し、アートが果たし得る役割を模索し、世界中の送電線網のないエリアに持続可能なエネルギーを届ける「Little Sun」のような活動を行なってきたオラファーのようなアーティストでも、皮肉にも展覧会のタイトルにある「現実世界」の人間の多様性には目配せしていなかったことに。彼が展望する「世界」には障害のある人は含まれていなかったのだろうかと思わざるを得ないし、少なくとも美術館側の対応は、彼らが想定した展覧会の世界に彼らは含まれていなかったことを示してしまっている。
作品の環世界を美術館に持ち込めるか
ソフト面の課題として、障害のある人の作品展示を見る時にとりわけ思い知らされるのは、「現場はここではないのだ」ということだ。障害のある人の表現は、作品だけを切り取って美術館に展示されることを目的としてつくられていない場合がかなり多い。そして、その創作の現場には、施設で働く職員や他の施設利用者、いつものアトリエや使う道具といったさまざまな要素が揃って、作者はそれらに影響を受けながら制作を行なっている。
生物学者のユクスキュルは、「生物がそれぞれの感覚や身体を通して生きている世界」★4を「環世界(Umwelt)」と名付けた。例えばマダニは視覚や聴覚がない代わりに、嗅覚、触覚、温度感覚に優れ、木の上から下を通りかかる哺乳類が出す匂いを感じて、木から獲物をめがけて落ちる。紫外線が見えるミツバチや蝶、嗅覚に優れた犬、すべて異なる環世界を持っている。人間は一様に同じような機能を持っていると信じられてきたが、それは人間にも当てはめられ、同じ視覚障害でも見え方が異なるといったことは、人間一人ひとりも異なる環世界に生きることを教えている。
障害のある人の表現は、彼らの環世界の表出であり、それが美術館という制度のなかに置かれた時、そこに含まれたさまざまな作用、つまりそれぞれの環世界から切り離された「作品」はそれまでとまったく異なる佇まいを見せる。その問題への対応として作者のアトリエを再現したり、そこで本人に制作してもらったりという試みも見られるが、それは環世界とは異なるため、作品だけを切り取ることとほぼ変わらない。作品至上主義のなかでは捉えきれない環世界こそに魅力的な表現が存在し、障害の有無を問わず鑑賞者にそれを感受してもらうには、単に制作や展示のプロセスを扱うことの難しさ以上の障壁がある。そこには、普段美術館で完成された作品で判断する鑑賞の態度をなかなか脱ぎ捨てられない鑑賞する側の問題もあるだろう。
また、障害のある人と作品を鑑賞する際は、それぞれの障害に応じて伝え方を変えるだけでなく、それが本来の鑑賞体験を阻害していないかを考える必要がある。障害があるからといって説明しすぎてしまい、思い思いに想像する楽しみを奪ってしまうという失敗はわたしも経験してきた。どう伝えれば鑑賞という行為や現象が成立するのかを考えるのは、本来障害の有無問わず考えられるべきことだが、障害のある人と共にすると特にそれが顕著にわかる。
従来の絶対的な存在としての作者ありきで作品を見るのではなく、例えば、障害を含めた環世界のなかでそれぞれが作品を解釈していく「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」や「美術と手話プロジェクト」のような取り組みは健常者の鑑賞にとっても有益なことがわかっているし、他の障害の場合、さらには健常者同士でもそれぞれの感覚の違いに着目することでどういった鑑賞体験をつくることができるかといったことはまだまだ探求する余地がある領域だろう。それが「(通常の鑑賞が難しい)障害者のため」という免罪符のもとに行なわれるものと見なすのは惜しい。美術館が作品を通してだけでなく、鑑賞者がそれぞれ持っている環世界の多様さに触れたり、それを通して鑑賞する自由さを予め許容する場になっていくことは、社会における美術館の役割として重要なものだと思う。
人間と非人間の作用を考える潮流
脳性麻痺の当事者であり東京大学准教授の熊谷晋一郎が「自立は、依存先を増やすこと」★5と言うように、人間は誰しも自分の体の延長として外在化されたモノに依存している。障害のある人の場合は特に、自分が備えていない機能を道具や盲導犬、介助者などで代替し、時に健常者には真似できないほど巧みに使いこなし生活している。そんな彼らと接していると、人間と生き物、モノとの境界が曖昧なものに感じられてくる。
環世界という概念、そして、人間と人間以外の生き物やモノとの関係性について考えることは、ひとりの人間が普段当たり前に感じている世界がひとつの可能性でしかなく、意思の表現の仕方は違えども、あらゆる人間、生き物、モノがそれぞれに働きかけて世界を構築していると考えることにつながる。そのことは、表現を鑑賞するうえでも、行為する主体だけでなくさまざまな作用者の存在を考えるきっかけを与えてくれる。
近年盛んな動きを見せる脱人間中心主義を扱う表現においても、人間を頂点としたヒエラルキーにおいて人間以外の存在を擬人化やアニミズム、見立ての対象として捉えるのではなく、人間の尺度を超えた時間や自然環境のなかで人間の存在を相対的に見直し、行為の主体と客体の関係性を再構築しようとする姿勢が伺える。

チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』2019 ロームシアター京都
[© ︎Yuki Moriya]
観客に向けられていない演劇を目指した公演『消しゴム山』の制作途中のインタビューで、岡田利規はレストランのテラス席でご飯を食べていた際のことを「奇跡的な瞬間」として挙げている。岡田の周りで、ハエがテーブルの周りを飛び回ったり、テーブルの面にとまったりしていた。その時なぜか岡田はハエが自分が食事しているスペースに侵入してきたとは思わず、「自分にとってのその場所の定義と、ハエにとっての定義は違うということを当たり前に受け入れられていた」と話している★6。そこには、岡田という人間とハエがそれぞれの環世界のなかでテラス席を共有する情景が見える。
しかし、その情景を舞台上で起こすにあたり、従来の劇場という人間中心に構築された制度的空間で上演するという困難を『消しゴム山』という演劇作品は予め備えていた。そのなかで、普段演劇公演ではあまり遭遇しない周波数や音圧の用途を持たない音を存在させたり、モノを小道具としてではなく舞台上に俳優と併置させたりという試みが図られた。意思疎通の可能性を暗示する有機的な性質が限りなく排除されたモノ(人工物)たちは、上演の過程で人間との関係性のなかで人間と等価に扱われたり、人間よりも存在感を増したり、人間を置き去りにしたりもする。それらは、舞台上に人間が普段認識しているのとは別のレイヤーでモノの世界や時間が同時に存在していることを示すだけでなく、人間とともに世界をつくりあげる役割を負っていた。それは、テラス席での人間とハエの関係にどれくらい近づけただろうか。『消しゴム山』は、制度的設えの中で、どれだけ従来の主従関係を超えた複雑で可塑的な形態として人間やモノを読み取ることができるかという視点の変容を迫る試みであり、劇場という空間やそれに規定されてきた観客の態度に対する挑戦であったと言えるだろう。
また、展覧会を「独立した一つの生命体」★7とし、作品同士が作用しあう生態系を提示した『岡山芸術交流2019』が同時期に開催されたのは興味深い。それは、異なる環世界をもとにつくられた作品が鑑賞者を介してゆるやかに繋がっていき、作品と作品の世界が融解していくさまがフィクションとして紡がれていくかのような、文学作品のような展覧会という印象を受けた。カタログに書かれたピエール・ユイグによるテキストが作品解説ではなくSF小説のような体裁をとっていたのも象徴的だった。
ユイグもインタビューで、作品同士の関係において「継続性」あるいは「つながっていくこと」がひとつのキーになっていると話し、「それぞれの作品にはそれぞれの作品が持っている自然な状態がある」★8と指摘する。それは、作品が持つ環世界とも言える。
多くの作品は屋外や美術館ではない旧小学校校舎や体育館などに設置され、制度的空間からの解放は物語が立ち上がることに少なからず貢献しているが、それよりも多くの作品に共通していたのは、作品で扱われていたマテリアルが作家によって制御された客体あるいは作家の思考を投影する対象としてではなく、自ら意思を持った主体として活動しているように映ったことではないだろうか。それらの活動は、鑑賞者の視点がさまざまに変容し、作品間を浮遊し、独自の物語を構築することを支えている。そこにあったのは、鑑賞の対象として据えられた完結したオブジェクトではなく、同じ場を共有し、流動的に鑑賞に作用してくる“ハエ”に近い意味合いを持っていたと思う。

IF THE SNAKE, Okayama Art Summit, 2019
John Gerrard X. laevis (Spacelab), 2017
[Courtesy of the artist, Thomas Dane Gallery and Simon Preston Gallery]
Pamela Rosenkranz Skin Pool (Oromom), 2019
[Courtesy of the artist, Karma International, Miguel Abreu Gallery and Sprüth Magers,
Photo: Ola Rindal]
さまざまな作用者がつくりあげる鑑賞の場
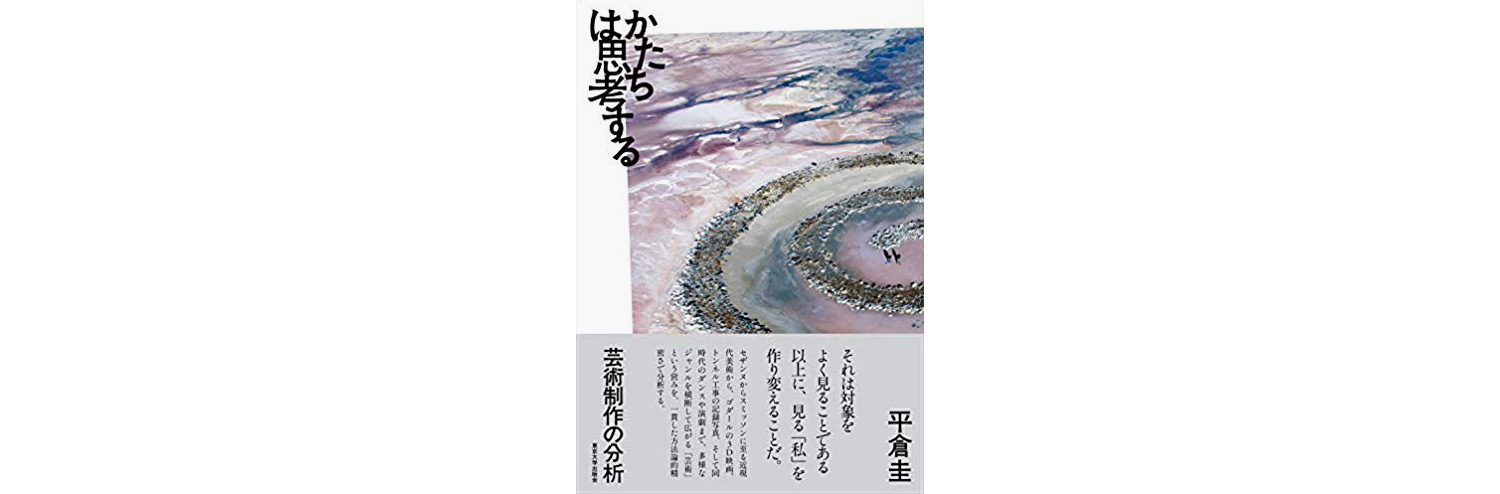
芸術を制作するうえでの人間と非人間の生態系を捉えた平倉圭による『かたちは思考する──芸術制作の分析』(東京大学出版会、2019)は、作用者の多層性をとらえる示唆的な論考集であり、読み進めるうちに読者の身体が形象を結ぶ過程に巻き込まれ変容せざるをえないという意味で、他にない読書体験をもたらしてくれる。平倉はダナ・ハラウェイの言葉に倣い、形象を「多数の人間的・非人間的作用が絡まりあう、心的─物的な記号過程の結び目をなす形★9」と捉え、その複合的な思考過程を、人間ではなく、形象を中心として論じている。例えばロバート・スミッソンの《スパイラル・ジェッティ》について書かれた第7章では、「人の心が物へと砕けながら物とともにおこなう記号作用★10」として《スパイラル・ジェッティ》が「思考」する過程を分析する。その後詳説される同名の映画制作の過程を通して、複数の異なる螺旋の間で「異鳴的うなり」をあげて主─客の分離が破壊される過程が描かれる。それにより読者は、視─聴覚および観念─物体を横断する複数の「うなり」を体感しながら小説を読み進めるような主体的な没入感をもってその過程に身を浸していく。(その分析を展開する手法で障害のある人の表現について書かれたものを読んでみたいと思った)
これらの作品は、従来の価値観や構造のなかで捉えられてきた非力さを捉え直し、人間も人間以外の存在も作用者と捉え、新たな関係を結び直そうと模索している。それを作家性に帰結させるのではなく、鑑賞における新たな対話につなげることはできないだろうか。また、表現を表現たらしめている制作過程や作用者の諸要素を詳らかに見つめ直し鑑賞することは、ソーシャリー・エンゲージド・アートや参加型アートとは異なるスタンスで鑑賞者が作品制作に共に関わる主体となることである。それは展示室や劇場を出た時に、彼らが自ら思考し、社会に関わっていく未来を開くことにもつながるのではないだろうか。そこで重要なのは、人間総体としての客観的な議論ではなく、一人ひとりが自分の世界の中でその表現を位置付け、主観的に体感し、物語や対話を紡ぎあうことを受容する態度を醸成することではないか。そのためには、その過程により多様な人々を巻き込める環境をハード面およびソフト面から整えることは欠かせないことであり、そのことこそが美術館や劇場という場を現実世界において豊かにすると信じている。
★1──The 20 Most Powerless People in the Art World: 2019 Edition https://hyperallergic.com/535484/powerless-list-2019/
★2──Wheelchair User Criticizes Tate Modern for Inaccessibility Issues at Olafur Eliasson Exhibition https://hyperallergic.com/513173/wheelchair-user-criticizes-tate-modern-for-at-olafur-eliasson/ 原文の「a co-producing element」は、近年のオラファー・エリアソンの発言から、「(作品を)共に作り出す要素」と訳した。
参照:https://www.dezeen.com/2019/06/06/olafur-eliasson-ikea-sammanlankad-solar-panels-design/
★3──Ciara O’Connorの当該スレッド https://twitter.com/cioconnor/status/1159895481364955137
ハッシュタグ#askSOEには、O’Connorのツィートに対するさまざまな反響が寄せられている。https://twitter.com/hashtag/AskSOE?src=hash
★4──ヤーコプ・フォン・ユクスキュル/ゲオルク・クリサート『生物から見た世界』(新思索社、1995)
★5──「自立は、依存先を増やすこと 希望は、絶望を分かち合うこと」(TOKYO人権 第56号、2012年11月27日発行)https://www.tokyo-jinken.or.jp/publication/tj_56_interview.html
★6──「『人間中心主義の先にある演劇』というチェルフィッチュの挑戦──岡田利規×篠原雅武 対談」https://wired.jp/2019/10/02/chelfitsch2019/
★7──図録『岡山芸術交流2019 IF THE SNAKE もし蛇が』(美術出版社、2019、52頁)
★8──「なぜ『IF THE SNAKE』なのか? ピエール・ユイグに聞く『岡山芸術交流2019』に込めた意図」https://bijutsutecho.com/magazine/interview/20801
★9──平倉圭『かたちは思考する──芸術制作の分析』(10頁)
★10──平倉圭『かたちは思考する──芸術制作の分析』(175頁)
チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』
[KYOTO EXPERIMENT 2019 参加作品]
会期:2019年10月5日(土)、6日(日)
会場:ロームシアター京都(京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13)
岡山芸術交流2019 IF THE SNAKE もし蛇が
会期:2019年9月27日(金)〜11月24日(日)
会場:旧内山下小学校、岡山県天神山文化プラザ、岡山市立オリエント美術館、岡山城、林原美術館ほか
関連記事
「見えないこと」から「見ること」を再考する──視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ|林建太/中川美枝子/白坂由里:フォーカス(2019年7月15日号)
没入するモノたち──チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』|池田剛介:フォーカス(2019年10月15日号)
岡山芸術交流2019 IF THE SNAKE もし蛇が|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2019年11月15日号)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)