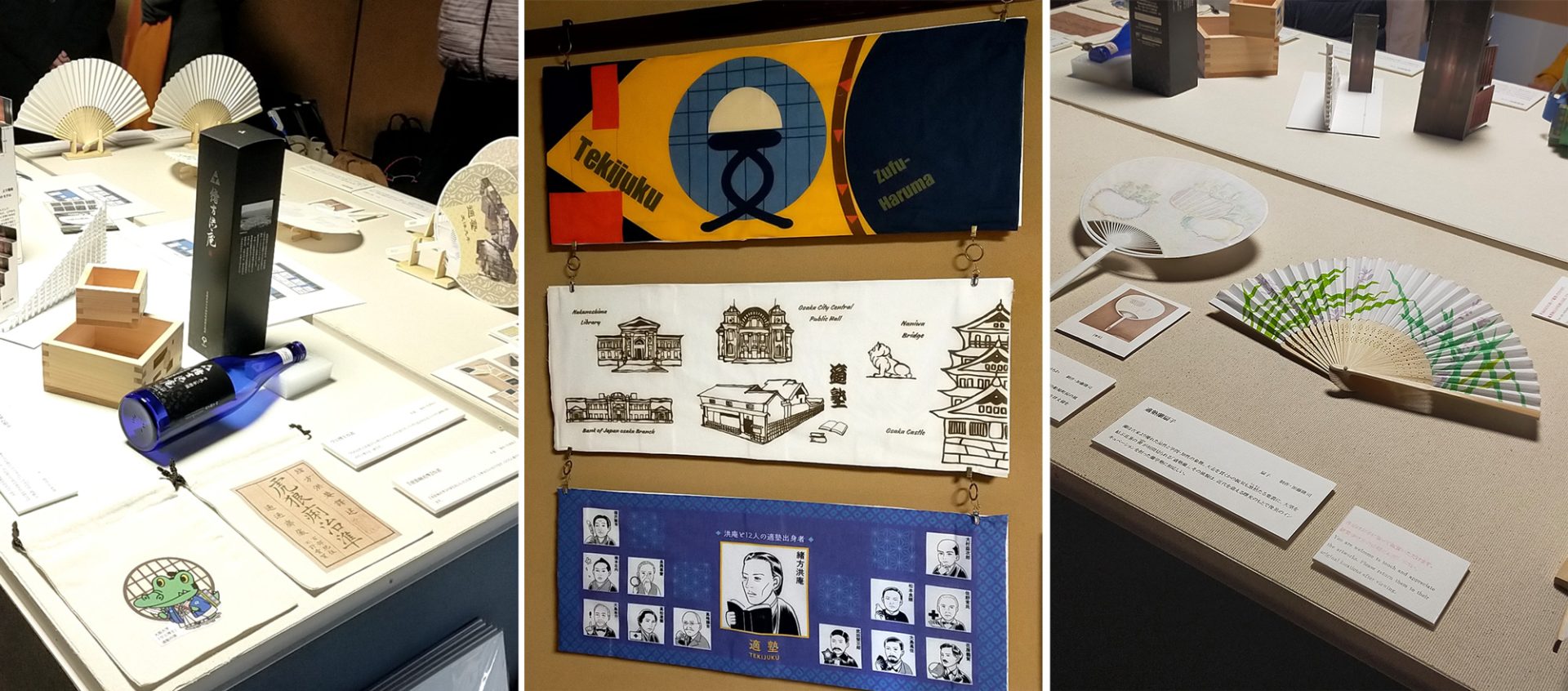マルク・シャガール《私と村》
1911年、キャンバス・油彩、192.1×151.4cm、ニューヨーク近代美術館蔵
Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence
© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2025 E5917
無許可転載・転用を禁止
ステンドグラスをおくる
地上の重力の法則を超えた永遠の愛を主題に、鮮やかな色彩に祝福されているかのように、恋人たちや動物が自由に空を飛ぶ。夢、幻想、神話を描くシャガール。そのシャガール芸術の源泉はどこから来ているのか。その深淵に触れる一文に出会った。
「苦しい自然のなかで黙々と苦しみに耐えて内向的になった民族の信念の強さと、そのゆえに外民族からきらわれ迫害される運命、(略)しかしこの人たちはその運命を打破するために、水との闘いを開始した。『悪地地形』と『最悪地質』の典型、それゆえに『迫害され殺されてきた人種』ユダヤ人、その君たちが『祖国』をもつことができたのは1949年、じつに2000年ぶりに君たちは祖先の土地にかえれたのである。ナチスに殺された600万人の霊は、アウシュビッツその他の焼却炉や行き倒れた街頭から祖国に迎えられた。その霊を慰めるために、石を砕いて一本一本植えられた600万本の杉やオリーブや柏や松は早くものびて、いま緑の色が『荒野』の景観をかえつつある。詩人であり、画家であるシャガールは、この2000年にして初めてつくられた新しい国にステンドグラスの大作をおくった」(並河萬里「シャガール その魂の故郷エルサレムをたずねて」[『現代世界美術全集17』パンフレット、pp.3-4])。
幻滅の多い現実に対して、美は救済となっただろうか。新たなシャガールの姿があるかもしれない。代表作《私と村》(ニューヨーク近代美術館[MoMA]蔵)を見てみたいと思った。カラフルな童話のような絵。ロボットみたいな人と人間みたいな牛が向き合って会話しているのだろうか。白色のグラデーションが静かに光を発して、澄んだ空間を作っている。牛の顔の中に牛が描かれていたり、教会の中からこちらを見ている人がいたり、逆さまになった人や家があり、おとぎ話を図像化したような作品だ。どのような物語なのか、しっかりとは読み取れない。何が描かれているのだろう。ポーラ美術館学芸部課長の今井敬子氏(以下、今井氏)に《私と村》の見方を伺った。
ポーラ美術館には、シャガールの油彩および水彩作品23点と、挿絵本10作品が収蔵されており、《私と村》(1923-24頃、キャンバス・油彩、55.5×46.1cm)という同名の作品がある。MoMA所蔵の本作品が、第一次世界大戦中に行方が知れなくなったとき、シャガールが同じ構図で、ポーラ美術館所蔵作品を再制作した。今井氏はシャガールに関する展覧会「シャガール:私の物語」(2008)、「紙片の宇宙:シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」(2014-15)、「ピカソとシャガール:愛と平和の讃歌」(2017)を担当されてきた。箱根登山電車の終点強羅駅で降り、バスに乗ってポーラ美術館へ向かった。

今井敬子氏
未知のクリエイティブな世界
ポーラ美術館は箱根の自然に溶け込むように建っていた。標高約760メートルという場所は、634メートルの東京スカイツリーより高く、平地より気圧が低いため、非日常的な環境に包まれリラックスできる。
今井氏は、1971年石川県金沢市に生まれた。兄2人の3人兄妹で、伝統工芸の材料を卸売り販売している家で育ったという。小学生の頃は、建築家に憧れた。金沢市出身の谷口吉郎(1904-79)と、息子の吉生(1937-2024)が建てた金沢市立玉川図書館のスペースが好きで、小学校の文集には、建築家という言葉を知らずに設計士になりたいと書いたそうだ。
高校時代にはバルザックやスタンダール、ジャン・コクトーやサン=テグジュペリなど、フランス文学やアメリカのSF、映画といった未知のクリエイティブな世界に関心をもち、1989年上智大学文学部フランス文学科に入学した。大学2年のときに作り手と社会を結ぶ学芸員という仕事のことを知り、フランスで学ぶ準備を始めて卒業後の1993年、ルーヴル美術館附属の国立ルーヴル美術学院へ留学。3年目のときにパリ第4大学ソルボンヌにも入学し、ダブルスクールを始めた。1996年ルーヴル美術学院の学士課程を終えて、パリ第4大学ソルボンヌ考古学美術史学科の修士課程も1997年に修了。帰国後は、金沢で大学の非常勤講師を務め、2001年にポーラ美術館の準備室に就職した。2002年の開館以来、フランス美術をはじめとする20世紀美術を専門に学芸員を務めている。
今井氏とシャガールとの出会いは、ポーラ美術館に入ってからだという。美術館の創設者であり、当時ポーラ化粧品本舗会長でもあった鈴木常司(1930-2000)氏は、シャガールが好きだったそうだ。所蔵品には油彩画と水彩画と版画があり、それらの作品を今井氏が整理・記録し、データを揃えていくなかでシャガールに関する展覧会を企画していった。MoMAの《私と村》は二度見たそうだ。ポーラ美術館所蔵の《私と村》と比べて、「大きさが全然違う。大きくてスケール感があり、描き込みとか、透明感とか、圧倒されるものがあった」と、今井氏は第一印象を述べた。
共同アトリエ「ラ・リュッシュ(蜂の巣)」
マルク・シャガールは、1887年帝政ロシア領のヴィテブスク(現ベラルーシ共和国)に、9人兄弟(弟2人、妹6人)の長男として労働者階級のユダヤ人居住区に生まれた。父イヘズケル・ザハールは鰊(にしん)を加工する工場で働き、母フェイゲ=イテは小さな食料雑貨店を営んでいた。複数の民族と言語文化がひしめき合う当時のヴィテブスクの人口は、65,000人あまり、鉄道駅のある州都であった。ユダヤ人は約40,000人で、シャガールはユダヤ人の言語イディッシュ語を母国語としたが、ヘブライ語にも親しみ、さらにロシア帝政下でロシア語教育を受けて育った。敬虔なユダヤ教徒の両親は、その聖典である旧約聖書の古代ヘブライ人の指導者モーセにちなみ、モイシェ・シャガールと命名した。しかし、パリへ出た青年シャガールは、そのユダヤ人名を名乗らずマルク・シャガールと名を変えた。
1906年シャガールは中等学校を卒業後、写真の修正の仕事に就く。画家になることを志し、肖像画家イェフダ・ペンのアトリエで絵画を学び、修業のため翌年ロシアの首都サンクトペテルブルクへ旅立った。しかし、ユダヤ人であるという理由で滞在許可が得られず、弁護士のゴールドベルグの庇護を受けることになる。サンクトペテルブルクの帝国芸術保護協会附属美術学校に入学することができたシャガールは、成績優秀で奨学金を得ると、ロシア・アヴァンギャルドの代表者と目された画家・舞台美術家のレオン・バクスト(1866-1924)が教鞭を執るスヴァンセヴァ美術学校へ入学し、フランス近代美術と出会う。
1911年24歳、代議士マックス・ヴィナヴェルの援助を得てパリへ留学する。華やかなパリに驚きモンパルナスにアトリエを借りて、美術学校へ通いながら《私と村》を描いた。翌年ヴォージラール屠殺場近くの共同アトリエ「ラ・リュッシュ(蜂の巣)」に移ると、詩人のブレーズ・サンドラール(1887-1961)と親交を結び、同じく詩人ギヨーム・アポリネール(1880-1918)とも知り合いになる。そして画家のモディリアーニ(1884-1920)やパスキン(1885-1930)、スーティン(1893-1943)など、後のエコール・ド・パリの巨匠たちと交流し、サロン・ドートンヌやアンデパンダン展などに出品を続け、評価を高めていった。
言葉とイメージを呼応させる
1914年、シャガールは初個展をドイツのベルリンにあるデア・シュトゥルム画廊で開き、大きな反響を呼んだ。しかし、同年第一次世界大戦が勃発。1915年ヴィテブスクの裕福な宝石商の娘ベラ・ローゼンフェルトと結婚し、ロシアのぺトログラード(1914-24年の間のサンクトペテルブルクの呼称)へ移住する。ベラはモスクワの名門女子大学で文学士号を取得し、モスクワ芸術座の創設者スタニスラフスキーの演劇学校にも通った才媛で、言葉とイメージを呼応させる共同制作のスタイルは、ベラの死まで続けられた。1916年娘イダが誕生。
1917年二月革命によってロシア帝国が崩壊、十月革命でロシア・ソビエト連邦社会主義共和国が成立すると、シャガールは家族を伴いヴィテブスクへ戻った。国家教育委員会から芸術人民委員に任命されて、1919年ヴィテブスク美術学校の校長に就任。ぺトログラード芸術宮殿(旧冬宮)での「第1回革命展」に24点を出品し、そのうちの多くが国家買い上げとなった。しかし、美術学校の教授として招いたマレーヴィチ(1878-1935)と対立し、校長を辞任。モスクワへ出て、ユダヤ劇場の舞台美術と壁画制作に没頭した。1922年、革命軍を名乗る暴徒によってベラの実家が破壊された。シャガールは自伝『わが回想』を完成させて、故国を去る決意で、リトアニアを経由してベルリンからパリへと向かった。
1923年、9年前に初個展を開いたベルリンのデア・シュトゥルム画廊に預けていた約200点の作品が無断で売却されていることを知り、裁判を起こす。《私と村》を含む3点の油彩画、グアッシュ10点が返却された。パリでは画商のヴォラールから、小説家ニコライ・ゴーゴリ(1809-52)の『死せる魂』の挿絵を依頼されるなど(出版は1948年)、経済的にも安定したものとなり、平穏な日々が続いていた。
1929年世界恐慌が起き、ファシズムが台頭する。1933年ヒトラーが首相となるとドイツのマイハイム美術館に所蔵されていたシャガール作品は退廃芸術とされ焼却されてしまった。1937年にフランス国籍を取得したが、ドイツの美術館に所蔵されていた全作品は撤去され、1941年にはナチスに屈したフランス政府が反ユダヤ政策をとり、シャガールはフランス国籍を剥奪されてしまう。シャガールは家族と共にアメリカに亡命することを決意した。「シャガールはユダヤ人、ロシア人、フランス人のすべてのアイデンティティを資本主義・社会主義の対立の時代に持ち続けるために『自制』するしかなかった。どれも捨てずに抱えたまま画家として生きる術(すべ)と表現を模索するしか選択肢がなかったのである」(圀府寺司『ユダヤ人と近代美術』p.142)。
20年ぶりのイスラエル
アメリカでは画商のピエール・マティスに迎えられ、ニューヨークへ移り住んだシャガールは、バレエ『アレコ』の舞台装置や衣装を制作して成功を収める。そして、メキシコに行って制作するほか、版画を始めたり、アメリカ最古の女子大学マウントホリヨーク大学で講演を行なうなどして過ごしていた。1944年最愛のベラがウイルスに感染して急死する。家政婦としてイギリス人のヴァージニア・ハガード・マクニールが娘ジーンとともに家に住み始めると、1946年にはシャガールとヴァージニアとの間に長男ダヴィッド・マクニールが誕生。同年MoMAで大回顧展が開かれ、翌年にもパリの国立近代美術館で大回顧展が開催された。フランスに一時帰国したシャガールは、フランスに戻ることを決心する。
1948年にヴァージニアと二人の子供とともにフランスに帰国し、第24回ヴェネチア・ビエンナーレ版画部門でグランプリを受賞する。1950年南仏のヴァンスに「レ・コリーヌ荘」を購入、ピカソ(1881-1973)やマティス(1869-1954)と交流した。1951年には20年ぶりにイスラエルを訪れ、エルサレム、ハイファ、テル・アビヴで開催される大回顧展の開会式に出席。ヴァージニアが2人の子供を伴って、シャガールのもとを去ったのは、シャガールが65歳の1952年だった。娘イダの紹介によってロンドンで服飾業に携わる45歳のロシア系ユダヤ人ヴァランティーナ・ブロドスキー(通称:ヴァヴァ)と再婚。ヴァヴァも先妻ベラと同様に才媛で、名声が高まった画家を助ける賢妻であった。
シャガールは南仏の光を受けて、陶器やステンドグラス、タペストリーなどにも着手し、作品は開放的でのびのびとした傾向を高めていった。1963年には日本初の回顧展が国立西洋美術館など、東京と京都で開催された。翌年パリ・オペラ座の天井画を完成させる。1966年住み慣れたヴァンスと同じ県の小村サン=ポール=ド=ヴァンスに移り住む。1969年パリのグラン・パレで「シャガールのオマージュ」展が開催される。1973年にはニースに「国立マルク・シャガール〈聖書の言葉〉美術館」が開館。東京国立近代美術館をはじめ、日本での回顧展のために1976年89歳で来日する。1977年レジオン・ドヌール最高勲章を受章し、エルサレムの名誉市民にも選ばれた。1981年銅版画集『夢』を刊行し、1985年サン=ポール=ド=ヴァンスの自宅で死去。享年97歳。フランス人としてサン=ポール=ド=ヴァンスのカトリック墓地に眠っている。
私と村の見方
①タイトル
私と村(わたしとむら)。英題:I and the Village。友人である詩人ブレーズ・サンドラール(1887-1961)が命名。
②モチーフ
私、牛、乳しぼりする女性、円屋根の教会、家並み、鎌を持った農夫、農婦、十字架、ネックレス、指輪、太陽、月、生命の樹。
③制作年
1911年。シャガール24歳。
④画材
キャンバス・油彩。
⑤サイズ
縦192.1×横151.4cm。
⑥構図
二つの対角線によって区切られる四つの部分からなる。人と牛が大きく向き合うように左右対称に配置され、そのほかの各モチーフは互いに交差、相貫しながらも中央の円によって全体が統一されている。
⑦色彩
赤、ピンク、緑、黄、橙、青、紫、白、黒など多色。明るく透明感のある鮮やかな色彩。
⑧技法
油彩。フォービスムやキュビスムや色彩をフォルムとして追求したオルフィスムなど、当時の新しい造形様式を取り入れながら、物語をイメージさせる画面を幾何学的に構成している。
⑨サイン
画面左下にえんじ色で「ChagAll.1911.Paris.」と署名。
⑩鑑賞のポイント
帽子をかぶった緑色の顔の男が“私”で、左の白い牛が村を象徴する。シャガールがパリで想起した思い出の故郷を凝縮して描いた。「あの悲しくて、それでいて楽しかった私の町よ」(マルク・シャガール『シャガール わが回想』p.9)。ヴィテブスクへの思いは単なる懐古の感情ではなく、アイデンティティに関わる、人生を支える心の拠り所であった。シャガールの心のなかに生きている真実のヴィテブスク村。村には世界、宇宙、平和の意味が含まれている。モチーフを重ねたり、空間を錯綜させて多重露光した詩的なイメージの結像。キュビスム風の造形感覚で構成し、三原色(赤、青、黄)と緑の濃い色調が幻想的な雰囲気を醸し出す。重力や左右の区別もなく、過去と現代、未来も超える。農村共同体の暮らしは人間と動物が共存し、動物が人間と生命の仲介者となって連綿と続いていく。牛の頭の中には、乳をしぼられるもう一頭の小さな牛のイメージがある。おそらく大きな牛の思考を表わしているのだろう。“私”と牛は一条の線で通い合い、画面中心には赤い太陽と月とが食の関係を結び、人間と自然の関わりを示唆する。しかし、楽園の村には死の影もある。大鎌を持った農夫を農婦は恐れており、教会からそれを覗き見る者がいる。それでも、赤と緑、黄と紫、橙と青の色彩が際立ち、男が差し出す花咲く生命の樹は輝かしく、世界は自由に開かれて肯定されている。シャガール初期の代表作である。
ハシディズムとダイナミズム
今村氏は《私と村》の鑑賞ポイントについて、「緑色の人物と牛が巨大で、どうしてこんなに大きく顔をクローズアップするのだろう、と最初はそのインパクトに圧倒される。おそらく自然と共に生きてきたシャガールの感覚を表わしていると思う。牛に見える動物が何かは諸説あって、牝牛とか牡牛、ほかにもロバやユダヤの宗教的な意味を持った動物という説もある。タイトルの“私”はすごく大切で、私というと普遍性がないように思われるが、シャガールは私というものの物語をずっと描き続けていた。それは閉じ込められたイメージではなく、広がっていったり、多様な読み解きができたりする“私”だった。“私”は、ここにいるけれども、ここではない世界。また“私”は、ここではない世界にいるけれども、不可思議といまここにいる。《私と村》はモチーフや色がどんどん移り変わって、錯覚を覚えるような作品。ハッピーかアンハッピーかというと、そこは宙吊りになっているはずで、両面性がある。幸せか悲しみか、わかりやすくどちらかに転がらないよう、多様な解釈が可能なようにシャガールはイメージをたくさん盛り込んでいる。《私と村》はシャガールが自分の故郷ヴィテブスクを思いながら描いたもので、絵画という虚構の世界のなかで故郷の村を再建した。この絵画の最大のポイントは、人物と牛の目を結ぶ細くつたない線。全体が丁寧に描かれているなかで、蜘蛛の糸のような細々とした線が目と目を通じ合って引いてあり、引き込まれる。シャガールが絵を仕上げるときに、インスピレーションによって、最後に描いたと思われ、鑑賞者はその線から細部へと目を移していく」と述べた。
細部を見ていくと、「三角形に囲まれた生命の樹と、それを持つ指にはめられた指輪。人物と牛の間を横断する天体のような赤い丸。画面の上の方では、男性とひっくり返った女性がいるが、どこの村にもいそうな普通の農民たち。さらに家や教会(シナゴーク)、逆さになった家も見える。十字架のペンダントと愛らしいネックレス。現実とは異なる転倒した世界と現実が一緒に合わさっており、絵具は何層にも重ねられていて、陰影がとても丁寧に描かれている。細かいタッチや色の施し方にバリエーションが見られ、その絵筆の動きがわかる。細部を探り探り描き重ねていったところが魅力的で、《私と村》はその細部の複雑さにおいて、シャガール作品のなかでも野心的で特別な一点である」と今井氏。
またシャガール芸術の特徴については、「ヴィテブスクにおけるユダヤの神秘主義的な民衆信仰ハシディズム★が、シャガール芸術の核をなし、一方でユダヤの民族性や宗教観にのみ収斂することなく、幾重もの翼を広げて多面的な姿に変貌していった。このダイナミズムにこそシャガール芸術の本質が見られる」と、今井氏は語った。
★──厳格なユダヤ教に対抗して生まれた民衆信仰。生活の場そのものの神聖性を説き、口頭伝承や対話を重視し、日常語としてのイディッシュ語を重視した。
今井敬子(いまい・けいこ)
ポーラ美術館学芸部課長。1971年石川県金沢市生まれ。1993年上智大学文学部フランス文学科卒業、1996年フランス国立ルーヴル美術学院学士課程修了、1997年パリ第4大学ソルボンヌ考古学美術史学科修士課程修了。2001年ポーラ美術館準備室へ就職、2002年ポーラ美術館学芸員、現在に至る。専門:西洋近現代美術。所属学会:美術史学会、日仏美術学会。主な展覧会担当:「シャガール:私の物語」(2008)、「アンリ・ルソー:パリの空の下で ルソーとその仲間たち」(2010-11)、「紙片の宇宙:シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」(2014-15)、「ルソー、フジタ、写真家アジェのパリ―境界線への視線」(2016-17)、「ピカソとシャガール:愛と平和の讃歌」(2017)、「ポーラ美術館開館20周年記念展 ピカソ:青の時代を超えて」(2022-23)。美術館開館当初より教育普及活動にも取り組んでいる。
マルク・シャガール(Marc Chagall)
ロシア出身のフランスの画家。1887~1985年。帝政ロシア領のヴィテブスク(現ベラルーシ共和国)のユダヤ人居住区に生まれる。父ザハールは鰊を加工する工場に勤め、母フェイゲ=イテは小さな食料品店を営んでいた。1906年中等学校を卒業後、写真の修正の仕事に就く。画家になることを志し、1911年24歳でパリへ留学。《私と村》を描く。後のエコール・ド・パリの巨匠らと交流し、サロン・ドートンヌやアンデパンダン展などに出品。1914年ベルリンのデア・シュトゥルム画廊で初個展。第一次世界大戦が勃発し、ロシアに留まる。ロシア革命後の1923年再びパリで制作活動に入り、平穏な日々を送る。1937年フランス国籍を取得。第二次世界大戦が始まり、ナチスのユダヤ人迫害を逃れて1941年アメリカへ亡命。戦後1948年フランスに帰国。以後、南仏を拠点に国際的に活躍する。1973年にはニースに「国立マルク・シャガール〈聖書の言葉〉美術館」が開館。1985年南仏サン=ポール=ド=ヴァンスの自宅で死去。フランス人としてカトリックの墓地に埋葬された。享年97歳。代表作:《私と村》《アポリネールへのオマージュ》《誕生日》《白い磔刑図》《エッフェル塔の花嫁、花婿》《パリ・オペラ座天井画》。
デジタル画像のメタデータ
タイトル:私と村。作者:影山幸一。主題:世界の絵画。内容記述:マルク・シャガール《私と村》1911年、キャンバス・油彩、192.1×151.4cm、ニューヨーク近代美術館蔵。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者:ニューヨーク近代美術館、Scala、日本美術著作権協会、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Jpeg形式27.0MB、300dpi、8bit、RGB。資源識別子:scala_0163060(Jpeg形式30.7MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールあり)。情報源:(株)DNPアートコミュニケーションズ。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:ニューヨーク近代美術館、Scala、日本美術著作権協会、(株)DNPアートコミュニケーションズ。
画像製作レポート
《私と村》の画像は、DNPアートコミュニケーションズ(DNPAC)へメールで依頼した。シャガールの著作権については、日本美術著作権協会(JASPAR)のホームページより、「著作権使用許諾申請書」をダウンロードして申請。JASPARからの返信メールによって許諾を得て、「著作権使用料」8,000円をJASPARへ支払う。後日、DNPACからのメールにより、作品画像をダウンロードして入手(Jpeg、30.7MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールあり)。トリミングなしで、掲載は1年間。
iMac 21インチモニターをEye-One Display2(X-Rite)によって、モニターを調整する。ニューヨーク近代美術館のWebサイトにある作品画像を参考に、画像を確認しながら、入手した画像のカラーガイド・グレースケールを取り除くため、作品の外側を切り取った(Jpeg形式27.0MB、300dpi、8bit、RGB)。作品画像は、カラーガイド・グレースケール入りのフォーマットに配置したと思われる。MoMAでの画像製作は、作品とカラーガイド・グレースケールが同時に撮影された形跡がなく、作品画像にカラーガイド・グレースケールが自動に入るようシステム化されているようだ。美術館業務にデジタル化が普及している様子を感じ取ることができた。
セキュリティを考慮して、高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」を用い、拡大表示を可能としている。
参考文献
・『原色版美術ライブラリー25 シャガール』(みすず書房、1956)
・矢内原伊作解説『現代美術4 シャガール』(みすず書房、1960)
・『みずゑ』No.704(美術出版社、1963.10)
・マルク・シャガール著、三輪福松+村上陽通訳『シャガール わが回想』(美術出版社、1965)
・アルベルト・マルチニ+富永惣一監修、黒江光彦解説『ファブリ世界名画集48 マルク・シャガール』(平凡社、1970)
・座右宝刊行会編『現代世界美術全集17──シャガール』(集英社、1970)
・日本アート・センター編、岡田隆彦解説『新潮美術文庫47 シャガール』(新潮社、1975)
・ヴェルナー・ハフトマン著、酒井忠康訳『CHAGALL』(美術出版社、1976)
・高見堅志郎編著『25人の画家 シャガール 現代世界美術全集第22巻』(講談社、1980)
・ピエール・プロヴォワユール著、太田泰人+幸福輝訳『シャガールの聖書』(岩波書店、1985)
・黒江光彦責任編集『アート・ギャラリー 現代世界の美術16 シャガール』(集英社、1985)
・フランソワ・ル・タルガ著、佐和瑛子訳『現代美術の巨匠 マルク・シャガール』(美術出版社、1987)
・図録『シャガール展』(東京新聞、1989)
・川口幸也「シャガール──近代を超えるもの」(図録『「シャガールのシャガール」展』、朝日新聞社、1989、pp.14-19)
・『週刊グレート・アーティスト 第8号』(同朋舎出版、1990)
・アンドリュー・ケーガン著、大島清次+川口幸也訳『マルク・シャガール』(美術出版社、1990)
・池上忠治監修、後小路雅弘編『シャガール』(日本経済新聞社、1993)
・安岡章太郎+千足伸行+高階秀爾『新装カンヴァス版 世界の名画19 ルソーとシャガール』(中央公論社、1994)
・高見堅志郎編著『シャガール(ヴィヴァン 新装版・25人の画家たち 第22巻)』(講談社、1995)
・『週刊アートギャラリー 第10号」(デアゴスティーニ・ジャパン、1999.4)
・ダニエル・マルシェッソー著、高階秀爾監修、田辺希久子+村上尚子訳『シャガール:「知の再発見」双書87)」(創元社、1999)
・『週刊美術館:小学館ウィークリーブック4号(時代順第39号)』(小学館、2000.2)
・モニカ・ボーム=デュシェン著、高階絵里加訳『岩波 世界の美術 シャガール』(岩波書店、2001)
・インゴ・F・ヴァルター+ライナー・メッツガー著、Mitsuo Hamma訳『マルク・シャガール 1887-1985』(タッシェン・ジャパン、2001)
・シルヴィー・フォレスティエ著、山梨俊夫監訳+籾山昌夫訳『美の世紀2 シャガール』(二玄社、2006)
・図録『シャガール展』(谷口事務所、2007)
・図録『シャガール:私の物語』(ポーラ美術振興財団ポーラ美術館、2008)
・小針由紀隆「マルク・シャガールとノスタルジアの行方」(図録『シャガール展:色彩の詩人』、西日本新聞社、2008、pp.200-203)
・『週刊 西洋絵画の巨匠 6号 シャガール』(小学館、2009.3)
・圀府寺司+樋上千寿+和田恵庭『ああ、誰がシャガールを理解したのでしょうか? 二つの世界間を生き延びたイディッシュ文化の末裔』(大阪大学出版会、2011)
・図録『シャガール展2012:愛の物語』(西日本新聞社、2012)
・木島俊介『アート・ビギナーズ・コレクション もっと知りたい シャガール 生涯と作品』(東京美術、2012)
・ジル・ホロンスキー著、湊典子訳『アート・ライブラリー シャガール(新装版)』(西村書店、2012)
・ジャッキー・ヴォルシュレガー著、安達まみ訳『シャガール 愛と追放』(白水社、2013)
・三浦篤『まなざしのレッスン2 西洋近現代絵画』(東京大学出版会、2015)
・圀府寺司『ユダヤ人と近代美術』(光文社、2016)
・図録『ピカソとシャガール:愛と平和の讃歌 ポーラ美術館開館15周年記念展』(ポーラ美術振興財団ポーラ美術館、2017)
・図録『ポーラ美術館コレクション展:印象派からエコール・ド・パリ』(TBS テレビ、2021)
・Webサイト:樋上千寿「シャガール・オタクは歌う」(『同志社時報』第115号「エッセイ」、同志社大学、2003.3、pp.44-47)2025.3.5閲覧(https://www.doshisha.ac.jp/attach/page/OFFICIAL-PAGE-JA-268/139700/file/115essay.pdf)
・Webサイト:梶原麻奈未「シャガールの神秘主義思想」(『岡山大学学術成果リポジトリ』、「岡山大学審査学位論文」博士(文学)甲第5007号、20014.3.25、pp.1-179)2025.3.5閲覧(https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/52641)
・Webサイト:『Musée national Marc Chagall』2025.3.5閲覧(https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/)
・Webサイト:「Marc Chagall I and the Village 1911」(『MoMA』)2025.3.5閲覧(https://www.moma.org/collection/works/78984)
掲載画家出身地マップ
 ※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。
※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。
2025年3月