 |
 |
| シドニー・ビエンナーレ/Art Gallery of New South Wales ほか |
 |
| 東京/新国立美術館 南雄介 |
 |
 |
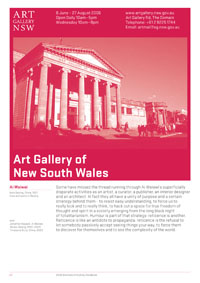 |
7月の末から2週間の日程でオーストラリアに行ってきた。この訪問は、オーストラリア政府の招待によるもので、オーストラリアの現代美術の調査や、美術関係者との交流といったこと以上に、特に明確な目的が設定されているわけではなかった。2週間でメルボルン、キャンベラ、シドニー、ブリスベンの4都市を訪れたのだが、私にとっては初めてのオーストラリア訪問だったので、なかなかに忙しく、また興味深い旅行になった。オーストラリアの文化政策とか、美術館の活動状況とか、現代美術に見られる活気とか、今回の調査で得た知見はいろいろとあるのだが、訪問の特に重要な目的の一つに、シドニー・ビエンナーレを見るということがあったので、それをレポートすることにしよう。
ビエンナーレの時代、国際展の時代と言われて久しいが、1973年に始まるシドニーは、今年で15回め、と歴史を重ねている。今回は、チャールズ・メリウェザーがアーティスティック・ダイレクター/キュレーターをつとめ、Zones of Contactのテーマのもとに、44ヵ国・57都市から85作家を集めている。直訳すれば、「接触地帯」、となるのだろうか。この主題は、いろいろなものを喚起する。そして、contactは「敵との〜」というように軍事用語でもあり、またfirst contactと言えば異星人との最初の接触のことだから、この言葉には何がなし、不穏な響きがある。
さて、展示の方は、アート・ギャラリー・オブ・ニューサウスウェールズ、シドニー現代美術館、ピア2/3(波止場の倉庫である)を中心に、シドニー市内の16カ所が会場になっていたのだが、全てを見ることができたわけではない。作家で勘定すれば8割ほどは目にした計算になるのだろうか。シドニー・ビエンナーレは初めて見るので、過去のものと比較はできないのだが──とはいえ、ほかの国際展もそんなに熱心に見てまわっているわけではない──、全体に落着いた感じがするなあというのが第一印象であった。運営が手慣れていてよく考えられている(ように見受けられた)というのと、出品作家や作品のクオリティが高く、安心して見られるものが多かった、というのがその理由かもしれない。あるいは、テーマ自体がビエンナーレという枠組みと親和性があり、違和感なく見ることができた──「なんでこの作家が出てるの?」という思いをすることが少なかった──ということだったのかもしれない。
会場で作品を一つひとつキャプションで確認しながら眺めているうちに思ったのは、中近東や、旧東欧・ロシア出身の作家がずいぶん目につき、逆に西欧圏やアメリカ合衆国の作家は少ないな、ということだった。近ごろの世界情勢に照らしても、このあたりは、テーマから受ける印象と矛盾しないように思う。不安定な、あるいは戦乱の地を母国とする作家たち。遠くない過去に戦禍をこうむった地を母国とする作家たち。このような衝突の地から亡命してきた作家たちはもまた、あらたな居住地で、異なる文化・異なる風土との接触を余儀なくされているに違いない。世界中に遍在するこのような状況/現場は、ポストコロニアルな世界の典型的な表象ともいえるのであり、そこからはアクチュアリティの表現としての芸術が生まれてくることになる。
だが、いわゆる状況/現場は、当然ながらこのような大きな世界にばかりにあるわけではない。性差別であるとか、芸術・文化のヒエラルキーであるとか、さまざまな曲面に、ポストコロニアルな状況/現場は存在するわけだ。植民地としての女性とか、植民地としての刺繍とか、まあそういったことがあるわけで、それゆえこのビエンナーレでは、ビデオや写真やテキストを用いた作品とともに、女性作家がひじょうに多く含まれていたのだし、一方でクラフト的な手の実践も目についたのである。
今回のシドニー・ビエンナーレは、このように、あまり奇を衒ったところのない、総体としてひじょうに真摯で率直な企てであったように思う。シドニーに住んでいる作家が教えてくれたのだが、今回のビエンナーレはscholarly showという評判なのだそうだ。ふうん、なるほど。つまり啓蒙的というわけなのだな。
ある意味で、それは、国際展を開くことの意義というところにまで、自己言及的に送り返されていく問題なのではないのか。商業化やグローバリゼーションへの加担を最小限にとどめながら──あるいはその危険を冒してもなお──、国境を超えたアートの生産と受容の場は確保され続けるべきなのだ。そしてそれこそが、(ポジティヴな意味での)Zones of contactの名に相応しい場なのである。 |
 |
 |
| [みなみ ゆうすけ] |
 |
|
 |

