バックナンバー
2023年04月01日号のバックナンバー
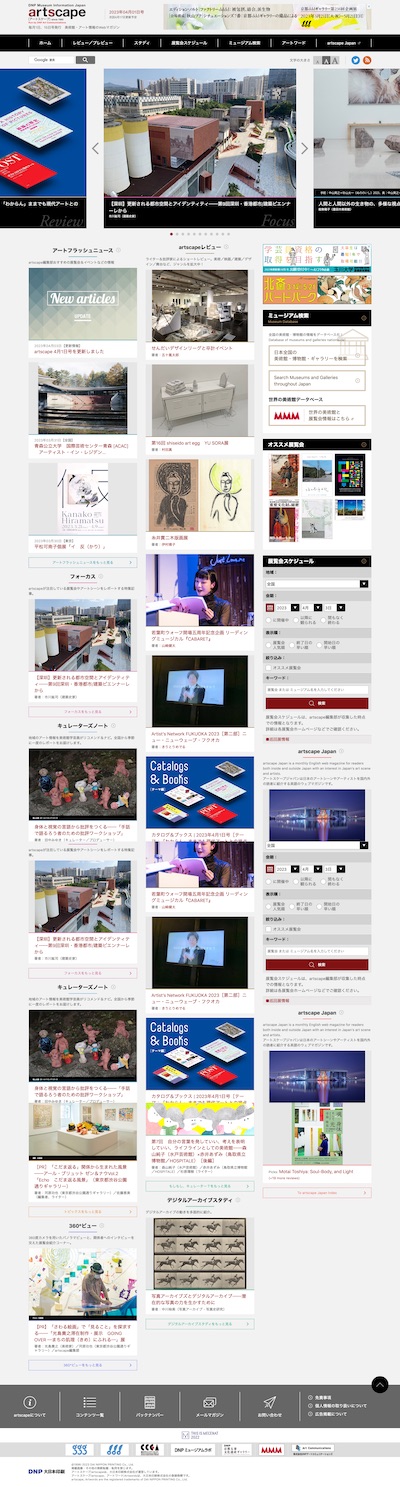
フォーカス
【深圳】更新される都市空間とアイデンティティ──第9回深圳・香港都市/建築ビエンナーレから
[2023年04月01日号(市川紘司)]
深圳と香港、2つの経済特区にまたがって、建築と都市をテーマに開催されている深圳・香港都市/建築ビエンナーレ(Shenzhen & Hong Kong Bi-city Biennale of Urbanism\Architecture。以下、UABB)。9回目の今年は開催期間が2都市で異なり、深圳では同時期に日本の現代建築家のプロジェクトを紹介する展覧会も開催されていた。コロナ禍以降の深圳と香港・西九龍文化地区の建築と都市をめぐる状況について、アジア、とくに中華圏の建築・都市論が専門の市川紘司氏にレポートしていただく。(artscape編集部)
キュレーターズノート
身体と視覚の言語から批評をつくる──「手話で語るろう者のための批評ワークショップ」
[2023年04月01日号(田中みゆき)]
この数年、映画『Coda コーダ あいのうた』に始まり、映画『ケイコ 目を澄ませて』、ドラマ『silent』など、ろう者や難聴者が脚光を浴びる作品が続いている。しかし、残念ながら特に国内では、主要なキャストがろう者や難聴者という設定の場合、その役柄は当事者ではなく聴者によって演じられてきた。それは、ただでさえオーディズム(聴能至上主義:聞こえることが優れていることを前提とした差別)により抑圧されてきたろう者・難聴者が表象する文化を聴者の文化に取り込もうとする文化の盗用のかたちであり、そのままでは社会構造の不平等は何らなくならない。少しでも減らしていくためには、演じる/つくる側だけでなく、見る側のそういった作品を語る言葉にも、当事者の視点が反映されるべきではないだろうか。しかし、日本語が母語でないろう者や難聴者(詳しくは後述するが、日本手話は日本語とはまったく別の言語である)が日本語で語ることは、日本語の規範や正しさという抑圧構造のなかで、彼らはやはり不利な状況にあることを意味する。ろう者が主体となって始まった「手話で語るろう者のための批評ワークショップ」は、ろう者・難聴者が自らの言葉である手話で芸術や文化を批評的に語るための土壌をつくる取り組みである。
人間と人間以外の生き物の、多様な空間と複数の時間──「ねこのほそ道」展
[2023年04月01日号(能勢陽子)]
現在、豊田市美術館で開催している「ねこのほそ道」展は、現代美術の企画展としては、あまりにゆるいタイトルだと思われるかもしれない。絵画や浮世絵、絵本におけるねこの展覧会はたびたび開催されているが、ねこの表象ではなく、その特質や人間と社会との関係を現代美術で扱う展覧会は、これまでなかったように思う。しかし、人間とは異なる別種の時間と空間を私たちの生活にもたらすねこを介せば、二足歩行による平均的な人間の身体に基づいた生活環境や、時代や社会により形作られる倫理や道徳を含めた思考の枠組みから逸脱する、多様な回路が現われてくるのではないか。そしてねこにとっては、自身の身体に直に伝わる匂いや感触がすべてであり、それは遠くにある「何か」というのではない。そんなねこの視点を借りれば、大きく抽象的な問題に向かいがちな私たちに、身の回りにある問題やその複雑さ、豊かさを見せてくれるのではないか。そして、最強のインターネット・ミームであるねこは、美術愛好者の間でのみ共有されがちな問題を、広く届ける媒体になってくれるかもしれない。そのようなことを考えて、この展覧会を企画した。本展が、ねこのように領域横断的に拡散し、社会や美術、そして美術館に対するさりげないカウンターになることを、密かに願っている。
「美しいHUG!」──ものとこと、作品と人、ホワイトキューブとジャイアントルーム
[2023年04月01日号(大澤苑美)]
八戸市美術館は、2021年11月に全面建て替えにより再オープンしてから2回目の春を迎える。新しい建築と運営に慣れたいま、開館前に作成した大風呂敷の運営計画や、「出会いと学びのアートファーム」というコンセプトワードなど、八戸市美術館の「トンマナ」(トーン&マナーの略、デザインの一貫性・統一性を言う)が、ようやく身体化されてきたように思う。案内スタッフは作品の前でよく談笑しているし、開館前、警備員さんや清掃員さんが作品をいち早く見て感想を言い合う風景もよく見かけて嬉しい。
もしもし、キュレーター?
第7回 自分の言葉を発していい、考えを表明していい、ライフラインとしての美術館──森山純子(水戸芸術館)×赤井あずみ(鳥取県立博物館/HOSPITALE)[後編]
[2023年04月01日号(森山純子/赤井あずみ/杉原環樹)]
学校と連携して教育普及事業を展開したり、地域と美術館をつないだり──従来の「学芸員」の枠組みにとらわれずユニークな活動を展開する全国各地のキュレーターにスポットをあて、リレー形式で話を聴きつないでいく対談連載「もしもし、キュレーター?」。前回と今回は、2025年春の鳥取県立美術館の開館に向けて準備を進める赤井あずみさんが、そのなかで出会った悩みを携えて、水戸芸術館のオープン当初から教育普及事業に携わる森山純子さんを訪ねます。
書籍『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』(集英社インターナショナル、2021) にも登場し、あらゆる文脈の人々と美術との接点のつくり方を模索し続けている森山さんは、ご自身も水戸出身。市民からの風当たりも強かったという1990年の開館当初から現在に至るまで、教育プログラムやボランティアスタッフとの協働、「高校生ウィーク」といったチャレンジングな試みの数々を通して開かれていった、水戸芸術館の奮闘の数々。後編の今回では、森山さんご自身の経験を通して改めて実感する、公共における美術館の役割などについても話が及びました。(artscape編集部)
[取材・構成:杉原環樹/イラスト:三好愛]
※対談の前編(第6回)「『ひとりの人間として扱ってもらう』経験に出会う場所を」はこちら。
※「もしもし、キュレーター?」のバックナンバーはこちら。







![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)