Dialogue Tour 2010
小さくてもマーケットに開かれていること
鷲田──CAAKをやりながら、その活動自体をどう位置づけられるか考えています。ひとつは、粉川哲夫の言うような、スペースの運動として、自由ラジオのようなオルタナティブなメディア、公共圏の実践としての位置づけ。たとえば京都のhanareは、そうした文脈でとらえることもできそうで、今回のツアーのなかでも、もっともアクティヴィズムに近いと思います。もうひとつは、美術史の文脈のなかで、日本の参加型アートプロジェクトの発展型としての位置づけ。参加型アートプロジェクトは、〈作品〉という形式を保持していて、作者としてのアーティストがいましたが、その形式が解体されて、特定の作者不在な状態というとらえ方です。参加型アートプロジェクトは日本で独特な広がり方をしましたが、欧米の美術ではリレーショナル・アートが近いかと思います。辻さんは、リレーショナル・アートについての勉強会をされていますが、どう思われますか。ちなみに第六回の土屋誠一さんのレビューでは先細りになっていくだろうとも書かれていますが……。たしかに地域の狭いグループ内の自己満足でやっているだけという評価もできると思うんです。
辻──土屋さんのテキストは、唯一、批判的な文脈で書かれているレビューなのでおもしろく読みました。先細りしていくのか、美術史に接続できるかは、活動は8カ所それぞれ違うので十把一絡には言えない。ただ、たびたび公立美術館との関係に触れていますが、そういう山口や金沢のあり方というのはサステナビリティがあるのではないかと思っています。活動の良し悪しではなくて、経済的なバックボーンがある。すべてが先細りになるとは思わないけれども、単独でやって続くかというと難しいのではないか。そういう意味で、美術館はけっこう重要な位置を占めているといえます。
また、活動の持続性や広がりを考えると、内輪の小さいところで始めるからうまくいかないということではないと思います。「2ちゃんねる」は、ひろゆきが自分の友達とやり取りしたいからつくったシステムですし、YouTubeも友人とのあいだで結婚式とかパーティの記録などのプライベートなビデオを簡単にシェアするシステムが欲しくてつくったものが始まりです。はじまりが内輪かどうかは問題ではなく、構造的に複数の欲望や関心に開かれていて、参加のコストが低いことが重要だと思います。それはマーケットに開かれているということでもあると思います。
鷲田──これまでのお話は山口や金沢といった、各地域内での異なる組織間の関係のことだったと思います。一方、ダイアローグ・ツアーのように、異なる都市での共感できる活動を横糸で繋いでいくこと、あるいは、土屋さんのおっしゃるような〈聖地化〉といった、地域を越えた繋がりは、サステナビリティを持つための別の構造になるとも思っているのですが。
辻──横糸としてのネットワークとともに、縦糸も必要で、マーケットや美術館はその役割を担っているのではないかと。経験的に美術に関わる人、特に美術館関係者はマーケットに否定的な人が多いのですが、マーケットを多様な人たちの欲望が流通し、調整されながら蓄積していくオープンな場所ととらえることもできます。オープンなだけに調整の結果は偶然的なものになるわけですが。美術館も本来はマーケットのなかで重要な役割を担うプレイヤーのひとつでもありますよね。それから、〈Web 2.0〉以降はロングテールや顧客と商品のマッチングの手法の洗練など、マーケットにアクセスするために必ずしも大きな資本や組織が必要ではなくなってきています。「現代美術2.0」でもそういう議論や提案があってもよいのではないでしょうか。ともかく、僕はマーケットに肯定的な面を見ています。
作品と作者の関係
辻──『関係性の美学』において、著者のニコラ・ブリオーの主張は簡単に言うと、「作品の評価は、単体の作品に還元できなくて、それが体験される環境も含めて評価せざるを得なくなってきている」ということです。環境も含んだ評価対象としての芸術体験のまとまりはなにか。ブリオーはあまりはっきりとは言っていませんが、「時間的なまとまり」や「展覧会」ということで考えているようです。それを敷衍して考えると、美術館とかインスティテューション、ギャラリーなどといった、制度的なまとまりが包摂する鑑賞者の体験と言っていいと思います。ブリオーは、『関係性の美学』が1998年に出版された後、パレ・ド・トーキョーのディレクターに就任し、著書で主張した体験の可能性を実現しました。パレ・ド・トーキョーは普通のアートセンターとは開館時間が全然違います。普通、美術館は9時から18時くらいですよね。パレ・ド・トーキョーの開館時間は正午から夜中まででした。内部も一見、美術館という感じがしません。展示空間の仕切りがなくて、倉庫の一画の壁を塗って展示空間にしましたみたいな感じです。それがオルタナティブな施設ではなくて、公共施設として成立している。美術館での体験の限界に対して、たんなる制度批判を行なうのではなく、時間と空間を操作していた。制度は動かしがたくあるものではなく、ある種のネゴシエーションで変えられるというリアリティを持ち、実際に別の選択肢を提案していたわけです。
結果としてパレ・ド・トーキョーでは、美術鑑賞を一義的な目的でない人でも楽しむことができる空間になっている。クラブをやっているので音楽を聞きたいという欲求でも来れるし、ブックショップもすごく洗練されていて、インテリアもよくデザインされている。複数の関心を許容する空間を実現しています。ブリオーは、『関係性の美学』を書くときに1960年代の美学から逃れることを強調していますが、60年代に目指されていた模範的な作品と観客の関係は、自律した作品と自律した観客の1対1の関係なんですね。ブリオーは、マルセル・デュシャンの言葉を引用しながら、作品の姿は実際に作品を見た人がその体験のなかで作品の意味を変えられるといっています。美術館をそうやってつくり直すことで、個々の作品鑑賞では不可能な体験者の立場をつくろうとしたと僕は見ているわけです。
たとえば、金沢21世紀美術館には市民ギャラリーがあって公募展もやっていて、美術館の中にそういう複数の機能があることが重要だと思っています。市民展の作品は現代美術ではないわけです。でも、美術館がたんに文化の蓄積だけではなく、そのような多様性を孕んだ市民の活動を包摂しうる場所として設計されることで、美術館のサステナビリティを上げ、さらに周辺にあるオルタナティブなスペースのサステナビリティも上げることができますよね。
鷲田──多様な市民活動のひとつとして、こういう小さな活動が行なわれ、それを公的な機関が包摂することで、両者が美術史のなかに位置づけられるということですね。
辻──記録を多く残すことが重要ではないでしょうか。実際に運営している人が過去の活動との違いを強調するよりも、複数の体験や関心のレイヤーを許容するような選択肢を提案して、その活動が多くの人に受け入れられながら持続していくこと。山口の話にしても、世代が変わって持続していくことでその歴史に鷲田さんは気づいた。それで、こうして別のところで僕や服部くんや会田くんを招いてその活動を記録に残そうとしている。そういうことの連続が歴史に残る可能性ということではないでしょうか。

パレ・ド・トーキョー内観

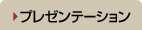

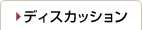
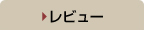
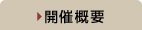
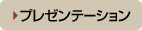

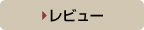
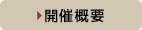




![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)