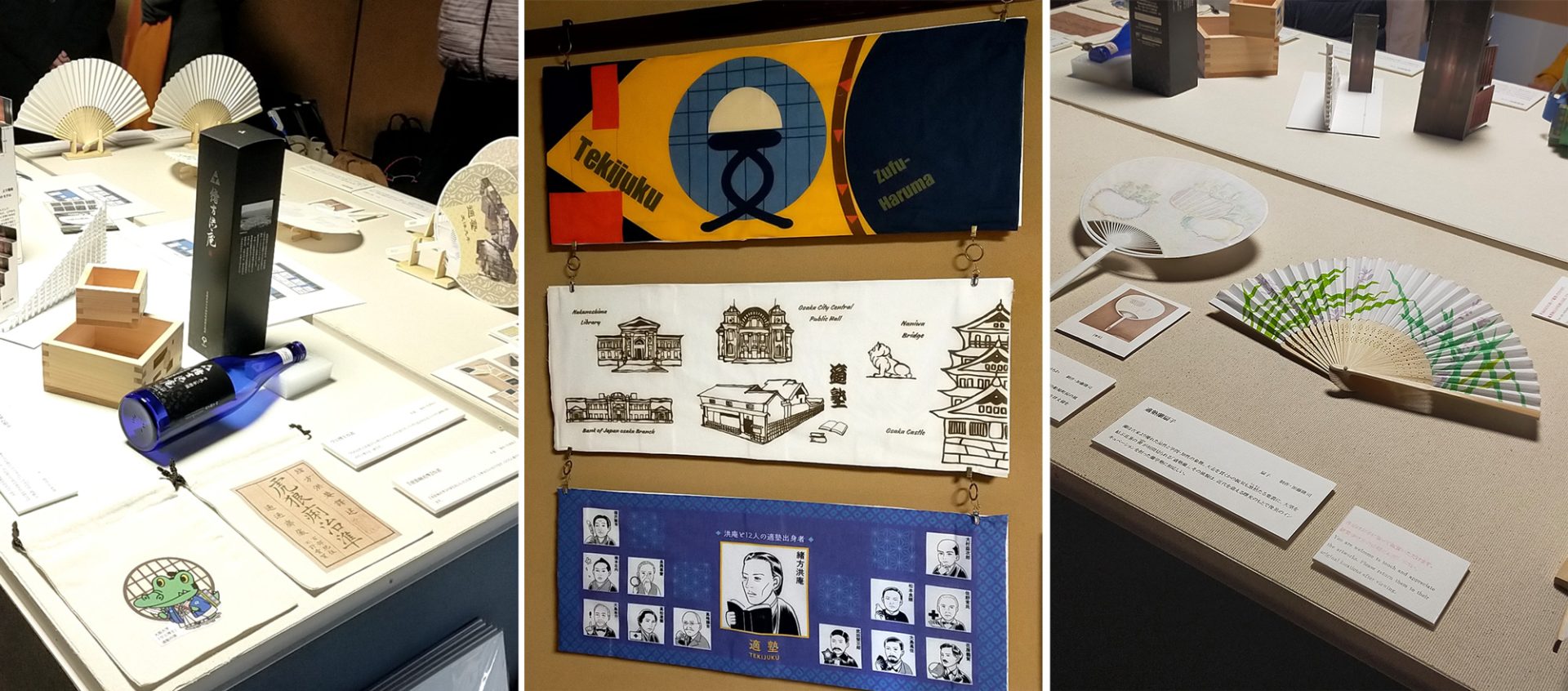※《十字架降架の三連祭壇画》の画像は2024年6月から1年間掲載しておりましたが、掲載期間終了のため削除しました。
悲痛さと静寂のなかの躍動感
梅雨入り前の晴天に恵まれ、旧東海道界隈が夏祭りで賑わっていた。本番前の夕方になると練習が始まり、太鼓の音に笛の音が夕空に響き渡った。東京・品川の天王祭である。揃いの半纏に、御神輿を担ぐ人の出で立ちで非日常の景色となり、祭りは時空を超える。江戸時代には大江戸夏祭りの花形だったという。江戸時代の初期、俵屋宗達(生没年不詳)や宮本武蔵(1584-1645)が、《風神雷神図屏風》や《枯木鳴鵙図(こぼくめいげきず)》を描いていた頃、ヨーロッパではペーテル・パウル・ルーベンスが活躍していた。
しかし、ルーベンスの名前は知っていても作品が浮かんでこない。個人宅の部屋に飾る小さな絵画ではなく、公共の場に掲げる大画面がルーベンスらしいのだろう。代表作と言われている宗教画の大作《十字架降架の三連祭壇画》(ベルギー、アントウェルペン聖母大聖堂蔵)を見てみたいと思った。イギリスの女性作家ウィーダ著の児童文学「フランダースの犬」で画家を志していたネロ少年が「ひと目見ることができるなら死んでもかまわない」とまで望み、実際に死の間際に愛犬パトラッシュと見たのがルーベンスのこの作品であった。
十字架に磔(はりつけ)にされ、死によって苦しみから解放されたキリスト。人々の恐れは悲しみへと変わり、光が射し込み悲痛さと静寂のなかにも躍動感がある。中央のパネルでは、白と赤の鮮やかな色彩が目を引く。左のパネルは女性が懐妊したことを告げ、右のパネルはキリストの誕生を祝うシーンだろうか。いずれもキリストの降誕と昇天に関わる絵画と思われるが、宗教を内包する名画はどのように見ればいいのだろう。どこが見どころなのか。東京都美術館の学芸員、髙城靖之氏(以下、髙城氏)に《十字架降架の三連祭壇画》の見方を伺った。
髙城氏は、17世紀オランダ絵画を専門とし、「ルーベンスの《十字架降架の三連祭壇画》──画家の才能と創意」(共著『ネーデルラント美術の精華[北方近世美術叢書4]』、ありな書房、2019)を執筆されている。東京・上野の東京都美術館へ向かった。

髙城靖之氏
細部を拡大しても実物
落ち着いた物腰で対応してくれた髙城氏は、1983年東京の外神田に生まれた。祖父母と両親と姉との6人家族、家は代々蒔絵師の家柄で父は4代目だが、いまは跡を継ぐ状況ではないという。中学、高校と美術部に入り、画家になる気持ちはなかったが絵は描いていたそうだ。
読書好きという髙城氏は、慶應義塾大学文学部に入学し、美術の授業で北方の画家ヤン・ファン・エイク(1387/95-1441)の《アルノルフィーニの夫妻像》を見て衝撃を受けた。「細部を拡大しても実物にしか見えない。実際の作品を見ると思いのほか小さい絵(縦82.2×横60.0cm)。15世紀の1434年にこんなに緻密に描けるものかと驚いた」と髙城氏。
美術史に関心をもった髙城氏は、ヤン・ファン・エイクをきっかけにオランダのだまし絵に興味をもち、レンブラント・ファン・レイン(1606-69)の弟子だった画家サミュエル・ファン・ホーホストラーテン(1627-78)について研究を始めた。ホーホストラーテンは、17世紀のオランダで、覗きからくり箱を制作し、理論書『絵画芸術の高き学び舎への手引き』も書いていた。髙城氏は慶應義塾大学の大学院修士課程に進み、2015年同大学院後期博士課程単位取得満期退学。卒論も修論もファン・ホーホストラーテンについて書き、2017年より東京都美術館の学芸員を務めている。
ルーベンスとは、17世紀のオランダ絵画を研究するなかで出会ったという。17世紀の西洋絵画研究をすると、必ず出てくるのがルーベンス。『ネーデルラント美術の精華』の出版を契機に踏み込んでルーベンスに取り組んだそうだ。
「17世紀フランドルの絵画のことを、『ルーベンスの時代』とか『ルーベンスの世紀』という言い方をするが、ルーベンスの場合、それは誇大表現でも誇大広告でもない。17世紀は本当にルーベンス抜きでは語れない、ルーベンスを中心にした世界になっている。ルーベンスの人生を知れば知るほど、ルーベンスは完璧超人と思えてくる。西洋の美術史のなかにおいてルーベンスは巨匠中の巨匠。しかし、どういうわけか日本ではあまり好まれない。よく言われるが、本格的なフランス料理が日本で受けないのと同じで、西洋絵画の真髄中の真髄は、日本人には馴染まないと。ルーベンスの場合は作品が建築と一体化した作品が多いので、その場に行って見ないとわからない。大きさなど、画集だと伝わらないものがある。ルーベンスは構図をまとめ上げる力がすごいと思う。大きい画面は大味になったりするが、ルーベンスの絵画はきちんと締まって迫力が伝わってくる。そこがほかの画家とは全然違う」と髙城氏は述べた。
イタリアに学ぶ
ペーテル・パウル・ルーベンスは、1577年ドイツ西部のジーゲンに生まれた。法律家の父ヤン・ルーベンスと、タピスリー商人の娘である母マリア・ペイペリンクスの第6子。両親共にフランドル(現ベルギー、オランダの国境付近とフランス北部)のアントウェルペン出身だったが、父がプロテスタントのカルヴァン派を信仰していたため、ルーベンス一家はドイツへ亡命していた。カトリック国スペインの領土となっていたネーデルラント(現ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)では、異教徒プロテスタントを迫害していたのだ。
1587年父の死後、母は子供たちとアントウェルペンへ戻り、もともと信仰していたカトリックに復帰した。ルーベンスは教養が深く、ラテン語学校にも通い、画家を志して1591年頃、風景画家トビアス・フェルハーヒト(1561-1638)に入門、次いでアダム・ファン・ノールト(1562-1641)、さらにオットー・ファン・フェーン(1556-1629)に師事し、1598年に画家組合である聖ルカ組合に親方として登録され、一人前の画家として第一歩を踏み出した。
1600年、古代遺物や最先端の絵画を学ぶためイタリアへ赴き、マントヴァ公に仕えながら8年あまり各地で研鑽を積み、祭壇画も制作した。ローマでは古代彫刻やミケランジェロ(1475-1564)、ラファエロ(1483-1520)の作品に接し、イタリアの理想的形態美や調和的構図、シンボリックな記念碑性を学び、同時にバロック様式の創始者である同時代のカラヴァッジョ(1571-1610)の劇的な明暗対比や写実的表現を吸収していった。1603年に訪れたスペイン宮廷では、ヴェネツィア派の華麗な色彩や大胆な構図に親しんだ。それら古代とルネサンスと現代を融合させたルーベンス様式を確立、荘重さと生き生きとした生命感を表現した。
ルーベンスは、1608年母危篤の報を受けて一時帰国の予定でイタリアからアントウェルペンに戻った。ところが翌年、フランドルの共同統治者であった大公アルブレヒト7世と大公妃イサベラから破格の年金を与えられることや弟子を無制限に取ることを許可され、特別待遇で宮廷画家に任命される。折しも1609年は、スペインから独立を宣言していたネーデルラントとスペインが休戦協定を交わし、平和が到来していた。そして32歳のルーベンスは、イサベラ・ブラントと最初の結婚をした。
王の画家にして、画家の王
経済復興とカトリック復興の熱気が漂うなか、ネーデルラントとスペインの休戦条約が失効する1621年までの10年あまりに、ルーベンスは工房を設立して弟子のアンソニー・ヴァン・ダイク(1599-1641)やヤーコプ・ヨルダーンス(1593-1678)らとともに63点の祭壇画を制作するなど、大きな活躍を果たした。なかでも1611年の《十字架降架の三連祭壇画》は、イタリアでの経験が発揮された重要な作品となった。
版画の刊行を思いついたルーベンスは、彫版師リュカス・フォルステルマン(1595-1675)に版刻をさせ、1622年から国外へ進出。《十字架降架の三連祭壇画》の中央パネルを銅版画化した作品は、ヨーロッパ中に広まり、各国から注文が入ると同時に多くの芸術家を惹きつけることになった。フランス王母マリー・ド・メディシスの注文に応じ、宮殿を王母の一代記で飾り、また英国王チャールズ1世の注文により、ホワイトホール宮の迎賓館天井に先王ジェームズ1世の栄光を描いた。さらにスペイン王フェリペ4世には、マドリード郊外の狩猟館を飾る神話画連作を制作している。30歳年下のレンブラントは、ルーベンスの銅版画を参考にして、《十字架降架》(ミュンヘン、アルテ・ピナコテーク蔵)を1633年に完成させた。その注文主はオランダ総督フレデリック・ヘンドリックであった。
1626年妻イサベラが死去する。ルーベンスはアルブレヒト大公亡き後、大公妃の外交使節としても重用され、オランダ語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ラテン語を自在に使いこなし、各国との外交交渉を担当した。1630年にはスペインとイギリスを和平に導いた功によって、フェリペ4世とチャールズ1世から騎士に叙せられた。ルーベンスは53歳になっていたが16歳の絹商人の娘エレーヌ・フルマンと再婚した。1636年ネーデルラント執政フェルディナンド枢機卿の宮廷画家に就任する。
晩年は、自らの喜びのために妻や豊満な裸婦、農民の生活などを描いた。しばしばヴェネツィア派の巨匠ティツィアーノの再来と言われるルーベンスだが、油絵の特質を生かした華麗な色彩で積極的に表現したのは、1630年代のことだった。「王の画家にして、画家の王」とも呼ばれ、画家としても外交官としても活躍し、世界でもっとも成功した画家と言われている。1640年5月30日、持病の痛風が悪化し、アントウェルペンの自宅で亡くなった。享年62歳。
十字架降架の三連祭壇画の見方
①タイトル
十字架降架の三連祭壇画(じゅうじかこうかのさんれんさいだんが)。英題:Descent from the Cross
②モチーフ
■中央(十字架降架):
キリスト、細長い白い布、十字架、青い服の聖母マリア、赤い衣の聖ヨハネ、キリストの隠れた弟子で遺骸を引き取りたいと願い出た富裕なアリマタヤのヨセフ、梯子を登るニコデモ、キリストの左足を支えて跪くマグダラのマリア、クロパの妻マリア、十字架の横木の上にいる二人の男、夕暮れの空、梯子、金の器、棘(イバラ)の冠、釘、石、紙。
■左翼(聖母のエリサベツ訪問):
エリサベツの家の前、赤い服のキリストを宿した若い聖母マリア、対照的な中年夫人の従姉妹エリサベツ、聖母の夫ヨセフ、エリサベツの夫ザカリヤ、籠を頭にのせた女性、犬、坂を下る人、孔雀、三羽の鶏。
■右翼(キリストの神殿奉献):
神殿、司祭シメオン、幼いキリスト、聖母マリア、聖母の夫ヨセフ、横顔は火縄銃射手組合★1のニコラース・ロコックス、つがいの鳩。
③制作年
1611〜14年。中央パネルは1611年から翌年、2年後の1614年に両翼が完成。ルーベンス34~37歳。
④画材
板・油彩。板は、目が詰まり硬く、虫食いや反ることも少ないオーク(樫)が使われていたと思われる。
⑤サイズ
開閉式の三連祭壇画で、中央パネルは縦421×横311cm、両翼はともに縦421×横153cm。壁画的なスケールの大画面。教会の礼拝堂に合わせた大きさ。
⑥構図
■中央(降架):
右上から左下へ動的な斜めの構図。
■左翼(訪問):
安定した水平の構図。
■右翼(奉献):
自立した垂直の構図。
右翼の神殿のアーチ状の天井から左翼の聖母マリアたちが佇むアーチ状の玄関まで、キリストの降架によって、右上から左下にかけてつながり、独立した場面でありながら連帯感を出している。
⑦色彩
ヴェネツィア派の明るい色彩が採用されており、赤、白、青、緑、紫、茶、黄、金、灰、黒など多色。
⑧技法
板に平滑に白色の地塗を施し、柔らかい貂(てん)毛の筆を用いて絵具を重ねて塗り、さらにハイライトを適切に入れて、透明感を出している。キリストのねじれた身体は、古代彫刻の《ラオコーン群像》(ヴァチカン美術館蔵)を引用している。人物群は、右上から左下へ対角線に沿って配置、またカラヴァッジョの明暗法を昇華させ、画面全体の構成を考え、細部描写とダイナミズムの調和を図っている。
⑨サイン
なし。
⑩鑑賞のポイント
■中央(降架)パネル:
十字架に磔られたキリストの亡骸を十字架から降ろそうとしている。釘を抜かれた両手と両足、槍で刺された脇腹からは血が流れているが、青白い肉体は力強く理想美を保っている。聖母マリアがキリストをいたわるように手を差し伸ばす。光が射し込み、死せるキリストの身体を包むたっぷりとした白い布と、ヨハネの赤い衣に光が当たり、暗闇に8人の人物像が一体となって浮かび上がる。静と動、暗から明へ、色彩のバランスが美しく、沈痛な静けさに支配されているなかにも一筋の光明がある。
■左翼(訪問)パネル:
身籠った処女マリア(聖母)が、従姉妹のエリサベツを訪ねたシーン。エリサベツの家の玄関で出会い、赤い服のマリアはおなかに左手を当て、エリサベツは右手でマリアのおなかを指差している。エリサベツの夫ザカリヤに天使が告げたとおり、エリサベツも洗礼者ヨハネを宿していた。神に祝福された者どうしが互いに喜び讃えている。
■右翼(奉献)パネル:
聖母マリアと夫ヨセフが、初めての男の子を聖別するためにエルサレムの神殿へ詣で司祭シメオンと出会う。金の飾りのついた豪華な赤い衣を着た司祭シメオンが聖母マリアから幼児キリストを受け取り、天上の神に祈りを捧げている。救世主に会うまでは死ねないという予言を受けていたシメオンは、キリストを抱き上げ、彼が救世主であることを宣言するとともに、将来待ち受けているキリストの受難を予言する。シメオンの左隣の横顔の男は、絵の発注者である火縄銃射手組合の組合長で、アントウェルペン市長でもあったニコラース・ロコックス。ロコックスは高い教養を備え、古典古代への深い見識をもち、美術愛好家でルーベンスと強い友情で結ばれていた。
両翼のパネル外側には、左翼に幼児キリストを背に担ぐ聖クリストフォロス★2、右翼にその二人をカンテラで照らす隠修士が描かれている。聖クリストフォロスは、火縄銃射手組合の守護聖人であり、「キリストを担う者」を意味する。本図左翼では、キリストは聖母マリアの胎内に担われ、右翼では司祭シメオンの腕に担われており、中央ではキリストの亡骸を聖ヨハネが担い、赤い衣を着た者が三連祭壇画の主題を結び付ける鍵となっている。実物大の人物が登場するスケールの大きさと表現の明快さ、劇的な迫力、そして全体をまとめる卓抜な構成力が鑑賞者を画中世界に引き込む。ルーベンスの全画業中でもっとも重要な作品とされ、17世紀バロック絵画を代表する名画である。
★1──自警団。つねに警備をしている組織ではなく、儀礼的な地域の団体。富裕層で武具や甲冑、火縄銃など、高価なものを揃えられる社会的ステイタスの高い人たち。守護聖人は聖クリストフォロス。
★2──聖人の逸話を集めた『黄金伝説』によると、火縄銃射手組合の守護聖人である聖クリストフォロスは、筋骨隆々の大男で、国中でもっとも偉大な人物に仕えることを目的としていた。最初、ある王に仕えたが、王は悪魔を恐れていたため、悪魔の方が偉大だと思い悪魔に仕えた。悪魔が十字架の前で震え上がるのを見た大男は、キリストに会うべく放浪をする。荒野で修行をしていた隠者に導かれ、貧しい者や弱い者を背負って川を渡る仕事に専念していた。ある晩、クリストフォロスは、小さな子供を背負い川を渡ったが、一歩進むごとに子供は重くなっていく。やがて子供は自分がキリストであることを打ち明け、その重荷は全世界の重さであると告げた。キリストは証拠としてクリストフォロスに、自分の杖を地面に植えてみよと言った。翌日花を咲かせ実をつけていた。大男の名前はもともとクリストフォルスではなかったが、「キリストを担う者」という意味のギリシア語のクリストフォルスとなる。大男は聖人となった。
キリストを担う者
「十字架降架」の主題は古くから絵画化されてきたという。髙城氏は「ロヒール・ファン・デル・ウェイデン(1399/1400-64)の《十字架降架》(1435頃、プラド美術館蔵)や、1545年頃にダニエーレ・ダ・ヴォルテッラ(1509頃-66)がローマのトリニタ・デイ・モンティ聖堂に描いたフレスコ画《十字架降架》などがあるが、特にダニエーレ・ダ・ヴォルテッラの作品は17世紀当時、非常に高く評価され、「十字架降架」を描くうえでは重要な作品であった。ルーベンスはその作品を目にし、十字架の横木の右側から身を乗り出して、キリストの亡骸を降ろそうとしている人物を、ルーベンスの本図では左右を反転させた状態で、左側の横木の上に配した」と述べた。
また、《十字架降架の三連祭壇画》をルーベンスに発注した火縄銃射手組合の守護聖人である聖クリストフォロスについて、「当時としては人気のある聖人であったが、カトリックとプロテスタントとの宗教対立があり、カトリック教会は、聖書や福音書に記述がないものは絵に描かないと決め、崇拝を禁じた。注文主の守護聖人は、一般的に祭壇画の内側の一番重要なところに描かれるが、崇拝が禁じられた聖クリストフォロスを内側に描けなくなり、外側に描くことになった。ルーベンスは祭壇画の内側に、キリストの生涯のなかからギリシア語で『キリストを背負う者』を意味するクリストフォロスに合致する三つの場面(『十字架降架』『聖母のエリサベツ訪問』『キリストの神殿奉献』)を選び、注文主を満足させた。3枚のパネルを眺めてみると、何の脈絡もなく並んでいるように見えるが、各パネルには鑑賞者の目を引く赤い衣を身につけた人物がひとりずつ描かれている。これが『キリストを担う者』の徴(しるし)である。特に聖母マリアは伝統的に青い服が多いが、左翼のマリアは意図的に赤い服を着せられている。つまり聖母マリアは、三つの場面すべてに登場しているが、懐妊した左翼のマリアだけが赤い服を身につけている。そして、外側に描かれている聖クリストフォロスの背後にも赤いマントがはためいている。赤色のつながりが、キリスト救済をイメージさせる」と髙城氏。キリストを担った聖クリストフォロスは、キリストが全世界の重さと同じであることを知る。全世界を救済するというダイナミズムが想起される。
救世主キリストの生涯
《十字架降架の三連祭壇画》については、「この作品はルーベンスがイタリアへ絵画を学びに行き、帰国後すぐに描いたためイタリアで得たものが生かされている。本図を受注する前年、ルーベンスはもうひとつの重要な依頼を受けていた。《十字架昇架の三連祭壇画》である。現在は降架と昇架が対になって同じ聖堂内に飾られているため、動きの激しさや静けさなど比較して語られることが多い。ルーベンスが育った北方のネーデルラントは、西洋美術の根幹を形成している古代ギリシア・ローマの中心地から離れていて、古代の遺物を目にする機会がなかった。そのため北方の画家たちは、古典・古代を求めてイタリアに渡った。《十字架降架の三連祭壇画》は、最新のイタリア風の絵画というだけでなく、描写力を特質とした北方と、古典と現代のイタリアが融合した作品であった。大きな画面を上手に構成し、見事に調和が取れている。中央の登場人物は8人に絞られて静かで瞑想的。バロックの明暗と対角線構図を使いながら人物をバランスよく配置している。見落としがちだが、生々しいキリストの傷跡。釘を刺された両手、両足。それから槍で刺されておなかから流れている血。北方の画家らしい細密な表現が見られる。3枚のパネルは、キリストが救い主としてこの世に生を享け、人類の原罪を引き受けて死を迎えるという、救世主キリストの生涯を表わす。《十字架降架の三連祭壇画》は、17世紀以降の画家たちにとっての道標であり、目標となった」と髙城氏は語った。
髙城靖之(たかしろ・やすゆき)
東京都美術館学芸員。1983年東京都生まれ。2007年慶應義塾大学文学部人文社会学科美学美術史学専攻卒業、2010年同大学大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了、2015年同専攻後期博士課程単位取得満期退学。2014年文京区役所の非常勤学芸員を経て、2017年より現職。専門:17世紀オランダ絵画。主な展覧会担当:「ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜」(2018)、「ハマスホイとデンマーク絵画」展(2020)、「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」(2022)、「デ・キリコ展」(2024)。主な論文:「漆器のパラドックス──海を渡った漆器と17世紀オランダ静物画の中の漆器」(『17世紀オランダ美術と〈アジア〉』所収、中央公論美術出版、2018)、「ルーベンスの《十字架降架の三連祭壇画》──画家の才能と創意」(『ネーデルラント美術の精華[北方近世美術叢書4]』所収、ありな書房、2019)、「スコットランドの風俗画家デイヴィッド・ウィルキ──その作品の特徴と意義」(『東京都美術館紀要』No.30所収、東京都美術館、2024)など。
ペーテル・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)
フランドル(現ベルギー)の画家。1577~1640年。アントウェルペン出身の法律家の父が亡命していたドイツのジーゲンに生まれる。1598年3人の画家の工房で修行し、アントウェルペンの画家組合(聖ルカ組合)に親方として登録され独立。1600年イタリアでの宮廷画家を振り出しに、ミケランジェロ、ラファエロ、ティツィアーノ、ティントレットの作品に親しみながら、ネーデルラントのアルブレヒト大公、イサベラ大公妃らに仕えた。1609年イサベラ・ブラントと結婚。1620年代にはアントウェルペンの聖シャルル聖堂やリュクサンブール宮の歩廊、タペストリーの連作を制作。1626年妻イサベラが死去し、1630年に絹商人の娘エレーヌ・フルマンと再婚。ロンドンのホワイトホール宮殿バンケティング・ハウスの天井画を受注。外交官としても活躍し、和平交渉のため各国を歴訪。晩年には親しみのある温かい色調で豊満な裸婦像や肖像画、風景画などを制作。1640年痛風に悩まされ、アントウェルペンにて没。享年62歳。バロック美術を代表する画家である。代表作:《十字架降架の三連祭壇画》《十字架昇架の三連祭壇画》《レウキッポスの娘たちの略奪》《マリー・ド・メディシスの生涯》《パリスの審判》など。
デジタル画像のメタデータ
タイトル:十字架降架の三連祭壇画。作者:影山幸一。主題:世界の絵画。内容記述:ペーテル・パウル・ルーベンス《十字架降架の三連祭壇画》1611-14年、板・油彩、中央:縦421×横311cm/両翼ともに:縦421×横153cm、ベルギー、アントウェルペン聖母大聖堂蔵。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者:アントウェルペン聖母大聖堂、Bridgeman Images、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Jpeg形式118.3MB、300dpi、8bit、RGB。資源識別子:コレクション番号=BAL715412、画像番号=LAF715412(Jpeg形式118.3MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールなし)。情報源:(株)DNPアートコミュニケーションズ。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:アントウェルペン聖母大聖堂、Bridgeman Images、(株)DNPアートコミュニケーションズ。
画像製作レポート
《十字架降架の三連祭壇画》の画像は、DNPアートコミュニケーションズ(DNPAC)へメールで依頼した。後日、DNPACの返信メールから、作品画像をダウンロードして入手(Jpeg、118.3MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールなし)。作品画像のトリミングは2点まで、掲載は1年間。
iMac 21インチモニターをEye-One Display2(X-Rite)によって、モニターを調整する。作品を所蔵するアントウェルペン聖母大聖堂のWebサイトの画像と、『世界美術大全集 第17巻 バロック2』(小学館、1995、p.157)のカラー図版を参考に、Photoshopで色調整を行なった(Jpeg形式118.3MB、300dpi、8bit、RGB)。参考画像を見ながら明度と彩度を調整して色を合わせた。色の微調整にはカラーガイド・グレースケールが必要だと思った。
セキュリティを考慮して、高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」を用い、拡大表示を可能としている。
参考文献
・C.V.ウェッジウッド著、嘉門安雄監修『巨匠の世界 ルーベンス』(タイムライフインターナショナル、1969)
・『別冊みづゑ ルーベンス』No.61/季刊・冬(美術出版社、1970.12)
・座右宝刊行会編『世界美術全集 12 ルーベンス』(集英社、1975)
・黒江光彦著『ファブリ研秀世界美術全集 第6巻 ルーベンス/レンブラント』(研秀出版、1975)
・坂本満『新潮美術文庫10 リューベンス』(新潮社、1976)
・杉浦明平+越宏一『世界美術全集8 ルーベンス/フェルメール』(小学館、1977)
・フランス・ボードワン著、黒江光彦+磯見辰典+荒木茂子訳『ルーベンス』(岩波書店、1978)
・山崎正和+高橋裕子『カンヴァス世界の大画家13 ルーベンス』(中央公論社、1982)
・図録『ルーベンス展──巨匠とその周辺』(アート・ライフ、1985)
・ジェイムズ・ホール著、高階秀爾監修、高橋達史+高橋裕子+太田泰人+西野嘉章+沼辺信一+諸川春樹+浦上雅司+越川倫明訳『西洋美術解読事典』(河出書房新社、1988)
・中山公男監修『週刊グレート・アーティスト 第61号』(同朋舎出版、1991)
・アンドリュー・モラル著、倉田一夫訳『巨匠の絵画技法 ルーベンス』(エルテ出版、1991)
・『アサヒグラフ別冊 美術特集 西洋編24 ルーベンス』通巻103号(朝日新聞社、1993.6)
・図録『リール市美術館蔵 バロック・ロココの絵画:ヴェネツィア派からゴヤまで』(朝日新聞社、1993)
・高橋裕子「リュベンスとその流派」(『世界美術大全集 第17巻 バロック2』、小学館、1995、pp.192-208, 435)
・高橋裕子+高橋達史監修『週刊アートギャラリー 第24号』(デアゴスティーニ・ジャパン、1999.7)
・『週刊美術館 第11号 ベラスケス/ルーベンス』(小学館、2000.4)
・図録『ルーベンスとその時代展 : ウィーン美術大学絵画館所蔵』(毎日新聞社、2000)
・クリスティン・ローゼ・ベルキン著、高橋裕子訳『岩波 世界の美術 リュベンス』(岩波書店、2003)
・中村俊春『ペーテル・パウル・ルーベンス──絵画と政治の間で』(三元社、2006)
・ジル・ネレ著、Kazuhiro Akase訳『ペーテル・パウル・ルーベンス 1577-1640──絵画界のホメロス』(タッシェン、2006)
・村田真構成・執筆『週刊 西洋絵画の巨匠 第50号 ルーベンス』(小学館、2010.2)
・『芸術新潮』No.827(新潮社、2018.11)
・図録『ルーベンス展──バロックの誕生』(TBSテレビ、2018)
・髙城靖之「ルーベンスの《十字架降架の三連祭壇画》──画家の才能と創意」(今井澄子責任編集『ネーデルラント美術の精華 : ロヒール・ファン・デル・ウェイデンからペーテル・パウル・ルーベンスへ[北方近世美術叢書4]』(ありな書房、2019、pp.155-188)
・Webサイト:『RUBENSHUIS』2024.6.5閲覧(https://www.rubenshuis.be/nl)
・Webサイト:「The Descent from the Cross」(『De Kathedraal』)2024.6.5閲覧(https://www.dekathedraal.be/en/rubens-descent-cross)
掲載画家出身地マップ
 ※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。
※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。
2024年6月